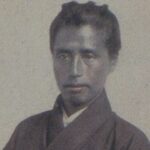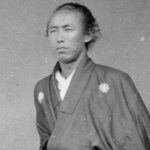安政二年(1855年)10月24日は、江戸幕府が長崎海軍伝習所を設立した日です。
「幕府が海軍?」
そう疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
幕末の江戸幕府というと、無知で、時流に乗り遅れた人たちの集まり――なんて思われがちですが、それは大きな誤解。
鎖国政策の中でも海外の情報を取り入れ、無闇やたらに「攘夷じゃ!」と叫ぶ連中より、はるかに豊富な見識を有しておりました。
まぁ、260年に渡って政権を担っていたので、当たり前と言えば当たり前なんですが、学校の授業だと
【幕府=無能だから倒幕→明治維新】
みたいな印象が植え付けられてしまいますよね。
そんな誤解を解きながら、幕府が作った長崎海軍伝習所を振り返ってみましょう。
長崎海軍伝習所を設立したキッカケは?
伝習所を作るキッカケは、ときのオランダ商館長ヤン・ドンケル・クルティウスです。
「幕府も海軍くらい持っておかないと、今後も諸外国から軍艦で脅されちゃいますよ? ウチから先生を呼んできますから、海軍学校を作ったらどうです?」(※イメージです)
クルティウスからこんな風に言われた幕府は、早速その通りに準備を進めます。
気前がいいのか、諸々の思惑があってのことか。
オランダは先生のついでに船まで送ってくれました。
無事に船と先生を迎えた伝習所。
まずは慣れない西洋の船を動かせる人材を育て始めます。
また、船員だけでなく海防に携わる人間も必要になるため、少しずつ生徒を増やしながら体制を整えていきました。
同時に士官(軍の中間管理職みたいな立場の人/会社に例えると課長~部長くらい)の育成も始めています。
何故その手際の良さをもっと早く発揮しなかったのかといいたいところですが、一応ペリー来航から2年でやっているので、まあ妥当といえば妥当ですかね。
どうせならアヘン戦争で清が負けたときに始めれば良かったんじゃないかという気もしますけども、それは後世の人だからこその視点かもしれません。
龍馬や陸奥が学んだのは神戸の海軍操練所
伝習所には当初幕府から生徒が送られていました。
が、少しずつ諸藩からも海防を学ぶ人がやってきました。
もちろん、薩摩や長州の人も行っています。
一番多かったのは佐賀藩で、倒幕に一役買った藩ですね。
その他もほとんど西日本の藩だったのですれけども、この理由をいろいろ想像すると面白そうです。考えすぎかもしれませんが。
しかし、長崎の伝習所はたった四年でその役割を終えることになります。
江戸・築地に軍艦操練所ができて、教師も生徒もそちらに移っていったからです。
ただし、神戸にも海軍操練所ができたので、西日本における海軍養成が完全に途絶えてしまったわけではありません。
こっちには勝海舟が絡んでいて、当時まだ漁村だった神戸が港湾都市として発展するきっかけになりました。

勝海舟/wikipediaより引用
また、坂本龍馬や陸奥宗光など、後々日本史に名を残す人物も神戸海軍操練所で学んでいます。
長崎には英語伝習所や養生所(長崎大学医学部の前身)があったので、やはり西洋の学問や情報については、東日本よりもずっと手に入りやすかったことでしょう。
それに、外国人教師から海軍の知識を教わることができたのは、長崎海軍伝習所だけでした。
軍艦操練所の先生は長崎で学んだ日本人だったのです。
軍艦操練所ではイギリスから先生を呼ぶ予定だったのが、倒幕によってポシャっています。もっと早く呼んどけば……(´・ω・`)
後継者争いから大きな政争に発展してしまった
そもそも西日本にばかり学校を作っていたら、西の大名ばかりが西洋の学問や技術を吸収してしまうでしょう。
なぜ幕閣の中でそのことに気付いた人がいなかったのか。
反対に、佐賀藩は独自で三重津海軍所という造船所兼海軍学校を作っていたりします。
「明治日本の産業革命遺産」の一つとして世界遺産に登録されていますね。
まぁ、この頃の将軍は十三代・徳川家定で後継者問題が勃発していたので、幕府中枢では政争に追われていたという事情もあります。

徳川家定/wikipediaより引用
島津斉彬と西郷隆盛が一橋慶喜を将軍にしようとして、結果的に井伊直弼に負け、【安政の大獄】やら【桜田門外の変】やら、何かと混乱が始まる時期です。
幕府は、全国の諸藩に先駆けて外国船の圧力も認識しておりながら、結局、水戸藩に振り回され過ぎて、壮大な混乱が生じてしまったのが失敗でしたね。
まぁ、御三家に暴走されてしまうと、最早どうしようもないですが、勝海舟や、幕臣・中島三郎助はどれほど悔しかっただろうか……。
以下の記事に詳細がございますので、よろしければ併せてご覧ください。
あわせて読みたい関連記事
-

脆弱どころか十分戦えた江戸幕府の海軍~創設の立役者・中島三郎助は箱館に散る
続きを見る
-

あのペリーが日本人を接待していた?日米和親条約の交渉で用いたほのぼの作戦
続きを見る
-

ペリーはアメリカで無名な存在だった!? めちゃめちゃ苦労して進めた開国交渉
続きを見る
-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか? 最期の言葉は「コレデオシマイ」
続きを見る
-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか? 最期の言葉は「コレデオシマイ」
続きを見る
-

坂本龍馬は幕末当時から英雄扱いされていた? 激動の生涯33年を一気に振り返る
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
国史大辞典
歴史群像編集部『全国版 幕末維新人物事典』(→amazon)
安岡昭男『幕末維新大人名事典(新人物往来社)』(→amazon)
長崎海軍伝習所/Wikipedia