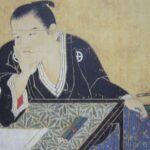そんな小さな家から、徳川家康の天下取りを支え、大出世を遂げた人物が井伊直政です。
彼らの苦難を描いた大河ドラマが2017年『おんな城主 井伊直虎』だったことはよくご存知のことでしょう。
しかし、井伊家が主役を飾ったのは、直虎が初ではありません。
栄えある大河ドラマ第一作『花の生涯』。
その主人公こそ【安政の大獄【や【桜田門外の変】で知られる井伊直弼でした。
二つの出来事があまりにインパクト強く、歴史作品では往々にして悪役にされますが、史実の評価となると事はそう単純でもなく、例えばNHKドラマ10『大奥』ではかなり見直された描き方になっていました。
では実際はどうだったのか?
文化12年(1815年)10月29日が誕生日である、井伊直弼の生涯を振り返ってみましょう。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
彦根藩主の庶子として
井伊直弼は文化12年(1815年)、近江の彦根藩第11代当主・井伊直中(なおなか)の14男として生まれました。
母は側室のお富。
直中と富の間には既に二人の男子(11男・直元、13男・直与)がおり、直弼は富にとって三番目の子ということになります。
母の富は、美貌と知性で寵愛を受けましたが、実家は浪人でした。
しかも直中はこのころ既に隠居しており、直弼は晩年の子になります。
我が子というよりは孫のような感覚でしょう。
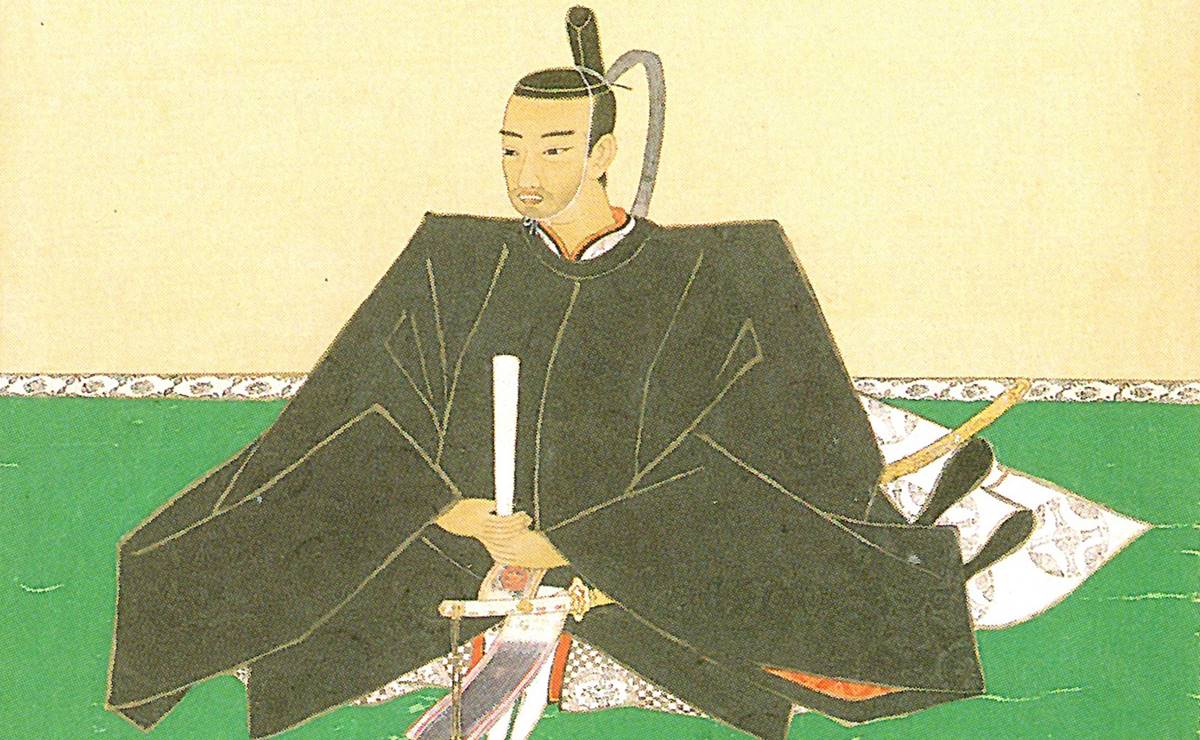
井伊直中/wikipediaより引用
彦根藩の江戸屋敷で、直弼は父母に可愛がられて育ちました。
5才の時に母、17才で父を亡くすという不幸はあったものの、当時は彦根藩の藩政も比較的安定しており、直弼は穏やかな暮らしを送ることができました。
「埋もれ木」の生活
父の死後、直弼は彦根城内の屋敷に移ります。
18才で元服もしますが、出自は庶子で、兄もかなり多い。
直弼は、世捨て人のような境遇に置かれました。
名門井伊家の子でも、さすがに14番目の男子となりますと、養子になれる道もありません。300俵の部屋住みとして、ほとんど未来のない日々を送ることになるのです。
かくして32歳までの15年間。
300俵の部屋住みとして過ごした直弼は、自邸を「埋木舎(うもれぎのや)」と名付けました。部屋住みの身として、花咲くことのない我が身を、埋もれ木にたとえたのです。
後に、直弼の住まいは、「埋木舎」から「柳和舎」、「柳王舎」へと移ります。
柳は直弼の好んだ木でした。

直弼が暮らしていた埋木舎/photo by 663highland Wikipediaより引用
もちろん、ただ漫然と過ごしていたわけではありません。
直弼は井伊家の男子らしく、武芸学問に励んでいます。
武芸は、剣術、鑓術、馬術、居合術――居合術については一派を創設したほどです。
学問は、兵学、古典文学、和歌、俳諧、狂歌。
その他にも能、茶道、禅、和楽器をこなし、いずれの道においても、卓越した才能を見せます。
そうした修養の日々を送りながら、直弼はやはり己の境遇に虚しさを感じてしまいます。
仕方のないことでしょう。
いくら才能があっても持て余すだけなのですから。
井伊家の庶子は、仏門に入ることがありました。直弼の叔父も、そうでした。
この俗世にいても埋もれ木なのであれば、いっそ仏門に入った方がよいのではないか――そんな思いから、直弼は禅にも傾倒していきます。
天保14年(1842年)頃、直弼は、後の行動をともにする長野主膳義言という人物と知り合った、とされています。
※以下は長野主膳義言の関連記事となります
-

井伊の懐刀・長野主膳義言とは? 乱世を駆け抜けた和歌の先生 48年の生涯
続きを見る
出会った頃の二人は和歌について関心を持っておりました。そのうち国学を習うようになり、直弼はその方面も造詣を深めることになります。
井伊家の世子として
ずっと燻っていた直弼に、急な転機が訪れたのは32才のときです。
弘化3年(1846年)、兄・直元が急死。
江戸出府を命じられ、12代藩主・直亮の世子、次期藩主とされたのです。
17才から15年、およそ人生の半分を埋もれ木として過ごしてきた直弼にとって、予想外のことでした。
直弼自身も、戸惑いを隠せません。なんせ、埋もれ木という境遇が終わり、名門井伊家の世子となることは、大変なプレッシャーです。
跡継ぎとそれ以外の教育、暮らし、覚悟というのは、まったく違う。
しかも、30を過ぎてからの激変では、直弼でなくても相当なストレスと疲労を感じたことでしょう。
直弼からみると、養父となった直亮はどうにも自分勝手で、言うことを聞く家臣ばかりを重用しているように思えました。
直亮も、直弼に対して良い感情を抱いていなかったようです。

井伊直亮/Wikipediaより引用
直亮は、蘭学に興味関心があり、西洋の文物を積極的に取り入れようとしていました。
しかし当時の彦根藩は財政が悪化しており、そのような開発事業に予算を割いてもよいかどうか、難しい局面。
直弼と直亮の対立は、薩摩藩で言えば島津斉興と島津斉彬の対立に似たような部分があったのでしょう。
-

斉彬と久光の父・島津斉興~藩財政を立て直し薩摩躍進の礎を築いた功績に注目
続きを見る
-

幕末薩摩の名君・島津斉彬~西郷らを見い出した“幕末の四賢侯”50年の生涯とは
続きを見る
直弼は、直亮との対立に悩みながらも、井伊家世子としての意識を高めてゆきました。
なんせ彼らは、将軍家との関係において特別な間柄です。
井伊家は、将軍家にとって常に先鋒でなくてはならない――直弼はそう意識しています。
要は、ただ単に家を継ぐだけではなく、将軍家の危難に際して真っ先に動く家ではくてはならないと決意していたのです。
弘化4年(1847年)、直弼は政治の舞台において発言力を見せています。
海外からの船舶が接近する情勢の中、彦根藩は、相州警備の幕命を受けました。
しかし直弼は、井伊家は京都守護の家柄であり、二カ所も同時に守ることは不可能だと反発します。
井伊家は、2代目の井伊直孝以来、京都守護を行うことが慣例となっていました。正式な任命ではなく、家康が京都で鷹狩りを行った際に、密命を受けたのが始まりとされています。
直弼が相州警備に反発したのは、それだけが理由ではありません。
天下第一、先鋒として役割を果たすべき井伊家が、警備において不備を指摘されては不名誉なことであると考えてのこと。
この井伊家は別格であるという強い意識は、直弼の心の底にしっかりと刻みこまれたものでした。
※続きは【次のページへ】をclick!