こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【平安時代の色彩】
をクリックお願いします。
日本古来の色彩感覚は上書きされていった
植物染の繊細な色合いはとても美しい。
しかし現代人にとっては、非常に難解にも思えます。
『源氏物語』の登場人物たちが「なんと見事な色なのだ」「さすがセンスが抜群だ」と褒めあっていても、まず色と名前が一致しません。
季節がどれか?と問われても大変難しい。
そもそも『源氏物語』当時の衣装は現存しません。絵巻にせよ退色しています。
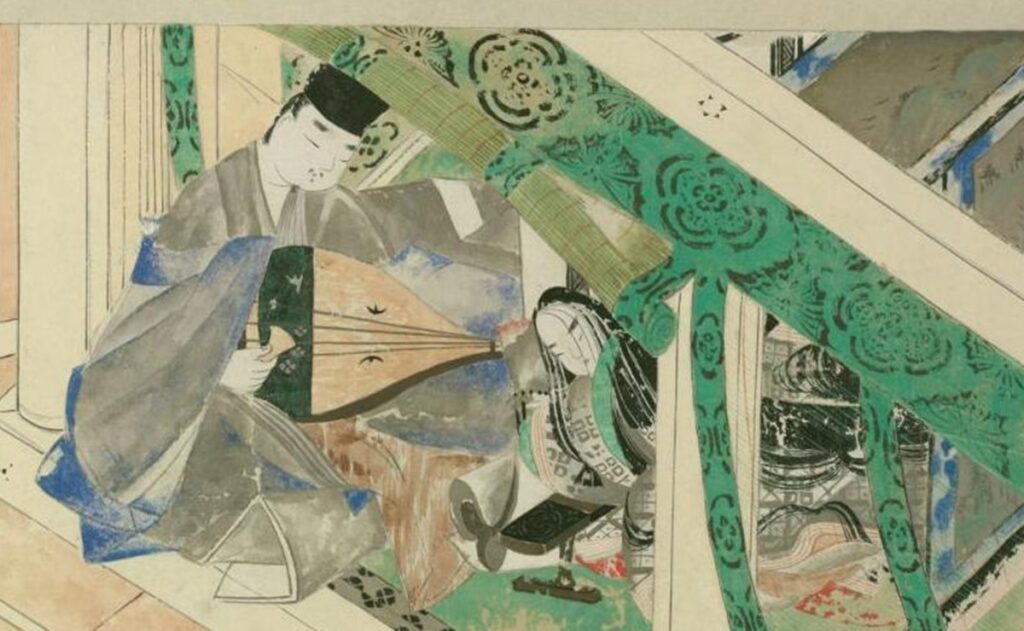
画像はイメージです(源氏物語絵巻/wikipediaより引用)
しかも日本人の色彩感覚も、時代と共に上書きされてきました。
例えば2021年の大河ドラマ『麒麟がくる』では、衣装の色合いについてクレームが入っています。
当時の色彩感覚を再現したところ、画面の色調整が強すぎたこともあってか、「あんな色はありえない!」と批判されたのです。
なぜ、そこまで怒られたのか?
というと、江戸時代以降、度重なる倹約令により、日本人の色彩感覚がかなりの渋好みになったことが強く影響しているのでしょう。
映画やテレビ時代劇は江戸時代後期以降の感覚で作られていることが多いもので、戦国時代とは違う。
それで視聴者にとっては「違和感がある!」となるわけですね。
明治以降は、西洋由来の色彩感覚も入ってきて、我々は様々な変遷を経ながら現在の色彩感覚となっています。
ゆえに日本の伝統色を想像し、描く――というのは簡単なようで実はかなり難しい。
衣装そのものを再現するにせよ絵を描くにせよ、時代が古くなればなるほど手間がかかるのは、ある意味当たり前のこと。
それだけにドラマを見る機会は貴重な経験であり、新鮮なものであっても何ら不思議はありません。
大河ドラマ『べらぼう』は江戸時代が舞台であり、当時そのままの錦絵が残っていまので、圧倒的にイメージがしやすい。
それと比べて『光る君へ』は非常に大変でした。
『源氏物語』の色をデジタルで再現するには?
『光る君へ』の色合いを、デジタルで再現したらどうなるか?
『源氏物語』に出てくる色と、そのカラーコードをみていきましょう(スマホでご覧の方は画面を拡大して、その色合いを楽しんでみてください)。
山吹
カラーコード:#FCAF17
明るい黄色です
葡萄色(えびいろ)
#640125
葡萄と書いて「エビ」と読むのは、魚介類は関係ありません。ヤマブドウの古称「エビカズラ」由来とされます。ワインレッドのような紫色です。
鈍色(にびいろ)
#727171
灰色や鼠色といった色名に変わってゆき、現代では馴染みのない色名です。
青鈍色(あおにびいろ)
#324356
青みがかった鈍色。鈍色の時点で現代人には馴染みが薄いため、やはり難解です。不吉な色で、当時の人は色を見る、あるいは出てくるだけで嫌な予感がするものでした。
麹塵色(きくじんいろ)
#bfbd9e
コウジカビの菌糸。栗の実が少し色づいた色。山鳩の首の周りの色などなど、さまざまな説明がなされています。もっとわかりやすい名前にして欲しいと困惑するか。あるいは風流だと感心するか。難解な色です。
今様色(いまよういろ)
#d05a6e
「今様」(今用)とは、「今時の流行色」。当時の人でないとピンとこない色名です。淡い赤と推察されますが、さまざまな解釈ができます。
撫子色(なでしこいろ)
#eebbcb
愛くるしいピンクです。
丁子色(ちょうじいろ)
#efcd9a
丁子で染めた淡い黄です。
色名を見て、パッと思い浮かぶ――なんてことは現代人では不可能ですよね。
実際、当時の色を特定できず、諸説ある場合もあります。
それでも今は便利な時代です。
日本の伝統色解説や、カラーピッカーアプリがあり、そうしたものを駆使してゆけば身についてゆく。
「#光る君絵」でも活用していた方がいたかもしれませんね。
「彼の国」と色も通じ合って
『光る君へ』の衣装と比較したいのが、制作側も意識しているという韓国や中国の時代劇です。
植物染にせよ、蘇芳、丁字といった輸入した植物。
紅花、槐といった渡来植物由来のものもあります。
さらに色そのものが中国から伝わり、日本にだけ残ったものもあります。
現在では日本の天皇のみが重要な儀式において着用する「黄櫨染御袍」は、唐の皇帝が身につけていた色を元にしています。
中国から日本の儀式を見るということは、中国伝統色を知る機会でもあるということです。
『光る君へ』でも、同じ見方ができます。
中国伝統色と似た服を着ている。あれはどういう由来なのか?そうして知的好奇心を刺激する可能性があるのです。
アジアの時代劇を見て、共通する色のセンスを感じたら、それはきっと正しい感覚です。
そしてこれは他の国の人が『光る君へ』を見た時も、起こり得る現象です。
そう考えるととても魅惑的で、可能性がある作品なのです。
ドラマを見て、描いて、『源氏物語』を読み返せば、きっと素敵な色の迷宮に迷い込めるようになることでしょう。
四季折々の花鳥風月をみて、その色を楽しみ、思いを馳せることもできるようになるかもしれません。
『光る君へ』は、見ているだけでより深い世界へ連れていってくれる、そんな作品に仕上がっていました。
あわせて読みたい関連記事
-

雅で華麗な平安時代の行事「曲水の宴」とは?起源は中国の「曲水流觴」だった
続きを見る
-

平安貴族は日記も大事なお仕事! 道長も行成も実資も み~んな記録を残していた
続きを見る
-

平安時代の手紙は男女を結ぶ超重要アイテム~他の誰かに読まれるのは普通のこと?
続きを見る
-

牛車は平安貴族の乗り物でありステータスであり 物語にも欠かせない存在だった
続きを見る
-

平安貴族は寺社参拝でどんな祈願をしていたか?道長や道綱母の実例と共に振り返る
続きを見る
【参考文献】
吉岡幸雄『源氏物語の色辞典』(→amazon)
浜田信義『日本の伝統色』(→amazon)
郭浩/李健明『中国の伝統色』(→amazon)
他





