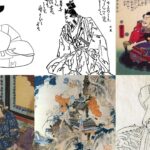鎌倉武士として現代でもその名が知られているのに、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』には登場しなかった。
むしろ、あまりにキャラが際立っていて、登場させられなかった?
そう思われるのが、承元2年(1208年)9月14日に亡くなった熊谷直実(くまがいなおざね)です。
畠山重忠と同じ武蔵国の坂東武者であり、源義経が活躍した【一ノ谷の戦い】でもド派手なエピソードを残すと、梶原景時を恨みつつ武士の兜を脱ぎ去り、最期は仏に救いを求めながら往生する――。
ある意味、典型的な鎌倉御家人であり、あの織田信長が好んだ謡曲『敦盛』にも登場します。
ならばなぜ『鎌倉殿の13人』には出なかったのか?
熊谷直実の生涯を振り返りながら、その理由についても考察して参りましょう。
畠山や比企と同じ武蔵の武士
熊谷直実は永治元年(1141年)生まれ。
直実の同年生まれで、同じくドラマに登場していない人物を二人挙げさせていただきますと、源義平と千葉胤正(たねまさ)がいます。
源義平:源義朝の嫡男で頼朝の長兄/永暦元年(1160年)の【平治の乱】にて討死する/享年20
千葉胤正:千葉常胤の嫡男
義平の弟である源頼朝が久安3年(1147年)生まれですので、直実らはその6才上になりますね。
直実の領地は武蔵国熊谷郷です。
【保元の乱】で源義朝に味方して戦うと、その後は平知盛に仕えました。
戦況に応じて、源氏や平家につくのは、当時の坂東武者としては、ごく普通の動きでもあります。
※以下は坂東八平氏の関連記事となります
-

関東に拠点を築いた坂東八平氏~なぜ清盛に従ったり源氏についたりしていた?
続きを見る
時代が一気に動いたのは、治承4年(1180年)8月のこと。
頼朝の挙兵です。
伊豆の北条や相模の三浦党を中心とした武士団を従え蜂起すると、迎えた【石橋山の戦い】では惨敗。
このとき武蔵国の武士たちは、比企能員は日和見をして、畠山重忠は平家につきました。
熊谷直実も当初は平家方として様子を伺っていましたが、房総半島に渡った頼朝が上総広常や千葉常胤の助力を得て、一気に勢力拡大すると、頼朝のもとへ馳せ参じています。
武蔵の武士としては、やはり典型的なスタンスでしょう。
ただし、遅れて参加しただけに、その後、とにかく“武功”を欲するような動きを見せます。
組み伏せた相手は花のような美童だった
石橋山の戦いから3年半後の寿永3年(1184年)2月――熊谷直実は頼朝の弟・源義経軍に従軍していました。
このとき勃発したのが、ドラマでも描かれた【一ノ谷の戦い】です。
平家が崖を背に布陣していたところを、義経が急な山を駆け降りて奇襲した戦いとして知られますね。
-

源平合戦の趨勢を決めた一ノ谷の戦い(鵯越の逆落とし)信長でお馴染み平敦盛も討死
続きを見る
-

なぜ義経の強さは突出していたか 世界の英雄と比較して浮かぶ軍略と殺戮の才
続きを見る
直実がこの合戦に参加しながら、ドラマに登場させられなかったのも仕方ないかもしれません。
なぜなら直実は、子の熊谷直家と郎党一人を引き連れ、わずか三人で抜け駆けをしようとして、危うく敵に囲まれ討死しそうになっていたのです。
それだけ前のめりになって戦果を求めていたのでしょう。
しかし同時に、そこで終わらなかったのが直実。
危機を脱し、血に飢えた獣のように敵を求めて彷徨っていると、船を目指す平家武士の姿が目に飛び込んできました。
「敵に背を見せ逃げるとは卑怯なり! 待たれい、戻られよ!」

熊谷直実/wikipediaより引用
直実がその武士を呼び止めると、侮辱されて黙っていられなかったのか、その相手は戻ってきました。
すかさず馬から引き落とし、組み伏せる直実。
いざ首を取ろう!
と敵の顔を見てみれば、我が子と同じ年頃だけでなく、花のように美しい美童ではありませんか。
直実は愕然とします。
こんな美しい少年を殺してもよいものか。
思わず名を尋ねると、彼はこう言います。
「ここで名乗らずとも首を取って人に尋ねればよい! さぁ、早くせよ!」
※続きは【次のページへ】をclick!