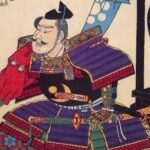こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【鎌倉殿の13人感想あらすじレビュー第12回「亀の前事件」】
をクリックお願いします。
景時と広元 二人の知恵者
頼朝は隠れ家の跡を見て唖然としています。
一応、義時が亀は無事だと伝えてホッとはしていますが、梶原景時が伝え聞いたところによると付け火(放火)だとか。
「恐ろしすぎる……ここまでするか!」
そう恐れ慄く頼朝です。
義時は政子に事件の経過を報告。
政子はさっぱりした顔で、鎌倉殿も冷や汗をかいたことだろうと平然としています。
梶原景時が調査中であり、牧宗親が詮議を受けるのはおそろしくないのか?と義時が尋ねても、やっぱり政子は平然としています。
りくが面白がって意地悪なことをしたと政子はわかっている。たっぷり叱られるといいと言い切ります。
「それで済めばよいのですが……」
ここで、ようやく館が焼け落ちたことを伝える義時。
女は逃げて無事だと付け加えつつ、ともかく詮議を受ける牧宗親が危険だと義時は懸念しています。そのころ……
頼朝は怒りの追及中。
知恵者の大江広元は、政子が「後妻打ち」をしたと推察します。
しかし頼朝は、そんな都の風習を政子が知らないだろう!と考えながら気づきます。
牧宗親とりくの兄と妹ならば、知恵をつけることができる!
と、あっという間に犯人が判明。すぐに調べよと息巻く頼朝に対し、梶原景時が義経も関わっていると目撃証言を伝えます。
「九郎が関わっておるのか! あの馬鹿めが!」
思わず怒鳴り散らす頼朝ですが、さすがに、このあたりで義経の凶暴性と危険性に気づいていればよいのに――そう思える秀逸な伏線ですね。
もうひとつ。
頼朝の知恵袋が揃った感のある、梶原景時と大江広元の違いでも簡単にまとめてみましょう。
武官である景時は、足で歩いて捜査をする刑事タイプですね。
目撃証言を集めて追い詰めてゆく。
一方、大江広元は、状況を察知し推理する探偵タイプ。
「後妻打ち」という都の風習にすかさず気が付くところから、そうした知恵を匂わせていましたね。
左右にこういう家臣がいれば、頼朝はますます強く盤石になる。
ドタバタの影に隠れておりますが、幕府の組織はかなり固まってきました。
「ああ、自分が嫌になる」
義時は一部始終を政子に報告します。
このままでは大変なことになるから、政子に鎮めて欲しいと言い出す。
しかしそっけなく「嫌です」と言い切ってしまう政子。
元はと言えばりくがやったことだと言い切ります。
義時は自責の念にかられていて、義経も関わってしまったと告げます。政子が困惑しつつ理由を聞くと、義時は泣きそうになっています。
「私のせいなんです! ああ、自分が嫌になる!」
この義時、毎週泣いておるなぁ……。
かくして頼朝の前に、義経と宗親が座り、詮議を受けています。
宗親が、御台所の頼みだと言い訳すると、頼朝は政子に頼まれればなんでもやるのか?殺せと言われれば殺すのか?と問い詰める。
火付けは義経のせいだと宗親も必死です。
一方の義経は己の一存だと、堂々としている。
頼朝がなぜ現場にいたのかと尋ねると、自分が頼んでしまったと義時がカットイン。
「お前は黙ってろ!」
そう怒鳴る義経。いやいや、ほんと、人徳がなさすぎる。部下の人身掌握……というレベルどころではなく、日常生活に影響のありそうな酷さだ。
頼朝は政子のためでも他の御家人に示しがつかないと、謹慎を命じます。
それにしても、義経があっさり認めたのはなぜなのか。
彼なりに脅したいのかもしれない。何もさせてくれないから火をつけた! 鎌倉でウダウダしているぐらいなら平家を襲わせろ! そう凄んでいるつもりかもしれません。
頼朝は宗親に怒りをぶつけるつもりでいっぱいだ。
かわいい弟の処罰もこいつのせいだと言わんばかり。言い逃れようとする宗親に対し、頼朝は景時に言い付けます。
「平三、この者の髻(もとどり)を切れ」
「堪忍しとくれやす!」
かくして宗親は髪を掴まれ、悲鳴が響きます。
嗚呼、悲しみの断髪。
現代人からすればただのお笑いシーンかもしれませんが、当時の感覚ではブリーフ一丁にされた上、写メを撮られ、SNSで拡散されるような恥辱です。
こんな一連の事件を見る羽目になる義時も哀れです。
鎌倉を離れ伊豆へ帰ってしまった時政
宗親は時政とりくに泣きつきます。
時政としては、なぜりくに相談しなかったのかと困惑してしまう。宗親はあんまりだと泣きついています。
頼朝がりくを呼びつける。
都なら側女くらい理解しろと言うと、りくは一生懸命励んでいる政子がかわいそうだと、黙ることをつっぱねます。
そこへ義時に案内されて政子も入ってきます。
政子がりくに礼を言うと、りくは聞かれたくなかったと返します。
政子はおなご同士の争いをしたことを詫びつつ、肝心なのは夫の裏切りだとキッパリ。
「咎めるべきは夫のふしだら!」
りくもここでそう重ねてくる。
盛長がなだめようとするとりくは「うるさい!」と一喝します。
命懸けで我が子を産んでいるとき、側女と会っていたなんて許せない! そう怒る政子です。
いますぐ頭を下げよと迫るりく。
「さあ!」
頼朝は怒鳴り返します。
「黙れ! わしに指図するなどもってのほか。源頼朝を愚弄すると、たとえお前たちでも容赦はせぬぞ! 身の程をわきまえよ、さがれ!」
「源頼朝がなんだってんだ!」
ここで突然立ち上がったのが時政です。
自分の大事な妻と娘を怒鳴られて許せなくなった――そう啖呵をきったあと「言っちまった」と力なく笑っている。
盛長が酔っているとフォローしようとすると、シラフだと返します。
「どうやらここまでのようだ。小四郎、俺は降りた」
伊豆へ帰って米でも作る宣言をしちまう時政。鎌倉は窮屈でしょうがねえってよ。
りくは「どうしてそうなるのです!」と困惑しているが、もう、腹は据わってしまったのでしょう。
「なんとかせよ小四郎!」
頼朝にそう言われる義時。いや、これをどうしろと……。
義時では手の負えないこの事態ではありますが、大江広元がこの様子をじっと見ていました。
亀は広常にも色目を
夜になり、義時は上総広常の家にいます。
幕府ってどういうことか?
御家人たちはそれぞれが伊豆なり、上総なり、下総なり、武蔵なり、相模なり、自分の所領に住んでおりました。
それが鎌倉に集まって、顔を合わせるようになった。
こうして誰かの家に立ち寄って酒を飲む余裕が生まれるのです。
もう家人は寝てしまったのでしょう。自ら酒と肴を探して持ってくる広常。こういう素朴さが中世らしくて味がありますね。
義時は部屋に書き損じがあるのを見て、孫の手習かと言います。すると……。
「俺が書いたんだよ」
こう来た。
若い頃から戦ばかりで、文字を習わぬままになっていた。京の連中に馬鹿にされたくないから練習をしているのだとか。
「人に言ったら殺す」
「はい」
そう凄む広常と、微笑む義時。
よい場面ですよね。
広常がこう言えるのは、義時を信じているからだと思います。彼は「武衛」の意味が理解できなかったあたりから予測できていたことではありますが、教養がありません。
-

なぜ上総広常は殺されたのか 頼朝を支えた千葉の大物武士 あまりに不憫なその最期
続きを見る
これは史実も反映していて、坂東武者の書状はシンプルで難しい漢字が書けていなかったりします。
ちょっと考えてみてください。
この時代のみなさんの呼び名って「小四郎」や「平六」です。シンプルかつ画数が少ない。幕末の勝麟太郎(海舟)とは違います。
当時の坂東は教養が深めにくかった。広常はその典型というわけです。
そして教養がいらない時代も終わりに近づきつつあります。
大江広元なら、こんな言葉を引っ張ってきそう。
士別れて三日なれば刮目して相待すべし。
士たるもの、別れて三日たてば、目を見開いて再会すべきです。
『三国志』の時代、孫権の配下に呂蒙(りょもう)という人物がいました。
家庭環境に恵まれず、若い頃から従軍し、広常と同じく学ぶ機会がない。
すると孫権は勉強をするように言います。
軍務が忙しいと言っていた呂蒙ですが、しぶしぶ学びはじめます。
そんなあと、孫権配下の魯粛(ろしゅく)が呂蒙と話してみると、彼はすっかり変わっていました。
魯粛はこういいました。
「参ったな、もうこれじゃ呉下の阿蒙(呉に住んでいる蒙ちゃん、子どもへ呼びかけるニュアンス)なんて呼べないね」
そこで呂蒙は「士別れて三日なれば刮目して相待すべし」と言い返したのでした。
広常は義時の災難を労います。
全てを放り出して伊豆に帰りたいと義時が言うと、部屋の外から声がします。
「まだおやすみにならないの?」
亀です。ここにいたのか。
広常が「おう」と返すと亀はこう言います。
「お忙しいこと」
広常はいつまで預かってりゃいいんだ?と迷惑そうな顔。亀は広常にも色目を使ってきやがったってよ。ああいう女は好かねえと広常は困惑しています。
義時は忠義を尽くす
そのころ大江広元が頼朝に助言をしています。
「小四郎殿は、決して手放してはなりませぬ。まだ若くしくじりもありますが、あの者は鎌倉殿に忠義を尽くします」
「わしもそう思う」
「ご安心を。鎌倉は御安泰でございます……ただひとつ、気になったのが」
「言ってくれ」
そう促す頼朝。もう、広元は別格の趣がありますね。主君にこう言わせるのは紛れもなく切れ物です。
広常にできず、広元にはできたこと。
それは読書。
広元がたっぷり読んできた漢籍には、こういうノウハウがある。
「どうすれば主君を諌められるの? 五種類あります!」
正諫:正面からいさめる
降諫:いったんは君主の言葉に従ったうえで、いさめる
忠諫:真心でいさめる。義時ができること
戇諫(とうかん):愚直にいさめる。義時が得意とするところ
諷諫(ふうかん):遠回しにいさめる
広元は理解している。頭が切れるだけでは通じないこともあると。
ゆえに、若くとも真心があって、正面切ってぶつかる側近はいたほうがよいのです。
この義時は、賢いとか、強いとか、只者ではないとか、そういう褒め方はされていません。
ただ「いいやつではある」とうっすらと言われてきたのを、広元は「忠義を尽くします」とまとめてきました。
広元は「月旦(げったん・人物鑑定のこと)」もできる。
どんなに優れた人物でも、その価値を見抜くものがいなければどうにもならない。
千里の馬は常に有れども、伯楽は常には有らず。
千里を走る名馬はいつでもいる。が、それを見抜く名人=伯楽がいつもいるわけではない。
こういうことですね。
広元はゲームチェンジャーになった。彼はとても楽しそうだ。
磨く玉を見出す。それを主君に言えば聞いてもらえる。
都にはなかった活躍の場を得て、それこそ水を得た魚になっている。
そしてそれを踏まえて次回予告でも見てください。
木曽義仲が出てきた。
-

なぜ木曽義仲は平家討伐に活躍したのに失脚へ追い込まれたのか?頼朝との違いは?
続きを見る
これまた目が透き通っていて、見るからに勇猛果敢ではあるのですが、義仲には広元のようなブレーンがいない。
このことが違いとなって響いてくるのでしょう。
※続きは【次のページへ】をclick!