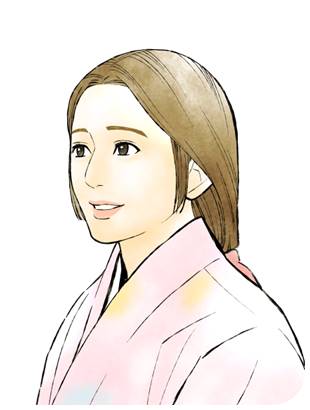こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【麒麟がくる第36回感想あらすじ】
をクリックお願いします。
小姓相手に木剣を振る義昭
二条城に光秀が参ると、三淵藤英が出迎えます。
公方様は広間ではなく、庭にいる。そう告げ、何かを振る仕草をしてみせます。
「せいっ!」
声をあげつつ、木剣を小姓相手に振る義昭。
「もう音をあげるのか、張り合いのない奴じゃ」
そう勝ち誇っております。
けれども義昭には何かが欠けている。公方様相手に、小姓が本気でぶちのめせるわけがない。
そんなことをするのは、フィクションの柳生十兵衛くらいです。
光秀は呆然としてしまいます。
なんでも剣術の達人であった兄・義輝様のことを気にしている、戦に行くにも心得があった方がよいと思い、習い始めたのだと。
何かがおかしい……。
そんな剣の達人だろうと、政治的なコントロールを失い、複数名の刺客に襲われたら何の意味もなかったのに。
光秀は苦い口調でこう言います。
「兄君は兄君、公方様は公方様なのだが……」
ここで決定的なすれ違いがある。
藤英は、光秀が喜ぶと思っていたのでしょう。庭で剣術をしていると告げた時からそうです。彼はよいと思っている。
公方様は武家の棟梁であり、諸大名に侮られては困る。摂津殿の追放以来、己の役割を自覚したのだと感じているのです。
難しい話ですよね。
例えば、好きな役者がいたとする。その人が出ている作品なら、どれだって好きだと思うか?
それとも、好きな役者だからこそ、その人自身が納得して演じられ、出来が良いものであって欲しいと願うか?
その人が、その人らしくあることを重んじるかどうか。
問題はそこです。
義昭はもう、義昭ではない
「おう、十兵衛か」
義昭は庭に降りてきて手合わせをして欲しいと言う。小姓では相手にならないと。
光秀は思わず「は?」と返してしまいます。
藤英も、十兵衛は弟・藤孝が舌を巻くほどほ剣の使い手、あまりお勧めしないと戸惑っています。
のみならず、十兵衛光秀という男は、決して手抜きしてわざと負けないこともわかっているのかもしれません。
しかし義昭は、それゆえ太刀捌きを見たいとせがむのです。
光秀は木剣を渡されます。
「十兵衛、参れ!」
はい、ここから先は、NHKひいては現代日本の殺陣でも気合の入った高度なものが展開されます。
すっと木剣を構える光秀――この時点で技量の差がちがうと一目瞭然なのです。
義昭は息遣いを荒くし、足元を整え、足捌きからなんとかしようとする。
光秀は木剣を握りつつ、これまでのことを思い出しています。
僧侶という弱き身ながら目に力強い光を宿していた過去の義昭を思い出しつつ、もうここまでにしましょうと訴えるものの、相手には通じない。
叫びながら、何度も打ち込んできます。
もしもここで心が通じ合えていたら……しかし、そうはならず、太刀筋に乗せた心がすれ違ってゆきます。
やっと藤英が止めにかかり、今日はこれまでにしましょうと下がらせます。
光秀は、呆然とした顔で落ちた木剣を見るしかないのです。
川を渡り、花を見る。そうして穏やかに生きていたような友、理解できた相手はどこへ行ってしまったのか?
思えば遠くへ来てしまった。もう、あのころの義昭はいません。
太刀を握るなんて考えられない、義昭の本質は消えてしまった。己を見失い、兄の亡霊をめざしてしまっている。
彼はもう、彼ではないのです。
この場面は、心の動き、技量の差、そういうことまで殺陣であらわすのですから、超絶技巧であったと思います。
以前も指摘しましたが、カチャカチャした1980年代以降の香港系アクションは、こういう表現にあまり向いておりません。心情や精神性を出すには不向きです。
香港でも『葉問』シリーズのように伝統武術回帰が進んでおります。
東洋由来の武術の動きと、精神性の融合こそ、今後めざすべき原点回帰であると思える。そんな場面でした。
煕子と二人で行く坂本城
光秀が家に戻ると煕子が出迎え、白湯でもお持ちしましょうかと問いかけます。
夫の疲れを察知しているのでしょうか。
光秀は、白湯はいらんと断ったあと妻相手にこう振り返ります。
「昨日御所へ行った。御所で帝のお声を聞いた……信長様が帝を敬うておられるのが少し分かった……」
武士は将軍様の元に集まり、世を平かにすべき――そう思うてきたけれども、信長様はもはやそうではないのかもしれぬ。そう思えてきたのだと。
煕子に膝枕をしつつ、そう語る光秀。
そんな夫に、昨日、左馬助が近江から帰り、坂本城がだいぶ出来上がったと嬉しそうに話していたと告げます。
光秀はそれを聞き、一緒に坂本城を見に行こうと誘います。
城ができたらまず誰よりも先に、そなたへ見せてやろう。そう思っていたのです。
かくして夫妻は、近江坂本城へ。
煕子はこれが天守というものかと驚いています。
-

なぜ光秀が築いた坂本城は織田家にとって超重要だった?|軍事経済面から徹底考察
続きを見る
手を繋ぎ、外を見る二人。こうして立って外を見ると、この城が湖に浮かんでいるように思える、湖の中にいるようだと語ります。
この城は水城で、堀は外湖に続いていると光秀は説明します。そなたと子どもたちを船に乗せ、月見にこぎ出したい。そして子どもたちに古き歌を教える。
月は船
星は白波
雲は海
いかに漕ぐらん
桂男はただ一人して
『梁塵秘抄』から読み、笑い合う夫妻。光秀はここで、必ず皆をここへ呼び寄せると言います。
人質としてそなたたちを京に残せとは、いかに公方様でも、なんと仰せになろうと、それだけはのめぬ! そう険しく言い切ります。光秀の心も、公方様から離れていくのです。
ここで煕子は問いかけます。
「この近江の国は、美濃国と京のちょうど中ほどでございましょうか。今はどちらに心ひかれておりますか」
光秀は考え込んでいます。
この二択はかつてあった。信長から仕えよと言われた時、光秀は公方様に仕えると即答したものです。
「どちらも大事なのだ、どちらも。ただ……今のままではすまぬやもしれぬ」
そう絞り出すように答える光秀は自分の心に素直です。
斎藤高政相手に仕官を誘われようと、きっぱりと否定した。信長相手にもそうした。
即断即決なのに、迷う時点で彼の中で何かが変わってしまったのでしょう。
甲斐の躑躅ヶ崎館では
元亀3年(1572年)4月――。
幕府と織田の連合軍は河内へ、松永久秀と三好の一党を討つため、大掛かりな出陣をします。
「これより松永を討つ!」
そう仰々しく公方様から宣言があるものの、織田信長自身はこの戦には加わらない。河内に攻めた連合軍も松永久秀を取り逃すのでした。
そのころ、甲斐・躑躅ヶ崎館では――。
信玄はこう宣言します。
「ここのところ、織田信長の動きが鈍い。公方様の足並みにも乱れがある。その公方様は、わしに上洛せよとの催促じゃ。出陣の機は熟したと思うが、どうじゃ?」
「はーっ!」
武田家臣団がうなずく。まずは遠江へ出て、浜松城の徳川家康を討つ。そう宣言されます。
その歳の10月、信玄は京へ向かいました。
「出陣じゃー!」
嗚呼、この信玄も怖かった……。
信玄は兵法をバッチリと知っている男。せっつかれようと、ノリに乗っていようと、相手が崩れるまでは動こうとしない。
情報網を駆使して、これはいけると踏んでの宣言でしょう。
兵法の達人は、馬の様子だの、軍の動きだの、気もそぞろで相手が弱くなっている気配を観察して察知してしまう。短くともそういう信玄の性質が出ています。
-

武田信玄の生涯|最強の戦国大名と名高い53年の事績を史実で振り返る
続きを見る
一方、美濃の岐阜城では?
※続きは【次のページへ】をclick!