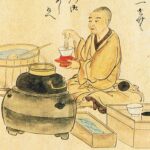こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【本因坊算砂の生涯】
をクリックお願いします。
天下人の相手から公認機関へ
信長が本能寺で明智光秀に討たれた後、本因坊算砂はどんな道を進んだのか?
というと豊臣秀吉とも対局し、その結果、20石10人扶持を与えられています。
他にも、豊臣秀頼の御前で碁を披露したり、徳川家康にも保護されて十石五人扶持を与えられたり。

豊臣秀頼(左)と徳川家康/wikipediaより引用
まさに腕一本で身を立て、江戸時代に入ると、算砂以外の碁打ちである中村道碩・安井算哲・林門入がそれぞれ囲碁の流派を興し、この四家が四家元の起源となりました。
日本棋院の公式サイトに同時代の名人就位一覧が掲載されており(→link)、その順として
①本因坊算砂
②中村道碩
③安井算知
と記されています。
算砂は僧侶ですので妻帯せず、弟子が流派を継ぎました。
時代が下って宝暦・明和年間(1751~1772年)頃には本因坊が最も格上とされ、将軍への指南や全国の棋士へ段位を発行するなど、幕府の一機関に組み入れられています。
そして明治時代以降も受け継がれ、タイトル戦の名に使われるようになったというわけです。
しかし、そもそも囲碁は、いつどこで生まれたのか?
最後に、その歴史も振り返っておきましょう。
碁はいつからあった?
囲碁の発祥は明らかではありません。
中国の聖帝として知られる尭(ぎょう)や舜(しゅん)が囲碁を好んだとされているのですが、これが今日の囲碁と同じものなのか、または似たようなものを指すのか、何かと不明です。
将棋の駒や麻雀牌に比べて碁石はシンプルですので、神代の時代から存在していたとしても不思議ではありません。
有名どころでは、三国時代の梟雄として知られる曹操、若くして亡くなった孫策も碁の名手だったとされていますね。
紀元200年前後の時点で、
「戦や政治に通じた人は囲碁を嗜むもの」
という概念が広まっていたとみて良さそうです。
日本へは、6世紀までに伝わってきたと考えられていて、奈良時代頃から囲碁が上手な人の記録がたびたび出てくるようになります。
といっても試合の記録ではなく、『懐風藻』などで作者のプロフィールに書かれているだけなので、やはり今日の囲碁と同じだったのかどうかは不明。
もう少し時代が下って8世紀になると「藤原広嗣が宇佐八幡神に碁を奉仕した」とか「吉備真備が唐に渡った際、幽霊に碁を挑まれて阿倍仲麻呂の霊に助けられた」とか、かなりファンタジーな話にも登場しています。
「囲碁=頭が良い人が嗜むもの」という概念が一般的になっていたんでしょうね。

月岡芳年『月百姿』の阿倍仲麻呂/wikipediaより引用
『大宝律令』の中の『僧尼令』にも、囲碁が出てくる面白い定めがあります。
「僧侶や尼が歌や賭け事で遊んだ際は百日の苦役を課す。ただし碁と琴はこの限りではない」
この頃には聖職者の間でも好まれるほど囲碁が広まっていたんですね。しかも、囲碁であれば遊んだとしても叱られないようで、逆に気になるのが賭け事でしょうか。
これは双六などのボードゲームのことですね。
古い時代の双六は現代のものとは違う形をしていて、たびたび賭け事に用いられました。
『水鏡』の中にも、光仁天皇が皇后・井上内親王と双六の勝敗で賭け事をしたという記述があります。
天皇でさえ賭け事に使っていたのですから、下々の者は推して知るべしでしょう。
そうした時代でも例外とされた囲碁。
歴代天皇も囲碁の名手を呼び、御前で試合をさせ、見物したとされる記録があります。
正倉院北倉には、聖武天皇が愛用したとされる碁盤や碁石が現存しておりますが、象牙や紫檀などで作られた、それはもう豪勢なものでした。

正倉院/wikipediaより引用
「仏教と同じ頃に囲碁が伝来し、上流社会に広まった」
ざっと、そうまとめてよいのではないでしょうか。
貴族社会では必須の教養
貴族社会では、宮中行事に囲碁の会が取り入れられ、必須の教養とみなされるようになりました。
例えば9世紀後半~10世紀前半頃の寛蓮(かんれん)という僧侶が、記録上における初の囲碁名人だったとされます。
宇多天皇の在位~譲位後だけでなく、その子・醍醐天皇にも仕えたといい、『今昔物語』ではこんな記録が残されています。
寛蓮があるとき金の枕を賭けて醍醐天皇と対局し、天皇が負けるたびに公家たちに枕を取り返させた
賭け事に使っていいんかーい!
ちなみにこの話、最後には寛蓮が金箔を貼っただけの偽物の枕とすり替えておき、見事、本物は手中に収めています。
醍醐天皇はその報告を受けて大笑いした……というところで話が終わっているので、お咎めはなかったようです。めでたしめでたし。

醍醐天皇/wikipediaより引用
平安時代の文学作品にも注目しておきますと『枕草子』や『紫式部日記』、『源氏物語』などにも囲碁は登場しています。
『源氏物語』では、あまり身分の高くない軒端の荻(空蝉の継娘)が囲碁を打つシーンがありますので、貴族社会ではかなり広い範囲で嗜まれていたんですね。
その後も囲碁は広く親しまれましたが、碁を打った逸話に関してはやはり僧侶の話が多い傾向があります。
そして本因坊算砂の時代へと続くわけで。
最近は、囲碁を全くできないという方に向けてのアプリも豊富にあります。
以前から興味を持っていたけど手を出せなかった、という方はチャンスですよ!
あわせて読みたい関連記事
-

茶葉は銭やでバクチやで! 清涼で雅ではないドロドロした茶の裏歴史が面白い
続きを見る
-

戦国武将たちが愛した連歌をご存知?光秀も藤孝も幸村も皆んなハマっていた
続きを見る
-

千利休の生涯|秀吉の懐刀で茶を極めた茶聖 なぜ理不尽な切腹が命じられた?
続きを見る
-

戦国時代にあった恐怖の風習『鉄火起請』焼けた鉄を素手で握ったら死に至る?
続きを見る
-

狩野永徳の生涯|唐獅子図屏風を手がけた信長の御用絵師が“天下一”となるまで
続きを見る
【参考】
中山典之『囲碁の世界 (岩波新書 黄版 343)』(→amazon)
国史大辞典
世界大百科事典
デジタル大辞泉
日本人名大辞典