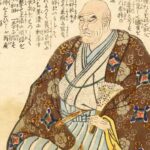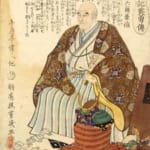織田信長といえば、とにかく革新的――。
戦場においてはいち早く大量の鉄砲を取り入れ、人事においては出自を問わず秀吉や光秀らを抜擢して。
そして教科書などでも強調されがちな“革新”が「楽市楽座」であろう。
信長が始めた楽市楽座は、同業者による組合「座」の特権を廃止して、税金も取らない。だからこそ色んな土地から大勢の商人がやってきて、街は大いに賑わいを見せる。
やっぱり信長様はすごい!
と、そんな風に語られるが、実際はそうでもない。
なんせ「楽市」については、信長より18年も前の記録が残っていて、とても最初に始めたとは言えない状況である。
一体どういうことなのか? 当時を振り返ってみよう。

織田信長/wikipediaより引用
信長の楽市は戦後復興策だった
まずは織田信長の「楽市楽座」から見ていこう。
信長による最も古い記録は永禄10年(1567年)10月のこと。
その2ヶ月前の8月に美濃の戦国大名・斎藤龍興を追い出し、稲葉山城を奪い取った信長は、

稲葉山城(岐阜城)/wikipediaより引用
城下町や周辺エリアの整備に取り掛かった。
このとき市場に向けて出されたのが「楽市場」という法令。
檜板の木札に「楽市場」と記され、以下のような内容が規定されていたのである。
◆永禄十年の「楽市場」
・岐阜の市場へ移住する者は国内の通行を保障する
・地子や諸役を免除する(土地の賃貸料や諸税などを免除)
・押買(強引に安値で買うこと)、狼藉(乱暴に振る舞うこと)、喧嘩、口論の禁止
信長はなぜ「楽市場」という法令を出したのか?

というと別に革新的だからでもない。
織田軍が美濃(稲葉山城)へ攻め込んだとき、戦火を回避して別の場所へ逃げていた民衆たちに「戻ってきて!」と呼びかけたのである。
ゆえに木札は市場だけでなく、稲葉山城近隣の村落でも同様に掲げられ、戦後の復興が進められた。
信長は翌年の永禄11年にも同法令を告知。
このときは「楽市楽座」と記されていて、引き続き自国内での経済振興・人口増加に努めていたことがわかる。
なお、当時の「楽市楽座」の木札を確認すると、長期間の使用による経年劣化の跡が見られ、一定の役割を果たしていたことが推測されるという。
革新的ではなくとも実際に効果があるため、地道に継続していたのだ。
最初の記録は確かに六角氏だが
一方、日本で最初の「楽市」の記録が見られるのが近江の六角氏。
天文18年(1549年)に出された文書の中に「観音寺城の城下町石寺に楽市があった」ことが記されていた。
より具体的に言うと
「枝村の紙商人に近江と美濃での特権は認めるが、石寺新市での独占は認めない(=石寺の市場は楽市である)」
という内容だ。

六角氏の居城である観音寺城の模型(滋賀県立安土城考古博物館所蔵)/wikipediaより引用
こうなると「六角氏が革新的だったの?」と新たな疑問が湧いてくるかもしれないが、ここは発想を変えた方が良いようで。
実は、近江六角氏の「楽市」は、六角氏が定めた政策だという証拠はない。
むしろ利益確保のため商人たちが主導で取り入れたと考えるほうが自然なようで……。
戦国時代は大名や武将だけが全てを動かしていたわけじゃない――そんなことがわかる事例となっている。
あわせて読みたい関連記事
-

近江の戦国大名・六角義賢の生涯~将軍家に翻弄され信長に滅ぼされる一部始終
続きを見る
-

信長と義昭の上洛 46日間の一部始終|信長公記第52話
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

信長相手に暗殺やゲリラ戦!六角義賢の戦歴は?|信長公記第110話
続きを見る
参考文献
- 日本史史料研究会(編)『信長研究の最前線 ここまでわかった「革新者」の実像(朝日文庫)』(朝日新聞出版, 2020年10月7日, ISBN-13: 978-4022620309)
出版社: 朝日新聞出版(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 新谷和之『図説 六角氏と観音寺城 ―“巨大山城”が語る激動の中世史』(戎光祥出版, 2022年12月23日, ISBN-13: 978-4864034586)
出版社: 戎光祥出版(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ