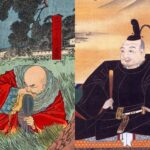こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【榊原康政の生涯】
をクリックお願いします。
小牧・長久手の戦い
特に強烈なエピソードが残っているのが天正12年(1584年)。
【小牧・長久手の戦い】でしょう。
豊臣秀吉
vs
徳川家康 with 織田信雄(信長の次男)
本能寺の変後、柴田勝家を破り、織田家の主導権を握った秀吉。
旧・武田領や家臣などを取り組み、東海甲信地方で絶大な力を有するようになった家康。
両者が覇権を競った争いであり、榊原康政は家康の家臣ですから、当然、秀吉は敵となりました。

『小牧長久手合戦図屏風』/wikipediaより引用
そこで康政は、槍働きだけでなく、意外な方向から攻撃を繰り出します。
【意訳】信長公の恩を忘れて主家を乗っ取ろうとする不届き者よ!
そもそもどこの馬の骨ともわからんヤツに従う義理はない!!
こんな風に秀吉を罵った手紙を、本人に送りつけたというのです。
敵を怒らせるのも戦略のうちとはいえ、康政の手紙は、空前絶後の度胸と言わざるを得ません。
当人は達筆だったので、この罵詈雑言(正論)も相当綺麗な字で書かれていたことでしょう。煽り度がうなぎ登りですね。
もちろん、秀吉は怒髪天を衝く勢いで怒りました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
「康政を討ち取った者には10万石を与える!!」
とまぁ、いかにも秀吉らしいリアクションで面白い話なのですが、話の出典が江戸時代の書物ですので、信ぴょう性については疑問符が付くところです。
実際に榊原康政が家康から10万石を貰っているので、それだけ活躍したということは間違いないんですけどね。
ちなみに「10万石」という懸賞首が本当だとしたら、これがどのくらいスゴイ賞金になるのか?
「石」は領地の単位というイメージをお持ちの方も多いかと思います。
元々はお米の量を指し、1石=大人一人が一年間に食べる米の量となり、だいたい150kgくらい。
つまり康政の首は、10万人を一年養えると見なされたことになりますね。秀吉のキレようったら……。
余談ながら、現代の日本人は一年で一人50~60kgくらいの米を食べているといわれています。
つまり戦国時代の人は、現代人の三倍前後も食べていた。
料理のレパートリーが少なかった時代とはいえ、米の重要性がわかりますよね。玄米でしたので栄養価も十分ありましたし。
そして康政、これだけの啖呵を切るからには、相当の覚悟も決めています。
家康はこの戦の際、一時的に『小牧城に康政を残し、撤退しようか』と考えていました。
重臣居並ぶ場でこの話を聞かされた康政は
「秀吉ほどの敵を引き受け、城を枕に討ち死にするのであれば、末代までの誉れ」
と言っていたそうです。カッコイイ。
従五位下・式部大輔の官位と豊臣姓を与えられ
榊原康政は、もちろん言葉だけでなく、武働きもきちんとしています。
小牧・長久手の戦いでは秀吉の甥・豊臣秀次の陣を突き崩し、同行していた池田恒興や森長可を戦死させたとも。
「実際に討ち取ったのは安藤直次とか水野勝成の部隊では?」という話もあり、個人的には「突きがかり戦法」を使ったという井伊直政の部隊のような気もしますが、いずれにせよ康政部隊も同様に凄まじい活躍だったのでしょう。

井伊直政/wikipediaより引用
幼少期の勉学好きといい、まさに文武両道の武将です。
ただし、この合戦で主の家康が秀吉と和解すると、当然ながら康政もそれ以上のことはしていません。
秀吉への使者を務めたり、家康が上洛する際のお供もするほど。
「強い敵を褒めることは自分の格を上げる事になる」というのが秀吉のスタンスでしたので、康政にも従五位下・式部大輔の官位と豊臣姓が与えられています。
さらには「お前のことが気に入ったから、これからは”小平太”と呼ばせてもらうぞ」とまで言われたとのこと。
目上の人が目下に対して通称や幼名で呼ぶ――というのはよくある話ですが、他家の家臣にまでというのは、少々別の思惑も感じますね。
というのも小牧・長久手の戦いの翌年、石川数正が徳川家から秀吉のもとへ出奔しているのです。

石川数正/wikipediaより引用
むろん康政はこの後も家康に仕え続けていますが、徳川家にとってはショッキングな出来事でした。
なんせ家康に幼少の頃から仕えた数正は、徳川軍のことを知り尽くしていて、軍事制度を変更せねばならないほど。
-

家康が学んだ信玄の「甲州流軍学」徳川軍に採用されたその後どうなった?
続きを見る
とはいえ両家が表立って仲違いすることはなく、豊臣の家臣となった徳川家で康政も【小田原征伐】に参加。
家康の関東移封後は館林10万石(現・群馬県)を与えられ、堤防や街道の整備に尽力しました。
館林は東北へ続く交通の要衝とも言える地点ですので、この辺も文武兼ね備えた感がありますね。
※続きは【次のページへ】をclick!