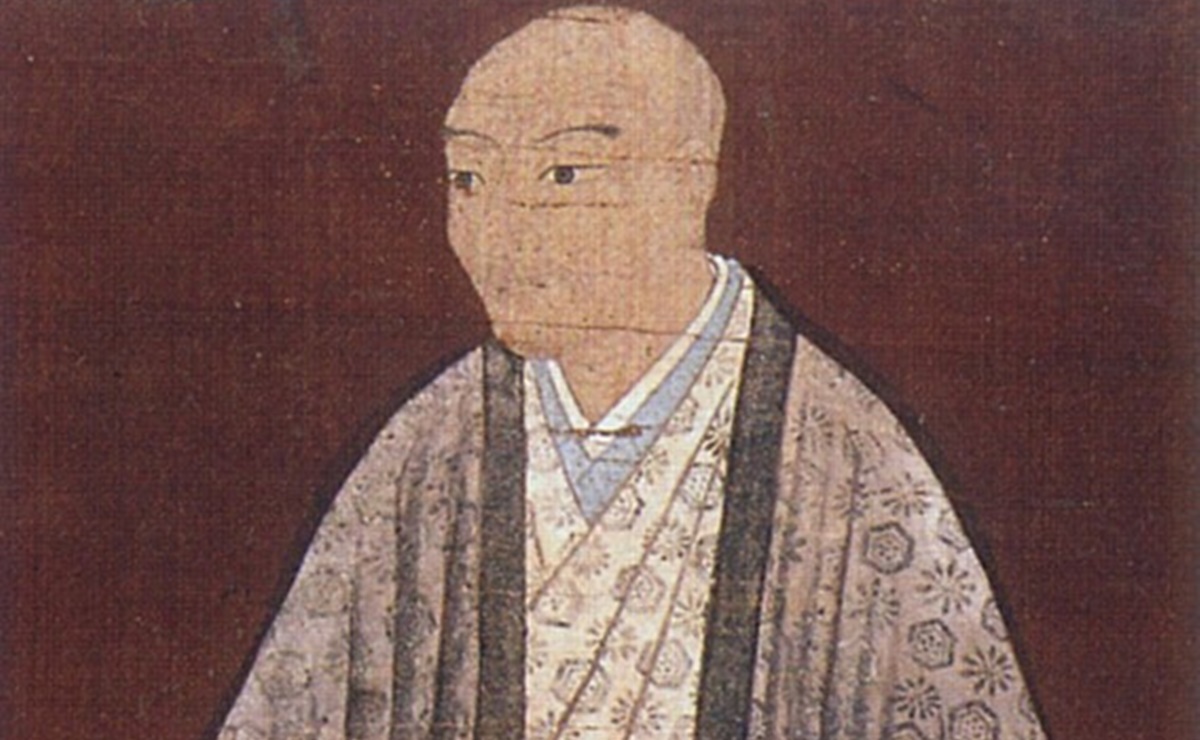慶長8年(1603年)2月13日は生駒親正の命日です。
織田信長と関係が深いとされながら織田政権では大して重んじられず。
しかし秀吉には気に入られ、豊臣政権では【三中老】と呼ばれるほどに出世を果たす。
それでもなお大半の方にピンと来て貰えないのは、何と言っても地味な存在だからでしょう。
いったい生駒親正とはどんな戦国武将で、どんな生涯を送ったのか?

生駒親正/wikipediaより引用
実は最終的に17万石の大名ともなった、その生涯を振り返ってみましょう。
信長と親族の可能性は?
生駒親正は大永六年(1526年)、美濃の土田という土地に生まれました。
血筋としては信長の実母である土田御前や、信長の側室とも囁かれる生駒氏の縁者だという説があります。
しかし実際は、織田氏の主流である岩倉織田氏(織田伊勢守家)や清洲織田氏(織田大和守家)に近い立場でした。
信長がこの二つを滅ぼして自分の家である勝幡織田氏(織田弾正忠家)を主流にしたのですが、それは親正が30代になってからの話。

織田信長/wikipediaより引用
こうした経緯もあってなのか。生駒親正は信長に仕えるのが遅くなりました。
下剋上はよそのことなら「ふーん」で済む話ですが、自分の主筋がされた側となると、気分が良くありませんもんね。
なんだかんだで織田家に仕えたのは永禄九年(1566年)のことでした。
親交のあった蜂須賀正勝のツテだったそうで、正勝が秀吉に親正を紹介し、秀吉が信長に仲介したのだとか。
蜂須賀正勝
↓
豊臣秀吉
↓
織田信長
という流れですね。

蜂須賀正勝/wikipediaより引用
信長時代の知行はわずか1000石のみ
生駒親正が織田家に仕えた時期は、悪くはないタイミングでした。
というのも信長にしても、有力な縁者が喉から手が出るほど欲しい状況だったからです。
当時の織田家親族の状況をざっくりまとめると、以下の通り。
◆父方の叔父(父・信秀の弟)
→討死や病死(突然死)や出奔でアテにしようがない
◆信長の兄弟
→庶兄の信広はいるが、長弟・信勝は既に粛清済み、その下の弟たちは若すぎて心もとない
◆舅の斎藤道三
→長良川で既に討死
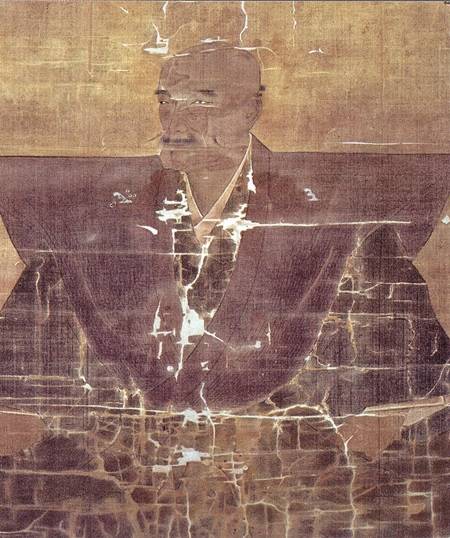
斎藤道三/wikipediaより引用
こんな感じで、非常に立場が脆い。
となると、近しい立場であるはずの親正は願ったり叶ったりだったはずなのですが……なぜか信長には厚遇されていません。
あくまで秀吉の寄騎(与力)として扱われ、1000石しか与えられなかったのです。
理由を考えてみますと……。
実際は、母方と信長の関係は希薄だったか、あるいは何の縁もなかったか。
親正がアピールしなかったのか。
そもそも当人の能力が劣っていると信長に判断されたのか。
理由は不明ながら、信長時代の親正はそれ以上出世することはありませんでした。
秀吉に認められ国持ち大名へ
信長からは特に目をかけられた形跡のない生駒親正。
秀吉の寄騎としては忠実に働いていたようです。
長篠の戦いや雑賀討伐などに参戦し、天正10年(1582年)6月【本能寺の変】が起きてからも、山崎の戦いなどをはじめ秀吉に従っています。
信長の親族として厚遇されていたら、本能寺の変前後で明智方に狙われていたかもしれない――そう考えると秀吉のもとにいて良かったですよね。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
そんな秀吉も、間近で見ていた親正には一定の評価を与えていたのでしょう。
天正十三年(1585年)には近江高島2万石と従五位下・雅楽頭の官位を与えます。
そして翌天正十四年(1586年)には伊勢神戸で4万石、さらには播磨赤穂へ転封の上に加増で6万石となり、どんどん出世していきました。
また、天正十五年(1587年)、仙石秀久が九州征伐の先陣で味方に大損害を出した上に逃亡した罪を問われて改易になると、秀久の領地だった讃岐が親正に与えられ、一気に17万石の国持ち大名となるのです。
当時の讃岐には本拠にできるような城がなかったため、天正十六年(1588年)から高松城の普請を始め、2年後に完成させています。
この高松城がなかなか面白いのです。
※続きは【次のページへ】をclick!