天明三年(1783年)7月3日は、諏訪藩の家老・諏訪頼保(よりやす)が切腹した日です。
諏訪藩のお家騒動である【二の丸騒動】当事者の一人。
お家騒動というと、跡継ぎ候補と、それぞれ派閥を組んだ家臣団のトラブルをイメージをしがちですよね。
しかし今回の場合は
・嫉妬心だけは人一倍の悪辣家臣→諏訪頼保
・無能すぎる殿様→諏訪忠厚
が揃ってしまったために起きた、本当に”騒動”という感じのドタバタ劇。
現代の会社や組織でも実はよく起きていることかもしれない、ムカッとする話ですが、最終的にはスカッとする(かもしれない)。
そんな二の丸騒動の顛末を振り返ってみましょう。
※大河ドラマ『べらぼう』で宮沢氷魚さん演じる田沼意知が、矢本悠馬さん演じる佐野政言に斬られて亡くなるのが天明4年(1784年)ですので、その前年にも切腹沙汰の事件が起きていたんですね
諏訪氏とは?
諏訪藩主の諏訪氏は、少年マンガ『逃げ上手の若君』の前半で目立ちまくっていた諏訪大社の大祝(おおはふり・同社のトップ)・諏訪頼重の子孫にあたる家です。
諏訪氏は【中先代の乱】で北条氏の生き残り・北条時行に味方して敗北。
室町時代初期の非常に厳しい時期をどうにか生き延びながら、続く戦国時代でもかなりキツい局面に立たされます。
隣国の甲斐武田氏に攻められ、当主の諏訪頼重(同名の別人)が滅ぼされてしまったのです。
その娘・諏訪御料人が武田信玄の側室となり、

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用
武田勝頼を産んだのはよく知られた話ですね。
その後も織田信長(総大将は織田信忠)による武田征伐の際に諏訪大社を焼かれるなど、散々な目に遭ってきました。
諏訪大社の主祭神・タケミナカタも国譲り神話でタケミカヅチと取っ組み合いをして負けたがために大人しくせざるを得なくなった……とされていますので、御祭神と同じような経緯を辿っていたんですね。
しかし【本能寺の変】で状況は一変。
信濃と甲斐の諸勢力が混乱に巻き込まれる最中、徳川家康に従うと、江戸時代には地位を認められて諏訪藩(高島藩)主となりました。
なお、本拠の高島城は諏訪湖の畔、諏訪大社の上社・下社の中間のような位置にあります。
二の丸騒動の背景
二の丸騒動が起きたときの藩主は六代・諏訪忠厚です。
騒動に至る遠因が少し前の時代にありますので、そこから確認しておきますと、約半世紀前、忠厚の祖父に諏訪頼篤(よりあつ)という人がいました。
頼篤は諏訪氏の一族ではありますが、いわゆる分家筋。
もともとは大名ではなく江戸で旗本をやっていました。

小姓組頭や江戸北町奉行を歴任した頼篤は、最終的に1,500石取りという中々の出世を果たし、92歳で大往生を遂げています。
文字通り「地味にコツコツ」やって大成したタイプですね。
この諏訪頼篤の次男が諏訪忠林(ただとき)といい、当時の諏訪藩主・諏訪忠虎の実子が早世したため、18歳のときに忠林が諏訪藩主家に養子入りして跡継ぎとなりました。
忠林は生来病弱で、養子になった後は、領内の政治より学問をやりたがるタイプの人でした。
なぜ、もっと早い段階から、こうした適性を見極めなかったのか。
忠林が養子になって忠虎が亡くなるまで10年もの月日があり、その間に藩主としての心得を教育するとか、しっかりした家臣をつけるとか、色々と方法はあったはずです。
忠虎も学者肌だったらしいので、「これでよし」と思ってしまったのでしょうか。
同時期に、江戸藩邸が焼失したり、元禄大地震で藩の財政が苦しくなっていたため、養子の教育に目が行き届かなかったなんてことは……。
ともかく享保十六年(1731年)に忠林が諏訪藩主となり、宝暦十三年(1763年)にその後を継いだのが二の丸騒動の当事者となる諏訪忠厚でした。
家老の対立
諏訪忠厚は、当初から政治に無関心な人物でした。
実務のほとんどを筆頭家老・千野貞亮(ちの さだすけ)が行っていたとされます。
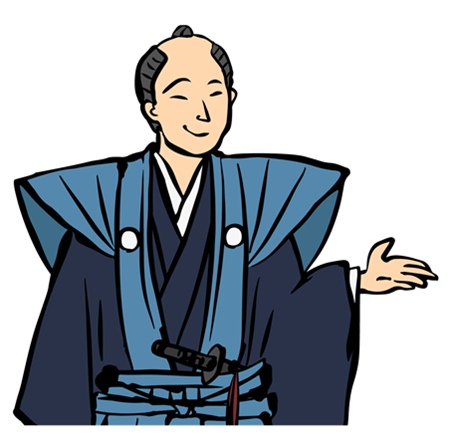
千野家は、別名を「三の丸家」ともいい、鎌倉時代から諏訪氏に仕えてきた文字通り譜代の臣。
貞亮もその誇りにかけて、知恵を絞って働いていたのでしょう。
生糸や繭に重税を課し、財政もほんの少しだけ向上しました。
しかし、貞亮が実績を上げたことを、諏訪氏の流れを引くもう一人の家老・諏訪頼保(よりやす)は懸念していました。
こちらは「二の丸家」と呼ばれていた家柄で、三の丸家とは知行も同じで、まさに双璧といった立ち位置。
だからこそ余計にライバル意識があったのでしょう。
騒動の名称は、この“二の丸家”からきています。
貞亮が実績を作ったことに対し、頼保は「このままでは、藩政を千野家に牛耳られてしまう」と、ズレた危機感を抱くのです。

それなら頼保も何か策を講じて、藩財政がちょっとでも良くなるように働いて認めてもらえばいいはずなのですが、そうならないのがお家騒動というものですね。
本当に「おまえもか!」とツッコミたくなるぐらい、後ろ向きな理由から起きているお家騒動だらけ。
まぁ、現代社会でも、無能な会社員ほどゴマすりと社内政治力を駆使しがちというのは、人間の本性かもしれませんね。
むろん、出来るリーダーが上に立てばそんなことないのでしょうが……ともかく頼保は、貞亮を陥れるため一計を案じるのです。
※続きは【次のページへ】をclick!
