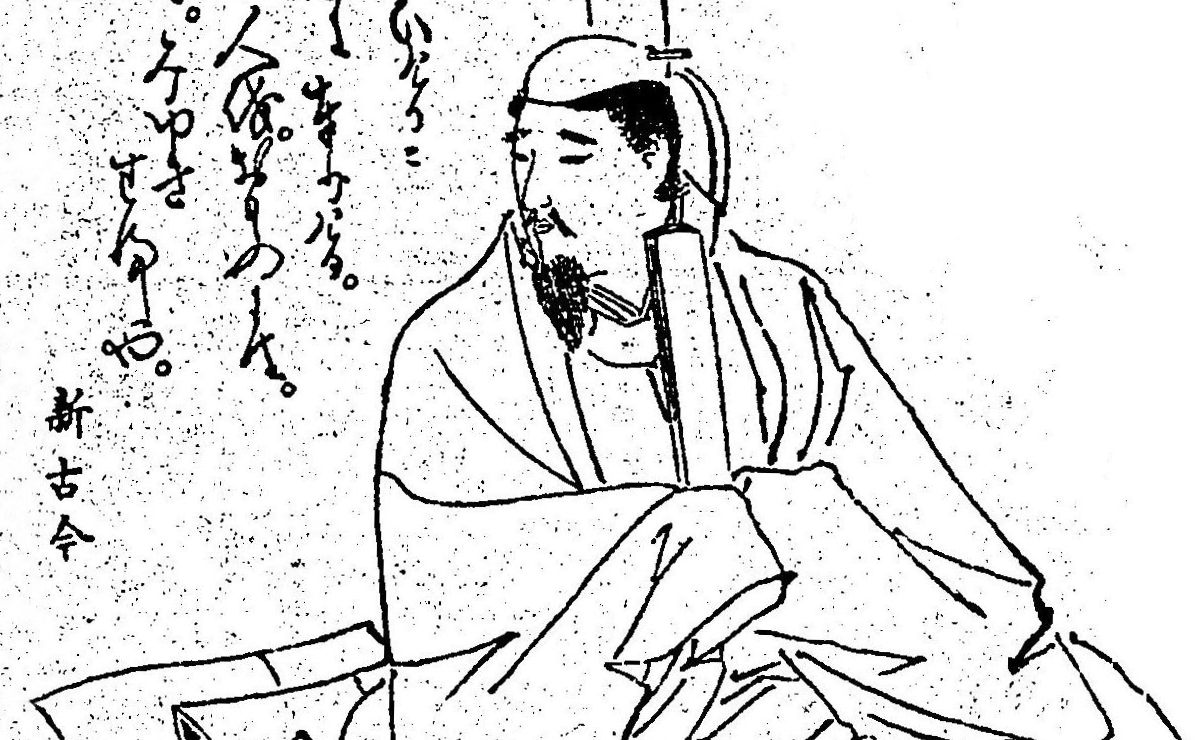正暦四年(993年)7月29日は、源雅信(まさざね)が亡くなった日です。
以前だったら「誰それ?」と答える方が大半だったでしょう。大河ドラマ『光る君へ』で益岡徹さん演じたことで一気に知られるようになりましたね。
といっても、本人の活躍が華々しかったわけではなく、黒木華さん演じる娘の源倫子が藤原道長に嫁いだからで……。
史実における源雅信は、宇多天皇の孫(敦実親王の三男)で、宇多源氏の祖とされる人。
藤原家に対抗するように公家として出世を重ねた方であり、「単なる道長の岳父」で終わるような人物でもありません。
では実際、本人はどんな生涯を辿っていたのか?
史実の源雅信を振り返ってみましょう。

源雅信/wikipediaより引用
「仕事中は仕事の話しかしないカタブツ」
源雅信の生まれは延喜二十年(920年)。
その後、承平六年(936年)の16歳時に臣籍降下しているため、武家というより公家に入ります(彼の子孫には武士になった人もいます)。
父は敦実親王で琵琶の名手でした。
そんな芸術の才能は雅信にも伝わったのか。
音楽はじめ、朗詠、和歌、蹴鞠など、当時の貴族の教養は一通り得意としておりました。
ただし、若い頃は村上天皇に「仕事中は仕事の話しかしないカタブツ」と言われるくらいまじめな人で、あまり好かれていなかったようです。

村上天皇/wikipediaより引用
それはそれで美点のような気がしますが、村上天皇も音楽や和歌を好んでいたので、そういった話をしながら楽しく政務をしたかったのでしょうか。
雅信は、出自が出自ですので、臣下になってからも順調に昇進を重ねていました。
円融天皇が安和二年(969年)に即位すると、その信任を得て出世スピードが倍増。
安和二年(969年)~貞元三年(978年)の9年間で左大臣にまで昇進し、亡くなるまでその位にあったのです。
また、弟の源重信(しげのぶ)も正暦二年(991年)に右大臣となり、兄弟で文字通り左右を固めました。
藤原家の権力争いが激化して
このとき世の中は、藤原氏が後宮政治に乗り出していた時代です。
源雅信が左大臣になったとき、それまで左大臣と関白を兼ねていた藤原頼忠が太政大臣、藤原兼家が右大臣となりました。
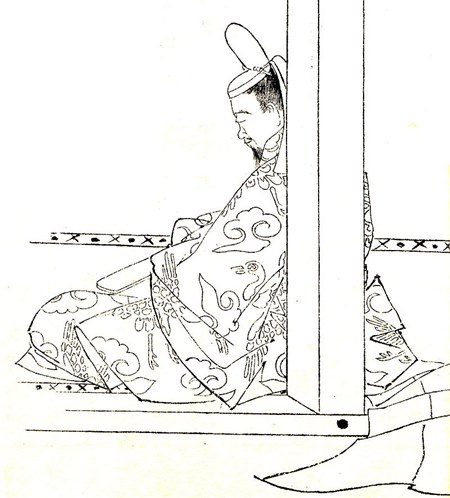
藤原兼家/wikipediaより引用
頼忠は歌人として有名な藤原公任の父、兼家は藤原道長の父です。
二人は後宮に娘を送り込んだり、表の政治でも争いを繰り広げていました。
円融天皇は、こうした藤原氏による政争と政治の私物化に歯止めをかけようと、雅信の官位を上げて対抗させようとしたのです。
雅信は円融天皇時代の皇太子だった花山天皇の傅役も務めており、円融天皇の悲願がうかがえます。
源氏物語に詳しい方ならご存知かと思いますが、右の藤原家・左の藤原家と光源氏、(作中の)冷泉天皇の関係ですね。
円融天皇と雅信、雅信と花山天皇は親子じゃありませんが、その辺は事実そっくりにしてしまうとマズイですから、紫式部が物語に仕立てる中で調整したのでしょう。
円融天皇が譲位して花山天皇が即位した後も、なにかと雅信を頼りにし、頼忠を遠ざけようとしています。
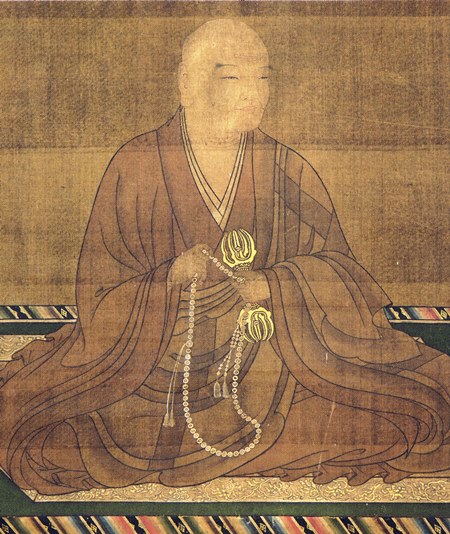
花山天皇/wikipediaより引用
そのため頼忠がそのうち政務への積極的関与をやめ、別系統の藤原氏で花山天皇の叔父である藤原義懐(よしちか)が台頭してきました。
65歳の高齢を過ぎてもなお働いて
源雅信は寛和元年(985年)あたりから足腰の不調を訴えるようになっていました。
が、それでもまじめに仕事をしており、大きなミスもなかったようです。
65歳というと、この時代ではかなりの高齢ですし、無理もないですよね。仕事をしていたことで張り合いが出て、より長寿を保てたのかもしれません。
さらに時は流れ、円融天皇の子である一条天皇が即位します。
一条天皇の生母が兼家の娘だったため、今度は兼家が摂政として影響力を強めました。
しかし、雅信は引き続き皇太子の傅役を務めて、権力を保っていたので、兼家にとっては目の上のたんこぶのような存在。
しかも雅信に手落ちがなく、政治的に失脚させることも難しかったため、さぞや歯噛みしていたと思われます。
兼家は悪あがきとして、左大臣の雅信より下の右大臣という地位から降りて摂政になり、「雅信の下じゃありません!」アピールをしましたが、大した影響はなし。
そりゃあ後宮政治を狙う気満々の藤原氏と、臣籍降下したとはいえ確実に皇室の血を引いている生真面目マンとじゃあ、世間も皇室も他の貴族も後者を信用しますよね。
※続きは【次のページへ】をclick!