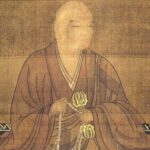こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【藤原為時】
をクリックお願いします。
越後で息子の惟規に先立たれ
越前守となった藤原為時は、紫式部を連れて現地へ赴きました。
その間、為時と同世代だったとされる藤原宣孝が紫式部に熱心な恋文を送り、結婚することになります。

藤原宣孝(栗原信充画)/wikipediaより引用
ただ、それに対して為時がどう思ったか?という記録は乏しく、想像の域を出ません。
大河ドラマのように「戸惑いつつも認める」というのが実際の流れに近かったのでしょうか。
越前守の任期が終わった後はまた官職から離れ、寛弘六年(1009年)に左少弁・蔵人として復帰。
寛弘八年(1011年)には越後守となり、息子の藤原惟規を連れて行ったようです。
残念ながら、惟規は間もなく越後で亡くなってしまいます。
-

藤原惟規(紫式部の弟)は実際どれほど出世できた?本当はモテる男だったのか
続きを見る
惟規は旅の途中で体調を崩していたのか。こんな歌を残しました。
逢坂の 関うち越ゆる ほどもなく 今朝は都の 人ぞ恋しき
【意訳】逢坂の関を越えてまだほどないのに、今朝はなんだか都の人々が恋しく思えます
宛先は源為善という人です。
政治の表舞台に出てくる方ではありませんが、『後拾遺和歌集』などには採られていますので、歌人として名を残した方ですね。
為善からの返事が越後へ届いたのは、既に惟規が亡くなった後だったため、父である藤原為時から丁寧な書面が届けられたとか。
子を喪ったばかりの為時も、手紙で友人の死を知った為善も切なかったでしょうね……。
悲しすぎる四首の歌とは
その後、藤原為時は長和三年(1014年)6月に越後守を辞職し、帰京しました。
「この直前に紫式部が亡くなったからではないか?」ともされていますが、『小右記』では紫式部と思われる女房が(1019年)に登場するため、定かではありません。
前述の通り為時の生没年は不明です。
おそらく950年代辺りの生まれかと思われますので、雪国での職務に心身が耐えられなくなったのかもしれません。
為時は、長和五年(1016年)4月29日に三井寺で出家した後、寛仁二年(1018年)に藤原頼通邸の屏風に詩を献じたのを最後に、記録から消え、その後、いつ亡くなったのかは不明です。
為時の和歌は4首しか伝わっていないため、まとめてご紹介しましょう。
おくれても 咲くべき花は 咲きにけり 身を限りとも 思ひけるかな
【意訳】咲き遅れたとしても、咲くべき花は咲く。私ももう出世することはないと思っていたが、そうでもなかったようだ
これは藤原道兼が「栗田右大臣」と呼ばれていた頃、散りゆく花の季節に詠んだものとされています。
為時本人も、そして紫式部も人生の後半に入ってから花開いたタイプですので、こういった感慨があったことでしょう。
いかにせん かけても今は 頼まじと 思ふにいとど 濡るる袂を
【意訳】今はもうあなたの気持ちを期待できないと理解してはいますが、涙で袂を濡らすのを抑えられません
為時と文通していた女性が他の男性になびいてしまったという噂を聞いて、その女性に送ったとされています。
その後どうなったのかは残念ながら不明です。切ない恋歌ですね。
われひとり ながむと思ひし 山里に 思ふ事なき 月もすみけり
【意訳】私一人だけが眺めていると思っていた山里だが、思い悩むことなどない月も共にあった
詞書がないため、詠んだ状況がわからないのですが、強く寂寥感が漂いますね。
もしかすると惟規や紫式部に先立たれた後の歌なのかもしれません。
山の端を 出でがてにする 月待つと 寝ぬ夜のいたく ふけにけるかな
【意訳】山の端から出られずにいる月を待ちながら過ごしていると、夜が深く更けてしまった
こちらも題知らずの歌のため、どういったシチュエーションや心境で詠まれた歌なのか伝わっていません。
何か吉報が来るのを待ち遠しく思っているような雰囲気ですね。
越前守になれるかどうか――そんなタイミングでしょうかね。
★
為時はこれまであまり着目されることがなかった人物です。
それが大河ドラマ『光る君へ』で岸谷五朗さんが演じることにより、一気に注目度が上がりました。
不器用な学者肌として、同じく不器用な娘を立派に育て上げ、そして孫となる大弐三位にとっては良き爺としてその育成に携わる。
地味で堅物なれど真摯に生きた中級貴族の姿は、我々視聴者の心に残る存在となったはずです。
あわせて読みたい関連記事
-

藤原惟規(紫式部の弟)は実際どれほど出世できた?本当はモテる男だったのか
続きを見る
-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは
続きを見る
-

藤原宣孝は妻の紫式部とどんな関係を築いていたか~大弐三位は実の娘だった?
続きを見る
-

花山天皇の生涯|隆家との因縁バチバチな関係で喧嘩も辞さない破天荒
続きを見る
-

骨肉の権力争いを続けた藤原兼家62年の生涯~執拗なまでにこだわった関白の座
続きを見る
-

藤原義懐はなぜ花山天皇と共に出家へ追い込まれた? 何か策は無かったのか?
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
国史大辞典
日本人名大辞典
後拾遺和歌集
新古今和歌集
他