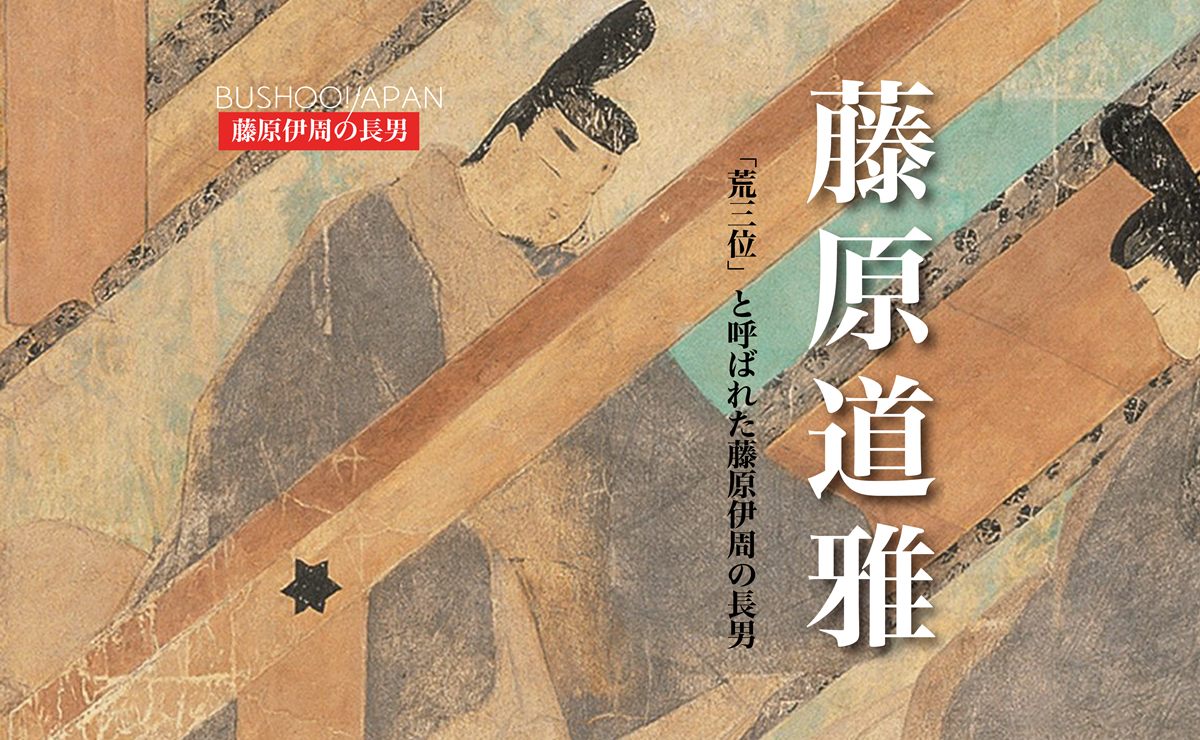大河ドラマ『光る君へ』で三浦翔平さんが演じ、悪い意味で注目された藤原伊周。
その息子である藤原道雅(みちまさ)が第34回放送でクローズアップされ、父親に対する不穏な空気が描かれました。
一体なぜあのような描写になるのか?
というと実は本人も「荒三位(あらさんみ・乱暴者の従三位という意味)」というキツ目のあだ名を持っており、なかなか興味深い存在だったのです。
しかし同時に「乱暴者という評価だけが正しいのか?」という疑問も湧いてきます。
なんせ父の伊周が周囲に疎んじられ、やたらと騒動を起こし、息子としては居場所がない思いだったでしょうし、三条天皇の娘・当子内親王との仲も悲恋に終わり、絶望感から詠まれた歌は「百人一首」に収められました。
いったい藤原道雅とはどんな人物だったのか?
天喜2年(1054年)7月20日はその命日。本記事で生涯を振り返ってみましょう。
幼い頃は可愛がられていた
藤原道雅が生まれたのは正暦三年(992年)。
父は前述のとおり藤原伊周であり、母は嫡妻である源重光の娘でした。
当時、伊周の生まれた中関白家は、いわゆる絶頂期です。
道雅にとっては叔母にあたる藤原定子が一条天皇の中宮として寵愛され、あとは皇子の誕生を待つばかり……といった時期。
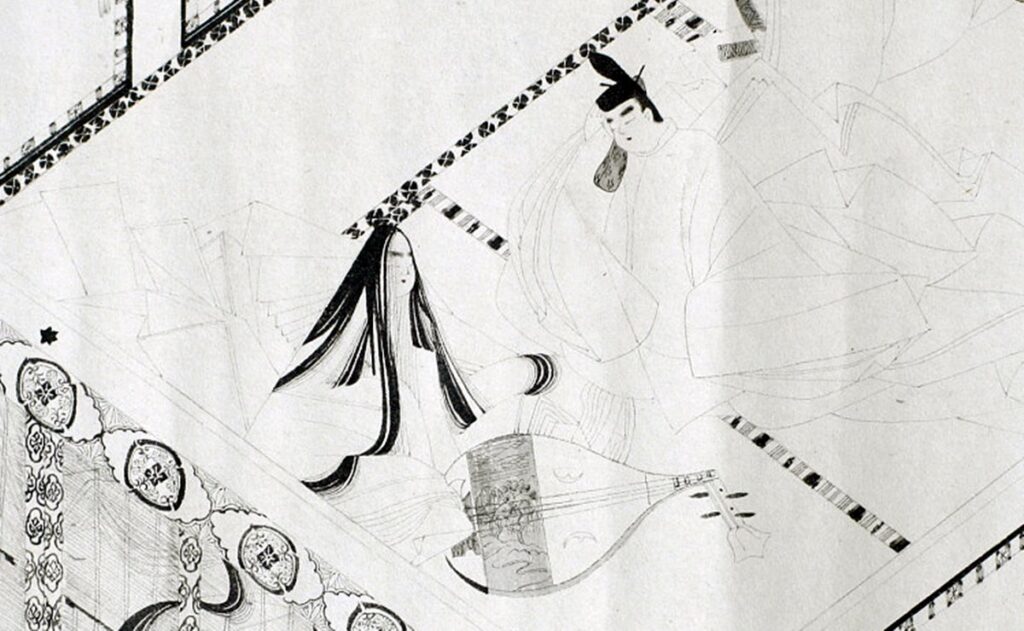
枕草子絵詞/wikipediaより引用
幼い頃の道雅(幼名:松君)も定子の御殿に連れて行ってもらったことがあり、その様子は枕草子にも描かれています。
このとき祖父の藤原道隆が、松君を指しながら
「中宮様のお子と言ってもいいくらい可愛らしいのに(なぜ中宮にはまだ子供が授からないのだろう)」
と発言し、定子が居心地悪そうにしています。
子供の催促だなんて誰が見ても気分の良いものではありませんし、ドラマでも酷い有り様として井浦新さんが熱演されていましたね。
ちなみにこの段では、直後に一条天皇が定子を訪れ「昼間から子作りに励む」という凄まじい流れが伝えられています。
もちろん道隆や清少納言をはじめとした女房たちは席を外していますし、当時の建物の作りや宮廷生活を考えると、昼間であろうと夜であろうと他者にそういう状況が感づかれるのは変わらないと思われますが……現代人からすると「えっ!?」となる場面ですよね。
実際、こちらの場面もドラマで流され、SNSなどでは大いに話題になっていました。
父・伊周のとばっちりで暗雲が垂れ込める
そうした微妙な雰囲気の中で育っていった松君こと藤原道雅。
しばらくは道隆の威光で父の藤原伊周もガンガン昇進しますが、天狗になりすぎたしか、やがて周囲の貴族だけでなく一条天皇からも不興を買うようになってしまいます。
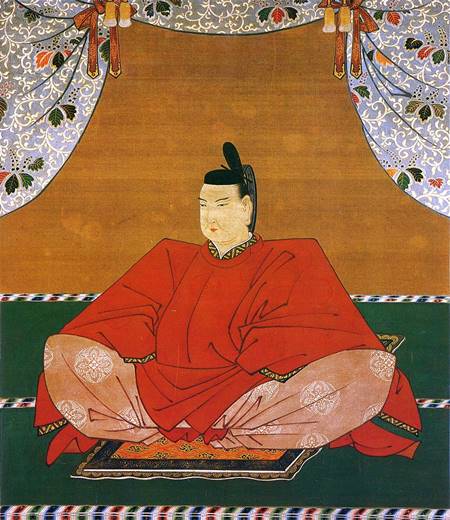
一条天皇/wikipediaより引用
決定的なことが起きるのは長徳元年(995年)以降のことです。
この年に道隆が糖尿病らしき病で亡くなると、その後を継いで関白になっていた藤原道兼も流行病で病死。
政治を主導できそうな人物が道長と伊周に絞られ、激しく火花を散らしながら、一条天皇の生母・藤原詮子(東三条院)がバックにいる道長がやや有利といった状況へ。
そして長徳二年(996年)に事件が起きます。
【長徳の変】です。
ドラマでも報じられたように、勘違いから花山院へ向けて藤原隆家が矢を放ってしまい、伊周と二人で流罪同様の処置が断行されました。
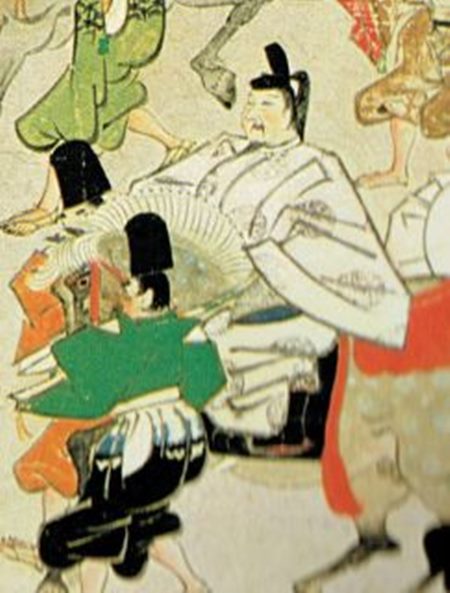
藤原伊周/wikipediaより引用
この件は「定子が自ら髪を下ろした」とか、「母の高階貴子が流罪になる伊周の車に取りすがった」とか、そのへんの話がクローズアップされがちです。
しかし、最も悪影響を受けてしまったのは、次代を担う藤原道雅といっても過言ではないでしょう。
伊周が品行方正でさえあれば、定子が皇子を産み次第、中関白家が盤石の地位を保てる可能性が高まったのですから。
それが、以前から伊周が貴族たちの反感を買っていた上に、長徳の変でどうしようもない状態になってしまったわけです。
道雅がどれだけ努力しても、もはや立場をひっくり返すのは至難の業。
しかも伊周は長徳三年(997年)に罪を許されてからも、自分の立場をわきまえようとしませんでした。
道雅の話から少々それますが、彼の背景を理解するために必要ですので、当時の状況をここで簡単にまとめましょう。
長徳二年(996年) 定子が最初の女児・脩子内親王を出産
長徳三年(997年) 伊周が罪を許されて帰京
長保元年(999年) 定子が第一皇子となる敦康親王を出産/同じ日に彰子が入内する
長保二年(1001年) 定子が媄子内親王を出産しながら翌日に産褥死
寛弘五年(1008年) 彰子が敦成親王(のちの後一条天皇)を出産
寛弘六年(1009年) 彰子が敦良親王(のちの後朱雀天皇)を出産
定子は、一男二女をもうけながら亡くなってしまい、一方で彰子が立て続けに皇子に恵まれたのです。
ただでさえ立場が弱まっていた伊周ら中関白家が再浮上する見込みは、これでほとんどなくなってしまいました。
しかも藤原伊周は、さらに不祥事を重ねます。
※続きは【次のページへ】をclick!