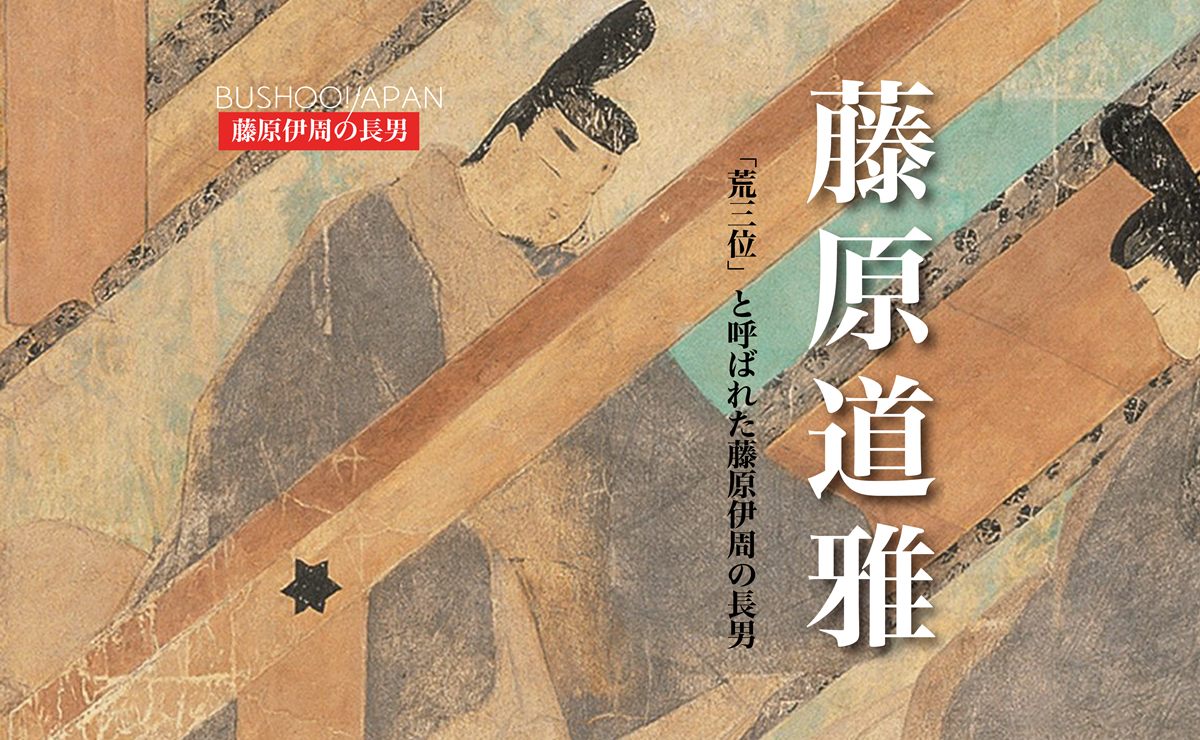こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【藤原道雅】
をクリックお願いします。
内親王との悲恋
藤原道雅と当子内親王との恋は、どのような道筋を辿ったのか。
藤原行成の日記『権記』などの記述によれば、
長和五年(1016年)9月:三条天皇の譲位により、当子内親王が斎宮の任を終えて帰京
日付不明:当子内親王の乳母が道雅を手引
寛仁元年(1017年)4月10日:密通が世間にバレる
4月11日:三条上皇にこの件が報告される
4月21~24日:三条上皇病悩
27日:三条上皇病悩
28日:三条上皇危篤
29日:三条上皇出家
5月7~8日:三条上皇病悩
5月9日:三条院崩御
という流れで、あれよあれよという間に三条天皇が崩御してしまうのです。
「斎宮の任期中ならばお怒りもごもっともだが、既に務めを果たされて帰ってきた後なのだから、問題ないのでは?」
世間ではそんな声もありましたし、おそらく内親王の周囲の人々もそう思っていたのでしょう。
しかし、前述の通り三条上皇は二人の仲を許しませんでした。
将来性などの問題からか、それとも「内親王は基本的に生涯未婚」という原則にそぐわないからか、真実は不明。
当子内親王を母后・藤原娍子のもとに引き取らせ、道雅が通ってこられないようにしてしまうのです。
ちなみに、娍子は遡ること13年前、寛弘元年(1004年)に、敦道親王(三条天皇の同母弟)の正妻であった妹を引き取っています。
これは敦道親王が和泉式部を邸に住まわせ、正妻を怒らせてしまったことによります。
娍子も有力な後ろ盾がないために苦労していましたが、その周囲でもなかなか難儀な立場の女性が多かったようです。
こうして愛する人に会えなくなり、道雅が詠んだのが、百人一首にも採られている以下の歌です。
今はただ 思い絶えなん とばかりを 人づてならで いふよしもがな
【意訳】人づてではなく、せめて最後に直接お会いしてお別れを申し上げたい。それだけなのにどうしようもありません
平易な分、道雅の心情がそのまま表れていますね……。
良くも悪くも情が濃い中関白家の人らしい詠みぶり、といえるでしょうか。
『後拾遺和歌集』に収められているのですが、実は前に二首、後に一首道雅の歌があります。
現代使われている通し番号と共に見ておきましょう。
◆00748
逢坂は 東路とこそ 聞きしかど 心づくしの 関にぞありける
【意訳】逢坂の関は東=吾妻に会いに行くための関所だと聞いたが、私にとっては心が尽きる=筑紫の関のような場所だ
◆00749
さかき葉の ゆふしでかけし その神に おしかへしても 似たるころかな
【意訳】あの方が榊葉の木綿四手(ゆうしで)に囲まれていた斎宮の頃のように、今はもう手が届かなくなってしまった
◆00750が「今はただ~」
◆00751
みちのくの 緒絶(おだえ)の橋や これならむ ふみみふますみ 心まどはす
【意訳】陸奥の緒絶の橋とはきっとこのようなものなのだろう。あの方からの文が来たり来なかったり、その度に橋の先へ踏み出そうかどうか心が惑う
四首とも当子内親王への強い愛情が感じられて、読み手としても切なくなりますね……。
「内親王との禁断の恋」というと、『源氏物語』の柏木と女三の宮を想起した方もいらっしゃるでしょうか。
・優等生が恋に狂った感のある柏木
・普段乱暴だけれども恋人には真摯だったらしき道雅
そんな違いがありますけれども、著者の紫式部がこの事件の頃も存命だった可能性が高いので、何か思うところがあったのかもしれません。
この件をモデルにして柏木と女三の宮の話が書かれたかどうか?というのは『源氏物語』の執筆ペースや順番がわからないのでなんともいいがたいところです。
壮年になっても一悶着起こす
一方、最高権力者である藤原道長としては、この恋の件をあまり気にしていなかったと思われます。
およそ半年後の寛仁元年(1017年)9月22日に、道長が石清水八幡宮を参詣した際、道雅が騎馬でお供しているのです。

『紫式部日記絵巻』の藤原道長/wikipediaより引用
翌寛仁二年(1018年)3月25日に、後一条天皇が道長の娘・藤原威子のもとを訪れる際にも、お供の一人として道雅がいたことがわかっています。
道長にしてみれば「既に中関白家は政敵になり得ない」と判断していたのでしょう。
しかし、道雅は万寿三年(1026年)に降格され、いよいよ荒んでしまいます。
万寿四年(1027年)7月18日、自らの名を落とす事件を起こしてしまうのです。
この日、道雅は高階順業という貴族の家で賭博をしていました。
他に誰かいたかどうか、詳細はわかっていませんが、道雅と順業の二人だけだった場合は、双六に興じていたのかもしれません。当時の双六は賭け事にもよく使われたためです。
順業は名字からして、おそらく道雅の祖母・高階貴子の親族でしょう。
賭け事にはよくあることで、二人は次第に「口角泡を飛ばす」感じになってしまったようです。
そして順業の乳母父にあたる惟宗兼任という人物が登場。
兼任は順業に助太刀しようとしてか、道雅の袖に掴みかかって引き破りました。
これによりさらに頭に血が上った道雅!
兼任と派手な殴り合いを始めてしまうのです――。
両者とも周りが見えなくなっていたのか、いつの間にか順業の屋敷から道端に出てしまい、その場に居合わせた庶民たちが見物するほどの大騒ぎへ発展。
冒頭で述べた通り、道雅は正暦三年(992年)生まれなので、この大ゲンカの時点で数え36歳です。
30~40代で亡くなる者も珍しくない時代に元気すぎというか、落ち着き無さすぎというか、大人げないというか。
こんな感じですっかりシャレにならない乱暴者になってしまった道雅は、
「荒三位」とか「悪三位」
とあだ名され、すっかり面倒な人扱いされてしまうようになります。
かつての恋人・当子内親王は治安二年(1022年)に薨去していましたので、この悪名が彼女に届かなかったことは不幸中の幸いと言えましょうか……。
晩年は和歌に生きる
一方で藤原道雅は、父・伊周の才能を受け継いだのか、和歌を愛する面もありました。
寛徳元年(1044年)夏と、永承二年(1047年)に八条の山荘で歌会を開催。
寛徳二年(1045年)には左京大夫に復帰しましたが、出世や現世への執着がなくなっていたようで、その後、この山荘を本邸にし、歌人たちとの社交に徹していたと伝わります。
もはや世捨て人のようになっていたのですね。
そして、亡くなったのは天喜二年(1054年)7月20日のこと。
当子内親王との大恋愛からは、実に27年の歳月が経過していました。
長徳の変が起こらなかったら……もしくは当子内親王との恋が実っていれば……これほど道雅が荒れることはなかったのではないでしょうか。
生まれながらに荒っぽい性格であれば、当子内親王との恋の前にそうした逸話があっても不思議ではありません。
単なる乱暴者に内親王がなびいたり、乳母が味方するというのも考えにくいです。
となると、やはり道勝の根っこには、純情さや真面目さがあったのではないでしょうか。
ちょっと贔屓しすぎですかね。
あわせて読みたい関連記事
-

史実の藤原伊周は長徳の変で左遷され その後どのような生涯を過ごしたのか
続きを見る
-

藤原定子が最期に残した辞世の句の意味は?一条天皇に愛され一族に翻弄された生涯
続きを見る
-

なぜ藤原道隆は次代の伊周へ権力を移譲できなかったのか「中関白家」の迷走
続きを見る
-

政争に敗れた藤原隆家が異国の賊を撃退!天下のさがな者と呼ばれた貴族の生涯
続きを見る
-

史実の一条天皇はどんな人物だった?彰子や道長とはどんな関係を築いていたのか
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
繁田信一『平安貴族 嫉妬と寵愛の作法』(→amazon)
繁田信一『平安朝の事件簿 王朝びとの殺人・強盗・汚職』(→amazon)
繁田信一『殴り合う貴族たち』(→amazon)
藤原行成『権記』(→amazon)
国史大辞典
日本人名大辞典
ほか