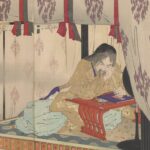こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【楠木正成】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
脇の甘すぎる後醍醐天皇や公家たち
楠木正成は、その後、北畠顕家と行動を共に転戦し、二月には摂津の打出浜合戦で足利軍を追撃して破りました。
尊氏たちは九州へ落ち延びていき、しばしの間、畿内には平和が訪れます。
後醍醐天皇や公家たちはこの戦果にすっかり満足してしまったらしく、顕家を東北へ帰してしまいました。
尊氏の再起を予測していた正成は、慌てて奏上します。
「義貞を討って尊氏と和睦するべきです! その使いは私が務めましょう」
しかし、すっかり安心しきっていた後醍醐天皇と公卿たちは受け入れなかった……という話もあります。
なぜ戦をできない者たちの意見が最重視されるのか。理不尽というほかないですが、それが「権威」の最大の欠点かもしれません。
ちなみに顕家は鎌倉近辺で尊氏から鎌倉を任されていた斯波家長により足止めを喰らい、その間に、正成最期の戦いとなる【湊川の戦い】が起きることになります。
湊川の最期
建武三年(1336年)春、尊氏は九州での兵力回復に成功し、海路で再び京都を目指してやってきました。
新田義貞は「尊氏の入京を阻止せよ」と命じられて西へ向かい、このとき赤松円心の白旗城を包囲しながら、円心に一杯食わされて時間をロスしてしまっています。
一方、後醍醐天皇は慌てて楠木正成を呼び、義貞と協力して兵庫で戦うよう命じました。
正成は逆に、そこでこんな戦術を提案します。
「義貞殿を京へ呼び戻し、陛下にはもう一度比叡山へ逃れていただいて、尊氏軍を市街に誘い込んで戦うべきです」
これが残念ながら却下。
正成は仕方なく討死覚悟で兵庫へ向かい、道中の桜井で嫡子・楠木正行と次男・楠木正時を地元へ帰しました。
別れる前、息子二人にはこう言いつけます。
「すぐに仇を取ろうなどとは考えず、充分心身を鍛えてから適切な時を待つように」
有名な【桜井の別れ】ですね。
正行はこの遺言を忠実に守り、後に南朝方の武将として大活躍することになります。
息子たちに別れを告げた正成は、その後、義貞と再会。
「一つも城を落とせておらず面目ない。このまま京まで引くことはできない」
義貞はそう言っていたそうで、さすがにバツが悪かったようです。
正成はそんな義貞を慰めつつ、戦に臨みます。
この二人、上で指揮を取る人がもっと軍事に長けていれば、もっと上手に協力できていたんじゃないですかね。
こうして湊川に布陣した二人。
途中で新田軍が足利方の細川軍を迎え撃つべく離れてしまい、尊氏本隊には楠木軍だけで応戦することになります。
楠木軍は果敢に戦いました。
16度もの突撃を敢行し、足利軍を突き崩した――まさに決死隊といったところで、想像するだけでも恐ろしいですね。
当然、損耗も激しく、一通り攻撃が済んだ後の楠木軍は76騎しか残っていなかったともされます。
当時の合戦では、騎兵一騎あたり2~3人の歩兵が従うのがセオリーだったことを考えても、最期まで正成に従った者は多くて300人程度だったことになるでしょうか。
「これまで」と悟った正成は、弟・楠木正季をはじめ一族郎党と共に近隣の民家にこもり、自害しました。
享年43という説がありますが、生年が不明なためあくまで推定。
息子の正行・正時がこの頃元服したばかりということを考えると、大きく離れてはいなさそうですね。
正成の首は尊氏軍に実検された上で六条河原に晒され、その後、妻子のもとへ届けられたといいます。
現代人からするとイヤミにも見えますが、これは尊氏が
「変わり果てた姿になっても、妻子は会いたかろう」
として命じたのだとか。当時の基準では慈悲深いということになっています。
ちなみに『太平記』には、この後の暦応五年=興国三年(1342年)に「正成が化けて出た」という話が出ています。
湊川の戦いに参加していた武士の一人・大森盛長のもとに怨霊と化した正成が現れ、盛長の持つ刀を奪おうとしたのだとか。
背後には護良親王や義貞だけでなく、源義経・平教経など源平時代の武士まで従えていたそうですから、いくらなんでも盛りすぎやろ。
怨霊の正成は、僧侶の読経で成仏したことになっています。

美女に扮した楠木正成の怨霊を背負う大森盛長/wikipediaより引用
忠臣の鑑なのか
楠木正成は、明治時代に入ると「最期まで帝に忠誠を尽くした」ことがクローズアップされ、忠臣の鑑と扱われるようになりました。
明治五年(1872年)には湊川の地に彼を祀る湊川神社と墓も建てられます。
さらに第二次世界大戦中には、やはり「忠臣の見本」としてプロパガンダに利用されましたが、正成にしてみれば、
「勝ち目の薄い戦いをするなら、もっと工夫を凝らさんかい!」
とでも言いたかったことでしょう。
歴史上の偉人は、盲目的に尊敬するのではなく、偉業を倣うべきですよね。
正成の幼名とされる「多聞丸」から名付けられた山口多聞は、確かにその名に恥じない軍人ですけれども……。
正成の足跡については『太平記』や『梅松論』などに頼る部分が多く、今後、新たな史料が発見された場合、全く違う人物像が浮かび上がってくる可能性も否定できません。
それも歴史の楽しみの一つですね。
あわせて読みたい関連記事
-

四条畷の戦いで楠木正行&正時兄弟が刺し違えて自刃~1人残された弟の正儀は?
続きを見る
-

北畠顕家~花将軍と呼ばれる文武両道の貴公子は東奔西走しながら21の若さで散る
続きを見る
-

後醍醐天皇の何がどう悪かった?そしてドタバタの南北朝動乱始まる
続きを見る
-

室町幕府樹立の功労者・足利直義の生涯~最期は兄・尊氏と衝突してからの不審死
続きを見る
-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様
続きを見る
-

史実の北条時行はどんな人物だった?漫画『逃げ上手の若君』のように戦い続けた?
続きを見る
-

建武の新政はあまりにお粗末「物狂いの沙汰=クレイジー」と公家からもディスられて
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
国史大辞典
生駒孝臣『楠木正成・正行 (シリーズ・実像に迫る6)』(→amazon)
榊山潤『新名将言行録 室町時代(講談社文庫)』(→amazon)
『新版 日本架空伝承人名事典』(→amazon)
日本大百科全書(ニッポニカ)
他