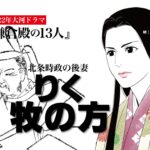こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【坂東武者の文化教養レベル】
をクリックお願いします。
スゲエ! 和歌ができるなんて謎の存在だよ!
中村獅童さんが扮する梶原景時は、頼朝に従った武将の中でも極めて賢い人物でした。
どのくらい賢いのか?
寒川町観光協会に素晴らしいまとめがありました。
◆梶原景時ってどんな人?(→link)

馬込万福寺蔵の梶原景時像/Wikipediaより引用
少し長いので、肝だけ引用させていただくと、次の見出し部分がそうです。
◆景時さんは日本で一番最初に「ほう・れん・そう」を徹底したデキル管理職⁉◆
「賢い」って「ほう・れん・そう」かーい!
そう突っ込まれそうですが、逆に言えば、それだけ当時の坂東武者が単純だったということです。
ドラマでは描かれませんでしたが、景時とその子が素晴らしい知恵者だったとする話も伝わっています。
文治5年(1189年)、平泉征討に向かう頼朝が、白河の関を越そうとしていました。
そこで景時の長男・景季を呼び出し、こう声をかけたのです。
「ちょうど今は初秋だね。能因法師のことを思い出さない?」
すると景季は馬を控えこう詠みました。
秋風に草木の露を払はせて君が越ゆれば関守も無し
そして頼朝が津久毛橋(宮城県栗原市金成津久毛)につくと、今度は次男の景高が詠みます。
陸奥の勢は御方に津久毛橋渡して懸けん泰衡が頸
これに頼朝は大喜び。
他の奴らと大違いだよ! あいつら話が全然通じないもんなあ。
と、盛り上がったのです。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用
確かに素晴らしい歌ですよね。武士らしく、これから討ち取る藤原泰衡のことも読み込んでいて、まさに智勇兼備。
単に風雅なだけでは詠めない、これからの武士の道を予見させるような歌でした。
梶原景時とその子は、頭ひとつ抜きん出た教養と機転があります。
ではなぜ、その能力を身につけられたのか?
景時は弟・朝景と共に上級貴族である徳大寺実定のもとに仕えていたことがありました。
徳大寺家は歌壇の大物であり、そこから教養をたっぷりと吸収した。勉強熱心で賢いのです。
しかし、これが他の鎌倉の連中からすれば気に食わない。
わけのわかんねえモンを見せびらかしやがって!
という不満も出てくる。
なんせ当時の坂東武者はこんな認識です。
「俺らがなんで強ぇかってそりゃよ、むしろ平家の連中が弱すぎんのよ。
夏になれば暑い、冬になれば寒い。
おまけに身内が死んだくらいでメソメソしやがって。
和歌なんて意味のねーモン詠みやがってよぉ!」
鎌倉政権において、景時は“チクリ魔”だと見なされてしまいますが、このあたりに理由もあるのでしょう。
坂東武者の代弁をしてみれば、こんなところでは?
いちいち俺らの殿に呼び出され、何を話しているかわかったもんじゃねえ。
和歌とかなんとか言って、ホントはチクってんじゃねえの?
ノリと勢いだけで済ませる俺らと、オツムの良いおめーはちげーってか、空気読めや!
かくして不満が鬱積していった。

画像はイメージです(男衾三郎絵詞/wikipediaより引用)
景時の死に至る原因も、ただのコミニケーションの誤解のように思えます。
冷静に話し合えば問題なかったのではないか?
そう気が重くなるほど些細な理由。66人もの弾劾を受けてしまう背景には、彼の教養に対する嫉妬もあったのでしょう。
それは死後のこんなやりとりにも現れているように思えます。
景時の死後、渋谷高重はこう言いました。
「景時ってさあ、インテリぶってたけどぶっちゃけ大したことなくね? 近くの橋落として館に篭ればいいじゃん。オタオタ逃げ出してやられちまって、口ほどにもねえブザマさでウケる」
畠山重忠はこう返答します。
「まあ、突然のことだから、堀を作るとか、橋を落とすとかできなかったと思うんだよね。厳しいと思うなぁ」
すると安藤右宗が黙っていられない。
「畠山殿は汚ねえ仕事やらねー大名だからしょーがねーかもしれねーッスけど、橋落としたり砦を築く具体的なやり方知らねえんスかァ? んなもん近所の小屋を壊して橋の上に乗せて火をつければ、橋落とすなんざよゆー、よゆー!」
失礼、意図的に頭が悪そうに意訳しています。
ともかく、こうしたヤリトリからは「インテリぶってるくせに!」という嫉妬心がどうにも見て取れてしまいます。
橋を破壊するやり口も生々しいもので。
景時が近所の小屋を破壊することを躊躇った、優しさの表れかもしれない。
しかし、そうした点はついに評価されませんでした。
智勇兼備の時代へ
京都由来の教養と、坂東の力強さ。
【承久の乱】で鎌倉が勝利をおさめたことで、武は勝ったのかというと、そんな単純な話でもないでしょう。
むしろ智勇が融合する新時代へ突入してゆきます。
ひとつの到達点が三代将軍・源実朝です。

源実朝/Wikipediaより引用
彼は、歌人として名高い藤原定家の教えを受け、『金槐和歌集』を編纂しており、こんな話があります。
東大寺再建に尽力した南宋人の建築家・陳和卿(ちんなけい)。
かつて源頼朝が面会を求めたところ、殺生を嫌われ、断わられました。
その陳和卿が、実朝には拝謁を望んだ。なぜかというと、宋にいた高僧の生まれ変わりだと感激し、そう願ったのです。
本当に生まれ変わりかどうかは、この際どうでもよくて、父・頼朝の代では野蛮とされたのが、子・実朝の代ではすっかり評価が変わった。そこまで洗練されたという証拠でしょう。
実朝のみならず、御家人たちも和歌を詠み、漢籍を読みこなし、仏教に帰依するようになってゆきました。
こうして和歌と文学の効能も、武士が理解できるようになった。
歌を詠めば気持ちが和らぐし、スッキリする。そう思えるようになり、武士が智勇兼備の存在へと変貌してゆくのです。
危険視される語彙力の低下
こうした文字・文学に対する歴史の流れを見ていて、僭越ながら一つ心配になる事があります。
学校教育の国語改革において導入された「実用文」の話です。
小説評論ではなく、契約書のような実用文を国語教育の主体にシフトにしよう――そんな動きがあります。
同時に古文・漢文不要論も浮上。
◆「本が読めない人」を育てる日本、2022年度から始まる衝撃の国語教育 | 教育現場は困ってる(→link)
◆古文・漢文“不要論”めぐり議論沸騰…問われる、中学・高校で必修にする意味と必要性(→link)
◆グローバルな時代だからこそ、古文・漢文は大事(→link)
さすがに危惧する声も上がっていますし、そもそも子供たちが言葉を覚えていく過程で、そんなことが可能なのでしょうか?
私はどうしたって、源平合戦のころの坂東武者を思い出してしまいます。

彼らだって文章が読めなかったわけではない。
米がどれだけ取れたか。
誰がどこに住んでいるか。
そういった当時の実用文は読めた。
しかし、何かが足りない――そう悟ったからこそ、それまでバカにして無駄だと切り捨てていた歌を詠み、書を読むようになった。
子どもの発育段階にせよ。
歴史の発展にせよ。
文章力を基準に判断することは意義があると、証明されています。
それなのに、なぜ、実用的な文章さえ読めればよしとするのか?
歴史をたどれば、文章の処理量が増えた段階で、社会が「大きな転換点」を迎えることはしばしばあります。
前述のような「紙」の普及。
宋代に高まった印刷技術。
ヨーロッパの宗教改革も、印刷技術の発達なくしては語れません。
逆に、文章力の低さが国家の停滞をもたらしたこともしばしばあります。
帝政ロシアでは、貴族階級がフランス語を用い、それ以外はろくに文章も読めないような状態でした。
革命を起こす前にまず教育から始めなければならないとされ、そこが重視されたものです。

現代にしたって、中国の文化大革命や、ポル・ポト(カンボジア)の知識人殺戮は、国や社会に大打撃を与えました。
こうした流血を伴わないにしても、教育の質を落とすことは社会に打撃を与えかねません。
歴史は既にそのことを証明しているのです。
小難しいことに話が逸れましたが、もう一度問いかけさせていただきます。
実用文だけでよくね?
文系の学問ってぶっちゃけ何の意味があんの?
そんな疑問を持つ時点で、すでに危険性を秘めていることは、「ほう・れん・そう」ができるだけの景時が嫉妬され、排除された時代からも、ご理解いただけるでしょう。
『鎌倉殿の13人』では大江広元などの影響もあって格段に知性は上がっていった。
皮肉や揶揄を使い、相手を煙に巻くこともある。
それこそが進歩の証だったのです。
あわせて読みたい関連記事
-

鎌倉御家人の宴会は刃傷沙汰にもなる命懸け!一体どんな飲み会だったのよ?
続きを見る
-

なぜ梶原景時は鎌倉御家人たちに嫌われたのか 頭脳派武士が迎えた悲痛な最期
続きを見る
-

なぜ北条時政は権力欲と牧の方に溺れてしまったのか 最期は政子や義時に見限られ
続きを見る
-

牧の方は時政を誑かした悪女なのか? 鎌倉幕府を揺るがした大騒動の根源疑惑
続きを見る
-

牧氏事件(牧氏の変)|新将軍の擁立を画策する時政が義時と対立 その決着は?
続きを見る
【参考文献】
野口実『源氏と坂東武士』(→amazon)
細川重男『頼朝の武士団』(→amazon)
井波律子『中国人の機智 『世説新語』の世界』(→amazon)
タミム・アンサーリー/花田知恵『世界史の発明』(→amazon)
他