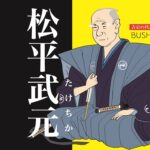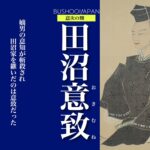こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第13回お江戸揺るがす座頭金】
をクリックお願いします。
検校屋敷が踏み込まれた
蔦屋重三郎が蔦屋で店番をしていると、武士がやってきました。
彼は赤本を取り出し「これはそなたのものか?」と尋ねます。
めくると「からまる」と幼い蔦重の字で書かれていました。
蔦重が認めると、武士は主人から話があるので屋敷まで来て欲しいと言います。
瀬以に何かあったのか?と驚く蔦重。
「来ればわかる」
そのころ瀬以は、蔦重が足抜けしようと手渡した「女 しお」と書かれた切手を見ていました。
そこに検校が入ってきます。
「もうすぐ蔦屋重三郎がくるぞ。どうだ、嬉しいか?」
瀬以は困惑しつつ、腰の物は何かと言います。小刀ではないですか。
「返事次第では斬ることいやるかもしれぬからな」
驚く瀬以。不義密通の罪だと言われ、瀬以はそんなものは吉原中の誰に聞いたっていいと言います。何もない、潔白だと訴えます。
「けど、心だけはある。いくら金を積まれようと、心は売らぬ。そういうことであろう。お前は骨の髄まで女郎だな」
瀬以は、ありんす言葉になって答えます。
「そう、仰せの通りでござりんす。重三はわっちにとって光でありんした。あの男がおるならば、吉原に売られたことも悪いことばかりではない。一つだけはとてもいいことがあった。そう思わせてくれた男にございんした。
重三を斬ろうがわっちを斬ろうが、その過去を変えることはできんせん!
けんど、わかっておるのでござりんす。主さんこそ、わっちをこの世の誰よりも大事にしてくださるお方であることは……人の心を察しすぎる主さんをわっちのいちいちが傷つけているということも!
人というのはどうして己の心ばかりは騙せぬのでありんしょう。今や抱いたところで詮無い主さんを傷つけるばかりのこの思い。こんなものは消えてしまえと、わっちとて、願っておるのでありんす」
涙ながらにそう訴える。
「けんど、この世にないのは四角の卵と女郎の実(まこと)。信じられぬというのならどうぞ、ほんにわっちの心の臓を奪(と)っていきなんし!」
そう刀を抜き、己の胸に向ける瀬以。
蔦重は鳥山検校の屋敷に向かってゆきます。
しかし、封鎖されています。いったい何が起きたというのか。
MVP:“神君家康公”
今週は見どころがたくさんありました。浮かびあがる“神君家康公”の存在感が圧巻でした。
今にして思えば『青天を衝け』冒頭の家康は陳腐な上に、日本史知識を悪化させておりました。
『どうする家康』の「神の君!」を連呼するキンキン声のナレーションは思い出だけでもうんざりさせられます。
歴史をおちょくっているようにすら見えた。
この幕末と幕府創成を扱う大河ドラマがもっと真っ当な出来であれば、視聴者の日本史知識はもっと向上したことでしょうに、貴重な時間を無駄にしたものです。
今にして思えば、あの手のドラマはジャンクフードのようなもの。
視聴者の、スマホをポチポチしながら深く考えずに見たい要求には応じられるけれども、なんの栄養にも知識にもならない要素が詰まっているだけ。
あれはお子様向けです。ガキってぇなぁ、自分の好きなお菓子ばかりぱくついて、大人が「もっと栄養になるものも食べないといけません」といっても嫌がるもんです。
大人になりゃ、健康診断の結果を踏まえつつ、我慢して意識して食べますよね。
そういう大人の鑑賞に耐えないしょうもない作品だったと思います。家康の墓前で謝るこたないんで、ああいうものは二度と作らないでいただければと。
今年の大河ドラマは江戸中期において、いかに家康の威光が暗い影を落としているのか描いてきます。
これに頼る筆頭は家治でなく松平武元であり、彼は日光社参にもひとかたならぬ思い入れを見せておりましたね。
それに抵抗するのが、田沼意次です。
彼は己の政治を貫くために、甥・意致失脚を利用し、西の丸に探りを入れました。彼の果断は、座頭金に踏み込んだこと。武元の狼狽ぶりをみればそれもよくわかります。
当道座の庇護を決めたのは、神君家康公です。
そこに踏み込むというのは大変なこと。いくら理不尽であろうが、人の命が失われ苦しんでいようが、偉大なる先人の権威に挑むことは人はそうそうできぬのです。
荒唐無稽なフィクションとはいえ、『水戸黄門』では大抵の悪党は徳川の印籠を見ればおとなしくなるではないですか。権威に弱いのです。
そしてこれは東アジア近世史を考える上で大切、かつ再来年『逆賊の幕臣』予習にもなります。
主役となる小栗忠順は、徳川が滅びる原因をこうまとめました。
「どうにかなろう。この一言が徳川を滅ぼしたのだ」
この「どうにかなろう」の中身を突き詰めると、神君家康以来のご威光あたりではないかと私は思います。まあ、神州だし、どうにかなろう。そういう心境でしょう。
小栗忠順が生きていたころのこと。
幕府はペリーが黒船艦隊を率いて来日することを、オランダから丁寧に説明する文書を受領していました。
ではなぜ、対処をしなかったのか?
というと、海禁政策は神君の決めたこと(ではなく、実際には家光時代に徹底されておりますが)であるし……ま、どうにかなろう。
そうして現実に向き合うよりも、逃避することを選んだというわけです。阿部正弘は焦り、対策を取ってはいたのですが。
さらにもっと遡ると、田沼政治の挫折にたどり着くのではないかと私には思えます。
今後ドラマで描かれることになると思いますが、意次はロシアの要求も踏まえ、海禁政策を変えようとしました。
その意次が挫折したとき、この小栗忠順の一言を思い出していただきたいのです。
田沼政治を全否定できるわけもなく、松平定信以降も幕府はロシアと向き合わねばならない事態に陥るにもかかわらず「どうにかなろう」とツケを未来にたらい回しにしてしまいました。
これは座頭金にせよ、旗本御家人の境遇ついても言える話でしょう。
当道座特権は明治維新まで保たれます。うまい具合に蓄財して、困窮した旗本御家人株を買い取る盲人も出てきます。
米山検校がその一人。男谷家の株を買い、息子を旗本にするわけです。
それでいいんですか、幕府は! そう突っ込みたくなりやしませんかね。結局これも「どうにかなろう」ですかね。
そしてこの米山検校の曾孫が勝海舟となります。
『逆賊の幕臣』では、小栗忠順が勝海舟のライバルとされます。
血筋という点では、三河以来の小栗と、検校の曾孫である勝ではかなり差があると思います。学業成績といった面でも、小栗がかなり上だったようです。
てなわけで『べらぼう』からずっと辿っていきますと、『逆賊の幕臣』にわりとすんなり接続できます。
舞台は江戸。百年経ていないからには、それも当然のことで、今から予習して再来年に備えるのもよろしいのではないでしょうか。
小栗忠順を演じる松坂桃李さんは、今年の渡辺謙さんに勝るとも劣らぬ気合いで演じることが求められます。
小栗の方が頭でっかちで理屈っぽいので、セリフもさらに長いかもしれません。
彼がどれほどの気合いで挑むか、楽しみでなりません。そんな再来年の予習のためにも、みなさまも今から横須賀のヴェルニー公演でも行ってみてはいかがですか。
総評
歴史を学ぶ意義とは何か?
去年に続き、今年の大河もそれを教えてくれるから、実に楽しい、刺激になると思えてきます。
戦国にせよ幕末にせよ、乱世はイレギュラーなことが多すぎます。
国民性や国のかたちということを考えると、実は例外的ともいえる。そういう時代ばかりを歴史として扱うと、意識が歪むのではないか。
その歪みを昨年と今年はマッサージして伸ばすような心地よさがある。
とはいえ、そうして得られる結論は、どうにも不都合なものかもしれません。
私なりに痛感させられることは、日本は基本的に貧しい――そうなります。
隣国の清は、当時の世界GDPの三割を占めていたとされ、圧倒的に豊かでした。西洋諸国はその富を狙い目を光らせており、かつ、世界各地から急速に富を収奪しつつありました。
そうやって次から次へと経済を上向きにできる国と比べると、どうしたって日本はそうもいかない。江戸中期となれば息詰まってきてしまい、成功しようと思うならば別の誰かを蹴落とすしかない。
奪い合うパイが小さければ、そうなってしまう。
蓄財しようにも質素倹約につとめるか。あるいは副業内職をするか。
そういう既視感のある生々しい頭打ち経済は、かつて通った道である。今年はそれをハッキリ示していて、いやはや、なんて勉強になる大河ドラマなのでしょう。
日本は明治維新で他のアジア諸国を先駆けて近代化へ突き進みました。
アジア・太平洋戦争で大敗北を喫するものの、その後、幸運が重なって高度経済成長を遂げた。
そのせいでずっと経済大国だったと幻惑されていると思うのですが、本来はそうじゃないでしょう、江戸中期以降を見てみろ、と。
幕末に幕臣たちが味わった焦燥感を再体験する必要があるのではないか。
歴史を学んで己を見つめ直すには、キラキラした英雄譚ではなく、眉間に皺が寄るような話が適しているのではないか。
良薬は口に苦いように、むしろスカッとしない歴史劇が求められているのではないかと本作を見ていると思えてきます。
確かに蔦重は快男児ですし、アイデアの数々はためになるし素晴らしい。日本のエンタメコンテンツはこうやってできたのだと思える。
確かに、スケール感がないというか、せせこましいといえばそうでしょう。
しかし、それでいいじゃねえか。精緻でおもしろいものを生み出せるのが、日本人のよいところではないか。と、幕末の幕臣が滞在先の外国で考えたことと一致する答えを、今年の大河は教えてくれます。
これは再来年もきっとそうなります。
地震大国日本に住むからには、いつ崩れてもおかしくない場所に建ったタワマンに憧れている場合じゃねえと思うんすね。
そういう本質を、大河が教えてくれるとは思いもよらねえことでした。
毎度毎度、ほんとうにありがた山すよ。
あわせて読みたい関連記事
-

松平武元『べらぼう』で石坂浩二演じる幕府の重鎮は頭の堅い老害武士なのか?
続きを見る
-

田沼政治を引き継いだ田沼意致(意次の甥)実際何ができたのか?
続きを見る
-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察
続きを見る
-

『べらぼう』市原隼人演じる鳥山検校はなぜ大金持ちなのか?盲人の歴史と共に振り返る
続きを見る
-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった
続きを見る
【参考】
べらぼう/公式サイト