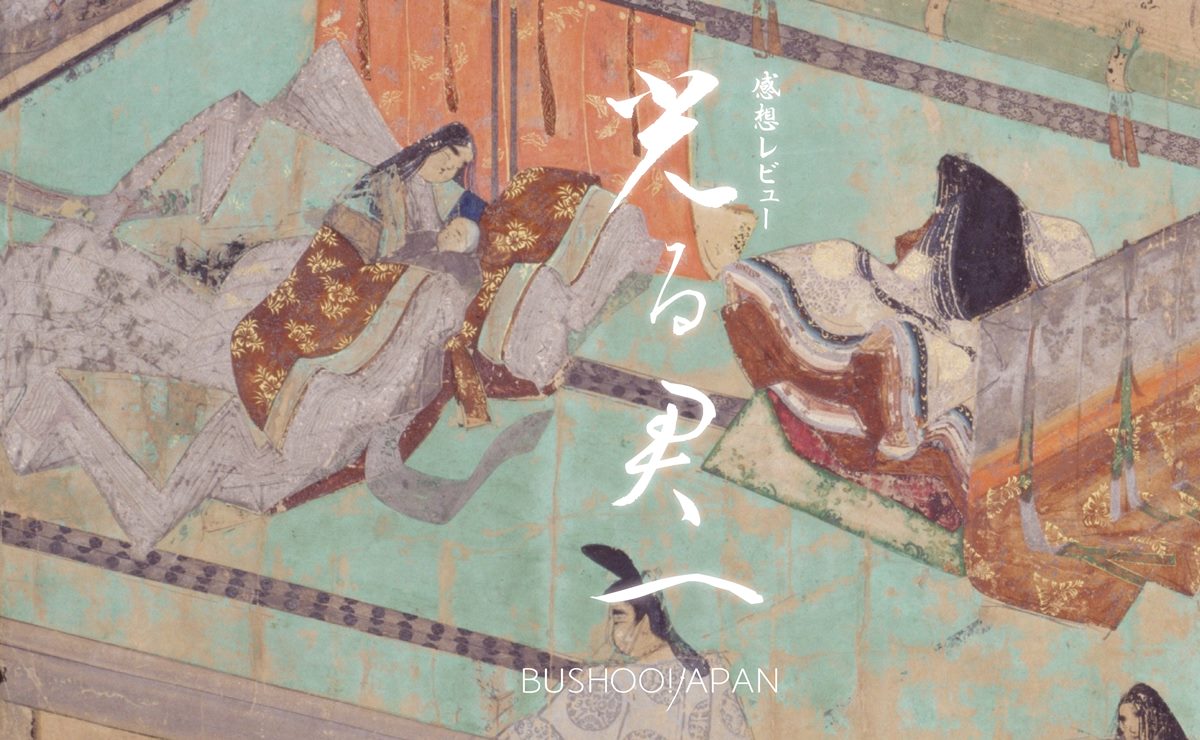こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『光る君へ』感想あらすじレビュー第21回「旅立ち」】
をクリックお願いします。
二人の再会
越前への出立前、まひろはあの廃屋で道長と再会します。
越前守にしてくれたことを素直に感謝するまひろ。道長は、お前の書いた文を帝が誉めていたと伝えます。
なぜ私が書いたとわかったのかと驚く彼女に対し、まひろの字はわかると答える道長。
明日の出立を控え、まひろは最後に聞きたいことがあって文をさしあげたと、再会を求めた理由を語り始めます。
「なんだ?」
「中宮様を追い詰めたのは、道長様ですか?」
小さな騒ぎを大ごとにし、伊周を追い落としたのはあなたの謀(はかりごと)かと、問いかけるのです。
「そうだ。だからなんだ」
「つまらぬことを申しました」
そう謝るまひろ。世間の噂に惑わされ、一時でも疑ってすまなかったと謝ります。あなたはそういう人ではないと今更ながらに悟った。
道長も、怒るわけでもなく自虐的にこう答えます。
「似たようなものだ。俺の無力のせいで誰も彼も全て不幸になった。お前と交わした約束は、いまだ何一つ果たせてはおらぬ」
確かに倫子が見抜けた詮子の策を見逃すほかなく、道長は傍観者になっていました。
これからどうしたらよいかもわからないし、もしもあのとき、まひろと遠くの国に消えても、守りきれなかっただろうと冷静に振り返っている。
するとまひろは、かの地であなたと滅びるのもよかったかもしれないと言い出します。
何もできない道長でも、愛する人を思うことはできます。
越前は冬は寒いから体をいとえと告げ、二人は抱き合う。
この十年、あなたを諦めたことを後悔しながら生きてまいりました。
妾でもいいからあなたのそばにいたいと思っていたのに、なぜあのとき、己の心に従わなかったのか。
いつもいつも、そのことを悔やんでおりました。
いつの日も、いつの日も――。
道長に抱かれてそう思うまひろ。
それは彼女だけでなく、道長も、いつの日も、いつの日も、まひろを思っていました。
やっと身を離し、今度こそ越前で生まれ変わりたいと願っていると語るまひろ。
「そうか。体をいとえよ」
頷くまひろ。二人はここで唇を重ねるのでした。
それにしても、感動的な場面ではあるものの、別の男の影は落ちています。
まひろがどうして道長を疑ったのか?というと、宣孝の推理のせいです。
別の男が吹き込んだことのせいで、疑われてしまった道長。そう考えると、それをわざわざ確認するまひろもなかなかの策士に思えます。
道長が流されやすいお人よしで、感情ケアが得意な劉備タイプだとすると、やはりまひろは諸葛亮なのでしょう。
道長がオロオロ系のドジっ子になる一方、まひろがどんどん腹黒くなる現象は興味深い。
道長の後年の権力者ぶりはどうするのかと考えていましたが、まひろの方がどす黒くなるのかもしれません。
いっそ『鎌倉殿の13人』の北条義時超えでも狙っていきましょうか。
気が早いけれども、来年の蔦屋もなかなか悪どいといいますか。
近年NHK大河は嫌われる勇気があるほど、良い出来だと思えます。つまり、来年も期待できる!
まぁ、こういうニュースもありますが……。
◆東京藝大「吉原展」が大炎上で大河「べらぼう」はどうなる? 「女郎屋の粋が出せるか心配」(→link)
◆次期大河ドラマ「べらぼう」早くも〝黄信号〟が 小芝風花、福原遥…清純派の配役に違和感、今のご時世「遊郭」が舞台のリスク(→link)
主人公は吉原ガイドブックでブレイクしています。題材の時点でNHKは覚悟はできていることでしょう。
越前へ
琵琶湖の上を船が進んでゆく。
指で琵琶を弾くまひろ。
彼女は白居易『琵琶行』を写していたことがありました。
女性が水の上で琵琶を奏でる姿は美しいものです。一瞬だけれども、素晴らしい絵になる場面です。

月岡芳年『月百姿』の「はかなしや波の下にも入ぬへし つきの都の人や見るとて 有子」/wikipediaより引用
船を降り、越前の山道を進んでいくと、「国府に行く前に立ち寄るところがある」として、為時は松原客館へ向かいました。
宋人の様子を見るために立ち寄ったのだとか。
迎える側は予想外の来訪に驚いています。
館の中で宋人は互いに怒鳴りあい、ざわめき、大変なことになっています。
ここで為時が「粛静!」と宋語で「静かにするように」と言うと、宋人が振り向きました。
ただし、この宋語はわざとたどたどしくしているとのこと。
遣唐使があるころはちゃんと先生を招聘したものの、そんなことはとっくに途絶えています。たどたどしい発音でこそリアリティがあるのでしょう。
中国語指導ではなく宋語とあるので、昔のものにするのかと思っていましたが、さすがにそこまではしないようです。華流時代劇に出てくるような、現代人でもわかる時代劇調の言い回しになりそうです。
ここでオウムが「你好!」と言います。声優の種崎敦美さんです。
それには全く文句はありませんが、劉セイラさんもいつか吹き替えてくれたらよいかな、と思います。
ここでざわつく中、ひとり距離をとり、無言の男がいます。
周明です。
-

『光る君へ』宋の周明(松下洸平)とは何者?紫式部の知力を強化する存在となる?
続きを見る
彼は他の宋人よりも肌を出しておらず、幞頭(ぼくとう)付きの頭巾をかぶっていて、文人らしさを滲ませていました。
※続きは【次のページへ】をclick!