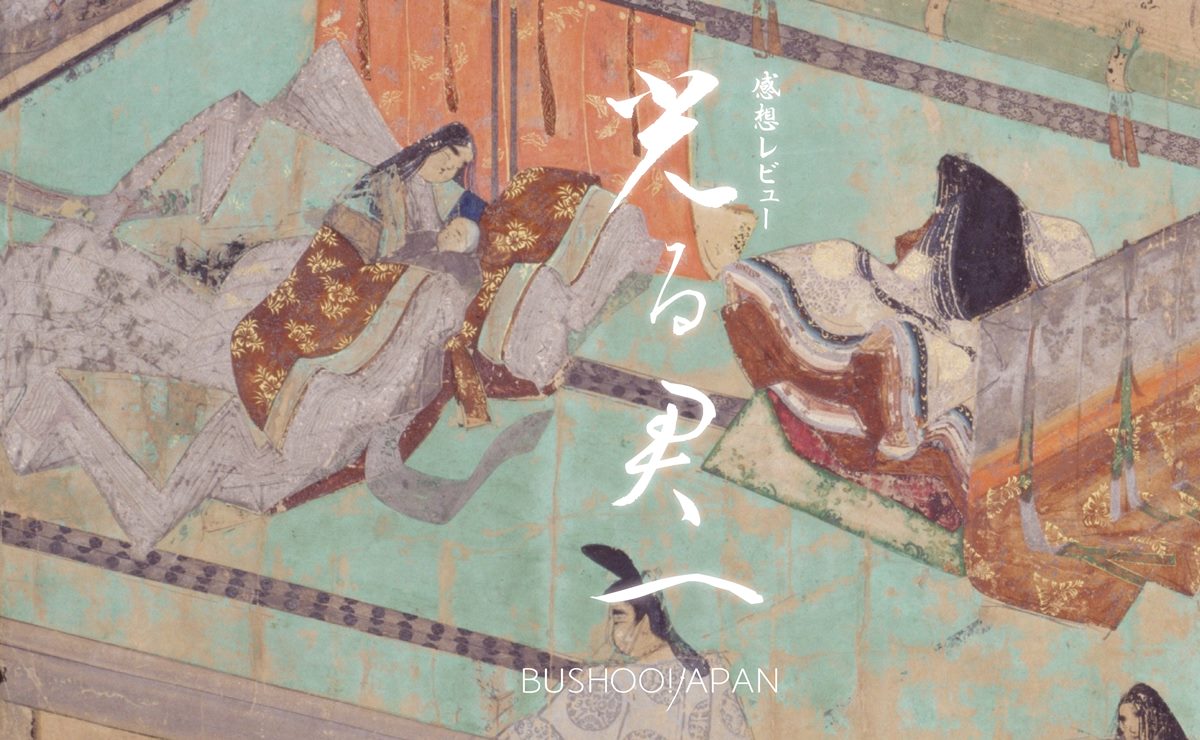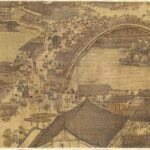こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『光る君へ』感想あらすじレビュー第21回「旅立ち」】
をクリックお願いします。
悲しき中宮に捧げる『枕草子』
清少納言がまひろのもとへやってきて、藤原定子の懐妊をそっと漏らします。
呪詛を防ぐため、帝にすら告げていないんだとか。確かに判明すれば、それこそ詮子ならば呪詛しかねません。
まひろは驚いています。
清少納言は出家以来、生きる気力を失い、食事も召し上がらない定子が心配だそうで。
中宮様を元気にするにはどうしたらよいか?と、まひろに尋ねています。
なかなか重たい話題に対し、「さぁ……」と戸惑うばかりのまひろ。さすがに清少納言も「そうよね」と返すしかありません。
しかし、まひろがふと思い出す。
清少納言は以前、中宮から高価な紙を賜ったはずだ。伊周が帝に献上したときにもらったもの。
帝が司馬遷『史記』を映す。ならば中宮様は何を書くべきか。そう尋ねられ、清少納言は「枕詞」を書くようにと申し上げました。
史記=しき=敷
敷に対して枕というわけです。
まひろが読み解くと、中宮様がおもしろがってくれたと清少納言は思い出しています。
ここでまひろが「その紙に中宮様のために何か書いてはどうか」と提案するのです。
“しき”だから“春夏秋冬”(=四季)ではどうか。
そんなまひろのアイデアに、「言葉遊びがうまい」と感心しきりの清少納言。笑い合う二人です。
ここは予告の時点で、どうしたものかと思っておりました。
清少納言の動機を、よりにもよって紫式部が提案するという誘導はいかがなものかと……。
ただし、会話のキャッチボールで決まるのであれば、よいかもしれません。
会話の中でアイデアが思い浮かぶことは多々あります。まひろが女諸葛だと思えば、これも許容範囲でしょうか。
早速、清少納言は墨を擦り、筆を執ります。
根本先生の指導を受けたファーストサマーウイカさんの所作が見事ですね。
そして、書いた紙を定子のもとに置き、それを手にして目を通す定子。
春はあけぼの――そう書かれた『枕草子』を読み進めています。
たった一人の悲しき中宮のために『枕草子』は書き始められた。
なるほど、こうきたのか、と腑に落ちました。
『枕草子』の様々な内容が、今回と重なって見えます。
藤原伊周の泣き叫ぶ姿は「上に候ふ御猫は」を思い出します。
帝や内裏の人々に愛されていた犬の翁丸が、猫の命婦のおとどに飛びかかったために、打ち据えられ、宮中から追い出されてしまう場面です。清少納言は翁丸が戻ってきたことに気づき、哀れむ様が描かれています。
あれはただの微笑ましい記録ではなく、帝の意思ひとつでああも寵愛を受けていた存在が、追い出されてしまうことを嘆いたのかもしれません。
「木の花は」は、植物をランクづけするような内容です。ここで清少納言は、梨の花はいまひとつ、どうにもパッとしないと思っていたと言います。
けれども『長恨歌』にはこうあります。
梨花一枝 春雨を帯ぶ
梨の花が春の雨を帯びた姿のようだ
楊貴妃の魂が玄宗の前にあらわれた姿のことです。
こう例えられるのならば美しいのかもしれないとじっくり観察すると、確かに趣があるとわかったと記しています。
今回の落飾した定子を見ていると、この段を思い出しました。
かつては満開の桜のようだったけれども、今は常にどこか寂しい。悲しみの色がある。そんな憂いを帯びた姿も尊く美しいのだと、そう腑に落ちる気がしました。
楊貴妃にせよ、後世の白居易が『長恨歌』を詠んだからこそ、その美貌が伝説になったといえます。
定子も清少納言の筆が、その魅力を残してきたといえる。
最愛の人が永遠に生きて欲しいと願い、筆を執ったと思える。
圧巻の場面でした。
-

中国四大美人の伝説&史実まとめ~西施・王昭君・貂蝉・楊貴妃~それぞれの美
続きを見る
-

『長恨歌』の作者・白居易は史実でどんな人物だった?水都百景録
続きを見る
-

猫は愛され鶏は神秘的だが犬は死体処理係で忌み嫌われ~平安時代のペット事情
続きを見る
宋人の狙いを見極めよ
藤原為時が藤原道長のもとへ挨拶に来ています。
共に参る娘が一生懸命準備をしていると語る為時。
道長には懸念がありました。
肥前博多に来ていた宋船なのに、若狭に来て新たな商いを求めてきた。
しかし、大湊もなく、異人をもてなす館もないゆえ、越前に移して松原客館にとどめおくことにした。
朝廷としては新たに商いの場を作りたくない。越前は都に近いから、乗り込む足掛かりを作らせたくない。
そんな懸念です。
しかも船には70人もの宋人がいて、中には商人だけでなく、官人や戦人も紛れ込んでいるかもしれないとのこと。
穏便に博多へ戻し、帰国させたいというのが道長の狙いであり、越前守の最も大きな仕事だと打ち明けられるのでした。
この場面は『鎌倉殿の13人』の序盤を思い出しました。
序盤の坂東武者はとても素朴で、地形を用いた戦術を献策する将が梶原景時だけで、絶望感が頭をよぎりました。
何が言いたいのか……?というと、
道長も為時も、もっと『孫子』でも読んでください!
本気で攻め込むつもりなら、さすがに70人は無理があるでしょう。
大湊がない場所にはそもそも狙って漂着するとも思えない。越前は中国大陸に近く、風や潮の流れのせいで偶然流されたと考えた方がしっくりきます。
いくら都に近かろうが、大型軍船が往来できる航路が確実に確保できなければ、日本に侵攻なんてできやしない。
道長は作中でも頭が切れるほうには属していないし、都の貴族は兵法を学ぶつもりが全くないと見た。
そこまで弱いからこそ過剰に怯えているように思えます。
彼を知り己を知れば百戦殆からず。『孫子』
これに尽きます。
外交的に引きこもっていないで、以前から遣宋使でも派遣していれば、こんなマヌケなことは言い出さないはずです。
宋は、北の遼や契丹へ軍事力を割かねばならず、日本に攻め込む余裕などありません。
そもそも中国は、どの時代も外に出ていくパターンがそこまで顕著ではありません。
広大な大陸を統治するだけで骨が折れる。
朝鮮半島すら制圧は難しく、攻めた結果反撃にあい、大変な目にあうことがしばしばあります。
このことは現代ニュースを読み解くうえでも重要です。
昨今、中国の脅威が盛んに喧伝されています。
主に英語圏が発信する脅威論が焚き付けられているものの、不発気味に思えます。
笛を吹いても、踊る国は限定的なのは、歴史を紐解けばヒントがあるかもしれません。
先日、『黒人の歴史』という本を読みました。
明代の鄭和の艦隊遠征が、アフリカ黒人の目線からだといかに斬新に思えるのかと書かれています。
鄭和はただ交易だけを求めてきました。
中国からアフリカまで、あれだけの大艦隊で遠征できるのに、奴隷貿易もしないし、攻め込むこともない。なんて素晴らしいことだ! 西洋諸国とそう比較して、称賛しています。
グローバルサウス相手に中国脅威論を西洋諸国が吹聴しても「ふーん、どの口が言うんだ? 中国の艦隊は貿易だけで戻って行ったけど、あなた方は何をした?」そうしらけられても何も不思議はないのです。
ちなみにこれは沖縄にしてもそうなります。
中国は琉球とは朝貢関係を続けてきた一方、無理矢理武力制圧したのは薩摩藩です。密約外交で手を結び、琉球王朝を滅亡に追い込んだのは日本とアメリカです。
歴史的に見て、日米が沖縄に中国の脅威を説いても、説得力がどの程度あるか、考えた方がよいのではないでしょうか。
そういうことをすっ飛ばし、自分たちの過去のこともさして反省せず、英語圏の雑誌や書籍が「中国は有史以来、周囲の国を脅していた!」と語ろうと、それこそこれで終了するような雑な論が実に多い。
彼を知り己を知れば百戦殆からず。『孫子』
貶すなとは言いません。ただ、そうするにせよ、中国史や思想をもっと学ぶ必要もあるのではないでしょうか。
話を戻します、道長の宋脅威論はトンデモ、当時の朝廷の外交がお粗末だったと示していると思えます。
そんなことだから、平清盛が日宋貿易に開眼したら、あっけなく政治の実権を握られてしまったのでは?
インフラ整備を輸入に頼っているのに、まともな外交をしないのでは限界に到達して当然でしょう。
-

銭を輸入すればボロ儲けで清盛ニヤニヤ~日宋貿易が鎌倉に与えた影響とは?
続きを見る
-

『光る君へ』宋と平安貴族はどんな関係だった?なぜ劇中では唐と呼ばれるのか?
続きを見る
そうはいっても、お粗末度は鎌倉幕府よりはまだマシかもしれません。
NHKで放映中の『三ヶ月でマスターする世界史』では、以下のように身も蓋もないことが語られていました。
元寇とは、日本の世界史デビューにあたる事件である。
元という世界史規模の大帝国にお粗末外交を展開した結果、無駄な戦争をした。
日本は元に異常対応したことで世界史デビューを果たした。
そんな血も涙もなく反論できない理論で、いろいろと考えさせられました。
今回の道長の見解からは、もう一つ、日本史のイヤな一面が凝縮している要素もあります。
それは兵站補給の把握が雑であること。70人を派遣したところで、兵站が整っていなければどうしようもない。道長はそこをすっ飛ばしているように見える。
迎える側がそうだと、ただの過剰な心配性で終わります。
しかし、外に出る際に兵站を軽視すると悲惨なことになります。
『麒麟がくる』では、光秀が信長に絶望する一因として、海を超えてまで戦うと言い出すようになったこともありました。
そんなことしたら泥沼に突っ込む。地獄だ!
光秀はそう理解していたように思え、身の程をわきまえない桂男こと呉剛まで持ち出されました。
光秀は理解できるそのことを、信長と秀吉はわかっていない描き方が秀逸であったと改めて思います。
とはいえ為時は真面目ですし、兵法書を読んでいるわけでもないでしょうし、道長の密命にちょっとやつれ気味です。
だいたい道長の命令はふわっとしていて具体性に乏しいんですよね。兼家の方がもっとしっかりと為時を使おうとしていましたよ。
道長は上司としては性格はいい。優しい。でも有能ではないかもしれない。
為時が、そんな苦労を背負い込んでいる最中、宣孝は儲け話に夢中でした。
国司は楽だ、土地で仲良くして懐を肥やせと語り、まひろはそんな宣孝を軽薄だと叱っています。
父はそういうものが苦手だ。
宣孝はしゅんとして、真剣に謝っています。とはいえ、いとがめざとく見抜いているように、叱られると嬉しそうでもあり……。
まひろは宋人に会うことを楽しみにしています。
宋人のよき殿御とかの国に行ってしまうかも――そう浮かれていると、宣孝もそれもよいと同調しつつ、もう叱られないと思うと寂しいと甘えます。
またもや、まひろとの距離を近づけたいように思える宣孝。
彼女はこのドラマの軍師、女諸葛ですので、道長の抜けた外交感覚とセットで、何かやらかす伏線は張り巡らせてあると言えるでしょうか。
すると弟の藤原惟規が帰宅し、出立に間に合ったと嬉しそうだ。
聞けば、文章生に合格したそうで、めでたいことばかりだと皆浮かれています。
-

藤原惟規(紫式部の弟)は実際どれほど出世できた?本当はモテる男だったのか
続きを見る
いとは、越前にはついていかないと為時に告げます。
大学寮からでて惟規がここに戻る。悪い女に誑かされぬように見張らねばならない。四年後の帰りを待っていると告げます。
為時も同意し、達者でいるよう答えるのでした。
※続きは【次のページへ】をclick!