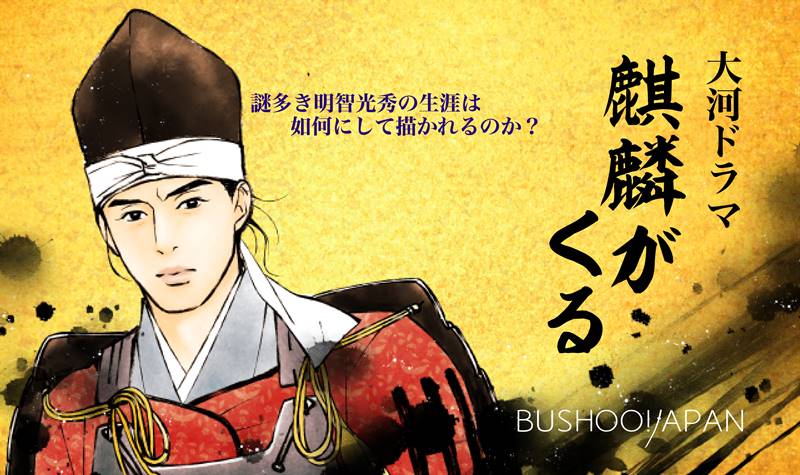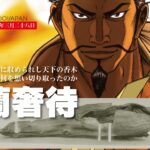こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【麒麟がくる第37回感想あらすじ】
をクリックお願いします。
茶器の目利きが久秀→宗久
今井宗久が、信長のもとで「これは80貫、これは50貫……」と目利きをしております。
この新しい時代は、高級茶器もポイントかもしれない。
私はずっと前から不思議に思っていることがありました。
かつては城なり土地を求めた戦国大名たちが、どうして茶器で納得するようになったのか? その心理的なこと、心情変化が見たかったわけです。
この場面には、その糸口があるように思えていいですね~。
松永久秀は光秀に許しを乞うてきた。信長がそう面白そうに告げるのですが、移ろいゆく世の中とは本当に残酷なものです。
かつて茶器の価格を決めていた大立者、審美眼の男といえば久秀でした。
それがアッサリ、宗久に替わっている。
ふと思い出しました。『世説新語』にある曹操の逸話です。
曹操が雇っている中で、抜群の美声を持つ歌手がいたものの、どうにも性悪で気に入らない。
そこで曹操は、歌手たちを猛特訓して、それ以上のものを育成します。
歌手育成が成功したら、性悪歌手を殺しました。
-

あの曹操が兵法書『孫子』に注釈をつけた『魏武注孫子』は今も必見の一冊である
続きを見る
人間の心をまるで踏まえない、合理主義にもほどがある。そういう奴って最悪だと思いません? と、そんな風に問いかけてくるエピソードです。
あの久秀ですら、彼以上の審美眼の持ち主が出てきたら、こうもあざわられるような存在になってしまうのか……。
光秀はやや苦しそうに、松永様は味方にすれば心強い、欲しいお方だとアピールします。
信長はそっけなく、なら許すかという。
「土産は城じゃ。多聞山城を渡せと」
あっさり信長はそう言いますけれども、多聞山城は当時最も美しく、画期的な城で、信長の安土城にも影響を与えています。
信長のセンスは、久秀のものを吸い取ったものだと考えると、おそろしいものがある。
宗久は目利きを終え、越前で5代続いた大名、名品揃いであったと満足げに告げます。そして、これだけのものを一手に収めた方はいないと告げます。もはや天下を取ったも同然だと。
蘭奢待
信長は茶を飲んでいます。
所作も整い、天下人の風格があるといえばそうかもしれない。
そしてここでこう言い出します。
「蘭奢待……存じておるか?」
光秀は顔を曇らせ、宗久も驚いています。
ふるめきしずか――。
そう呼ばれ、えもいわれぬ香りがするとか。光秀は「天下一の名木、伽羅(沈香)の香木」と答えます。
が、それは代々、大きなことを成し遂げた者しか見ることはならぬとか。
その蘭奢待が何かと問いかけるのです。
「わしはどうかな? 今のわしは蘭奢待を拝見できると思うか? どうじゃ?」
今井宗久は笑います。
「それはもう! 今やこの国の武家衆で、織田様の右に出るものはおりませぬ。拝見になんの触りもございますまい!」
信長は「そう思うか?」とうれしそうではある。
「ならば一度見てみるか。どうだ十兵衛?」
光秀は顔をまた暗くしています。拝見となれば、東大寺はもとより、帝の許しが必要となる。
そう言うと、信長はますますうれしそうな顔をする。
「帝? 帝はお許しになるであろう」
信長は自分を肯定する者を求めている。その承認欲求は確かに面倒です。子どもっぽいとは言える。
ただ!
それも、あるものさえあれば止められるはずではある。そのことを、宗久を見ていて痛感します。
宗久は人の心を見抜き、おだてることがうまい。こうすれば信長は喜ぶとわかったうえでおだてています。
何か物を売りつけたいだけなら、そんな調子でも構いませんが、忠臣となるならばそう簡単にはいきません。
良薬は口に苦けれども病に利あり、忠言は耳に逆らえども行いに利あり――。
この蘭奢待の拝見は、鼎の軽重を問うことだと思います。
-

「蘭奢待」東大寺正倉院にある天下の香木を切り取る|信長公記第108話
続きを見る
周囲の反発をいたずらに招くだけで、まったく得することはない。
どうせ帝を試すならば、帝に一族の娘を側室として押し込めるほうが、得することはあるのでしょう。
信長を通して、家康も見えてきました。諫言をたくさん集めてもいる『貞観政要』愛読者の家康は、蘭奢待は触ろうともしていない。それでいて、皇室と姻戚関係を結びました。
こうして見てくると【創業】の信長に対する【守成】の家康の姿勢もわかってきます。
単純に家康が優れていると言うことでもなく、彼は失敗を先例から学ぶことができたわけです。
足利義政拝観以来110年ぶり
光秀は信長がいない廊下で、蘭奢待拝見についての意見を求めます。
殿は一体、何をお考えなのかと。
宗久はすらすらと意見を言います。
公方様は京都を追われ、朝倉浅井を討ち果たした。今や敵なし。いわば一つの山の頂に立たれた――そういうお方なればこそ、見たい景色があるということでございましょう。そう解釈するのです。
光秀は疑う。
「そうであろうか。まことにそうであろうか? 私に言わせれば頂はまだこれから。公方様を退け、さてこれからどのような世をお作りになるのか。今はそれを熟慮すべき大事なとき。まだ山の中腹なのです」
麒麟の到来する世の中を作るためには、まだまだ先がある。光秀は麒麟の到来を告げる鳥なので、納得ができずにさえずるしかありません。
善悪正邪を超えた宿命をいつの間にか背負わされて、痛々しい限りではある。
宗久はそう同意しつつ、あのお方は自分の値打ちを知りたがっていると言います。人の値打ちは目に見えませぬ。しかし、何が見えるかで、お知りになりたいと。
「ちがいますかな? 見る景色が変われば、人もまた変わるとか。ごめんくださいまし」
まずい。
信長は変わり、光秀が変わらないのか? 信長は危険な兆候を見せてきてはおります。
自分自身はぶれないのに、周囲の見る目がコロコロ変わる。そのことをとことん試したいような、そんな危険な何かがめばえた。
光秀が陥る苦悩も見えてくる。
どうして、どうして、どうして止められなかったのか?
彼の心をしずめられなかったのか?
我を非として当たる者は吾が師なり。我を是として当たる者は吾が友なり。我を諂諛する者は、吾が賊なり。
それはいけないと真剣に言ってくる人は師匠になる。肯定してくれる人は友になれる。媚びへつらい、褒めてくるものは敵となる。
そういうことを、同じ根から生えた信長にできなかった己を悔やむ道が見てきたようです。
花咲く内裏では、三条西実澄が報告しています。
いよいよ明日、信長を従五位下に叙され、昇殿を許す運びになった。将軍なき今、信長にはしかるべき官位を与えねばならない。これで少し安堵したと。
帝はこう穏やかに言います。
「今の信長には勢いがある。天下静謐のための働き見事である。褒美をやってもよい……」
「仰せの通り」
「とは思うが。蘭奢待を所望して参った」
蘭奢待を!……これには実澄も唖然とします。
「いかがであろうな」
実澄は8代将軍・足利義政拝観以来、110年ぶりだと困惑しています。
然るべきものが然るべき手順を経てすべきものを、あまりに急な申し出。あまりに不遜の仕儀だと困惑しきっています。
それでも、帝の思し召しならば仕方ない。
※続きは【次のページへ】をclick!