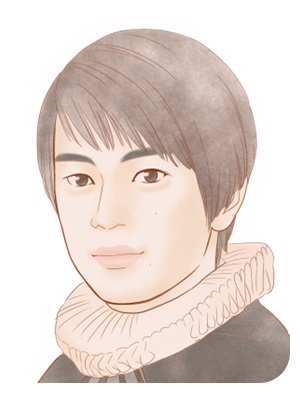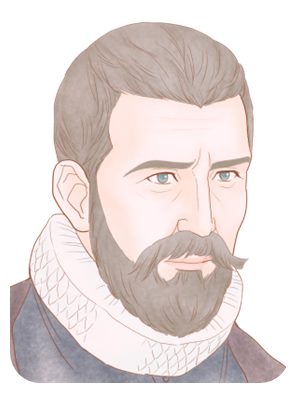船倉で少年たちは、祖国の味(食べ物)について思いを馳せます。
知的なマルティノだけは、日本の食べ物なぞ無用と言い切る。
宣教師が日本食はマズイと貶しておりましたが、当時の味を今の日本人が食べても同じような感想になると思います。
なんせ当時は、醤油すら普及していませんからね。
織田信長が徳川家康を招いて饗応した料理は、さすがに美味しかったでしょうけど、ナゼ豪華な食事でおもてなしをしたのか?
ちょっと想像してみてください。
「こんなに多種多様な食材を入手できるなんてスゴイだろ!」ってということです。
戦国時代は、敵の領地の名産物はそうそう口にはできません。
それを信長さんはやってのけた――というワケですね。
ただ、食については、このさき四名の少年たちもさほどには苦労しないでしょう。
日本人は魚が好きですからね。
カトリック教国であるスペインやポルトガルも、魚料理が豊富です。
幕末の遣欧使節も、ポルトガルでの魚料理には大満足だったとか。
海の上ならだから、魚を食べるなんて当たり前だろwww
と思います?
実は海洋国家ながら「魚は宗教的にちょっと……肉じゃないと……」という国がありました。
結果、あまり料理が発達しなかったのがイギリスです。
プロテスタントと食事の関係は、いずれ触れていきましょうか。
天下人・秀吉の笑み
南アフリカの喜望峰を東から西へと回り、船はイベリア半島へ。
ポルトガルはリスボンに到着します。
いよいよ、夢にまで見た土地です。
夜空に輝く南十字星が、北極星へと変わりました。
と、その前に、ドラマの舞台が日本へと切り替わりました。
画面に現れたのは【明智光秀の生首】だっ!
生首かぁ!
最近の大河ドラマでは、ここまでハッキリ&じっくりと映されることは減りましたねえ。
来年はどうでしょうか。
ここで豊臣秀吉の登場です。
演じるのは緒形直人さん。
緒形直人さんを秀吉に起用するした本作め……故・緒形拳さんの面影がやはり見えてしまいます。
緒形直人さんといえば、1992 年大河ドラマ『信長 KING OF ZIPANGU』(→link)の主演でしたね。
当時は若すぎる、カリスマ不足といわれたそうです。実は私も、当時のことはよく知らないので、これは何とも言えません。
が! そうした評価にリベンジを果たしたと言えるのかもしれません。
緒形直人さんって、もっと爽やかなイメージがあったと言いますか……こ、この秀吉は怖い!
「謀叛は用意周到にしなければならない」と語っているだけなのに、無茶苦茶怖いんですよ。
『な、なんだこの秀吉は?』
一瞬で心を掴まれてしまいました。
緒方さん、最近は仕事をセーブ気味だそうです。理由はわかりません。
本作におけるミゲルの緒形敦さんはご子息で、父子での出演になるんですん。
二世……というか三世とでも言うべきか。
俳優として、引く手あまたで話題性充分のはずなのに、父子揃って海外に出てしまったのかもしれない。
これは本気ですね。
ちなみに海外では、二世が日本ほどの力を持っているわけじゃありません。
スティーブンとタビサのキング夫妻の子であるジョー・ヒルは、ホラー作家となりました。
彼はデビューの際、父の名前を明かすことを断固拒否したそうです。日本では、ちょっと考えにくい話だと思いますね。
※『ホーンズ 容疑者と告白の角』の原作者です
血筋ではなく、あくまで本気で海外に出て行く。
そういう志のある役者を見つけてしまっているとすれば、ますます日本のテレビ界に危惧を感じてしまいます。
大河の主演経験者が、息子と共にこの作品を選んだのです。これは重要なことです。
大司教の冷たい目
そして1584年、船はリスボンへ。
ゴアといい、リスボンといい、日本ではできないであろう、この海外ロケ尽くし。
映像が美しい!
建築物が本物!
やっぱり、悲しくなってきてしまう。
いくら明治村にある教会をアレンジしたって、こんな豪華さは絶対に出せないんですよ……少年たちの驚きがこちらへも伝わって来ます。
そしていよいよ、大司教に面会します。
大司教の服装は緋色だぁ!
大司教にせよ、枢機卿にせよ、こういう衣装は日本のテレビ局ではストックがないはず。
ところが、海外にはあるわけです。
こんなキレイな緋色が見られるなんて……。
ボルジア家のドラマや『三銃士』みたいだ!
本作は、大河ファンだけじゃなく、西洋史や海外ドラマファンも見に来ますよね。
彼等をも満足させるこだわりっぷりです。
ただね……。
この大司教が全くいい人じゃない。
むしろ尊大で、差別性と俗悪さを垣間見せます。
しかし、ボルジア家好きならば、何も驚くべきことではありません。
井ノ脇海さんがラテン語をスラスラと語り出します。
うーむ。これは才能の塊ですね。
『おんな城主 直虎』のときからわかっておりましたが、こんな才能があったら日本に留まっちゃいられませんわ。
しかし、大司教はむしろ褒めるどころか「ラテン語を理解できるわけがない」と見下します。
マンショはこれに反発、大司教にいつも人を見下してばかりいるのか!と声を荒げます。
メスキータが制止に入りますが、ここもうまい描き方ですね。
当のマルティノはほとんど怒りを見せないのです。奴隷を見た反応といい、割り切っている。
これは歴史的な背景を知ると腑に落ちるものがあります。
ラテン語というのは、当時のヨーロッパでも日常生活では使いません。
ローマ人が話していた、古語扱いですね。
古代ローマ人がルーツにあると考えたからこそ、残されていたのです。
「ラテン語ができてこそ、教養ある人間でしょ!」
そんな意味があります。
「ローマ人の血を引く肌の白い我々が使う言葉を、東洋人ごときが喋るな」
そう大司教は思ったのかもしれない。
これぞ、差別ですね。
似たような言語の例は世界でもありまして。
戦国時代にも、関わることですので少し例を挙げておきましょう。
・百年戦争敗北以前のイギリスにおけるフランス語
→当時の王族はフランス語で話しておりました。
例えば、リチャード1世は実際にはフランス語読みの「リシャール」と呼ばれていたのです
・ロマノフ朝までのロシアにおけるフランス語
→貴族階級は話せて当然でした。
アレクサンドル1世は、ナポレオンよりもフランス語が流暢であったほど。
-

ナポレオン軍を殲滅したロシア皇帝・アレクサンドル1世は不思議王か英雄王か
続きを見る
・朝鮮半島における漢文
→ハングルは庶民のもの、漢文を使いこなせてこそエリートであるという思想でした
・日本における漢文
→武士階級は漢文を読みこなし、漢詩文を作ってこそ教養があるとみなされたもの。
俳句は町人のお遊び扱いだったのです。
大司教の態度にはイラッと来ますよね。
しかし、こういうタイプの人間が増えていったのは、実は当時の日本にもあてはまることかもしれません。
鎌倉武士あたりは、武士はヒャッハーしてこそ当然であり、さほどの教養は求められておりませんでした。
「和歌なんて貴族みたいに詠んでいるから、平家は負けたんだバーカ!」
そんな風潮ですね。
それが、戦国時代後半から変わって来ます。
武士だからってヒャッハーだけじゃダメ! そんな時代が来るんですね。
「『源氏物語』って感動するよね」
「連歌くらいこなせないと駄目!」
17世紀頃というのは、洋の東西を問わず教養やエレガントさが求められる時代に突入してゆく。
こんな時代の流れについて行けなかった人物が、どなたかわかりますか。
豊臣秀吉です。
信長は型破りではありますが、実家が武家だけに一定の教養は兼ね備えておりました。
しかし、農民(あるいは足軽)の出で、教育の機会がなかった秀吉にはその教養がありません。
秀吉が晒され続けた周囲からの“蔑視”には、血筋だけじゃなく、それ以外に教養の不足というものがあったのですね。
日本人は教養差別をしませんでした、と思うのは早計です。
ここで大司教は、メスキータに「彼らをローマに送り込むな」と釘を刺します。
カトリック教会も、ドロドロした世界ですからね。
この権力争いに巻き込まれた人物も、日本史にはおりまして。
支倉常長です。
奥州出身であるがゆえ、キリシタンを知る機会が遅れた伊達政宗。
「イエズス会」のライバル「フランシスコ会」のソテロ。
遅れを取り戻したいと話を盛りまくった二人に巻き込まれたのが、常長でした。
色んなところで繋がりがあって面白いですね~。
火刑の柱
一行はスペイン・マドリードを目指します。
馬車が道を進んでゆきます。
なかなか、立派な造りですね。
馬車での移動はジュリアンがこぼすように、臀部への負担がありまして。
それを克服するためにも、スプリングが重要視されたのです。
裕福な者にとって、快適な馬車はステータスシンボル! 庶民は乗り合いの馬車で我慢するしかありませんでした。
そして道中、四人は衝撃的な光景を目にします。
燃え盛る柱が立ち並ぶ、磔にされた……異端者の処刑だー!!
『ゲーム・オブ・スローンズ』で鍛えられた視聴者なら動じなかった?
※ネタバレ&閲覧激烈注意! あの子の火刑です
海外ドラマ視聴者ならば、この程度は余裕でしょう。しかし、かつてはともかく今の大河では無理でしょう。
本作についても頓珍漢な視聴者から
『織田信長を悪く描いた』
『日本人を貶める気か』
という意見もあったようですが、フェリペ2世を見てから言おうね。
翌朝、ジュリアンはドラードに異端者について尋ねます。
重要です!
本当に、この宗教改革描写は重要ですよ!
これは言い出すと止まらなくなりそうですが、最近のNHKドラマにおけるカトリックとプロテスタントの混同は余りに酷いものがあります。
マトモだったのは、同志社関係者チェックを通した2013年『八重の桜』ぐらい。
ゆる〜い。『なんとなくこれでいいでしょキリスト教♪』で作っているということが、伝わってくるのです。
そして、フェリペ2世は異端を絶対に許さない主義者でした。
スペインの異端審問は西洋史でもかなり悪名高いものです。
※『宮廷画家ゴヤは見た』では、異端者疑惑をかけられる女性が描かれています
イギリスのコメディ『モンティ・パイソン』でも、「まさかの時のスペイン宗教裁判!」("Nobody expects the Spanish Inquisition!")というネタにされたほどですね。
歴史的背景を知ると、本当に『イギリス人って……』と遠い目になれます。
うん……フェリペ2世をさんざんおちょくりまくったのは、イギリスなんです。
このあたり、頭の隅に入れておくと良いかもしれません。
プロテスタントの台頭、カトリックの斜陽――このことは本作に深く関わってきます。
異端者殺しの王と呼ばれるフェリペ2世ですが、夫人はこの方。
実は夫婦揃って異端者殺しなんですね。
イギリスがプロテスタントになるまでは、なかなか面倒なものがありました。
フェリペ2世がイライラしているのは、カトリックに戻りかけたイギリスが、またプロテスタントになっていったという背景もあるのでしょう。
※コイツのせいです!
メアリー1世の妹であるエリザベス1世は、宗教的にスペインに喧嘩を売るのはまずいなあ、と考えておりました。
しかし、幽閉していたスコットランド女王・メアリー・スチュアートの陰謀が堪えきれなくなり、イヤイヤながら斬首したのです。
彼女がカトリックであったために、フェリペ2世がついにキレるのです。
そして勝ったのは、エリザベスでした。
※この数年後、エリザベス1世からボコボコにされます
あ、メアリー本人はカトリックですが、スコットランドはプロテスタント国です。
メアリーが自国民から追い込まれたのは、宗教的な理由もありました。
そしてこのあと『V・フォー・ヴェンデッタ』仮面でおなじみの事件が、イギリスで発生します。
日本の戦国時代における世界史といえば鉄砲とキリスト教の拡散に終始しがちですけど……。
そうではなく世界史の中に日本がある感覚ってのも、中々いいと思いません?
そしてここで出てきたフェリペ2世(続きは次ページへ)。
日の沈まぬ国の王
フェリペ2世――エリザベス1世にやられたという扱いのせいか、映像作品ではよい扱いを受けていない印象があります。
このフェリペ2世は、廊下を歩くと本性をのぞかせるからと覗き見するという癖がありまして。
実は、スペイン王室にはあまりよろしくない話もつきまとっております。
近親結婚を繰り返すあまり、よろしくない傾向が出ているのではないか……とされているのです。
この場面、一瞬、紋章が映っておりました。
本当に、よくやるなぁと思うんですよ。
ヨーロッパですと、時代によって変わりますので。こちら(→link)のHeraldryを見てくださいね。
ちなみにここでも出てくる「ドン」。
『ドン・キホーテ』でもおなじみですが、スペイン語の男性尊称ですね。日本の大名たちも、相手から「ドン」をつけられております。
フェリペ2世は、大司教とはちがってニコニコ、上機嫌です。
マルティノが書状を読み上げると、縦書きで右から読むことに興味津々です。
あ、マルティノ、ラテン語挨拶はしないのね。
井ノ脇さん、フェリペ2世との会話には英語(劇中設定はスペイン語と思われます)を使っておりまして。劇中とは関係なく、御本人の海外進出も決まったかなぁ。
小野万福が、井伊谷から世界へ!
ウェーイ!!
ここで、ミゲルから日本刀が献上されます。
そして請われるままに日本の剣術を披露。
きっちりと殺陣をこなさないとできない、緒形敦さん、これは相当練習をしましたね。
動きが流麗です。
こんな逸材が海外に進出していくのか? いいのか、それで!
和服の着こなしも、本当に綺麗です。
剣舞に上機嫌で拍手を送るフェリペ2世。
同時にマンショは、おそろしい光景を目にしてしまいます。
同席していた人物が、脇腹をブスリと刺されて退場していったのでした。
なんだかほのぼのとしたやりとりが続きますけど、死人が出ているのですよ……なんなんだ。
このあと、マンショ一人が呼び出されます。
メスキータは警戒しております。
ドラードをつけて、マンショは王の前に立ちました。
ここで少し日本刀の蘊蓄でも述べておきましょう。
日本刀は武器としてかなり特殊なものです。
一般的に片手剣は、スペインはじめヨーロッパでは刺突武器が主流です。
両手剣ですと、重みで叩ききるスコットランドのクレイモア系が多いもの。
中国でもそうです。
中国では刀剣は廃れまして、長柄系の武器が主流となります。
『水滸伝』で用いられる武器もそうです。宋代には、そんな状況でした。
一方、日本刀は両手剣でありながら、持ち運びができる。
突くよりも斬る。そんな特徴があるわけです。
ただし、戦国時代の戦場でも、あくまで主流は槍、弓矢、鉄砲です。
日本刀が猛威をふるうようになったのは、甲冑が廃れていて、かつ屋内戦闘が猛威をふるった幕末ですね。
そうした剣術が研ぎ澄まされて「ピストルで武装しても意味がない! 日本刀怖いよ!」というのが幕末でした。
甲冑が必ずしも装備されていない、かつ近接戦闘が多い。
この条件が揃った中、日本刀が強すぎてこりゃ困ったもんだ、と考えた将が明代におりまして。
戚継光です。
日本刀および影流を取り入れ、倭寇を倒すべく対策を練ったのです。
こういう背景がありまして、中国にも「倭刀」と呼ばれて日本刀が伝わっておりました。
中華民国の時代に「苗刀」と改称されております。
異端者を愛せないのか?
フェリペ2世は、人払いをしてマンショと向き合おうとします。
ドラードも下がれと言われるものの、通訳だからと無理に残る。
フェリペ2世は、マンショに対して剣術を見せろとせがみます。
ドラードの佐野岳さんも、英語で話しておりますね~〜!
マンショは、武士ではないから出来ないと断ります。
ちなみに武士への剣術の普及も、当時はまだそこまででもないかなぁ、と思いますね。
武道として一通りは出来るのでしょうけれども。
マンショは「信長と似ているものがあるから見つめた」とフェリペ2世に告げます。
するとフェリペ2世は信長に興味を持ち、何を託したと尋ねます。
イエスの愛は何か?
真っ直ぐに生きることとは何か?
問われるままに、その疑問をフェリペ2世にぶつけるマンショ。
すかさず「敵を倒すこと、信じることだ」と言い切られたマンショは一歩も引かずに言い返します。
それでは、イエスの愛とは!
汝の敵を愛せと言われたのではないか!
ドラードが訳すと、フェリペ2世は顔色を変えます。
おまえは異端者なのか?
そう激昂し、刀を抜き放つ。
ここはちょっと惜しいかな。
実は刀って、抜くのが大変なんですよ。
先の中国明代の将・戚継光の場合、「ペアになってお互い抜き合うことがコツだ」と指導したそうですよ。
MVP:フェリペ2世
フェリペ2世!
これはいい、狂気の印象です!
どうしてもエリザベス1世にやられる印象がある、そんな気の毒な人物です。
名君であるとは思いますし、スペインの愛国心に訴える人物でもありまして。
紙幣に採用されていたこともあります。
そういうことを踏まえますと、信長よりえげつない描写だろご理解いただけるかと。
「スペイン人は怒らないのか! 失礼じゃないのか!」
そんなことにはならないと思いますよ。
特定の国を貶めるためとか、褒めるためとか、そんな動機は感じないでしょう。
そんなことを、このマッドな描写で学びましょうね。
総評
本作レビューの方針について、ちょっと書かせていただきます。
比較する大河につきましては2000年代年以降を対象とさせていただきます。
ギリギリで『天地人』までですね。
それ以上の隔たりがあると、学説や世相に変動があって、比較対象としては不適切なのです。
それ以前の大河を挙げて「過去には、こんな大河があったもんねー!」という意見は、ノスタルジックに浸るだけで、今と将来の話には繋がりにくい。
直近10年ぐらいが現実的だと考えています。
もしもすべての大河作品を見なければ何も語れない――そんなご意見があるとすれば、それこそ大河ドラマを窮地に陥れるものだと思います。
20年、30年、あるいはもっと古い作品と比べることに、さしたる意義は見いだせません。
現実的に、今、そしてこの先、どうやって作っていくか。それが大切なことでしょう。
本作シリーズには、大河ドラマですと紀行にあたるミニコーナーもあります。
これが実に豪華かつ勉強になるものでして。
わかりにくい背景については、この枠を見ればより理解が深まります。
それにしても、回を追いかけるごとに面白くなってきました。
こんなに歴史ドラマにワクワクしたのは、いつ以来でしょうか。
本作の魅力は、日本史をテーマにしているからではない。
『世界の中の日本だからではないか?』
そう思えて来ました。
16世紀から17世紀は、激動の時代です。
どの国でも、代表的な文学作品や名君が登場している。
スペインを例にとると、フェリペ2世、そして『ドン・キホーテ』ですね。
日本ですと、この枠は徳川家康になるというのが世界史的な見方です。
その家康前夜にあたる織田信長と豊臣秀吉。
そしてヨーロッパとの関わりというのは、世界中の視聴者から興味を持たれるテーマのはず――そういう狙いがあるのでしょう。
鎖国しない、家康が作り上げたものとはちがう、そんな日本があるとしたら?
それはどんな国だったのだろう?
世界史の中の日本に、興味がある人はいるものなのです。
別に「日本はスゴイ、唯一無二の国」ではなく、「世界史というパズルのピース」だと本作は教えてくれます。
だからこそ見えてくるものもあれば、理解も深まる!
このレビューでは、同時代を描いたものや関連作品をあげています。
本作を起点にして、是非ご覧になっていただき、そして語らいを楽しむ機会があれば嬉しいことですね。
文:武者震之助
絵:小久ヒロ
【参考】
◆アマゾンプライムビデオ『MAGI』(→amazon)
◆公式サイト(→link)