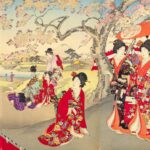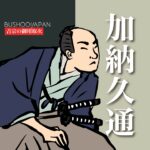こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【徳川家光】
をクリックお願いします。
・婚姻関係
家光には正室として、摂家鷹司家から鷹司孝子が迎えらました。
以降、徳川家将軍は京都から正室を迎えることが定番となります。
しかし、正室との間に成人する男子を授かることはなく、徳川将軍家で嫡出だったのは家光が最後となりました。
これ以外にも、家光が定めた国の形は数多くありますが、この辺にしておきましょう。
慶安3年(1650年)に病に倒れ、翌慶安4年(1651年)年に江戸城内で死去するまで、江戸時代の基礎を築いた人生でした。
享年48。
なお、幕末を迎えると、家光時代に推し進められた幕府制度に亀裂が入ります。
人口増加と比例するかのように頻発する飢饉。
米ではなく銭を主体とした経済の発展。
封建社会にそぐわない思想の隆盛。
など、社会情勢が刻々と変化し、ついには崩壊してしまいます。
しかしながら約260年もの間、江戸幕府の体制が保たれたのは、家康・秀忠から受け継いだ国作りの基礎を家光がしっかり固めたからでしょう。
「大奧」は家光時代から?
日本史の授業では、家康から家光までの時代が武断政治であり、家綱以降に進められたのが文治政治と習います。
捉えようによっては家光の時代で一区切りつけられたような、そんな印象も受けるかもしれませんが、江戸時代の長きにわたって存在した主要な制度をキッチリ固めたのは家光であり、政治的に重要な人物と言えるでしょう。
しかし、前述の通り、どうしてもプライバシーやフィクションの印象が先に立ってしまう。
弟・徳川忠長(国松)との後継者争いはスキャンダルとして定番であり、そうした作品では、己の容姿や才能、愛されなかったことに劣等感を抱く、屈折した青年として描かれがちです。
大奥関連作品でも、複雑な家光像が定番でした。
正室として迎えられた鷹司孝子とは相性悪く、子が出来ない。
最初の子である千代姫は、寛永14年(1637年)に生まれ、嫡子である家綱は寛永18年(1641年)に生まれています。
家光が34歳、38歳の時ですから、当時としてはかなり遅く、世継ぎがいないことに周囲も苛立ったことでしょう。
なぜ、こうも時間がかかったのか?
男色のみを好んだからだとされますが、真実は不明です。
江戸時代前期における男色は確かにタブーでありません。ただしそれは、女性相手に世継ぎを作っていればの話です。
再びフィクションに目をやりますと、家光の男色関係を扱った作品として、隆慶一郎『柳生非情剣』があります。
『柳生非情剣 SAMON』というタイトルで漫画化もされた同作品。
家光の寵愛で出世した次男・柳生左門(友矩)に対し、父の柳生宗矩が激怒し、長男の柳生十兵衛に斬らせるという、ハードボイルドBLです。
このように家光と男色はフィクションの定番であり、そのことに悩む春日局もおなじみです。
そこで春日局が考えたのが、美貌の尼僧作戦でした。
寛永16年(1639年)、伊勢慶光院の院主を徳川家光に謁見させたのです。
たちまち家光は恋に落ち、還俗させてお万の方(永光院)として寵愛。
彼女に子供はできませんでしたが、家光の心に火をつけた女性として存在感が大きい。
男女逆転版のNHKドラマ『大奥』では、万里小路有功の名で登場します。
映画版では堺雅人さん、そしてドラマ版では福士蒼汰さんが演じ、家光の閉ざされた心を開く重要な人物です。
お万の方(永光院)に目覚めてからの家光は、複数名の側室を置き、夭折した者も含め6人の子が生まれました。
その中には徳川家綱と徳川綱吉という二人の将軍もいます。
男女逆転版をはじめ、大奥ものは家光が起点となることが定番です。
世継ぎのできぬことを案じた春日局が、女性だけが集う場所を作り上げたからとされています。
大奥という呼び名は家光時代ではないものの、制度の原型が生まれたとされるのです。
日本人と社会の象徴と言える人物
以上、散々取り上げましたように、徳川家光はフィクションの登場回数が多い人物です。
その表現方法は荒唐無稽なようでいて、家光時代の特性も反映されている。
蛇足ながら、過去作品で注目される人物等に注目してみますと……。
・『柳生一族の陰謀』における烏丸文麿
やたらと強い麻呂として有名な人物です。
烏丸文麿は架空のキャラとはいえ、幕府に圧迫される朝廷再建のため剣を振るっている設定。
江戸時代初期に朝廷への締め付けが強固になっていった、そんな史実を反映しています。
・『柳生一族の陰謀』における根来衆
本作品の根来衆は柳生一族のもとで使われているものの、柳生宗矩によって虐殺されたうえ、里を焼き捨て。
このことに宗矩の子である十兵衛が激怒するシーンがあります。
平安時代以来、武士にも恐れられていた僧兵ですが、江戸時代には武装解除され、仏教は穏健な集団とされていった。
そんな牙を抜かれる集団としての象徴といえなくもありません。
家光が扱われる頻度が高いのは、彼が幕藩体制を固めた象徴であり、今日に至るまでの日本人の気質を定めた象徴とされるからでしょう。
上記の作品を世に送り出した深作欣二、山田風太郎、隆慶一郎、南條範夫は、日本人精神への批判精神を込めている。
ただ、このことが誤解を生じさせているとも思えます。
家光時代に確立されたこうした諸要素が、家康のものと混同されることが多いのです。
「家康が鎖国したせいで日本人は閉鎖的になった!」
こんな意見が典型例ですが、家康自身はむしろイギリス人であるウィリアム・アダムスを重用するなど開明的な一面がある人物でした。
2021年大河ドラマ『青天を衝け』では、ナビゲーターとして徳川家康が登場しておりました。
福地桜痴が『徳川慶喜公伝』で家康と慶喜を対比させた影響かもしれませんが、徳川将軍を登場させるなら、むしろ家光の方が面白かったかもしれません。
「せっかく私の代で定めた制限外交が、諸外国の干渉で、なし崩し的に増えていってしまった!」
「私の時代に来日した朱舜水が、水戸藩に思想的に大きな影響を与えたんだよね……」
といった調子で色々と絡みやすいのです。
ただし、苦々しいボヤキ尽くしにはなってしまいますが。
わかっているようで、実はそうでもない。
フィクションの印象が強すぎて、かえって曇っている――徳川家光とはそんな人物ではないでしょうか。
あわせて読みたい関連記事
-

春日局の生涯|明智家重臣・斎藤利三の娘は徳川家光を育てた“最強の乳母”だった
続きを見る
-

徳川秀忠の生涯|全部で11人いた家康の息子 なぜ秀忠が二代将軍に選ばれた?
続きを見る
-

家光の心を掴んだお万の方(栄光院)ついに子を産まなかったゾッとする理由とは?
続きを見る
-

五代将軍綱吉の母・桂昌院の生涯「八百屋の娘だった」という噂は本当なのか?
続きを見る
-

加納久通 NHKドラマ10『大奥』で注目された吉宗の側近 史実ではどんな人物だった?
続きを見る
【参考文献】
藤井譲治/日本歴史学会『人物叢書 徳川家光』(→amazon)
森和也『神道・儒教・仏教 (ちくま新書)』(→amazon)
他