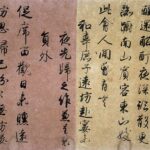こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【平安時代の手紙】
をクリックお願いします。
文が回し読みされるリスク
平安貴族にとって気の利いた文はステータスシンボルです。
あまりに素晴らしいと、家族、友人、はたまた職場中で回し読みされてしまう。
現代人からすればあまりに無神経に思われるかもしれません。
とはいえ、今だって面白いSNS投稿やメッセージはネタにされるものであり、アクセス稼ぎに利用する人もいますから似たようなものかもしれないですね。
そんなステータスシンボルとしての文と自慢といえば、清少納言と藤原行成でしょう。
和歌は苦手でも筆跡が美しい藤原行成。
文が届いて清少納言が放置できるわけもない。
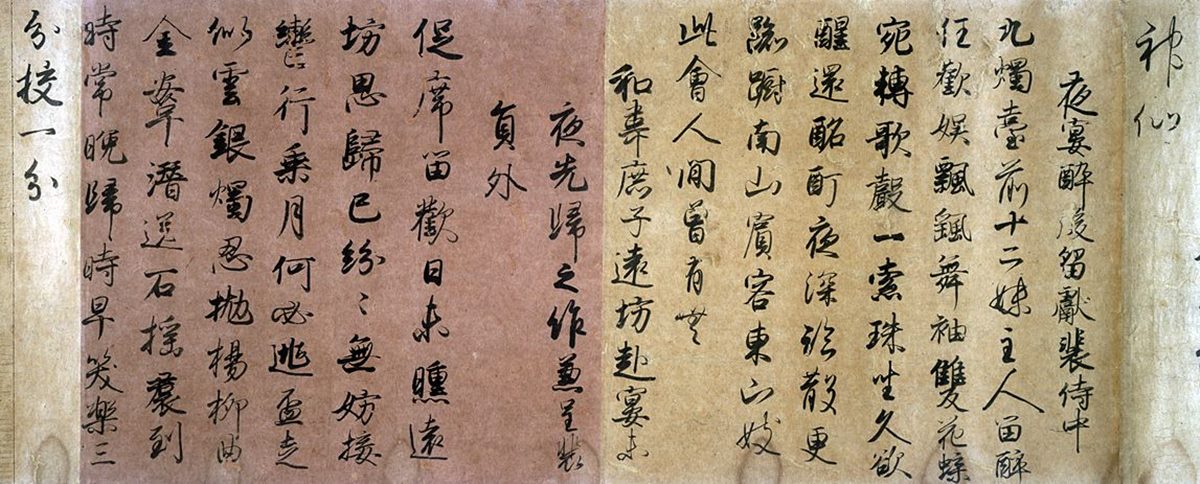
藤原行成『白氏詩巻』/wikipediaより引用
定子たち周囲に見せて回り、「さすが字が美しい!」と褒められていたことでしょう。行成としても清少納言に出すのであれば、そこは織り込み済みであったと思われます。
サロンを盛り上げる華やかな要素として、美しい文も存在していた。
逆にあまりに痛い文もネタにされます。
『光る君へ』第3回でも道長と同僚たちが文をネタに喋っていました。
文を盗み、チェックすることはありなの?
『源氏物語』でも“恋文チェック”が重要な役割を果たしているシーンがあります。
光源氏は昔愛した夕顔の娘である玉鬘を引き取り、六条院に住まわせました。
筑紫に暮らし、悪質ストーカーのような求婚者の大夫監から逃げてきた玉鬘。
光源氏が頼りになる養父となって一安心かと思っていたら、どうにも雲行きが怪しくなってきます。
有力者である光源氏の娘となれば、玉鬘には求婚者が迫ってきます。
その恋文をいちいちチェックし、ダメ出しまでし始める光源氏。玉鬘もだんだんと薄気味悪くなってきます。
さらには添い寝するまで露骨なセクハラをするものだから、玉鬘はすっかり焦燥してしまう。
この「玉鬘十帖」は、玉鬘に執着する光源氏がともかく不気味です。
四十を過ぎた光源氏は親子ほど歳の差のある女三の宮を妻に迎えるも、幼さに興味を失ってしまいます。
そんな女三の宮は、柏木と密通してしまう。

画像はイメージです(『源氏物語絵巻』より/wikipediaより引用)
光源氏は自分の留守中に懐妊した女三の宮に疑念を募らせていました。そして、女三の宮に送られた柏木の恋文を見つけ、その不貞を確信するのです。
光源氏は、若い頃、父の妻である藤壺と通じ、懐妊させました。その報いか……と恐れ慄くのみならず、柏木を軽蔑します。
己の若い頃ならば、恋文を書くにせよ、当事者しかわからないように書いた。柏木は迂闊だと。
自分の方が密通をうまく隠し通せたとマウントする光源氏はどういうことなのか。
このあと、光源氏は柏木を追い詰めるような言動をし、そのせいで柏木は命を落とします。女三の宮も男児・薫を出産すると、出家してしまうのでした。
こうした文のチェック場面を見ていると、登場人物のマイナス要素に繋がっています。
玉鬘の恋文を格付けする光源氏は、気持ち悪い。
「玉鬘十帖」の光源氏は、どちらかといえば中年以降のいやらしさ、マイナス面が目立ちます。
女三の宮と柏木の関係を気づいき、柏木にきつい嫌味を言うことで死へ追い詰めたその展開は、光源氏が柏木を「睨み殺した」と言われたほど。
文を盗み読むことは確かにできます。
しかし、それを実行に移すと悪役スイッチが入ってしまうようにも思える。
文を焼き捨てず、文箱に入れっぱなしにして婿入りした道長も悪い。とはいえ、倫子も悪役への一歩を踏み出したのかもしれません。
それを踏まえた上でまひろが文を盗み読む光源氏を悪どく描くとすれば、ドラマとして盛り上がるかもしれませんね。
現代でも、夫のスマホをチェックする妻はよほどのことだと思われます。
フィクションではありがちな描写とはいえ、ある程度のハードルはある。
『源氏物語』はフィクションであることをふまえても、はしたない行為であったともみなせるのです。

画像はイメージです(源氏物語絵巻/wikipediaより引用)
役割を終えたら、文は燃やす
平安時代のモノは、現存するものが少ないとされます。
建造物でも平安京当時のものは平等院鳳凰堂ぐらいであるとされ、

藤原頼通といえば平等院鳳凰堂ですが
藤原行成ほどの伝説的な能書家ならば、さぞや数多の作品が残っているかと思えばそうでもない。
「伝藤原行成書」も含めて、限られた作品が今日まで伝えられています。
日記類は貴重であればこそ、巻数に抜けが生じつつも伝授されてきました。
平安時代の書状は、そこまで多くは残っていません。
『源氏物語』には、光源氏が紫の上の死後、書状を焼き捨てる場面があります。
思い出はあるけれども、見られては困る――そう焼き捨てていく光源氏の姿からは、自らの死を悟っているとも思えるのです。
愛が終われば愛をつないだ文も役割を終える、そんな価値観も感じさせます。
『源氏物語』の作者である紫式部の価値観も、そこにはあるでしょう。
それを踏まえて自分の文を取っておいた道長のことを、まひろはどう思うのか。
しつこい、気持ち悪い、非常識といった嫌悪感が先立つのか?
それとも、私との誓いを忘れていない、民のために政治をする思いはまだあるかもしれない、と希望を抱くのか?
倫子にせよ、まひろにせよ、道長の残した文にモヤモヤは積もりそうです。
ドラマではどう解決するのか。
道長はあの文を、いつまで燃やさず手元に置くのか。
非常に気になるところです。
あわせて読みたい関連記事
-

史実の藤原伊周は長徳の変で左遷され その後どのような生涯を過ごしたのか
続きを見る
-

藤原定子が最期に残した辞世の句の意味は?一条天皇に愛され一族に翻弄された生涯
続きを見る
-

かな書道が光る『光る君へ』「三跡」行成が生きた時代
続きを見る
-

清原元輔(清少納言の父)は底抜けに明るい天才肌~身分低くとも歌人として名を残す
続きを見る
-

本当は怖い「平安京のリアル」疫病 干ばつ 洪水で死体が転がり孤児がウロつく
続きを見る
【参考文献】
高木和子『源氏物語を読む』(→amazon)
倉本一宏『紫式部と藤原道長』(→amazon)
『枕草子』(→amazon)
他