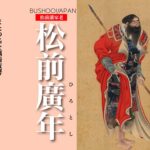こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第25回三人の女】
をクリックお願いします。
米の難局はそうそう乗り越えられない
田沼意次が米の株仲間廃止案を徳川治貞に提案。
意知が詳しく説明します。
株仲間は本来物価安定のため認められているのに、今では結託し、値段を釣り上げている元凶だと指摘します。
自由販売にすれば、安く売って儲けたい者、この機に乗じる者が出てくる。そんな欲深ものを好きにさせてならぬ!と、値下げに動くのだろうとの見通しを語るのです。
これには治貞も納得した様子。
かくして難局を乗り切ったように思える田沼親子でしたが、本当の正念場はここからでしょう。
そんな親子の背をジッと見つめているのは佐野政言と松前廣年。廣年は何かを察知したようで、そんな弟の様子をあの松前道廣も見ている。
いくつもの思惑が交錯する中、一橋治済が登場します。
彼のもとへ、松前道廣と廣年が何か持ち込んでいるようですが……。
MVP:三人の女(つよ・てい・喜多川千代女)
ていが蔦重を陶朱公に喩えたことには、重要な意味があると思います。
渋沢栄一の『論語と算盤』はやたらと拡大解釈され、『論語』の教えを商売に持ち込んだことが優れているとされました。
しかし、渋沢栄一は若くして田舎から上洛し、商売を行っていた。
儒学者でもなんでもなく、そもそもが儒教解釈が正しいかどうか疑ったほうがよろしいでしょう。明らかに誤読しているか、解釈を捻じ曲げた言動も残されています。
『論語』本場の中国からすれば「それは誰でも知っている、むしろ商売特化型マニュアルは陶朱公の教えだろう」となる。
『論語』は人として生きていく上の道徳規範ですので、商業とはまた別の話。
そんな商業神となった蔦重の周りに、三人の女がお供をするかのような回でした。
まずは蔦重を捨てた母。母性の真逆をいくようで、客を呼び込む様は福の神のように思えます。
それに蔦重はこの母親そっくりであることも明確です。この母にして、この子あり。蔦重を産み出した存在が日本橋進出と同時に出てくるというのも、なかなか興味深い話です。
そして二人目は、妻となったてい。
そのていは劣等感を覚えてしまっています。つよのような営業もできない。歌のような才能もない。己の存在意義を見出せておりません。
ていの悩みは、妻の枠をあえてはみださせたような、再定義のようにすら思えます。
結婚したというのに、寝室を別にしていて、心を開くことすらなかった。その個性は客観的に俯瞰してみることで、自分自身にそれを発揮した結果、離縁が最善策だと結果を出しました。
相談もなしに勝手にそんなことをしてしまうていはかなりの変人かもしれませんが、それでもなんとも魅力的であるのが本作のよいところでしょう。
実はていは、ジェンダー的にかなり興味深い造形になっていると感じます。
先週から指摘しておりますが、ていの漢籍教養は男のものとされています。ていみたいに楷書やら候文で恋文が届いたら、相手は「うわあ、なんだこのかわいくねえ女」となります。
それこそ北尾政演あたりなら「無理〜」と逃げ出すってモンです。
笑顔は少ないわ。理屈ぽいわ。お堅いわ。自分でも分析した通り、石頭のかわいくねえ女と思われてもおかしくない。
そう自己分析を始めてしまったのも、自己完結で満足できず、蔦重という存在に心惹かれてしまい、はたして彼に寄り添う像としてふさわしいのか悩んだ結果なのでしょう。
偶然なのか、瀬川のような高嶺の花の花魁こそふさわしいと言いだしたあたり、なんとも切ねえものはあります。
でも、これで瀬川がどういう存在だったのか、かえって理解が深まりました。
高嶺の花、歌舞音曲に優れた天女であるとされる花魁。
彼女たちはいわば人工的な女性美の結晶といえる。
客が喜ぶ文面を流麗な書で書き送る。人工的な廓言葉で話す。化粧に突き出した髷。何本も刺さったかんざし。重たい衣装に高下駄で、不自然極まりない八の字を踏んで道中を歩く。
結局全てが作り物であることが、ていとの対比で見て取れます。
女郎の悲劇とは、性的搾取はむろんあります。それだけでなく、人工的で不自然な美しさの中に閉じ込められていることではないかと、ていは伝えてきたように思えるのです。
蔦重はそこを理解しているからこそ、ありのままのていはおもしれえ女だと見抜いた。
こうして見てくると、女性美は江戸も今も、人工的で極めて不自然なモノに見えてきます。
花魁の美は加工され尽くした不自然なものなのだと。そんな美を磨くより、蔦重のようなありのままをおもしろいという相手を探した方がよいのではありませんか。
そして三人目の女は、喜多川千代女でした。
その正体である歌麿も、ジェンダーがあえて曖昧な造型にされております。
女郎の子として生まれ、強引に男娼にされてしまっていた過去には、男性も性的搾取に晒される残酷さがありました。
ドラマの初回冒頭で蔦重に救われ、それが行方不明となった際には、蔦重は悲しみ、再会を待ち望んでおりました。
ドラマの序盤のヒロインは瀬川のようで、実は歌麿との方が劇的な関係が多かったものです。そして再会を果たしたあと、義兄弟となった二人は極めて幸せなときを過ごしておりました。
蔦重は歌麿のために日本橋に出たいという一方で、歌麿は有名にならなくてもよいから吉原に止まりたいと訴える。
蔦重の縁談に衝撃を受ける。そして今回、出て行きたいとすら言い出す。
彼の思いは複雑です。本当に生まれ変わって女になって、蔦重と夫婦として添い遂げたいのか。それともただ、二人でずっと一緒にいたいのか。
あの川縁を二人で思い切り駆け抜けたときが、幸せの最高潮だったのか。
『光る君へ』に続き、日本を代表する創作物の背景に愛があると描くこのドラマ。
視聴者が歌麿の作品を平常心で見られなくなるところまで含めて、描きたいのでしょう。
神になった蔦重の背後に並ぶ三人の女たち――なんとも凄まじいものを見せられました。
ついでに言いますと、『べらぼう』では擬人化した儒教朱子学がていです。
『麒麟がくる』では光秀でしたね。
ていは親孝行こそ美徳だと信じておりますので、義母であるつよが無茶振りをしてきても、おとなしく服従しています。
一方で蔦重は「べらばあめ!」と罵倒してしまう。
夫婦で対比させてきていると思えます。
総評
三人の女が揃って、姦しいどころかなんとも悩ましい回でした。
そのことはさんざん書いてきましたので、歴史を振り返りたいと思います。
前にも指摘しましたが、戦国時代のドラマは、実は日常生活においてさして役に立たないと思えてきます。
それに引き換え、今回は現実社会とリンクしすぎていると思える。
田沼意次の焦燥感。太田南畝の米を求める叫び。米屋の前で列を作り、品切れで声を上げる人々。
こりゃ実際のニュース映像じゃないかと不思議な気持ちにすらさせられました。
蔦重は、米一粒も作れないと自虐的なことを語っておりましたね。
これもコロナ禍においてエッセンシャルワーカーが重視されたことを思い出すと、実感としてある言葉のように思えてきます。
この米政策に関していえば、単純に現在の状況と結びつけることも避けたいところです。
株仲間解散の流れは今も通じるようで、当時と今ではシステムがまるで異なることは踏まえておきたい。
今回の米に関する描写は、さまざまな要素が絡んでいます。
たとえば気候です。
気候変動と歴史の関係は切っても切れません。
天明年間は世界規模で災害と気候変動が起きました。農業大国フランスでもその影響を受け、穀物価格が暴騰したことがフランス革命につながっています。
日本史と大河ドラマで振り返ると、『鎌倉殿の13人』の時代も天災による不作が起きています。
あの劇中序盤でも、米がないという場面がありました。坂東武者は「平氏が悪ぃんだ」と不満を爆発させておりましたが、根底には気候不順もあったわけです。
当時は貨幣経済が未発達ゆえ、農作物を保管して換金する発想がまだありません。そのため今回言及されていた蔵米すらなかった。
鎌倉時代以降、宋銭が導入され、やっと備蓄する発想が出てきます。そうはいえども乱世が続きますので、食料備蓄整備は江戸時代になってからのこととなります。
平安後期から鎌倉時代よりは格段に良くなったようで、田沼時代ともなると別の要素も出てきます。
江戸時代前半、日本各地では米の生産高が増え、いくつも米どころが生まれてきます。
それは大変素晴らしいことのようで、本来、寒冷で稲作に必ずしも適していない奥羽でも稲作へ置き換わってゆきます。米本位で換金しやすいため、そうされてしまったのです。
五穀豊穣という言葉があるように、気候や土地ごとに栽培する穀物は変えるべきもの。それが稲作ばかりが強くなった結果、気候不順に弱い状態となってしまいました。
貨幣経済がないならないで、備蓄する発想がないことは前述のとおりです。かといって、過度なマネーゲームが勃発してもそれはそれで危ういのは今回描かれた通り。
人間の生活インフラや衣食住に直結する事柄、福祉に過度な資本主義を取り入れるとろくなことになりません。
赤字になるからといって交通網や水道を廃止されたらどうなるか。
結果は実際のところ江戸時代の時点ですでに出てきていたということになります。
こうしてみてくると、実にこの時代の大河ドラマは勉強になる、有用だと思えてなりません。
近世から近代へ向かう胎動が聞こえてくるのが、いわばこの時代です。
ひとつの時代が変わりゆくその痛みも含めて味わえる。
江戸時代中期を扱う意義は実に深い。
そしてそれがこうもリンクしてくるということは、あっしも時代の変化に立ち会っているのかと妙な気分にさせられるドラマです。
天意と噛み合っているのではないかと毎回驚かされてばかりです。
あわせて読みたい関連記事
-

『べらぼう』高岡早紀演じる蔦重の母つよ(広瀬津与)を史実面から深堀り考察!
続きを見る
-

『べらぼう』橋本愛演じる“てい”は勝ち気な地女~蔦重とはどう結ばれるのか
続きを見る
-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察
続きを見る
-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット
続きを見る
-

『べらぼう』ひょうろく演じる松前廣年(蠣崎波響)史実ではアイヌ絵で有名な凄腕絵師
続きを見る
【参考】
べらぼう/公式サイト