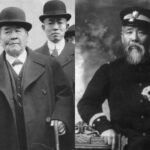こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第39回白河の清きに住みかね身上半減】
をクリックお願いします。
貞女の覚悟
ていはゆっくりと目を覚まします。
彼女は半分目覚めつつ、人の話す声を聞いていました。
彼女が目覚めたのは公事宿。訴訟に出てきた人たちが泊まる宿でした。
目覚めると眼鏡を掛けるてい。最愛の父が残した眼鏡が勇気づけるようです。
彼女は宿に集まった人々の元へ入ってゆきます。
そして倒れて煩わせてしまったことをまず詫びる。夫とは違い、迷惑をかけたらまず謝るところが彼女の美徳です。そのうえで、蔦重の命乞いはできまいかと訴えます。
鶴喜は冷静に、累が及ぶことを考えればできないと答えるしかない。皆、家族も店もあるのです。
ていは即座に理解し「愚につかぬことを申しました」と返すしかありません。
「訴え出られるとすれば、おていさんしかいません」
鶴喜にそう言われ、ていは顔を上げます。
宿屋飯盛が続けます。
「いえね、公事宿の連中がぼやいてんですが、厳しいお裁きってなぁ、朱子学の説くところとは矛盾してるんだよなぁ、って」
「では、その矛盾をつけば……」
平蔵は、うまくいくとは限らぬと忠告を入れます。かえって怒りを増すこともある。命乞いをした者もただでは済まされぬ。そう懸念しているのです。
しかし、ていは覚悟を決めたようです。
「……参ります。座して死を待つだけなのであれば」
入牢から十日経ちました。蔦重は、京伝や行事らを巻き込んだことを詫びつつ、これだけ長いならば何か揉めている、大丈夫だと言います。
「大丈夫(でぇじょうぶ)だ、大丈夫……」
己に言い聞かせるような蔦重です。
ていと栗山の朱子学問答
「面をあげなされ」
ていは平蔵に見守られつつ、柴野栗山の前におりました。
なぜ栗山が会っているのか?
鶴喜にせよ、平蔵にせよ、ていが門前払いされる可能性については語っておりません。
それというのも、ここで定信がそうしたら朱子学の教えに背きます。
妻が夫の命乞いをすることは「貞」そのもの。ていの場合は父の店を守りたいのであるから、「孝」でもあります。そういう心掛けの正しい相手をすげなく拒むことはできず、聞き入れるものです。
一例として、孝女ちか子でも。
彼女は祖父と父が抜け荷で入牢した際、奉行所に無実を訴え出たとされます。講談やら何やらで脚色され、冷たい川で水垢離をしたとまで展開され、浮世絵の題材にもなりました。

月岡芳年『月百姿 朝野川晴雪月 孝女ちか子』/wikipediaより引用
栗山は、会う時点でていを認めているため、柔らかい顔に見えます。
彼女は丁寧に挨拶をしながら、『論語』を引用します。
子曰く、之を導くに政を以てし、之を斉(ととの)えるに刑を以てすれば、民免れて恥なし。
これを導くに徳を以てし、これを斉うるに礼を以てすれば、恥有りて且(か)つ格(いた)る。
民を導くために政策を用い、また治めるために刑罰をもってすれば、民は法律の穴をみつけ、恥じないようになる。
徳により民を導き、礼をもって国を治めるならば、民はおのずからその身を正すようになる。
栗山はこう返します。
君子は中庸し、小人は中庸に反(はん)す。
小人が中庸に反するは、小人にして忌憚(きたん)無きなり。
君子は中庸であるが、小人は中庸に反する。
小人が中庸に反するのは、小人は恥ずかしいと思う心がないからだ。
ていは、定信の政治批判をしているといえる。
政策と刑罰で政治を実現しようとすれば、治める側は抜け道を見つけます。そうではなく、徳と礼による統治をすべきではないか。
そうすれば民は恥を知り、身を正すようになると問いかけたのです。
一方の栗山は、そもそも小人は恥を知らないという。蔦重は二度目であり、恥なんて知らない。許しても改めぬ者を許してどうするのか?と問いかけます。
すると彼女は怯むどころか、花弁のような唇にほんの少し笑みを浮かべ、こうきました。
義を見てせざるは勇無きなり。
そして夫なりの義を説きます。
彼は女郎の苦難が見過ごせぬ。揚代の倹約によって彼女らは苦しめられている。そこで遊里での礼儀や女郎の身の上を伝えることで、なんとか正したいと考えたと誘導します。彼なりに礼儀を守る遊客を増やしたかったのだと訴えます。
そしてこう続けます。
「女郎は、親兄弟を助けるために売られてくる、孝の者。不遇な孝の者を助くるは正しきこと。どうか、儒の道を損なわぬお裁きを願い出る次第にございます」
栗山はじっと考えています。平蔵も、これならよいのではないかと思っているようです。
ていの言葉は全て裏付けと出典があり、江戸時代と文化を考える上でも重要です。
歌舞伎や落語には廓ものや女郎をヒロインにしたものがあります。これは何も助平心だけでもなく、ここでおていさんが言うように、親兄弟のために苦界に身を沈めたという儒教の「孝」の美徳があるとされたからのこと。
ちなみに仏教禅宗の祖である「達磨面壁」と女郎の苦難を重ねることも行われました。達磨は壁に向かい九年間座禅を組んで悟りを得る。女郎も何年間も苦難に耐える。そう両者を重ねたのです。
要するに、日本では女郎の苦難を堕落とみなし、否定するだけではない。そんな考え方があったわけです。
そこをきっちりと回収してきましたね。
なお、こうした考え方は明治時代の「娼妓解放令」により否定されたため、好きで身を売っている女とみなされるようになり、むしろ女郎への蔑視は悪化したとされています。
-

困窮した女性たちが苦海へ落ちる明治時代の深い闇~天保老人ら遊び自慢の陰に泣く
続きを見る
こういう理論展開はおていさんの知識量がなければできません。
定信の懐刀たる柴野栗山と渡り合うとは、やはりおていさんは女諸葛ですね。
そして橋本愛さんにもふさわしい役だと思えます。
おていさんの話にすると眼鏡とか、目力とか、そういうネタばかりで内心残念に思っておりました。
橋本さんは容姿のみならず、心と知性も美しい方であると、週刊文春の連載を読んで思いました。
大河ドラマでは主人公の妻役は三度目ですが、三顧の礼よろしく今回ようやく内面の美まで示す妻の役を得たと私は思います。
漢籍を詠む口調も堂々としていてわかりやすく、実に素晴らしい。橋本さんあってのおていさんです。
蔦重の裁きは「身上半減」
蔦重がついに牢から出されました。
白洲に引き出され、いよいよお裁き。ていと駿河屋の前に引き出されてゆきます。
山東京伝こと伝蔵は、淫らなる風俗を描き、市中の風紀を乱したとして有罪。
伊勢屋吉兵衛、新右衛門も引き出されています。
このあと、蔦屋重三郎は淫らなる書物の発行、風紀を乱したこと、御政道批判により、「身上半減」とされました。
ただ、この「身上半減」がよくわからない罰のようです。
「そりゃァ……縦でございますか? 横でございますか? はっ……身を真っ二つってことにございますよね」
すると初鹿野が、蔦屋耕書堂とその身代の半分を召し上げることだと説明します。蔦重は身体を真っ二つにすると誤認したんだな。
こう説明されて「それは富士より高きありがた山」と軽口を叩いておりますが……駿河屋は階段から落としてやりたいような顔をしています。
初鹿野はあくまで心を入れ替え、真に世のためになる本を出すよう、念押しするのでした。
「真に世のため……それが難しいんですよね。どうでしょう、真に世のためとは何か……御奉行様、一度膝を詰めて……叶うなら、越中守……」
まだ文句たらたらの蔦重に対し、ていの目が眼鏡の奥で光ります。
彼女は立ち上がり、まだ話そうとする夫の頬を叩きました。駿河屋は「やるじゃねえか」と言いたげな表情です。蔦重の折檻担当者交代が、親父から妻へと実現しましたね。
ていは困惑する夫をさらに叩き、こうきました。
「己の、考えばかり! 皆様が、どれほど……べらぼう!」
おていさんが本当に素晴らしいのは、自分が命懸けで柴野栗山と対峙したことは含めていないところです。
あくまで「皆様」と自分以外に迷惑をかけたとしています。蔦重との対比になっていて「俺が!」と押してくる態度とは真逆といえる。
ていは感極まって啜り泣き、その声が青い空に吸い込まれてゆくのでした。彼女の貞女ぶりを見たら、定信も「夫は小人だが、妻は貞女なので許す」となることでしょう。
※続きは【次のページへ】をclick!