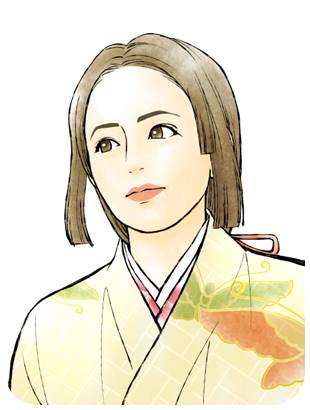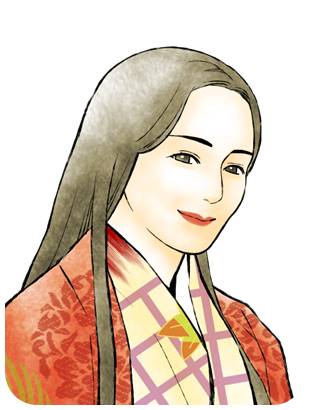天文16年(1547年)秋。
織田信秀に攻めこまれた斎藤利政(斎藤道三)が勝利を収め、その半年後――。
この争いの背後には、土岐頼純の暗躍がありました。
美濃の勢力図が大きく変わる中、父と夫の争いに巻き込まれてしまった女性がいます。
夫・頼純を父・利政から毒殺された結果、寡婦となってしまった帰蝶です。
彼女は儒教規範を踏み越え、父に対して夫のことを謝罪しておりました。
その態度は変わらず、服喪することもなく、髪も長いまま。
本気で夫を弔うのであれば、墨染の地味な服装をして、読経し、肉食を辞めて、尼削ぎにしてもよいところなのですが。
帰蝶はそういう性格ではないようです。でも、彼女の心が傷ついていないとは、言い切れません。
彼女は引きこもるどころか、馬で出かけてゆきます。
川口春奈さんの乗馬にはもう、敬服しかありません。ご武運を!
菊丸の恩返し
そのころ明智荘では初夏を迎えて稲作の真っ最中。口の中に泥が入ったと言いながら、明智光秀もがんばって農作業をしています。
すると、そんなやり方じゃ駄目だと、ある人物が光秀に声をかけます。
菊丸でした。
第1回の野党襲撃で捕らえられていた三河の民です。光秀に鉄砲のことを教えた人物でもあります。
「ああ、あのときの」
光秀もそう言われ、相手の素性を思い出しています。光秀は優しいのです。なんでも三河まで戻ったところ、母に明智十兵衛光秀様にお礼をしてこいと促されたそうです。
お礼に味噌を持ってきました。ウッ、三河の味噌か。
焼き味噌が溢れただけ……そういうネタはともかくとして、実際に三河の味噌はおいしい! 中部の味噌を使った料理はもう、最高としか言いようがない。
むしろ何がなんでも味噌かけまくって、休日朝にはモーニング食べてますよね。いや、そういう中部の人を無意味に煽るような話はさておき。
菊丸は、餅も持ってきたそうですよ。そして、腹痛に効く薬草もドッサリ!
まさかこんなところで野良仕事をしているとは思わなかったと、菊丸から言われる光秀。
光秀は藤田伝吾が負傷したので、皆で農作業を手伝っているそうです。
その伝吾を支えて駒が歩いています。駒の手当てはよく効くそうです。なんでも薬草が尽きてしまっているそうです。
二人とも気遣う光秀が、本当に優しいんですね。本作の光秀はちょっとした言動に、共感能力と優しさが満ちていて、ほんとうにすごいと思う。
駒は、稲葉山城の東庵も薬草集めが大変だと言います。
ここで菊丸が、どんな薬草かと尋ねるのですが。
「イワソバ草! どこでこれを?」
そう駒に尋ねられ、家の近く、ここに来る途中にもあったと返されます。
カタバミもある! そう喜ぶ駒に、菊丸はそれも近くにある、向こうの麓にあると返すのでした。
「あの……お名前は」
「菊丸」
「菊丸さん! わたしをその場所に連れて行ってもらえませんか!」
「フフッ」
そう意気投合する二人に、光秀は咳払いをしています。
光秀は堺で遊女にデレデレすることもない。極めて真面目な性格だと伝わってきます。
それがいいんですよね!
それこそ、長谷川博己さんにピッタリですし、本作の光秀がそうでなければならない、深い理由はあると思うのです。
帰蝶がやって来る
光秀は、鉄砲で肩を撃たれた与八の具合がよくなったとうれしそうです。
タニシを踏んだ佐助も無理をするなって。
治るかのう……そう呼びかけつつ歩く彼らは、どれだけ光秀を慕っているのか伝わってきます。
戦国時代だろうと、現代だろうと。学校だろうと、会社だろうと、ご近所だろうと。光秀が皆に好かれる性格だとわかりますね。
そこへ帰蝶が馬で走ってきます。
皆は驚いてしまいます。サプライズ訪問のようです。
「帰蝶様、こんなところまで何用でおいでになりましたか」
そう光秀が尋ねると、伯父上の怪我の見舞いだとそっけなく言います。
「それはかたじけのうございます」
帰蝶はそう頭を下げる光秀に、十兵衛が何をしているのか城に来た者に聞いたと言います。農作業で腰が翁のように曲がっているから、それを見るのも一興かと思ったとキッパリ言うのです。
「うっ、ああっ、この通りでございます」
からかってきた帰蝶に付き合う――そんな光秀はしみじみといい奴だと思う。ムッとしたりしないんですね。
帰蝶は子どものように笑い飛ばします。
「そなたの母上に土産を持参した。リスをこれへ」
「リス?」
なんと、帰蝶は木の上にいたリスを、そっと捕まえたそうです。かわいいゆえ、伯母上が悦ぶと思ったとか。ところが、お供が逃してしまうのです。
「愚か者! 紐で結んでおけと申したであろう!」
「申し訳ございませぬ」
苛立ち、ため息をつく帰蝶。しかも結構きついことを言う。
川口春奈さんは魅力的です。そこを差し引いて帰蝶の性格にはきついところがあるという点はおさえておきましょうか。
「もうよい、使えぬ奴じゃ。そちは城へ帰れ……あっ痛っ」
帰蝶は木の登った時、小枝で足を切っていたそうです。さしたる傷ではないものの、痛いと声が出てしまう。
「ご辛抱を」
ここで光秀が怪我を見ます。
帰蝶の痛い傷は、足だけのものでしょうか?
それとも心も?
牧は帰蝶を迎える準備をしています。帰蝶はいきなり行動をする、我慢できないタイプなのかな。怪我が重いのか気にして光秀に確認をすると、こう答えが返ってきます。
「木に登って小枝で足を傷つけた。それだけです」
さて、帰蝶は明智荘で何をしたいのでしょうか。
帰蝶は相談したい
「五十一じゃぞ!」
「まことなのですか」
帰蝶は駒の治療を受けつつ、ケラケラと笑っています。そこへ牧が入ります。
室内にきっちり几帳が置かれていて、帰蝶の治療がいきなり見えないようになっているところが細かいですね。光秀が農作業をしているとはいえ、この家は武士だとわかる。
絵として見ても綺麗で、設計が練られています。
今年は本気だなあ! こういうのが見たかった。
帰蝶は十兵衛の弱みを握っていると母である牧に言います。これをいうと、十兵衛はこそこそ逃げていくとか。伯母上はご存知ないと前置きをして、駒に同意を取りつつ、もったいぶって言うのです。
帰蝶はよくここに遊びにきて、双六遊びをしたもの。五十一回遊んで、全部十兵衛が負けたとか。
このとき、別室でその光秀がくしゃみをして、風邪かと気遣われ「違う!」と即答しているのですが。
なんでしょうねえ。
光秀が本当に弱い?
帰蝶がやたらと強い?
それとも光秀が、負けず嫌いな相手のためにわざと負けてあげていた?
帰蝶は、ここへ来ると懐かしいと言います。子どもの頃を思い出すのだと。母・小見の方ができたばかりの稲葉山城にいて、この館に預けられて一年ほどいたそうです。
伯母上はお話が上手で、夜になると話してくれた。そう帰蝶は振り返ります。
狐の娘と若者と
どういう話か?興味を持つ駒。
ここで美濃の狐の話を始める帰蝶です。
むかしむかし、村の一人の若者が、お嫁さん探しの旅に出ました。
ある野原で美しい娘を見つけ、大層気に入って嫁にしたのです。
かわいい子どもがいて、幸せに、幸せに暮らしていたけれども。
犬がその娘に吠えて仕方ないのです。
その娘は、狐でした。
犬がほえて娘に迫り、娘は若者の前で狐の姿を見せてしまいます。
ここで暮らすことはできないと、子どもを残して出て行ってしまうのです。
そう聞かされ、駒はこう言います。その若者は歌うのでは? そう言い、歌を口ずさむのです。
わたし一人残して
玉の光のように
ほんのわずかの間で
おん前は消えてしまった
「少し違うけれど、そなたは京から来たのに、どうしてこの話を?」
これは美濃に古くから伝わる話だと、不思議がられます。
駒は、それをある人から聞いたことがあると思い出しているのでした。その教えた方は美濃の方かも……そう運命を感じます。
『日本霊異記』に、美濃の話として残っております。
こういう「狐女房」は中国大陸から伝わってきているものではある。安倍晴明も狐の母・葛の葉を持つという伝説がありますね。そこをふまえても有名で古いものとなれば、美濃のものではあるのです。
他愛ないようで、悲しい話かもしれない。
かわいい子どもも生まれ、幸せに暮らしていたのに。普通の人とは違うだけで、去ってゆくその妻も。去られる夫も。そういう別離は悲しいものです。
ここで光秀が、すぐ城にお戻りになるようにと使いが来たと告げます。
「ではまた城で。伯母上、今日はかたじけのうございました」
「歩けますか」
「心配いりません。十兵衛、話があります」
帰蝶はそう告げると、廊下で夕陽を浴びながら語るのです。
「夫の土岐頼純が相果てたいきさつ存じておるか? 皆はどう思うている? それを知っておきたい」
光秀は叔父上から聞いただけだと前置きして、語り出します。
「どう聞いた?」
頼純様が尾張の織田信秀と密かに通じ、あの戦を起こすよう陰謀を練った。それゆえ、利政は頼純を亡き者にした。そう伺っていると。
「それを聞いてどう思うた?」
「……やむを得ぬと。理由はどうあれ、守護のお立場にある頼純様が、他国の手を借り、美濃が戦に巻き込まれたのです。やむなしと」
帰蝶は物足りないような、それでいて吹っ切れたような顔で光秀を振り返ります。
「わかった」
「ただ……頼純様とお父上である殿との間に立たされた帰蝶様のお気持ちは、誰もがよく承知をいたしております。母も胸が痛むと」
そう聞いて、帰蝶は何か胸に染み込んだような顔になります。
気丈に振る舞って、感情の処理を終えたように見える帰蝶。けれども、理屈では納得してやむなしと思っても、胸に何かわだかまりがある。
十兵衛なら、そのわだかまりを軽くしてくれるかも。そんな気持ちがあればこそ、二人きりで話したのではないかと思えるのです。
誰かが、やむなしと片付けるのではなく。むしろ気遣って、見て見ぬ振りをするのではなく。自分の気持ち、傷ついた心に少しでも目を向けてくれたらば。
そういう救いを求めて、ここまで来たのかな。そう思わせるものが、光秀にはあるのかな?
そう思えてしまいます。
駒が治療の後片付けをしていると、光秀が入ってきます。
駒は、牧が帰蝶様のお供に蒸し菓子を差し上げると表へ行ったと伝えます。
「お優しい母上様ですね」
駒はしみじみとそう言います。そうなんですよね、明智母子はともかく親切だということが見て取れる。駒に対しても、何度も世話になったと頭を下げるそうです。
駒は不思議な話を伺ったと切り出します。
私が子どもの頃、火災から助けてくださったお武家様は、慰めようといろんな話をしてくれたのだと。
その中に、狐と若者が一緒になる話があった。それと同じ話を、母上と帰蝶様がしてくれた。
「ひょっとして、私の命を助けてくれたのは、美濃の方かもしれません。美濃に連れてきてもらえてよかった」
「もしそうなら、そのお侍に会えるといいですね」
「はい、会いたいです! 私の命の恩人だから、いろんないいお話を教えてくれた人だから。会ってみたい」
光秀は微笑みます。
さて、このお武家様は誰でしょうか。
光秀の父? それはあり得る話ですけれども。
私は誰でなくてもよいとは思います。名もなき人が、誰かの一生を変えるような親切をして、去ってゆく。
そのことそのものが、大きな意義であり、素晴らしいことだとは思う。
何かで成功するとか。セレブになるとか。
そうでなくとも、こういうことをできる人は勇気があって素晴らしいのです。光秀は、そういう名もなき英雄に通じる何かがある人物設定なのでしょう。
土岐頼芸は鷹を描く
ここで土岐氏の説明が、家系図入りで入ります。
土岐氏は言辞の流れを組む名家であり、美濃で絶大な権力を保持しておりました。
それが分裂し、権力が衰えていた。
日本全国、どの地域でもそういう家はあったものです。乱世あるある。
土岐氏は、土岐頼芸とその兄・土岐頼武が争ってきました。毒殺された頼純は、頼武の子です。
ここで鷹の鳴き声が響きます。
土岐頼芸は一度は守護になったものの、今は家臣・斎藤利政(斎藤道三)が実権を握っており、隠居同然の生活を送っているのです。
「山城守、お越しにございます」
そこへ斎藤父子がやって来ました。
「利政、楽にいたせ」
そう言い、頼芸は鷹を描くのは辛いと言います。苦であると。
土岐氏といえば、鷹の絵が有名、祖父・土岐成頼より、父・土岐政房が継いだ輝ける画材なのだそうです。今回セットに飾られているものも、現存するものを複製したとか。
そんな祖父や父のように描けるか悩んでいるそうですが、問題の本質はそこではありません。本業が順調ならば、高尚なご趣味でございます。が、そうでないと暗君の手慰みでしかないと。
己の苦しみを訴える頼芸ですが、それで利政の良心が痛むわけがありません。ここで、ズバリこう来ました。
「利政、そなた頼純を殺したそうじゃな」
「私が? 頼純様を? 誰がそのような世迷いごとを申しました?」
「女どもがそう申しておるぞ」
ここでしらじらしい演技から一転、利政はため息をつきます。
頼純様は土岐家の大事なお世嗣、頼芸の甥御なのに殺すはずはない。そうシラを切りつつ、嫌味も放つ。
そう責めるお前だけれども、お前の敵を始末してやったぞ。そういうふてぶてしさがあるのです。
「あの戦を起こした張本人であることを恥じられ、自ら毒をあおられたのでございませぬか」
利政はそう言う。
なるほど、それでああいう殺し方ですか。
確実に殺すのであれば、服毒よりも物理的手段が効率的ではあります。岡田以蔵やラスプーチンのような例もありますからね。
けれども、こういう名目にするのであれば、あの毒殺は理にかなっております。
シラを切られ、頼芸は「親子揃って何用なのか」と聞いてきます。
頼純死後、守護不在となった美濃。
これではまずい、すみやかに世継ぎを決めねば政治が滞ると、相談に来たのだそうです。
頼芸は守護がいようがいまいが、今や土岐家は操り人形だと自嘲します。守護になってそなたに毒を盛られたくないと、嫌味を返す。
頼芸は頼純より賢く、なかなか厄介なものがあるようです。本作の凄みは、本当に愚かな人がいないところだとは思う。
先週の織田信秀が愚将だという意見も見かけましたが、相手がぶっ飛びすぎていただけで、彼の判断は理解できるまっとうなものだったとは思うのですね。
「……操り人形に毒は盛りませぬ」
そう前置きをして、利政は正直に言います。
戦で街が焼けました。田畑も荒らされました。一刻も早く、元の街に戻さねばなりませぬ。
その復興に、利政ではどうしても壁に当たってしまう。国衆が乗ってこない。今はみ皆で力を合わせねばならないのに、これでは立ち上がれない。土岐家が声をかければ、皆動くと。
「どうかお力をお貸しください」
そう頭を下げるしかありません。
これが本作の重要な点なのでしょう。
合戦からの復興を、最近の出来の悪い大河はあまり真面目にやっていなかったとは思う。
戊辰戦争にせよ。西南戦争にせよ。太平洋戦争にせよ。
復興の過程がミニマムか、カットされるか。
そこを本作は逃げない。美濃が勝ちました。それで終わりか? いいえ、そうではないのです。
もうひとつ、戦に勝利する策だけではない。そういう合理性だけではなく、人の心に共感し、慰撫し、動かす力。それもないと勝利できないというテーマを感じます。
このあと、侍女が高政(斎藤義龍)に「しばしお待ちを」と言います。
頼芸が笑顔を浮かべ、高政に近づいてきます。
「高政殿、お母上の深芳野殿にお変わりはないか?」
几帳面に「つつがなく」と答えると、頼芸はこう言い出すのです。
「元はと言えばこの館でともに過ごした女性じゃ。よろしう伝えてもらいたい。……そなたの父は頼りにならぬ。わしが頼りとするのはそなたじゃ」
そして扇で口元を隠し、こう言うのです。
「我が子と思うて頼りにしておるぞ」
かしこまってこの言葉を受け取る高政。
利政は頼純に毒を盛りました。
けれども、頼芸にそうはできない。それどころか、逆に毒を盛られたのです。
背後にいた利政は、それに気づいたかどうか。気づいたにせよ、鼻で笑い飛ばしたのか。
一方で息子の高政は心が濁った瞬間です。
頼芸は足音を鳴らして、戸を開けて織田信秀に使いを出すよう家臣に命じます。この美濃をあの成り上がり者から取り戻すのじゃ。そう意気込んでいます。出兵を促し、手立ては選ばぬと言い切るのです。
本当におそろしい人物とは、無害無能を装える者かもしれない――そう鮮やかに見せる本作のお手並みをじっくりと味わいました。
このあと、高政が父を見つめる目は疑念で濁っています。
我が父は誰か
高政は父に冷たい目を向けてつつ、廊下を歩んでゆきます。
そして雨が降るしきる中、母・深芳野の部屋に向かっていくのです。
頼芸の伝言を聞き、深芳野は乾いた声音で嫌悪を口にします。
「ははっ、いやらしいお方じゃ 人の気を引くようなことをいつまでも」
「別に母上の気を引く為仰せになられたとは思いませぬが」
「私の気を引く以外に、誰の気を引くのじゃ。昔側にいた女子が今になって懐かしくなって、さてもしくじった、家来にくれてやるのではなかったと、ほぞを噛んでおられるのじゃ」
うーん、ここで母子揃って誤解していると思う。
頼芸の狙いは、深芳野ではなく高政でしょう。高政の心に疑念という毒を盛ればよろしい。
「母上にお聞きしたいと思うていたことがあります」
「ん?」
「このところずっと心を離れぬことです。私の父親は、まことにあの父上でございますか? 私の父親は、頼芸様では?」
「何をたわけたたことを! そなたの父親はまぎれものう殿じゃ、わかったか!」
これは高政の妄想とは言い切れないところです。
寺で漢籍を習ったからには『史記』のことは知っている。あれには、始皇帝の父が呂不韋だと記されている。
懐妊期間をふまえて、現在では否定されたこの説。それでも司馬遷が記し、かつ医学知識が曖昧な時代は史実として通ってしまう。
高政の胸には、当然のことながらこのことが渦巻いていることでしょう。
そしてこの場合、一番悪いのは高政でも、頼芸でも、深芳野でもありません。その悪い男は、雷鳴の響く中、この部屋に入ってきます。
「殿〜!」
これは利政が悪い。
どれほど妖艶な美女だろうと、相手の心を踏みつけるためだろうと。主君の手がついた女を欲しなければこんな疑惑は生じようがない。
深芳野の発言権も選択権もここではなかった、物のように取引されたからには、彼女を妖婦だの悪女だの貶めるのも、筋違いです。
そして……。
※続きは次ページへ