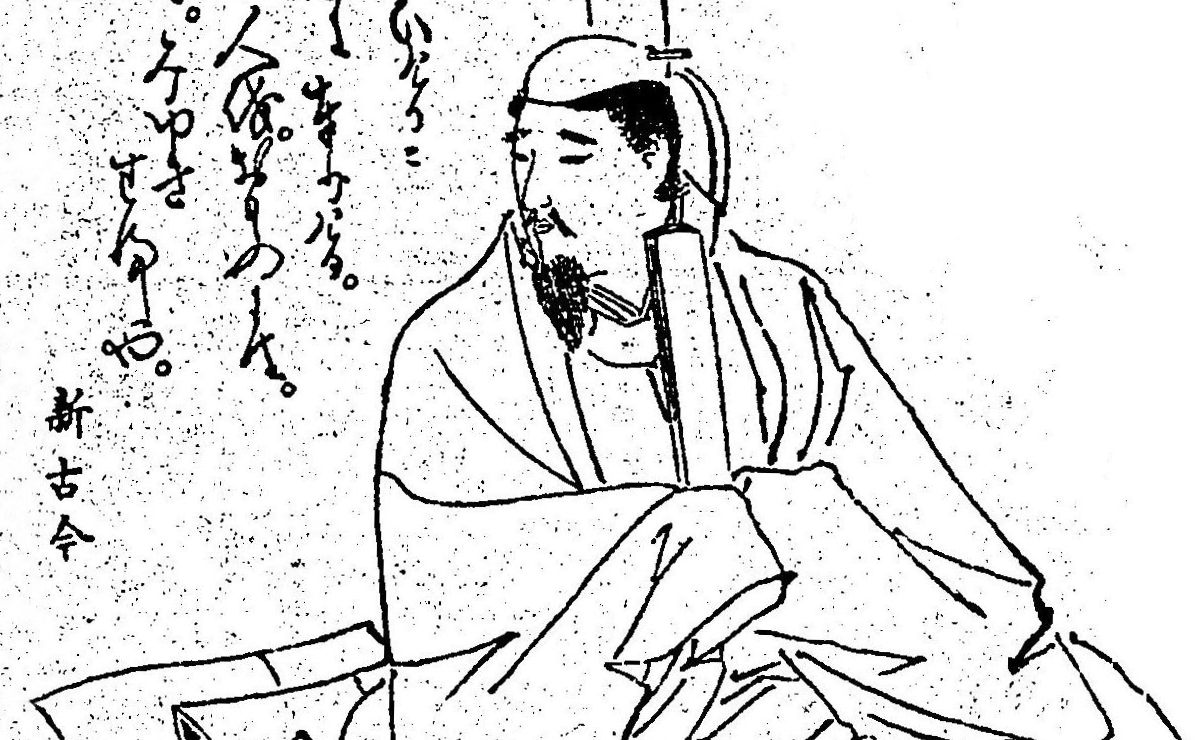こちらは2ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【源雅信】
をクリックお願いします。
ついに政敵・道長に娘を嫁がせる!?
源雅信も後宮政治に全く興味がなかったとか、自ら禁じていたわけではなかったようです。
彼は子々孫々のため、自慢の娘である倫子をいずれかの天皇に入内させることを考えていました。
しかし、年齢の釣り合う花山天皇は退位してしまい、入内先選びが難航。
上皇に娘を嫁がせて皇子が産まれたとしても、皇位を継承できる可能性はとても低くなってしまいます。
その矢先に、雅信にとっては政敵である兼家の四男・道長に「お嬢さんを僕にください!」(※イメージです)と申し込まれるちょっとした事件が起きてしまいます。
当時の道長は兄たちとの政争に勝てる見込みがなく、将来性があるとは言いがたかったため、雅信はこの結婚に乗り気ではありませんでした。

『紫式部日記絵巻』の藤原道長/wikipediaより引用
しかし、雅信の正室・藤原穆子(ぼくし or あつこ)が、以下のような理由から道長と倫子の結婚に賛成します。
・一条天皇は倫子より16歳も年下である
・ときの皇太子(後の三条天皇)も8歳下で、釣り合うとは言いがたい
・無理に倫子を入内させるよりも、将来が未知数な道長に嫁がせ、いずれ産まれる姫(自分たちにとっての孫娘)を入内させるほうがいい
こうして穆子は、倫子を半ば強引に道長とくっつけてしまったのだそうです。
双方の父である雅信も兼家もボーゼンとしていたとか。カーチャンつよい!
道長と倫子は仲睦まじく2人の間に彰子が生まれる
すったもんだな経緯ではありましたが、道長と倫子の夫婦仲は良好。
結婚の翌年に藤原彰子が産まれています。
後に一条天皇の中宮となり、紫式部などによる華麗な文学サロンを開くあの人です。

画像はイメージです(『源氏物語絵巻』/wikipediaより引用)
雅信は彰子が2歳のときに73歳で亡くなっているため、孫娘やそれ以降に続く一族の繁栄を見ることはありませんでした。
同時期に道長は兄たちを蹴落として藤氏長者になっており、穆子の目が正しかったことが証明されます。
そのため、道長も穆子には頭が上がらなかったとか。義理でもカーチャンはつよいなあ(小並感)
ちなみに、穆子も倫子も80代後半~90歳まで生きています。彰子が長生きだったのも、母や祖母の遺伝だったのでしょうね。
他にも雅信の子孫はいくつかの公家や武家の佐々木氏に続き、栄えていきました。
なお、道長は倫子より前に醍醐天皇の第十皇子・源高明(たかあきら)の娘・源明子を妻にしていました。
しかし高明が雅信よりも先に亡くなっていたために、明子の後ろ盾はないも同然で、これも倫子とその子供たちが出世していくきっかけになっています。
高明は延喜十四年(914年)生まれで天元五年(983年)に亡くなっているので、雅信と大差はありません。
もしも高明と雅信の死去の順番が異なっていれば、倫子の子供である彰子や頼通と、明子の子供である能信(よしのぶ)の言動は入れ替わっていたかもしれません。
こういう紙一重な歴史ってワクワクしますよね……。
あわせて読みたい関連記事
-

暴力事件を繰り返し摂関体制を狂わせた 藤原能信(道長と明子の息子)がヤバい
続きを見る
-

なぜ源倫子は出世の見込み薄い道長を夫にしたのか? 超長寿90年の生涯に注目
続きを見る
-

道長も頭が上がらない藤原穆子(倫子の母)はどんな女性だった?超長寿の生涯86年
続きを見る
-

なぜ皇族から源氏や平氏が出てくるのか「臣籍降下」による皇位皇族の法則
続きを見る
-

骨肉の権力争いを続けた藤原兼家62年の生涯~執拗なまでにこだわった関白の座
続きを見る
【参考】
国史大辞典
源雅信/Wikipedia