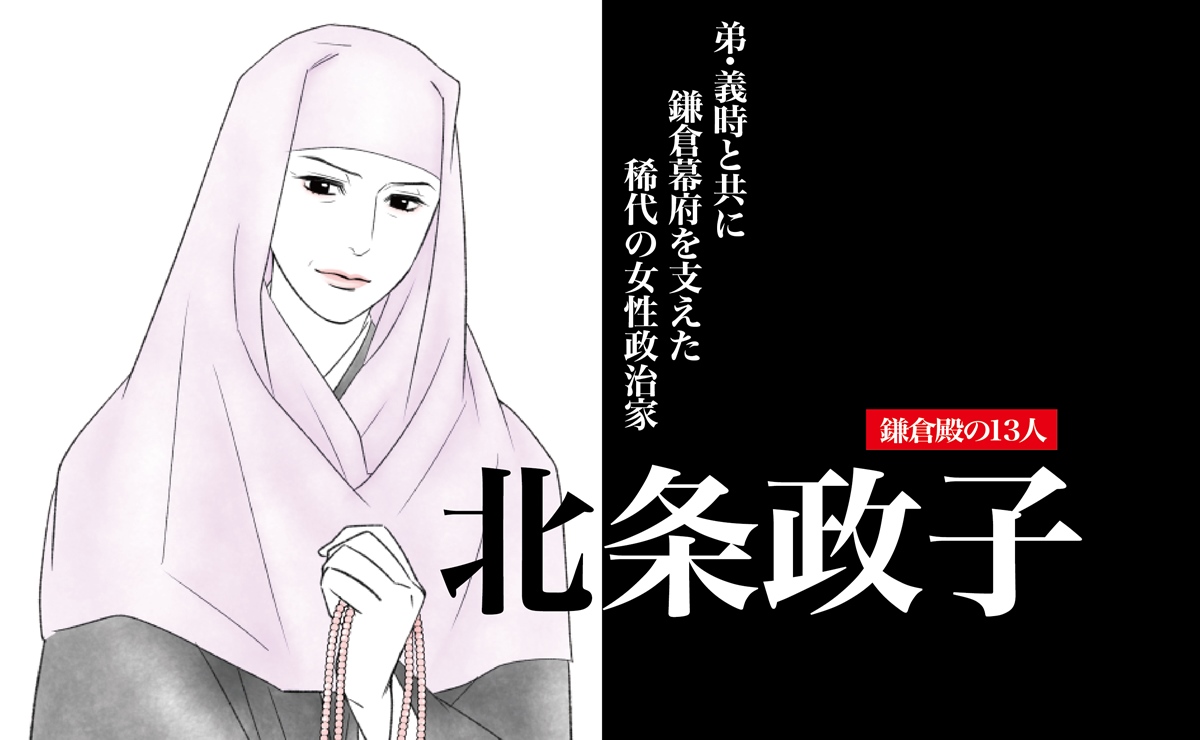生前は嫉妬深かったとされる逸話や、承久の乱での大演説など、なんとなく“キツイ女性”というイメージの方が多いかもしれません。
日本三大悪女の一人とも言われたりしますしね。
しかし、生涯を追いかけてみると、必ずしもマイナス面ばかりの人物でないことを感じさせられます。
特に昨今は、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で小池栄子さんが、逞しくも賢い女性を演じられ、その印象が大きく変わりつつありますよね。
史実においては、夫の女癖に厳しい一面は確かにあるけれど、不幸な身の上の者たちには慈悲深い政治家――。
嘉禄元年(1225年)7月11日はそんな北条政子の命日。
その生涯を振り返ってみましょう。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
時政の長女・北条政子
北条政子は保元2年(1157年)、伊豆の豪族・北条時政の長女として生まれました。
北条氏は現在の東海道線三島駅から東南にある北条を発祥とする一族で、領内の狩野川流域が肥沃な土地だったため、かなりの財力を持っていたと考えられています。
そんな彼らの運命が動き出すキッカケは永暦元年(1160年)。
【平治の乱】に敗れた源義朝の三男・源頼朝(数え14歳)が流されてきました。
※以下は平治の乱の関連記事となります
-

伊豆に流された源頼朝が武士の棟梁として鎌倉幕府を成立できたのはなぜなのか
続きを見る
当時の政子は4歳。
彼らの年齢差についてはあまり触れられることがありませんが、10歳も離れていたんですね。
流罪になったといっても、頼朝は一つ所に監禁されていたわけではなく、かなり自由な暮らしをしていました。
京の乳母や比企氏の支えもあり、生活の心配もなかったようです。
ある意味、悠々自適だったことでしょう。北条氏を含め、伊豆・相模など現地の土豪たちと一緒に狩りを楽しんだり、一族の菩提を弔うために読経したりしていました。
その中で時政とも知り合い、いつしか政子と深い仲になったと思われます。
とはいえ、娘と流刑者が結婚するというのは、父親としてはあまり歓迎したくない状況。
時政は慌てて政子を別の人へ嫁がせようとしましたが、政子が抜け出して頼朝のところへ逃げたので、諦めて二人の仲を認めたといわれています。
-

なぜ北条時政は権力欲と牧の方に溺れてしまったのか 最期は政子や義時に見限られ
続きを見る
そういった経緯のため、政子と頼朝の結婚がいつだったのか、具体的な日時ははっきりしていません。
長女・大姫が治承2年か3年(1178・1179年)生まれとされているため、それより前だったことは間違いないのですが。
頼朝の挙兵
長女誕生からさほど経たない治承4年(1180年)4月、頼朝の下へいわゆる【以仁王の令旨】が届きます。
この頃には北条政子との仲は認められ、時政との仲も親密なものになっていました。
しかし、以仁王が敗れ、それについた源頼政も敗死。
続いて平家打倒に動いた武士が追討されると聞いたため、すぐには兵を挙げず、関東の武士たちへ協力を呼びかけて時節を待ちます。
そして治承4年(1180年)8月、頼朝が挙兵します。
まずは伊豆の山木兼隆を討ち取ると、流刑生活中に親しくなった武士たちとも一致団結することができ、とりわけ時政とは腹を割って話す間柄だったとされています。
楔となったのが、言わずもがな政子。
旗揚げの時期、政子はただひたすら伊豆で頼朝の無事と戦勝を祈っていたようです。
しかし【石橋山の戦い】で、頼朝軍は平家軍の大庭景親・伊東祐親に敗北。
-

大庭景親は相模一の大物武士だった~それがなぜ一度は撃破した頼朝に敗北したのか
続きを見る
-

伊豆の武士・伊東祐親が孫(頼朝の子)を殺害~平家と頼朝に挟まれ苦渋の選択
続きを見る
頼朝はもちろんのこと、従軍していた北条時政・北条宗時・北条義時も行方不明になってしまったと聞き、政子は気が気ではありませんでした。
残念ながら兄の宗時は逃げる途中で討死にしてしまいます。
-

北条宗時は時政の嫡男で義時の兄~ドラマのように最期は暗殺されてしまうのか
続きを見る
頼朝・時政・義時はなんとか逃げ延び、いったん安房へ渡りました。
頼朝は安房へ向かう船に乗る前、政子に無事を知らせる使いを出したといいます。
鎌倉を都市に発展させた八幡宮
体制を立て直すため、頼朝は関東の武士たちへ使いを飛ばし、改めて味方になってくれるよう工作し始めました。
その一環として、時政や義時は再び海を渡って甲斐・信濃などの武士や豪族を説得したと考えられています。
おそらく北条政子には知らされていたでしょう。
さすがの彼女も、そういった状況では駆けつけられず、夫婦の再会がかなったのは、頼朝が鎌倉入りをした後でした。
頼朝は、鎌倉の人々に受け入れられるように、まずこの地で信仰されていた鶴岡八幡宮を源氏の氏神として敬いました。
当時は海岸近くにあった八幡宮を、現在の小林郷へ移すと同時に、大規模なお宮を建設。
頼朝自身の屋敷や大姫のための家などもその周辺に建てたので、御家人たちも競って周囲に屋敷を構えました。
これにより鎌倉は、東国一の都市へ発展します。
なんせ、それまで都から来た武将といえば、関東で朝敵を討伐しては帰っていくだけの存在でした。
しかし、頼朝は地元の神社を敬い、屋敷を建てたことによって、「私はこれからこの地に根付く覚悟だ」と示したのです。
これが関東武士たちの心を大きく掴みました。
元々、東国の武士は、頼朝の祖先である源頼義・源義家の活動により、源氏には何かしらの縁を持っています。
ここではその発端である前九年の役と後三年の役には触れませんが、よろしければ以下の記事を併せてご覧ください。
-

前九年の役で台頭する源氏! 源頼義と源義家の親子が東北で足場を固める
続きを見る
-

後三年の役~頼朝の高祖父・義家を「武士のシンボル」に押し上げた合戦を振り返る
続きを見る
これらに加え、妻が都の出身ではなく、鎌倉から比較的近い伊豆出身の政子であったことも、頼朝への好印象を増したと思われます。
長男・頼家の誕生と亀の前
夫婦仲も円満であり、寿永元年(1182年)8月には、長男・源頼家が生まれました。
-

源頼家は風呂場で急所を斬られて暗殺?二代将軍も粛清される鎌倉幕府の恐ろしさ
続きを見る
北条政子の懐妊を知った頼朝は喜び、安産のために祈願をしたり、自ら指図して鶴岡八幡宮と由比ヶ浜の間に参道を作ったりしています。
後者は、現在も鎌倉に存在する段葛(だんかずら)の発祥だとか。
さすがに何回も改修されているので、現在の段葛がそのまま鎌倉時代のものというわけではありませんが……現地へ行かれる方は、頼家誕生の頃を想像してみるのも一興でしょう。

しかし、偉大な頼朝も一人の男。
政子の妊娠中に耐えられなかったようで、伊豆にいた頃知り合った亀の前という女性を鎌倉近くの小坪まで呼び寄せ、寵愛していました。
また、新田義重の娘にも恋文を出していたとか。こちらは本人に突っぱねられた上、義重も政子を憚って、別の男への縁談をまとめたため、未遂に終わっています。
幸い、政子の出産は無事に終わったのですが、亀の前の件は少々尾を引きました。
時政の後妻(政子にとっては継母)である牧の方が、頼朝と亀の前の関係を政子に告げてしまったからです。
当然政子は怒り、牧の方の父(兄とも)である牧宗親(まき むねちか)に言い付け、亀の前が滞在していた伏見広綱の邸を壊させました。
広綱はかろうじて亀の前を連れて逃げ出しましたが、これが今度は頼朝の怒りを買います。
「俺に黙って妾を隠すとは何事か!」というわけです。まあ、勘ぐられても仕方のない状況ではありますね。
宗親は謝罪しましたが許されず、頼朝に髻(もとどり)を切られてしまいます。勝手に出家させられたようなもので、当時の武士にとっては耐え難い屈辱。
これに対し、今度は時政が「妻の一族に恥辱を与えた」と怒って、伊豆へ帰ってしまいます。
まだ平家のことが片付いていないことを考えると、随分なタイミングで内輪もめをしていることになりますが……頼朝は構わず、亀の前を寵愛し続けたといいます。
一方、政子は伏見広綱を遠江国に流してしまいました。
当時と現代では価値観に大きな違いがあるとはいえ、なかなかひどい話です。
こうして夫婦喧嘩は長引きましたが、天下の情勢がそれどころではなくなりました。
木曽義仲が信濃で挙兵し、その後京都で諸々のしくじりをしたことによって、立場が危うくなっていたのです。
※続きは【次のページへ】をclick!