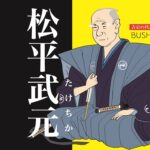こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第6回鱗剥がれた『節用集』】
をクリックお願いします。
ありがたく受け取って、噛み締めて前へ進め
柏原屋から奉行所に相談があった――平蔵が手入れに入った経緯を蔦重に告げます。
訴えたいものの、江戸の板元の口が堅い。「丸屋源六」の正体が掴めない。
普段なら「おめえらが調べろ」となるところを、この件については何故か上から鱗形屋を調べろと命がくだった。
あの贈賄大名を庇った田沼一派の差金でしょうな。
平蔵は、探りを手伝っていたと言いつつ、鱗形屋の前で椅子に腰掛けます。
当時のこうした椅子は座る時以外はひっくり返しておいて、座る時に立て、立ち上がったらまたひっくり返す仕組みです。
平蔵は奉行所ではなく、御書院番士を務めていたようです。
無役を脱したのはよい。三河以来の名門でなければ就けない役ではあります。
しかしこれが性に合わないんだってよ。んで、奉行所に移るために顔を売っているんだとか。
ちなみにあの与力は江戸のモテ男ベスト3こと「江戸の三男」に入る役職でさ。残りは火消しと力士ですね。
町人は、なんとなく武士が煙たいもの。しかし与力は町のトラブルを解決するし、町人に距離が近いってんで、モテました。
平蔵も、与力になってモテたいのかもしれない……と思いましたが、町人と近い役目があっているということですかね。
そしてここが平蔵のよいところ。
佐野政言も、平蔵も、三河以来の名門旗本でして。佐野はその由緒を使い、田沼に取り入ることで打開しようとする。一方で平蔵は、顔を売り込むことで打開しようとしているのです。
トップダウンで打開しようとする佐野政言か。
ボトムアップで打開しようとする長谷川平蔵か。
この対比があるわけですな。
そんな平蔵は懐から粟餅を取り出し、食べ始めます。
鱗の旦那の悪行も、柏原屋が騒いでいることも知っていたと打ち明ける蔦重。そのうえで一言「危ねえ」といえばこうならなかったと悔やんでいますが……。
「何故言ってやらなかったんだ?」
「そりゃあ、心のどっかで望んでたからっすよ。こいつがいなきゃ、取って代われるって」
「じゃ、願ったり叶ったりじゃねえか」
平蔵にそう言われ「濡れ手に粟」「棚からぼた餅」とつぶやく蔦重。
腰を下ろし、こう言います。
「俺ぁうまくやったんでさ。けど、うまくやるってなぁ……堪えるもんっすね。すいません、つまんねえこと言って」
そう頭を垂れてしまいます。
いい奴だな、天下太平だな。真田昌幸なら室賀正武を謀殺成功してもこんな態度をしなかったもんな。
「武家なんて、関取争いばっかりやってるぜ。出し抜いたり、追い落としたり、気にするようなことじゃねえよ。世の中、そんなもんだ」
そう言いつつ「そろそろ行くか」と立ち上がる平蔵。
そして粟餅を蔦重に渡してきます。
「濡れ手に粟餅。“濡れ手に粟”と“棚からぼた餅”を一緒にしてみたぜ。とびきり上手い話に恵まれたってことさ。おめえにぴったりだろ」
受け取る蔦重。
「せいぜいありがたく受け取っておけ。それが粟餅落としたやつへの、手向けってもんだぜ。じゃあな」
そう去ってゆく平蔵でした。ずっと澄ましていられなかったのか、最後の最後で吹き出しているところに味がありますね。
吹っ切ったように粟餅かぶりつく蔦重。
「そうだよな。鱗の旦那! 濡れ手に粟餅、ありがたくいただきやす!」
そう決意を固めるしかない。
ま、今さら何したところで、取り返しつかねえしな!
MVP:鱗形屋孫兵衛
蔦重を罠にかけるところは憎たしいようで、あとはどうにも悪人に思えない人物像でした。
彼のことを憎めなくなったのは「赤本」と「青本」のくだりです。
思えば彼の衣装は赤と青を基調としたものの二種類があります。その意味がつかめました。
曽祖父が作り上げたものを磨き上げて残したい。そう語る彼は本当に本を作るのが好きで、誇りがあるのだと思えたものです。そりゃあ、蔦重も告げ口を踏みとどまるわな。
そして鱗形屋を片岡愛之助さんが演じる意味が実に素晴らしい。
片岡愛之助さんは上方歌舞伎の出で、いわば「下りもの」。江戸まではるばる流れてきたともいえる役者です。
今でも歌舞伎や落語は東西で違う。いわばその違いを肌で感じてきた役者がこう江戸っ子らしく語っていると、実に味と説得力があるのです。
鱗形屋孫兵衛は、上方と江戸を繋ぐ片岡愛之助さんが演じるに相応しい人物。本来誇り高く、立派な商人です。火災で家が傾く不運がなければ、あんなことにはならなかったかもしれない。
鱗形屋だけでなく、話を持ち込んでおきながら、裏で賄賂を贈って、逃げた大名も酷いわけでして。
突き詰めてゆくと、江戸中期の財政逼迫が根元にあるのではないかと思えてきます。
となると、田沼政治は正しいと思えてくるようで、その田沼一派が鱗形屋を地獄に落としたところが実に難しい。
問題解決は困難だ――そう突きつけて毎回毎回、頭が捻れきれそうなほどに惹きつけてくるのが、このドラマの味なんですね。
業が深ぇよ。
鱗形屋の失墜と、田沼政治をこうもうまく絡めてくるなんて、とんでもねえことですよ。
総評
毎回毎回、見ているうちに頭がテカテカしそうなほど面白いこのドラマ。どうしたもんでしょう。
今回は「青本」について蔦重が語るところで、グッときました。
これは様々なものに当てはまるのではないかと。
思いつくところでは時代劇ですかね。
時代劇はエンタメとして堂々と王道をいくもののはずでした。
それがいつの間にか、途中で筋書きがわかるというか説教くさいというか、「カビくせえ」ものになってしまった。
しかし、フォーマットが悪いわけではない。
そのため、韓流や華流時代劇が日本に追いついて入ってくるとヒットしてしまう。そういう流れがあったんだと思います。
そこを意識して変えてきて、その成果がここ最近出てきたと感じています。
これは、そうした苦境の中でも続けて放映されてきた、大河ドラマそのものにも言えるんじゃないですかね。
ここ数日、『豊臣兄弟』のキャスト発表を見ていて、心がさして動かないことにハタと気づきました。
カビくせえは言いすぎにせよ、見た瞬間にどういう人生を送るか把握できているんですよね。
そりゃ、美女をキャストする。こういう優等生タイプを好演した俳優を据えてくるだろう。そう予測がついてしまう。
確かに戦国乱世は面白い。でも、わかりきった展開じゃないか?と思ってしまいました。
そう思ってしまうのは、きっと『光る君へ』と『べらぼう』で、予測のつかない面白ぇ、かつ「今」を取り込んだ大河ドラマを見てしまったからじゃねえかと思った次第でして。
そういう業の深さがあるんだな。
本作もまさに「うがち」で、ドラマを通して何か深いもんを語りかけてくる気がするんです。
それを読み解こうとして毎回脳が捻じ切れそうになりやす。疲れます!
またしても重なる因果(ネタバレ注意)
さて、以下は思い切りネタバレしますんで、読みたくない方はすっ飛ばしてください。
鱗形屋と西村屋の因縁は続きます。
あの聡明な万次郎は、のちに西村屋に養子として入り、西村屋与八の名前を継ぐ。
まだ幼い彼は、この偽板事件の顛末を曖昧にしか知らない。そして父は蔦重がチクったと誤解している。この父から蔦重への恨みつらみを聞かされ、逆恨みしてもおかしくありません。
次週以降、西村屋と蔦屋の対決が始まります。
ラウンド1ともいえる【美人画】対決は、喜多川歌麿というカードを擁した蔦屋の勝ち。
そしてラウンド2は何か?
【役者絵】です。
蔦重は東洲斎写楽というカードで挑む一方、西村屋は歌川豊国を擁してきます。
結果は西村屋と歌川豊国の大勝利となります。
このラウンド2のころは、初代でなく、二代目の与八(万次郎)です。
父の仇討ちに成功したということになるのでしょう。
それにしても、この万次郎を演じた野林万稔さんの目元の涼しさ。それに見るからに賢そうな顔立ち。成長したら、ぜってぇ出るはずだと私が信じている、ある役者さんを彷彿とさせるんですよ。期待しかありやせん。
もしこの予感が当たったら、見ている側は頭がドッカンドッカン、てぇへんなことになるぜ。
こう考えてくると、やはり唐丸の正体は喜多川歌麿だと思えてきます。
歌麿は「写楽なんか売り出しやがって」と恨みつらみを残しています。彼が唐丸だとすれば「唯一無二の“相方”を替えたから負けたんだい!」となりましょう。
ちなみに西村まさ彦さんが西村屋与八を演じるのは二度目となります。
『眩(くらら)~北斎の娘』で二代目を演じ、今回は初代を演じているんですね。別人物ですので注意が必要です。
それから佐野政言。
彼の田沼意知殺害の動機は不明とされます。錯乱していたともされます。
ドラマでは家系図の扱いにより、その動機の発端が見えてきました。
黒幕なし、単独犯になるのか。それとも一橋治済でも動くのでしょうか。
一橋治済といえば、知保と家基の周辺も何やら匂いますな。この母と子を田沼一派が警戒していることも、伏線なのでしょうか。
そして「赤本」と「青本」と来まして、別の色の本も気になってきますね。
その別の色の本のアイデアも、キンキンから粟餅まで、今週にはみっちりと出てきました。
ドラマ関連のニュースではことさら伏線回収ということを取り上げます。
しかし、伏線がありゃァ回収するのはフィクションの基本っちゃそうですぜ。ゆえにあれだけ伏線が張り巡らせた唐丸が実は再登場しない……とかなんとか言うのは失礼な気がしますけど。
でも、わかったことがあるんです。
伏線もフラグも、受け止める側が偏見なく、材料を集めてこそ見えてくるもんだと。
伏線云々、ネット、特にSNSで騒がれる作品というのは、ただのお約束に忠実で、やりすぎていて「カビくせえ」ことすら時にあるんすね。
今年の場合、稲荷が蔦重に向かって言うように、証拠を掴まねえと読み解けねえ因果だらけで、脳が毎回捻じ切れてまさ。
これのどこが簡単な大河ドラマなんですかい!
あわせて読みたい関連記事
-

『べらぼう』片岡愛之助が演じる鱗形屋孫兵衛~史実では重三郎とどんな関係だった?
続きを見る
-

徳川家基は意次に謀殺された?18歳で謎の死を遂げた幻の11代将軍
続きを見る
-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察
続きを見る
-

松平武元『べらぼう』で石坂浩二演じる幕府の重鎮は頭の堅い老害武士なのか?
続きを見る
-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察
続きを見る
【参考】
べらぼう/公式サイト