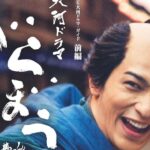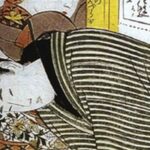こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第18回歌麿よ、見徳は一炊夢】
をクリックお願いします。
MVP:喜多川歌麿
唐丸が喜多川歌麿であるというのは、わかりやすいヒントが複数あったと思います。
染谷将太さんが歌麿役という時点で凄いことになりそうだという予感があったことは、事前予想の記事でも書いておりやす。
-

直前予想!大河ドラマ『べらぼう』は傑作となるか?タイトルから滲む矜持に期待
続きを見る
歌麿の描く絵は、美しいだけでなく、身を売るものの哀愁も滲んでいるものもあります。
彼自身の人生はドラマの創作にせよ、そうせざるを得ない人々の哀しさを知っていて、それを描いた人だと思えたものです。
春画も実に味があり、どこか哲学的なものがあるとすらされます。
ただの天才売れっ子絵師というだけでなく、吉原を舞台にする意味まで、哀愁まで載せてこなければならない。
そんな高い要求に、この歌麿像は応えてきたと思えます。
それだけでなく、さらに大河の歴史に残る大きな一歩を刻みました。
見えなくされてきた男性の性被害者の声を残したのです。
日本史では、他の文化や宗教圏とは異なり、同性愛が強い禁忌とされてこなかったとされます。
同性愛で関係を持つ人はいたわけであるし、性虐待の被害者も男女双方にいる。
-

江戸時代の男色・BLをナメたらアカン! 時には暴力的で甘~い要素はまるでナシ
続きを見る
それなのに、いなかったことにされるか、あるいはお笑いネタにされるか、BL(ボーイズラブ)だのなんだの客寄せに使われるか、そういう酷い状況でした。
しかし、こういうことをしていると、傷ついた人の心は癒されないどころか、余計に傷つけられてしまいます。口を塞がれてしまいます。
2023年『どうする家康』は、BLだのなんだの喧伝し、耳を噛んだり、まだ幼い竹千代を信長が相撲で投げ飛ばしたり、何を考えているのかと私は苛立っていたものです。
ジャニーズ問題が燃え盛った直後に何も反省していないのか?と驚愕したものですが、NHK局内、大河チームでも怒髪衝天している人はきっといたのでしょう。
そのひとつの答えが、今回見られたと思えます。
捨吉の辛い境遇を、誰一人として笑い話にも、堕落の証にもしない。
苦しみ傷ついてきたことを否定しない。
「好きでこの仕事をしている」と捨吉に言われたら、いねに聞きに行って、どうしてそうなるのか蔦重は確認する。
そして彼を決して否定せず、ただ、生きていてよいのだと寄り添う。
時代劇であるのに、サバイバーへの寄り添い方は現代の知見が反映されています。
お見事です。
「歴史総合」時代へ対応した大河ドラマへ
2022年より「歴史総合」が新科目として登場しました。大河ドラマもこれに対応してきていると思えます。
2024年『光る君へ』は、歴史総合で扱うよりもはるかに前の時代です。
そうはいっても、日本と中国の狭間に生きる人々の存在を再認識させました。
歴史総合は近世以降を中心に学ぶだけではなく、日本史の枠を出る範囲もカバーしています。
そういう観点からすればあのドラマは対応できていました。
周明はじめ歴史に名を残さなかった人物に焦点が当てられています。
彼は親から対馬の海に投げ捨てられ、死んでいたはずの存在。それが国と国の狭間で生き、歴史の狭間で命を落としていったことが描かれたのです。
まひろが九州までくだり、刀伊の入寇に出くわす展開はかなり強引でした。
それでも周明のような歴史の狭間に消えた存在を再生させるという意義を踏まえれば、私は大いにありだと思います。
こうした範囲は地理的なものだけでなく、身分にも及びます。
歴史に名を残した為政者や有名人だけでなく、庶民がどう生きて歴史を築き上げていったか。
見なかったことにされる被害者や犠牲者を、どう再検討するか。
2020年『麒麟がくる』の時点で、駒を通してそんなアプローチはされてきました。
これも別に歴史総合やBLM運動からやってきた近代の流行ともいえず、「江湖」や「野史」「稗史」として伝統的にあったことなんですけどね。
2025年『べらぼう』はそこに正面切って取り組むから、実に新しいアプローチなんですな。
「番組の一部に性の表現があります」というテロップについて
このテロップは、まだ大河ドラマは発展途上だと思えました。
「性の表現」であれば、初回からずっとつけ続けるべきだという意見があり、私もそれには賛同します。
あくまで推察ではありやすが、性的同意が取れていないということかもしれませんぜ。
HBOの『ゲーム・オブ・スローンズ』から考えてみましょう。
あれはそもそも成人指定がされてはおりまして、性的な表現は随所に出てきます。
それを承知した上で問題視されたものとして、性的同意がないまま行為に及んだ場面があげられます。
吉原女郎は一応契約範囲内であるのに対し、幼い捨吉は強引に客を取らされている。そこが一線を越えたということかもしれません。あるいは捨吉の年齢も考えられます。
ま、まぁさんの腎虚がらみという可能性もありやすが。
羅切は「殿方にはつらい表現さ!」ってことかもしれねえなぁ。
そこを踏まえ、次のような意見には賛同できかねます。
「女郎は美化して描いているのに、男が被害に遭ったら取り上げるのは男尊女卑の証拠だ!」
唐丸の過去は悲惨だとしつつ、女郎の苦労、妊娠、性病、暴力的な搾取はないと言い切るSNS投稿を見ました。
しかし、それは全てあるでしょう。
捨吉の母は、そもそも望まぬ妊娠をしているし、暴力的な搾取のなかで人間性までおかしくなっています。
こういう投稿や打ち切りハッシュタグに同意するものは、固有名詞が間違っていたり、見ていないと断言していたり、見ていても見落としが多い傾向があります。
叩くこと、強い言葉で批判してスッキリするか、バズることが主目的に入れかわっているんですね。
投稿する方も、さほど江戸時代の文化文芸に興味ないまま生きてきたのでしょう。
そこに興味を抱くと、どうしたって吉原や女郎の扱いをどうするのか、向き合わないといけなくなります。
特に女性ともなれば、セクハラじみたからかいを受けつつも、調べて自分なりに考えていて、苦労も伺えるわけなのですが。
そういうことで悩まずに「大河で扱うとはけしからん!」と仲間内でエコーチェンバーを形成をしているのかもしれません。
どんどん過激できつい主張になっているし、論点をずらしてでもなんとしても叩きのめしたい、攻撃性の高さが滲んでいます。
いくら根にある思想が立派でも、必要以上に攻撃的で、対象を知りもしようとせず叩くことは、何も生み出さないと思います。
女性の権利を大義名分にして、攻撃や承認の欲求を満たしたいように思える。
次に叩ける格好のものが見つかれば、すぐにそちらへ移動するのでしょう。
総評
大河の感想を誰がどう何を言っても、知ったこっちゃねえってのがあっしのスタンスですが。
でも気になるこた、あるんすよ。
まず、唐丸の正体論争について。これはわかりやすく歌麿だと導線が引いてあると思いました。
でも、こういう意見はある。
「いかにも歌麿ぽいけど、これは“匂わせ”、“ひっかけ”だよ」
そういうSNS投稿と作家の技術を混同するもんではないと思うんですよ。
森下佳子さんは手堅い作風かつ歴史が好きなので、そこまで大きく無茶なこと、意外な展開はしない。むしろ安定感があると思います。
そういうただのウケ狙いと意外性だけで史実を捻じ曲げるのは、出来の悪い歴史もののむしろ悪い要素です。
徳川慶喜は実はいい人であるとか。
お市と淀殿の恋した相手が徳川家康であるとか。
そういう演者やそのファンへの目配せを奇想というメッキで誤魔化した創作とは別物でしょう。
これでいくと東洲斎写楽も展開は読めてきて、謎の人物をあえて引っ張るスタイルにはしないと思います。
まず史実をつなぎ合わせてどうするのか考えるというのが、森下さんの作風でしょう。
そういう手堅さが持ち味だと思っておりますので、SNSでのウケ狙いのような、ただ意外なだけというストーリー展開はしないと思うのです。
写楽の正体についても色々な推察出ておりますが、確定している説で来ると私は踏んでいます。
一捻りあるとすれば「喜多川千代女」でしょうか。
歌麿の別名義、弟子、あるいは妻という説もある女性絵師で、挿絵のみを手がけている。知名度が低いながら、公式ガイドに紹介が出ております。
今までずっと薄々思っておりやしたが、このドラマの作風は山田風太郎に近いと思えます。
山風もぶっとんだ作風とされますが、要素と要素をかなり緻密に組み立ててプロットを練ってきます。ユニークな特徴がいくつもあるんです。
しかしそのせいで、評価が下がっているかもしれないところはあるんですね。
山風の持ち味のひとつは、下ネタで笑いをとりにくるところです。
今週のまぁさんのアホそのものの下ネタは、あまりに酷い捨吉の境遇だけでは辛かろうという配慮に思えましたし、山風らしいんです。
そしてもうひとつ、「エロい」とされることを扱う点。
司馬遼太郎を読んでいるというと「えらいね」と言われるのに、山風を読んだというだけで「エロいね」と苦笑されるというのは、よくある話でした。
そもそも好きな作家の名前にあげない方がよいと思えることすらあった。
露骨にバカにされたり、そんなもの読むならこっちを読めと司馬遼を勧められることもありましたね。
大河の原作だって、司馬遼はあっても山風はないです。
でも、山風の「エロ」って、悲惨なことがほとんどです。
エロに耽溺した悪役は羅切も含めて大抵酷い目に遭う。そのエロの場面だって、サービスどころか虐待や搾取であり、それを批判するニュアンスもあるのです。
でもそういうことを説明しようにも、本題に入る前に打ち切られることが往往にしてある。
真面目な人とほど、むしろ話せませんでした。
今にして思うと、何かおかしな隠蔽が社会全体にうっすらとあったと思えるんですよ。
性的な虐待を問題視することすら、サービス、エロや堕落とされることすらあったものでした。
それこそかつては、真面目な人やエリートこそ、そういう態度を取ることも往々にしてありました。
女権を訴えていた女性議員が、吉原視察の際、見ないようにそそくさと通り過ぎていったなんて話は耳にしますわな。
でもそうしてきたことで、世の中がよくなってきたとも思えない。
それが、今は大きく変わっている。
ここまできた。性的搾取を隠すのでもなく、客寄せにするのでもなく、悲惨なことだと描き切った。
捨吉の境遇は悲惨です。
しかし、ありふれた話だったと思います。
今回の展開で『鬼滅の刃』の「遊郭編」を連想する感想もありました。それだけありふれていて、典型的な話ということです。賑わう江戸には、ああいう地獄がぽっかりと穴を開けていたということです。
このドラマの制作チームは、吉原を美化されているという批判に、どこか覚悟ある対応がありました。
将来振り返ったら足りないことは出てくるだろうけれど、現状で精一杯こなしているからには、批判も作品を磨く砥石として受け入れるという潔さがあるのでしょう。
確かにテロップの是非やなにやら、ちょっと説明不足のことはあります。
でもそれも次に活かせるでしょうし、世の中に風穴を開けることがまず大事だと思いますんで、私はともかく今後も期待していますぜ。
来週についてちっといえば、万次郎に要注目ですね。
唐丸と万次郎のその後が示唆させたことで、最終回までの伏線がしっかりと見えてくると思います。
あわせて読みたい関連記事
-

江戸時代の男色・BLをナメたらアカン! 時には暴力的で甘~い要素はまるでナシ
続きを見る
-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道
続きを見る
-

『べらぼう』唐丸少年の正体は喜多川歌麿か東洲斎写楽か?はたまた葛飾北斎か!
続きを見る
-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?
続きを見る
-

『べらぼう』眞島秀和が演じる将軍・徳川家治~史実ではどんな人物だったのか?
続きを見る
【参考】
べらぼう/公式サイト