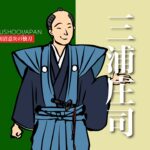こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第34回ありがた山とかたじけ茄子】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
ありがた山に、かたじけ茄子
蔦重が向かったのは、田沼屋敷でした。
意次は部屋に入るやいなや心配そうに声をかけてきます。
「何かあったのか? まさか、そなたにまで累が?」
蔦重は否定します。意次には、まず相手を気遣う優しさがあり、何度か同様のシーンがありましたね。

田沼意次/wikipediaより引用
「何かあれば遠慮のう申せ。今となっては力になれるかどうか怪しいが」
力なく笑う意次に対し、蔦重が続けます。
「田沼様。私は先の上様のもと、田沼様が作り出した世が好きでした。皆が欲まみれで、いいかげんで。でもだからこそ、分を超えて親しみ、心のままに生きられる隙間があった。吉原の引手茶屋の拾い子が、日本橋の本屋にもなれるような」
「俺も、お前と同じ成り上がりであるからな。持たざる者にはよかったのかもしれん。けれど、持てる側からしたら、憤懣やるかたない世でもあったはず。今度はそっちの方(かた)が正反対の世を目指すのは、まぁ、当然の流れだ」
「田沼様……私は書を以て、その流れに抗いたく存じます。最後の田沼様の一派として。田沼様の世の風を守りたいと思います。ただ、そのためには、田沼様の名を貶めてしまうかもしれません。いや……貶めます。そこはお許しいただけますでしょうか?」
そう覚悟を決めたように言う蔦重。
平賀源内の「書を以て世を耕す」からここまで到達しました。
「許さぬなどと申せるわけなかろう。もしそんなことをしたら、源内があの世から雷を落としてこよう」
そう理解し、笑い飛ばす意次。

平賀源内/wikipediaより引用
「好きにするがよい。自らを由(よし)として、“我が心のままに”じゃ」
「田沼様、ありがた山の寒がらすのございます」
そう深々と頭を下げる蔦重。
その手を執る意次。
「こちらこそ、かたじけ茄子(なすび)だ」
笑い合う二人。
初回の放送で二人が出会ったときは、ありえないだの身分差がないだの、意次が下劣だのなんだの言われていましたが、ここにこう繋げてきた。さすがの脚本ですね。
蔦重が部屋から出ると、別の部屋で見慣れない光景を目にしました。
田沼の家中の者が、箱の中に紙を投函しているのです。
一体あれはなんなのか?
聞けば、家中の役目を入れ札(投票)で決めようとしているようで、女性も参加しています。
「誰に役目を頼むか?というのは上が決めることだが、別に皆の考えで決めてもいいのではと思うてな。これを国を挙げてやったら、面白いことになると思わぬか? 世はひっくり返るかもしれぬ」
そういたずらっぽい目線で言われ、「田沼様ってなぁ」と蔦重は言いかけます。
「べらぼうでござろう?」
背後から三浦庄司が続けてきました。思えば三浦も農民出身でしたね。
「ではここで。楽しみにしておるぞ、ありがた山」
田沼意次が去ってゆきます。
このあと、本多忠籌が田沼意次を解任する沙汰が申し渡される場面が。二人の距離は隔たっていて、蔦重と意次の触れ合っていた距離とは大違いです。
【史実の三浦庄司解説記事】
-

『べらぼう』原田泰造演じる三浦庄司とは何者か?元農民が意次の下で果たした役割
続きを見る
ふざけられねえ世の中なんて無粋じゃねえか
蔦重が狂歌師や絵師を集めて席を設けています。
大河ドラマ『麒麟がくる』の時、鮮やかな色使いの和装に対し、「衣装が派手だ!」という批判がありました。
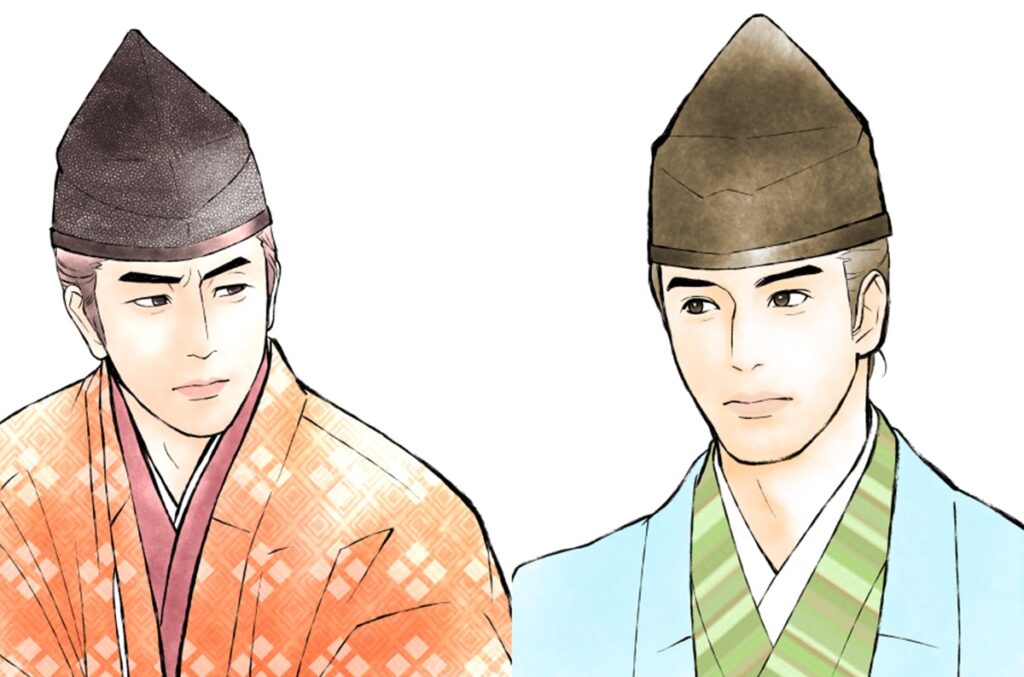
『麒麟がくる』細川藤孝(左)と明智光秀イメージ
実は考証の結果、そうした色使いになっていたのですが「和装は地味な色合いだ」という思い込みがあるからこそ、戦国時代の衣装も派手だとおかしいと思ってしまったのでしょう。
日本人の色彩センスが落ち着いていくのは、江戸幕府の統制ゆえのことです。
そんな江戸の感覚から見ても、大田南畝の服装が地味になりすぎたわけですな。
蔦重が挨拶すると、皆ふざけだします。
金が欲しいのかい? 吉原に繰り出すのかい? 大文字屋と扇屋どっちがいい? そうふざけだすわけでさ。
「楽しいですよねぇ。ふざけるってなぁ。けど、これから先、ふざけりゃお縄になる世が来ると思ってます。新しいご老中、私ゃふんどしの守って呼んでんですが。そのふんどしが言うには、万民、倹約を心がけ、遊興に溺れず、分をわきまえつとめろと。そうすりゃいい世になるって話でさ。まぁまっとうだ、正しい、ごもっとも。けどその正しさからはみ出す奴は許さねえ。戯歌一つで沙汰を待てなんてなぁ、まぁ、頂けねえと思うんでさ。そりゃいくらなんでも野暮が過ぎる。そうは思いませんか?」
こりゃ確かに無粋だと同意する皆。
「ま、粋だの野暮だの、ふんどしにとっちゃどうでもいいんでしょ。恐らく世の大方にとっても。その証しに世の大方はふんどしのやることなすことに大喜びだ。ふんどしについてきゃ、てめえらにいい世を作ってくれると信じてる。けど、どうもまやかしにしか思えねえんでさ」
「まやかし?」
恋川春町が聞いてきます。
「ええ。倹約を心がけ、遊興に溺れず、分をわきまえつとめろってなぁ、裏を返しゃ死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢すんなってことじゃねえですか。そんなの誰が楽しいんです? 面白えんです? 面白いのはただ一人だ。世をてめえの思う形にしてえふんどし野郎だけじゃねえですか! これから先、ふんどし以外はちってもよくねえ世がくると思ってまさ。遊ぶことも、戯けることも、よしとされねえ。正しくて、厳しくて、息の詰まるような。俺ゃそんなのごめんだし、遊ぶななんて言われりゃ、うちの商いは上がったりやのかんかん坊主! だから、この流れに書を以て抗いてえと思います! 皆様、力をお貸しくだせえ」
蔦重がこう語る間、ふざけることもなく、水を打ったように静まり返る一同。
ていがハッとした顔をしています。
ていの双眸が蔦重を見つめ直す
ていは、蔦重の何を信じたのか?
陶朱公を彼の中に見出したから。
陶朱公は皆を縛り付け、正しく生きるように説いたか?
否。民を笑顔にした人だった。そう敬愛の原点回帰にたどり着いたような顔です。
恋川春町が「書を以て抗う?」というと、喜三二はふざけだし、政演は吉原に遊びに行くよう促します。

『吾妻曲狂歌文庫』に描かれた恋川春町/wikipediaより引用
しかし真面目な春町は、蔦重にどんな書で抗うのかと尋ねます。ニッコリ笑ってこう返す蔦重。
「ふんどしのご政道をからかう黄表紙を出したいと考えています」
皆の顔色が変わり、大田南畝が叫びます。
「ありえぬ! 御公儀をからかうなど、首が飛ぶぞ!」
「そもそも、お上をネタにすることを禁じられてなかったか?」
そう動揺しますが、蔦重もそこは承知。
建て前はそのはずが、おかしな読売が野放しになっているところを突きました。
最近の読売はやたらとふんどしを持ち上げている。しかも読売とは思えねえほどネタが確か。こりゃ一体どういうことだ? お上自らの漏洩なのか?
そう疑った蔦重が調べた結果、案の定、松平定信はメディア工作をしていた。それを完全に掴んだんですね。
南畝は動揺しつつ、頼まれているから許される、ネタにするのとは違うのだと反論します。
そんなツッコミは想定の範囲内とばかりに蔦重は己のアイデアを広げます。
「表向きは“田沼叩き”とすればどうでしょう?」
自分のいい噂を金を払って書かせるような相手ならば、極悪人田沼を叩き、ふんどしの守を持ち上げればこれ幸いと見逃されるんじゃないか?
それを聞いて、つよは売れそうだと喜び、ていは目が醒めたような顔になっています。
おていさん、気づいたかい?
蔦重のやりてえこた、おていさんの好きな漢籍にもあることでさ。
まず、ふんどしの無粋なところは、江戸っ子目線でなく唐様文人から見ても下劣なんでさ。
『三国志』でおなじみの曹操は奸雄扱いが定番ですが、褒められるところもあり、その一つが陳琳(ちんりん)の助命と登用です。
陳琳は文才に恵まれていました。
曹操のライバルである袁紹に仕え、両者が対決する前に曹操を罵倒する檄文を執筆。
それを読んだ曹操は激怒し、陳琳は必ず殺す!と歯軋りしました。
しかし曹操にも文才があり、陳琳の文章を読んでいくうちに、この作者は素晴らしい才能の持ち主だと認めざるを得ません。
結果的に曹操は袁紹に勝利をおさめ、陳琳を捕縛すると目の前に連行させました。そのうえで「なんでこんな俺を貶す文を書いたんだ?」と問いかけます。
陳琳はこう返します。
「矢が弦の上にあれば、発射するしかありません」
要するに、自分の才能を発揮できる機会があれば、書いてしまうということ。
檄文作者だと認めた上での開き直りに、曹操は感心しました。そして陳琳を釈放し、自らの幕下に加えたのです。
このやりとりを踏まえた上で、大田南畝の尋問を思い出してくだせえよ。
定信の度量は、曹操に遠く及ばないと思いませんか?
中国では、こういう文人迫害の際、「あーあ、あの人は陳琳を認められないんだねえ」とこぼすことがあります。
おていさんなら、そういうことを読み解けても不思議はありゃしません。

月岡芳年『月百姿』シリーズ『南屏山昇月』/wikipediaより引用
もうひとつ、明末の顧炎武の言葉でも。
天下の興亡、匹夫に責あり。
これは、ふんどし流でいけば、庶民だろうと真面目に暮らして天下を保つようにということになりまさ。
でも、それだけですか?
天下が誤っているのであれば、それを民が指摘するという問いかけもあるのではないですか?
ふんどし流でいけば、あの新之助の義挙である打ちこわしも、民衆のわがままに収まってしまいます。
でもそういう流れに異議ありということだって、民衆の責任ではないですか?
おていさんの思考回路はあくまで私の想像ですが、彼女は考えに考えて、蔦重の中にもう一度光を見出してきたと思える。そんな眼鏡の奥の眼光でした。
※続きは【次のページへ】をclick!