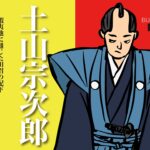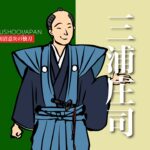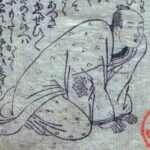こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第34回ありがた山とかたじけ茄子】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
贅を尽くすならば、四方赤良は欠かせない
といっても、ふんどしを持ち上げたいのか、からかいたいのかわかりません。そういう困惑もある。
持ち上げると見せかけてその実、からかうと言うことではないか?と北尾重政が指摘します。
その通り!だと蔦重。
そういう黄表紙を出すと言い、無邪気な子どものような歌麿に目線を向ける蔦重。驚く歌麿。
さて、どういうことか?
蔦重はおもむろに歌麿の絵を取り出します。

『画本虫撰(えほんむしえらみ)』蝶・蜻蛉/国立国会図書館蔵
倹約の世の中で、目玉が飛び出るほど豪華な狂歌絵本を出す!という宣言です。
歌麿は自分の絵がそうなることに驚いています。
蔦重が売り出したい気持ちはわかっていても、ここまで読めていなかったようです。
こんなサプライズ、痺れちまいまさ。
蔦重はかわいい弟の売り出しにぬかりはない。豪華本には南畝先生の作品が必要だと猛烈にオファーしてきます。
「俺はやらぬぞ。やらぬと言ったはずだ」
「俺は贅を尽くしたもんを作りてえんです。贅沢すんなって言われても、欲しくてたまんなくなるような。けど、四方赤良の狂歌がねえ狂歌絵本は、贅を尽くしたとは言えねえ。どうか一首、載せてもらえませんか。俺ゃ狂歌ってのは素晴らしい遊びだと思ってまさ。意味もねえ、くだらねえ、ただただ面白え。これぞ無駄、これぞ遊び、これぞ贅沢! しかも身一つでできる贅沢だ。だから上から下まで遊んだ。分を越えて遊べた。これぞ四方赤良が生み出した天明の歌狂いです。俺ゃ、それを守りてえと思ってます。南畝先生はどうです?」
そう言われ、目が泳ぐ南畝。心が揺れ動いているようです。
絵を手にして歌を読む四方赤良。
毛をふいて
傷やもとめん
さしつけて
君があたりに
はひかかりなば
下世話な恋の歌でさ。毛虫に寄せる恋。毛虫が勢い込んで夜這いをしたとしても失敗するってさ。
それだけでなく「毛を吹き疵(きず)を求むる」という『韓非子』からの引用と引っ掛けて、あえて人の欠点を求める定信を皮肉っているようにも思える。綺麗事を引っぺがして本性を暴く気合いも感じさせると。
「……屁だ」
大田南畝はそう言います。
「戯歌一つ詠めぬ世など、屁だ!」
へ! へ! へ! へ!
そう呼びかけだし、回り始める一同。ていも迷い、意を決したように踊りの輪に加わります。
こうやってやけっぱちになって、変な顔をして踊り回る皆には、覚悟が宿っています。
まさか屁の踊りでここまで感動するとは思いませんでした。
文武をおちょくり、歌麿を売り出せ
政治は動き続けています。
田沼意次は2万7千石を没収で相良城も取り壊し。
定信は、田沼を叩けば叩くほど己の人気に繋がると理解し、それを徹底してきました。
「文武出精」という幕臣評価一覧も提出されました。あれほどの弓を放てる長谷川平蔵も載っていることでしょう。
蔦重たちもこの「文武出精」の噂を知ります。
文武に秀でた者たちを集めようとしたところ、人が全然いない、弛緩しきっていた武士たちにそんな骨のある者などいないと話題になっているようで。
蔦重は何か思いついたようです。
鳥山石燕は歌麿の絵を見て感心しています。
「ちっぽけな虫の恋をお前、キンキンキラキラにして! 酔狂だねえ」
そう嬉しそうに語る石燕に、蔦重は本に載せる祝いの言葉を頼みたいと依頼します。
「そりゃちょいと、硯の魂に相談してみねえとなあ」
石燕が茶目っ気たっぷりに返答します。
そして12月、土山宗次郎が公金横領の罪で斬首されました。
妾の誰袖は「押込(拘禁)」の刑とされました。このあと誰袖は身寄りがないため大文字屋に戻され、消息は不明です。
ちなみに鳥山検校と連座させられた瀬川は「叱り」ですので、それよりもはるかに重い刑となりました。
松本秀持は、土山の監督不行き届きの罪にて百石没収のうえ、逼塞(自宅軟禁)。
-

『べらぼう』土山宗次郎(栁俊太郎)貧乏旗本が誰袖花魁を身請けして迎えた惨い斬首
続きを見る
-

『べらぼう』松本秀持(吉沢悠)は蝦夷地政策のキーマン 幕府と意次の起爆剤となるか
続きを見る
田沼派の粛清は止まりません。
そんな天明8年(1788年)、ふんどし政治をからかう黄表紙が出版されます。
さらにかつてないほど豪華な狂歌絵本『画本虫撰』(えほんむしえらび)。
これが蔦屋の軒先を飾ったのです。
さっそく松平定信は、うれしそうな顔で『文武二道万石通』を受け取るのですが……。
MVP:田沼意次
田沼意次退場のとき、九郎助稲荷の言葉に胸打たれました。
軽輩から成り上がり、老中まで上り詰めた政治家、田沼意次。
進取の気性に富み、最後まで新しき政の仕組みを考え続けた人生であったと言われています。
ここまで思いやりにあふれた田沼意次退場になるとは思ってもいませんでした。
初回で蔦重と田沼意次が顔を合わせたことが回収され、なんとも趣のある退場です。
この退場においても挑発的であるのが、田沼意次が家中で入れ札という選挙の仕組みを取り入れ、それこそが政治を変えると喝破していたことでしょう。
何の進歩もなく、惰眠を貪っていた江戸時代。
そこへ黒船がやってくる。
世は乱れたものの、西洋からもたらされた政治理念により、近代国家へ駆け上がってゆく。坂の上の雲を目指すように――こんなシナリオが、長いこと日本では定番だったものです。
第二次世界大戦後は果たしてそうであったのか、疑念を抱く歴史観が形成されます。
他ならぬ大河ドラマがその証左。
第一作は当時のベストセラーである井伊直弼を再評価する『花の生涯』が原作でした。明治維新は果たして正しかったのか?と突きつける作品だったのです。
井伊直弼は安政の大獄で吉田松陰を処刑しました。そのせいで長らく長州から絶対悪とされ、顕彰すら妨害されかねない状況が続いてきたのです。
そんな彼を主役と据えた作品は、どうしたって薩長史観脱却の意図を感じさせたのです。
しかし、田中清玄が「薩長の提灯持ち」と喝破した司馬遼太郎作品がベストセラー定番になってくると、流れが変わってきます。
戦争に負けて自分たちを見つめ直すよりも、当時の日本人は自分たちの青春の焼き直しを選んだわけです。
高度経済成長期の日本の支配層は、幼い頃に武士道礼賛、薩長史観を叩き込まれて育ってきました。
人間は十代のころにどっぷり愛した趣味や嗜好からなかなか逃れることができません。
武士や支配者、明治維新を礼賛するコンテンツが懐かしくなっていったのでしょう。
そうなっては厄介だからアメリカも戦後しばらくは武士道礼賛エンタメは規制したものですが、解放されたらあとは回帰するわけですな。
そういうノスタルジー礼賛をした方が作品も売れる。
となりゃ、水は低い方に流れるということです。
これは今も続いていて、毎日のようにSNSでは高杉晋作のこんな歌を引用している投稿を目にします。
おもしろきこともなき世をおもしろく
なぜ、人は自分と高杉晋作を重ねるのか。やはり、明治礼賛は残ってはおりませんかね。
んじゃ、日本人がもう一度、歴史観を糺すには敗戦しかない? って、そんなわけはなく、別の流れがあります。
西洋のみが近代化を成し遂げる資質があったとみなすのは、白人やキリスト教徒を礼賛する古臭い価値観であると、見直されつつあります。
西洋を模倣せずとも、東洋だって民衆からの政治改革ができたのではないか?
その芽を示すのが、今回の入れ札場面と思えます。
田沼意次の再評価のみならず、再来年は小栗忠順も見直されます。
歴史観を変える先頭に、大河ドラマが立ってやるという流れを感じさせる。
『べらぼう』があと3年くらい続いても良いという意見には賛同しますが、再来年がありますので、来年は江戸後期の歴史でもおさらいしておくと良いかもしれません。
実は蔦重の没後、お上とふてぇ版元文人の攻防はますます苛烈になっていくのです。
そしてもうひとつ、本作には2010年代半ばあたりから歪んでいた大河ドラマのデトックス効果もあると思いやすぜ。
田沼意次再評価の機です。その子孫の名誉も回復したい。
慶喜免罪のために天狗党大量処刑の責任を田沼意尊に押し付けた『青天を衝け』は、本気で反省してください。あれは歴史修正もとい歴史捏造だった。
ついでにいえば、あの作品でなされた徳川慶喜の過大評価も再来年で修正されるでしょう。
『逆賊の幕臣』の慶喜は生田斗真さん再登板でもよいのではないかと思ってしまうほど。
彼に対して姑息な悪党イメージがつきすぎてしまうかもしれない……とはいえ、今年の一橋治済を超える不快感を発揮する、そんな豚一像の徳川慶喜を大いに期待したくなるのです。
総評
毎回大絶賛しかしてねえ!
我ながらそう感じていますが、こんなすごい大河ドラマがあっていいのかとありがた山なので仕方がない。
日本の伝統とされてきたモノそれに対する見方や、歴史の常識とされてきたこと、それらをひっくり返す力を感じさせてくれます。
今回の第34回放送は「エンタメに政治を持ち込むな」というSNSでよく見かける論をぶちのめしてきました。
長い歴史をたどりますと、そういう点は確かに日本の文芸にはあります。
『光る君へ』を思い出してみますと、定子と清少納言「香炉峰の雪」の映像化は実に感動的でしたが、意地悪な言い方をすると漢籍知識マウントになっているところはあります。
元となる白居易の詩は、左遷された鬱屈のもとで詠んでいるものです。
そういう詠んだ背景を無視して自分の知識をひけらかすなんて軽薄ではないかという批判はあっても無理はないところでしょう。
光源氏は政治闘争の末に京都を離れ、須磨で暮らす展開があります。
このとき光源氏は「広陵散」という曲を弾いています。
一体どんな曲なの?というと、魏の嵆康(けいこう)という人物が処刑前に奏でたとされる伝説の曲でして。
嵆康は曹操の一族と姻戚関係にあり、そのせいで曹氏追い落としをはかる司馬氏一族に目をつけられ、政争の最中に言いがかりをつけられ、ほぼ冤罪で殺されました。
そんな嵆康と、朧月夜と密会を重ねて政治失脚を重ねた光源氏を重ねるってどうなのか。
これは清少納言や紫式部が軽薄ということでなく、実は日本人の文学許容における態度とされます。
中国から文学を学んだ日本では「風雅」を取り入れるべしと学びます。
この「風雅」が受け入れる過程で意味が異なってきたのです。
中国では、政治情勢や世の流れが自分に及ぼす影響をこう定義する。
一方で日本では、四季折々の花鳥風月を詠み込むと解釈されました。
そうはいっても、日本でも漢籍教養や唐様(中国式)から政治批判のニュアンスをまるきり無視できたわけでもない。
平安時代、公卿の日記は漢文で記されたものです。行政文書も漢文でした。
漢詩は政治的な主張を込めて詠むもので、恋心や日常生活のささやかな発見は和歌や俳句で詠むとされました。
それが時代がくだるにつれ、どういうわけか妙な変化が起きてきたのが『べらぼう』の時代なんでさ。
識字率が高まるうえに、狂歌は『べらぼう』でも言われる通り、ハードルが低い。
漢詩はルールが多くなかなか詠めませんが、狂歌はまったくそうではない。上から下まで自由に詠めます。
さらには政治批判をバンバン入れてこそ粋だ! という価値観が定着し、幅広い層が政治に物申すことが可能となってしまったのです。
同時代の清や朝鮮の場合、よき政治を志すとなれば、科挙を突破し官僚となることが道筋としてあります。
一方で日本の場合、世襲制度で政治には関与できないものだから、エンタメで物申すという妙なルートが出来上がったと思えなくもないんでさ。
いくつもの要素が結合し、日本なりの自由闊達な言論空間ができあがっていくわけです。
じゃあ、その流れを近代化に繋げられなかったのか?
これがどうにも頓挫します。
その第一の挫折が、田沼意次失脚である。
そうはいっても彼の政治姿勢は完全否定されたわけではなく、松平定信以降も引き継がれた部分も大きい。
ただし、その定信の政治生命もとある妖怪じみた人物の介入で頓挫してしまうわけですが。
その第二の挫折が、明治維新であると描くのが『逆賊の幕臣』だとあっしは見ますね。
今回、蔦重たちが江戸文化存続の危機に立ちあがろうとするわけですが、それこそ明治維新はその危機をもっと強烈に引き起こしているわけですから、セットにすることでより重みが増すのではないでしょうか。
そのためには、まず江戸文化の輝きを描いてこそでさ。
てなわけで、この大河ドラマは実質的に再来年とセットのように思えてきます。
それを意図した企画かどうかはわかりませんが、明治維新の意義を問い直すとなれば、江戸中期からの見直しが必須ともいえるのではないでしょうか。
「歴史総合」対応大河ドラマ第一弾として、本作は必ずや歴史に残ることでしょう。
最後に、喜多川歌麿の『画本虫撰』についてでも。
この素晴らしい絵も画集になっております。芸艸堂の豆本シリーズは和綴じで大変趣があります。気になる方はぜひどうぞ。
あわせて読みたい関連記事
-

『べらぼう』原田泰造演じる三浦庄司とは何者か?元農民が意次の下で果たした役割
続きを見る
-

『べらぼう』土山宗次郎(栁俊太郎)貧乏旗本が誰袖花魁を身請けして迎えた惨い斬首
続きを見る
-

『べらぼう』松本秀持(吉沢悠)は蝦夷地政策のキーマン 幕府と意次の起爆剤となるか
続きを見る
-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察
続きを見る
-

田沼の時代を盛り上げた平賀源内!杉田玄白に非常の才と称された“山師”の生涯とは
続きを見る
-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか
続きを見る
◆全ての関連記事はこちら→(べらぼう)
◆視聴率はこちらから→べらぼう全視聴率
◆ドラマレビューはこちらから→べらぼう感想
【参考】
べらぼう/公式サイト