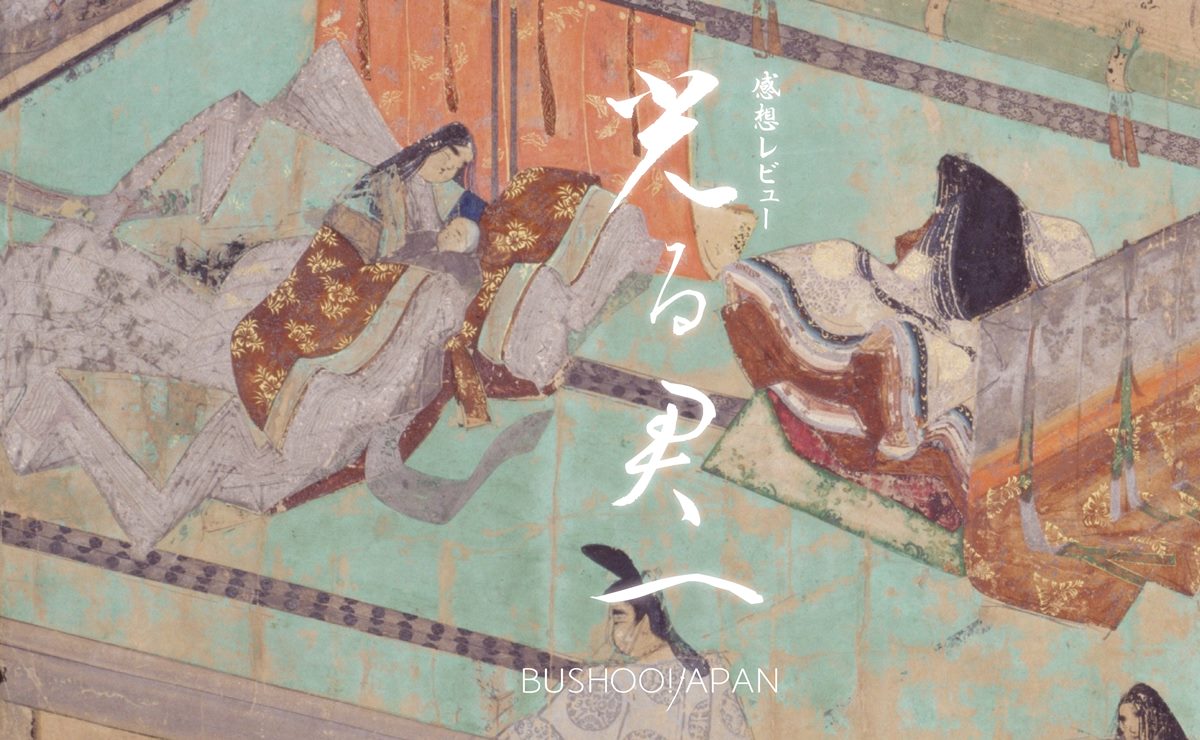こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『光る君へ』感想あらすじレビュー第43回「輝きののちに」】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
政治家としての道長は能力が足りない
「そもそも左大臣殿に、民の顔なぞ見えておられるのか?」
道長に対する実資の指摘からは、最近のニュースも頭に浮かんできます。
アメリカ大統領選でハリスに投票しなかった意見として、こういったものがありました。
「そんなにやりたい政治があったのならば、副大統領として実現に向けられていただろう」
政権中枢にいた政治家は、理想の実現を今さら訴えたところで、そこへ向かっていた歩みが理解されねば批判は避けられません。
いったい道長は二十年もの間、何をしていたというのか。
直秀の亡骸を埋めたとき。
まひろがたねの看病で倒れたとき。
兄である関白・道兼が理想を目指すと語り、何も成せぬまま命を終えたとき。
道長はそれなりに志の高いことを言っていたと記憶しています。
しかし、具体的に何をしたのか?
彼が民を見た最後の契機なぞ、まひろがたねの看病をしていたときまでとしか思えません。
別に民衆の視察をしなくともよいとは思えます。政治家なのだから政策を実現すれば良い。
しかし、この道長が、何か民衆救済をしようとしたことがあったのでしょうか?
ないわけではありません。旱魃の際、安倍晴明に祈祷を頼みました。ドラマではせいぜいがその程度にとどまっています。
実資はさらに続けます。
「幸せなどという曖昧なものを追い求めることが、我々の仕事ではございませぬ。朝廷の仕事は何か起きた時、まっとうな判断ができるように、構えておくことでございます」
実資は、未来への伏線も容赦なく用意し、道長をがんじがらめにしました。
このあと【刀伊の入寇】が起きた時、道長の無策ぶりがあらわになることでしょう。
朱仁聡と周明に関するフォローがないという批判を見かけましたが、意図的な放置と思えます。
道長が宋人にヤキモキしていたのは、単にまひろの周囲をうろついていたから、それだけのことではありませんか?
越前編では、宋の高い技術力と経済優位が描かれました。そこに目を留めない道長には、やはり政治センスがないのです。
「志を持つことで、私は私を支えてきたのだ」
あまりにしょうもない返答をする道長。そんな早寝早起きが健康のコツだと語る程度のことを言い返して、何がしたいのやら。
「志を追いかける者が、力を持つと、その志そのものが変わっていく。それが世の習いにございます」
「ん?」
苦笑する道長。
「おい、意味が分からぬ」
目を泳がせる実資。
道長よ、そこまで説明しないといけませんか?
「まったく成長していない」と遠回しに言われたようなものでしょうよ。
成長するということは、己の志を実現するために様々な条件付けがいると学ぶことでもある。だから変わらなければなりません。
『鎌倉殿の13人』の北条義時のように、道長が闇堕ちしたという見解もあります。
私はそうは思っていません。
道長は若い頃から変わらないように思えます。
人には器がある。その中に何か詰め込んでいくもの。
義時の場合は、源頼朝や大江広元から学んだ都流の謀略を詰めこみ、それが純朴な坂東武者としての青年像を上書きしました。
一方で道長は、大きな器があるのに中に何も入れようとしない。
これは若い頃から一貫性があった。
青年期は父や姉に流され、その命令にさして疑念を抱いたように思えないものでした。
姉を亡くしてからは安倍晴明にやすやすと操られる。そのあとも、結局は権力に群がりたい周囲に流されて己を見失っているように思えます。
まひろはその器に何か注ごうとした。
しかし、もはや諦めているようにも思えます。
実資は、そんな道長の“虚な器”に、全て投げ出したように思えます。まひろも、実資も、もはや打つ手がないと感じたのでしょう。
実資はあきらめたように「帝の譲位はいま少し待つように」と訴えるのでした。
道長は虚な目をしています。
「論破」というより相手にされていない道長
この場面、もしも中国時代劇の世界観なら道長はどうなっていたか?
恥辱のあまり柱に額を強打して倒れるか、捨てゼリフとともに血を吐いて倒れているか。
『三国志演義』の諸葛亮とそのライバルの舌戦でもご想像ください。
あるいは実資はこう言ってもよい。
豎子、与(とも)に謀るに足らず。『史記』
ガキが、お前ごときとは共に策を考えることすらできん!
そんな辛辣な実資の言葉だったにもかかわらず、道長には余裕があるように見えました。
これは一体なぜなのか?
実資役の秋山竜次さんのコメントで読み解けます。
実資は、道長を舌戦で追い詰めようと正論を吐きました。実際にある程度、追い詰められてはいます。
ただし“知識の程度”が違い過ぎたのです。
これでは道長に痛撃を与えられない。
武勇の戦いならば実力差があれば簡単に倒せますが、舌戦ではある程度、倫理観や知識が釣り合っていないと難しい。
相手が「意味わかんな〜い」とピュアなハートでシラをきるか。
呆れて黙りこくったときに「論破www」と嘲笑うか。
そんな小手先の手段で勝利を偽装することができます。
道長の勝利はその手の偽装です。
藤原公任あたりの学識があれば、顔を恥辱に赤らめたかもしれませんが、道長はそこに達していない。
『三国志』でいうならば、諸葛亮がいくら苦言を呈しても、劉禅がヘラヘラ笑って「んッんーッ、丞相の言うこと難しくてわかんないやぁ〜」というようなものだとご想像ください。
心底腹が立ちませんか?
ええ、私は苛立っています。
ここの道長は、本当に器が空っぽ、虚しい男だと確認できました。
為政者として実現できるだけの才能がない。
二十年間その座にいてそうならば、そもそもが器量不足なのでしょう。己に実行力がないなら恥と退き際を知るべきです。
位を譲るべきであるのはむしろ道長でしょう。
この時代の出世は上が空かねば下のものが這い上がれません。疲れたなり、もう無理だとわかったら、さっさと譲るべきなのです。
それなのに、曖昧な「民の幸せ」だのなんだの言い募る。
「志を抱いてきたんだ」なんて言い出す。
そんなものは所詮、皆勤賞なのだから仕事ができないことは許せと言い出したようなもので、組織の上に立つ人間が吐いていい言葉でもありません。
道長は、実資が説く為政者の心得ビギナーズすら習得できていないのです。
『蒙求』からやり直せ。道綱よりは多少マシだろうけど、所詮はその程度でしょう。
実資のこの場面とあわせると、先週の宇治川の場面まで汚れてきました。
あれは結局、仕事のできないおじさんリーダーが、銀座でバーのママに「人の上に立つってつれーよ、慰めてよー。今度二人で温泉ランドでも行かない?」と愚痴をこぼしていた程度の話では?
演出が素晴らしいから騙される人も多かったけれど……。
なんなんでしょう。道長の、この選挙戦の時だけ綺麗事を語る政治家のようなゲスさは。好きなだけ宇治川に流れていけばよろしい。
だが、帝も政治能力がない
帝が、何やら丸薬を飲んでいると、最愛の妻である娍子がやってきました。
宋から取り寄せたようで、この薬が効けば目も耳も治るとの説明に娍子は感動しています。
するとそこへ敦明親王がやってきて、友人である藤原兼綱を蔵人頭に推挙してきました。
道兼の子であるか?と帝が確認すると、蔵人頭にしないと私の顔が立たないと敦明親王は訴えます。
帝は迷っている。
しかし、娍子からも頼まれるとますます揺らいでしまう。
結局、この嘆願は通り、藤原資平は罷免され、兼綱が蔵人頭となりました。
実資は憤り、墨を擦って、この不満を日記に書き散らすのでした。
かくして帝は実資からの信頼も失ってしまいました。もうどうしようもない……腐り切った政治です。
帝が服用している薬は「金液丹」です。
水銀が入っているため、要するに毒。医学知識だけで作られた丸薬は、そこまで危険でもありません。
しかし、神仙を目指す道教要素が含まれると、毒を取り込んでしまい、実は逆効果なのです。
中国史では【紅丸案】という信じがたい事件が起きています。
明の第15代・泰昌帝が「紅丸」という丸薬を勧められるまま服用したところ、在位一ヶ月ほどで崩御してしまったのです。
そこまでインパクトは強くないものの、日本の天皇もこうした怪しい薬を服用していたというのは、困った話。
『麒麟がくる』では、駒という医者が「芳仁丸」という安価な丸薬を販売しておりました。
薬効が穏やかで、容易に採取できる薬草を丸薬にする程度が、むしろ良心的で安心なのだろうと思えます。
そして、道長の政治態度も酷いけれど、帝にも帝王学がないことが露わになりました。
ああも信頼を寄せてくれた実資の期待をアッサリ裏切る。しかもその原因は妻子への気遣いのせいです。どれだけ器が小さいのか。
たぶんこの周辺は、誰一人として『貞観政要』などを目にしてないでしょう。
あの本を読めば、夫である皇帝に諫言する皇后が褒め称えられています。娍子は悪い人ではないのでしょうが、それだけの人です。
道長の素人じみた政治に対し、帝が老練していればまだしも救いはあったかもしれません。
しかし結局は帝もこの程度でした。
仕方ないのかもしれません。日本の政治の程度は、当時はまだまだこのくらいなのでしょう。
朱子学導入はまだまだ先。
為政者たちが四書五経も読みこなせているかどうか、甚だ心許ないと思えてきます。
※続きは【次のページへ】をclick!