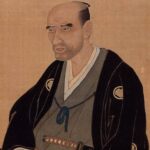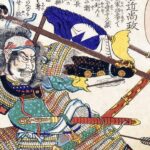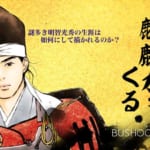まずは天正二年(1574年)元日の話。
今から446年前の今日かと思うと、少しだけ感慨深いと言いたいところですが、さすが信長さんだけあってインパクト大な正月を迎えます。
長政、久政、義景の首が……
この日、織田信長のいる本拠地・岐阜城へ、京都や近隣の大名が挨拶にやってきました。
それぞれに三献の作法で酒が振る舞われ、特にトラブルもなく宴は終わります。
大名たちが退出した後、信長は御馬廻衆だけを集めて、もう一度酒宴を開きました。
こちらは公私の”私”の集まりという感じでしょうね。
ここで信長が肴にしたのは、当時のみならず現代の我々も「あっ」と驚くものでした。
前年に討ち果たした朝倉義景・浅井久政・浅井長政の首を薄濃(はくだみ)にして、膳に乗せて並べたのだというのです。
-

信長を裏切り滅ぼされた浅井長政29年の生涯~その血脈は三姉妹から皇室へ続いた
続きを見る
-

なぜ朝倉義景は二度も信長を包囲しながら逆に滅ぼされたのか?41年の生涯まとめ
続きを見る
さすがに盃にして酒までは飲んでいない?
「薄濃」というのは、漆などを塗ってから金銀の粉や箔などを貼り付けて飾る手法のことを言います。
元々は古代中国の風習で、敵将に敬意を評し、その武力を自らに取り込むという呪術めいたものだったとか。
「岐阜」という字面も、信長の師の一人である僧侶・沢彦宗恩(たくげんそうおん)が古代中国の周王朝に縁のある地名からとったものです。
学問の中で、信長が薄濃のことを教わっていたとしても、不自然なことではありません。
太田牛一はこの”肴”のことを「いまだかつて聞いたことがない」と評しています。
牛一も織田家に仕える前は僧侶だったことがありますが、さすがに薄濃のことは知らなかったのでしょう。
この記述にはいつしか尾ひれがついて、
”信長は三人のドクロを切り取って盃を作り、それで酒を飲んだ”
という、いかにも恐ろしい話になったりします。
信長公記にはそこまで書かれていません。
おそらくは江戸時代あたりに、信長の残虐さを強調するために付け足されたものでしょう。
評価が低かった江戸時代の信長
自然の分解作用を利用して首をドクロにするまではまだしも、人間の頭蓋骨は20個以上もの骨が組み合わさっている複雑なものです。
戦国時代当時の技術で、酒を飲めるような形状に分解・加工した……というのは少々無理がありそうです。
他に例がないので、実際にできるかどうかはなんともいえませんが。
ではどうして”ドクロの盃”の話が出てきたのかというと、おそらく江戸時代では信長の評価がかなり低かったからだと思われます。
たとえば、江戸時代中期の儒学者・新井白石はこんな評価をしております。
「信長は好き放題に残虐なことをしたから、その報いとして本能寺の変で家臣に斃されたのだ」
-

幕府に呼ばれ吉宗に追い出された新井白石~学者は政治に向いてないのか
続きを見る
当時の庶民の娯楽である歌舞伎や浄瑠璃でも、信長を主役にしたものはほとんどありません。
出てきたとしても悪役か脇役で、今日のような主役級の人物ではなかったのです。
”神君”こと徳川家康の同盟相手なのですから、そこそこの評価をしても良い気がしますけれどね。
信長は皇室を復興させた勤王家
信長が再評価されるようになるのは、江戸時代後期の学者・頼山陽(らいさんよう)が好意的に評価してからのことです。
意外かもしれませんが、
「信長は、応仁の乱以降ボロボロだった皇室を復興させた勤王家である」
という評価でした。
-

脱藩上等!の自由人だった頼山陽『日本外史』著者の意外と破天荒な生涯とは?
続きを見る
幕末~明治にかけてこの見方が強まり、明治天皇によって「建勲(たけいさお)」という神号が贈られ、神社に祀られてもおります。
この建勲神社では、創建時に「織田家三十六功臣」という有力家臣たちも定められました。
詳しくは坂井政尚の記事にあるのですが、せっかくですから36名だけでも挙げておきましょう。
| 織田家三十六功臣 | |||
| 池田恒興 | 平手政秀 | 平手汎秀 | 堀秀政 |
| 豊臣秀吉 | 柴田勝家 | 丹羽長秀 | 佐久間信盛 |
| 佐久間盛政 | 佐々成政 | 前田利家 | 滝川一益 |
| 村井貞勝 | 山内一豊 | 毛利新助 | 簗田広正 |
| 森可成 | 森蘭丸 | 蒲生氏郷 | 河尻秀隆 |
| 坂井久蔵 | 坂井政尚 | 原田直政 | 細川藤孝 |
| 道家尾張守 | 湯浅甚助 | 福富貞次 | 不破光治 |
| 織田信業 | 織田信光 | 菅谷長頼 | 武井夕庵 |
| 稲葉一鉄 | 猪子兵助 | 氏家卜全 | 斎藤利興 |
御馬廻衆も信長も上機嫌だった
大正時代には正一位(臣下で一番エライ位)が追贈された信長。
世間の評価は、概ね好意的なものに変わっていきました。
ドラマや小説、ゲームなどのエンタメや、新しく発見された史料、インターネットの普及で細かなエピソードが伝播しやすくなったことなども、強く影響しているでしょう。
ですので、浅井・朝倉三人のドクロを薄濃にしたからといって、信長が残虐だったというわけではありません。
敵味方になって滅ぼした相手ですから、恨む気持ちもあったでしょうけれどね。
直接見た御馬廻衆の面々も「謡(うたい)や踊りで盛り上がった」そうですから、よくある正月の宴会風景といったものだったのでしょう。
信長も上機嫌だったそうです。
前年は足利義昭や浅井・朝倉両氏など戦ばかりでしたから、やっと一息つけたのでしょうか。
”肴”のインパクトさえなければ、のどかな光景といえなくもないですね。
あわせて読みたい
-

信長を裏切り滅ぼされた浅井長政29年の生涯~その血脈は三姉妹から皇室へ続いた
続きを見る
-

なぜ朝倉義景は二度も信長を包囲しながら逆に滅ぼされたのか?41年の生涯まとめ
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

坂井政尚の生涯|信長三十六功臣の一人 織田家に殉じた名無き功臣の働きとは
続きを見る
-

麒麟がくるのキャスト最新一覧【8/15更新】武将伝や合戦イベント解説付き
続きを見る
-

幕府に呼ばれ吉宗に追い出された新井白石~学者は政治に向いてないのか
続きを見る
-

脱藩上等!の自由人だった頼山陽『日本外史』著者の意外と破天荒な生涯とは?
続きを見る
信長公記をはじめから読みたい方は→◆信長公記
長月 七紀・記
【参考】
国史大辞典
『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)
『信長研究の最前線 (歴史新書y 49)』(→amazon)
『織田信長合戦全録―桶狭間から本能寺まで (中公新書)』(→amazon)
『信長と消えた家臣たち』(→amazon)
『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)
『戦国武将合戦事典』(→amazon)