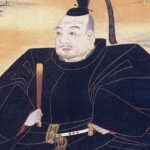信長・秀吉・家康の三英傑に気に入られた戦国武将を一人挙げよ。
そんな問題がクイズに出されたら、真っ先に書きたいのがこの方。
永禄7年12月29日(1565年1月31日)に生まれた池田輝政です。
父は信長の乳兄弟として知られる池田恒興。
その次男の時点で、戦国武将としてはラッキーな生まれとも言えますが、その後も不思議と秀吉や家康に重宝されていく生涯を送ります。
こうなるともはや運だけではないでしょう。
権力者に好かれる何かを「持っている」のではなかろうか。
もしかしたら現代でも通用してしまう?

池田輝政/wikipediaより引用
そんな池田輝政の生涯を振り返ってみましょう。
※池田輝政は、生涯のほとんどが「照政」表記でしたが、現代で慣れ親しまれた「輝政」で統一させていただきます
池田輝政は織田家一門に準ずる生まれ
前述の通り、池田輝政は永禄七年(1565年)12月29日、池田恒興の次男として生まれました。
父の恒興は織田信長の乳兄弟です。
当然、織田家との繋がりは濃く、輝政も父や兄(元助)と共に信長へ仕え、天正七年(1579年)に荒木村重が謀反を起こして以降、たびたび記録上に名前が出てくるようになります。

池田恒興/wikipediaより引用
村重が妻子を捨てて逃げ込んだ先、花隈城の戦い(天正八年=1580年)では、輝政自ら荒木方の武士を5~6人も討ち取り、信長から感状を与えられました。
感状というのは、主人が
「お前はこの日・この時・この場所で、これこれの手柄を挙げたことを証明する」
という証明書のようなものです。
言わずもがな、武士の功績というのは戦場での手柄で決まります。
当時は映像や画像で記録することができませんから、書面に記録することで手柄を証明したわけです。
万が一、何らかの理由で他家へ仕えることになったときも、感状があれば有利に仕官することができました。この場合は現代でいう履歴書や、資格の証明書に近いイメージになりますね。
このときの戦功については『信長公記』でも
「池田元助・輝政の兄弟は15~6歳の若年ながらに、比類なき手柄を挙げた」
と記録されています。
『信長公記』とは、その名の通り織田信長の功績や逸話を後世に伝えるために書かれたものですので、他の武将について感情的な表現をされているのは珍しいケース。
著者である太田牛一も、次世代を担う若者の活躍に感じ入ったのでしょう。
甲州征伐からの本能寺
天正年間(1573~1592年)は、信長の息子世代が徐々に元服し、戦場へ出始めた時期でもありました。
信長にしても嫡子・織田信忠へ家督継承を済ませていましたし、池田家のように、家臣たちの家でも若い世代がどんどん戦場へ赴いています。

織田信忠/wikipediaより引用
天正十年(1582年)2月には、池田輝政も兄と共に甲州征伐へ参加していました。
武田勝頼を滅ぼした一連の戦で、父の恒興は摂津の留守居役に残っています。
順当にいけば輝政も、そのまま信忠を支える重臣の一員として名を残していたことでしょう。
しかし、です。
この年の6月2日、織田家に大激震が走ります。
本能寺の変です。
ご存知、明智光秀が本能寺の織田信長に襲いかかった一大謀反であり、わずかな手勢で光秀の大軍に囲まれた信長は敗死。
輝政の父・恒興は上方に戻ってきた羽柴秀吉と合流し、【山崎の戦い】に臨みました。

「山崎合戦之地」の石碑(天王山/京都府乙訓郡大山崎町)
恒興は信長の乳兄弟であり、その母(輝政からみて祖母)の善応院は信長の乳母になりますから、織田家の親族に準ずる立場です。
秀吉にとっては重要な味方といえるでしょう。
長久手の戦いで討死寸前
山崎の戦いで勝利を得た秀吉は、次に【清州会議】に臨みます。
会議の中身は、織田信長の嫡孫かつ織田信忠の嫡男である三法師を誰が補佐するか?
まだ幼い当主の名代を、信長の息子である織田信雄と織田信孝が争ったのです。

三法師こと織田秀信/wikipediaより引用
そしてその背後には柴田勝家と羽柴秀吉たち重臣がいて、北条軍に敗れた滝川一益の代わりとして池田恒興が参加していました。
【清州会議メンバー】
・柴田勝家
・羽柴秀吉
・丹羽長秀
・池田恒興
清州会議というと、あたかも秀吉の弁舌で他の者たちを丸め込んだように描かれますが、実際はそんなことなく、その後、秀吉と反目した織田信孝と、柴田勝家が結びついて挙兵し、【賤ヶ岳の戦い】で羽柴軍と衝突します。
輝政や池田家の活躍について、ここで特記されることはありません。
ずっと秀吉サイドにいたのは間違いなく、賤ヶ岳の戦いに勝利した後も加増されるのですが、程なくして起きた戦いで池田家は重大なピンチに陥ります。
天正十二年(1584年)3月に始まった【小牧・長久手の戦い】です。
と、その戦いを見る前に、ここまで一気に来た流れを、いったん整理しておきましょう。
【天正10年/1582年】
①本能寺の変
↓
②山崎の戦い(秀吉vs光秀)
↓
③清州会議
↓
【天正11年/1583年】
④賤ヶ岳の戦い(秀吉vs勝家)
↓
【天正12年/1584年】
⑤小牧・長久手の戦い←NOW
本能寺の変から2年。小牧・長久手の戦いで池田家が迎えた重大ピンチとは一体何だったのか?
実はこの戦いで、父の池田恒興と兄の池田元助が、同時に戦死してしまうのです。

『小牧長久手合戦図屏風』/wikipediaより引用
小牧・長久手の戦いは、約8ヶ月に及ぶ大戦ながら、実際に激しい戦闘が起きたのは長久手の戦いぐらいで、その他のエリアでは睨み合い・小競り合いが続く耐久戦でした。
そんな戦況で焦りが募ったのでしょう。
序盤でヘマをした森長可と池田恒興が「家康の背後をつき、本拠地の三河を攻めましょう!」と秀吉に提言。
いわゆる【中入り】という戦術を強行したところ、これが家康にバレてしまい、長久手の地で迎撃を受け、父と兄が討死してしまったのです。
輝政も長久手の戦いに参加しており、一時は父と兄の後を追って斬死しようとしていたとか。
激情的なエピソードが他にない人物ですが、さすがに父と兄を同時に失い、冷静ではいられなかったのかもしれません。
このときは家臣が「お父上と兄君は討ち死になさったのではありません、先に戦線を離れておいでです!」と強弁し、半ば無理矢理に輝政を逃した……なんて説もあります。
いずれにせよ輝政は、すぐ下の弟・長吉と共に戦線離脱に成功し、この後の池田家を二人で支えていくことになります。
秀吉から重宝され破格の待遇
予期せぬ形で家を継いだ池田輝政。
秀吉も「当主と嫡子が同時に討死」というところに責任を感じたものか。
小牧・長久手の戦いの後、善応院宛ての手紙では「輝政殿と長吉殿を亡きお二人の代わりに取り立てていきたいと思います」と語っています。

豊臣秀吉/wikipediaより引用
秀吉にとって、池田家を味方につけるメリットは複数ありました。
一つは、前述のように池田家が織田家一門に準ずる立ち位置だったこと。
小牧・長久手で敵対していた織田信雄とは和解できた秀吉ですが、信孝については死に追いやっており、世間に「実力はあるかもしれんが、主筋の人間を押しのけたのはいただけない」と思われていても致し方ないところ。
不評を払拭するためには、それが気にならないほどの実績と後ろ盾が必要です。
もう一つは、秀吉の縁戚となって自分の政権を支えてもらいたいという狙いがあったことです。
広く知られている通り、秀吉は身一つから織田家で出世し、中国方面の責任者となっていた人物。
本人の能力は申し分ないにしても、武将から大名になるにあたって、親族や譜代の家臣が乏しいというのは非常に大きな弱点でした。
それを補うべく、福島正則や加藤清正など、見込みのある親族の少年たちや、石田三成・大谷吉継のように行く先々で見出した人物を取り立てていったわけです。

加藤清正/wikipediaより引用
しかし、それにも限界があります。
加えて秀吉の実子は幼くして世を去ってしまっており、後継者の懸念もじわじわと忍び寄っています。
となると、有力な大名と秀吉の親族との間に婚姻関係を結び、後ろ盾になってもらうのが最善の策です。
池田家の人々をみてみると、秀吉にとって非常に都合のいい存在でした。
日頃の態度も好ましく、また恒興の代から積み上げた世間の信頼も申し分ない。
加えて輝政を含め、一族の人間は健康に恵まれていて人数も多く、戦力としても縁戚候補としてもアテにできます。
こういった複数の理由から、輝政は秀吉から破格の厚遇を受けることになります。
家康の娘・督姫を継室に迎える
天正十三年(1585年)には信忠の城だった岐阜城を与えられ、10万石の大名に。
天正十五年(1587年)の九州征伐に従軍した後は羽柴氏の名乗りを許され、さらに翌十六年には豊臣姓まで与えられています。
さらにその2年後の天正十八年(1590年)、小田原征伐の後は東三河に四郡加増され、吉田城(豊橋市)に居城を移しました。
この頃から豊臣秀次の与力のような扱いを受けており、文禄の役では秀次の下で東国警備の役目を果たしています。

豊臣秀次/wikipediaより引用
慶長の役でも出兵せず、大船建造や兵糧の手配を担当しました。
輝政の姉妹である【若政所】が秀次の正室だったということも理由の一つかと思われます。
朝鮮の役と直接関係ないところでは、伏見城などの普請にも携わりました。
他にこの間あった出来事としては、文禄三年(1594年)に徳川家康の娘・督姫を継室に迎えています。
もともと彼女は北条氏直に嫁いでいたのですが、小田原征伐の後、実家に送り返されていました。
一説には「輝政の最初の正室だった中川清秀の娘(大義院)が、嫡男・利隆を生んだ後、産後の肥立ちが悪く実家に帰った」ため、徳川家と池田家の結び付きを強める意味もあって、秀吉が斡旋したのだとも。
その後も池田家と中川家との関係は悪くなさそうなので、大義院との離縁に裏はないと思われます。
また、輝政と督姫の間には忠継・忠雄らが生まれているため、こちらの関係も比較的良好だったのでしょう。
秀吉が輝政を重宝したのも、この人付き合いの良さが理由の一つかもしれません。
細川藤孝(幽斎)のように積極的に社交するタイプとはまた別種の、日頃の人当たりの良さで人脈が少しずつ広がっていったタイプでしょうか。
こういう人は本人が意識しなくとも、自然と他者を惹きつけますよね。
姫路城完成と哀しい逸話
こうして豊臣秀吉とも徳川家康とも、どうにかうまくやっていた池田輝政。
秀吉の死後は少々難しい立場になります。
慶長四年(1599年)に前田利家が亡くなった後、輝政が石田三成襲撃に加わったという説もあるのですが……記録によって襲撃に参加した武将の名が違うため、断定はできません。
伝えられている輝政の日頃の振る舞いから考えると、この手の荒っぽい件にはあまり関わっていなさそうです。
もしかすると関ヶ原の戦いで東軍についたことから、逆説的に
「輝政も三成を嫌っていて、襲撃にも加わったに違いない」
と考えられたのかもしれません。
関ヶ原当日は毛利軍などの押さえを務めていました。その毛利軍らが動かなかったため、輝政は戦闘をしていません。
前哨戦のひとつ【岐阜城の戦い】では福島正則と共に戦功を挙げているのですが、このとき城にいたのが西軍・織田秀信(三法師)だったというのがなんとも……。

福島正則/Wikipediaより引用
岐阜城は輝政の居城だったこともありますし、いろいろと因果がありますね。
この戦功によって、輝政は播磨に52万石を与えられました。
姫路城完成と哀しい逸話
姫路城に移ると、早速大改修に取り掛かります。
現代も名城として知られる同城の大部分は、このとき輝政が施したものです。
慶長六年(1601年)から9年もの歳月をかけた大工事で、その甲斐あって、姫路城は「白鷺城」の美称を持つほどの名城になりましたが、実は悲しい逸話もあります。

白鷺城こと姫路城
輝政が行った姫路城の大改修において、桜井源兵衛という男が大工の棟梁を務めていました。
彼は根っからの仕事人間で、この大任にも積極的に打ち込み、ついに完成の日を迎えます。
しかし、彼はふと気付いてしまいます。
「天守が少し、傾いていないか?」
そして源兵衛は妻を伴い、天守を見せました。
すると妻も「とても立派ですが、少し傾いているのが残念ですね」と言ったそうです。
源兵衛は非常に大きな衝撃を受けました。
同じ大工に指摘されるならばともかく、素人の妻にわかってしまうほどならば、輝政や他の重臣・武士、果ては一般人にもわかるはず。
そんな大失態をこの大仕事でやらかしてしまったのですから、自責の念は一層強まったことでしょう。
「俺が計った寸法がよほど狂っていたに違いない」と、ノミをくわえて天守から飛び降りてしまったのだそうです。
実際に姫路城の東と西の石垣が沈んで傾いていたようですが、これは源兵衛のせいとは限らないのでは……と、個人的には思います。
なぜかといいますと、ちょうど姫路城の大修築が行われていた最中である慶長九年(1605年)に、慶長地震が起きているからです。
慶長地震による姫路周辺の被害は不明ながら、この地震は関東~四国まで非常に広い範囲で何らかの被害が起きています。
となると、工事中の姫路城が、一見問題ないレベルで傾いてしまい、それが完成後に発覚した……ということも十分あり得るのではないでしょうか。
「姫路宰相百万石」
輝政が姫路に入ったのと前後して、他の池田家の人々にも所領が与えられました。
輝政の弟・長吉 鳥取6万石
輝政次男・忠継 備前28万石
輝政三男・忠雄 淡路6万石
長吉はともかく、忠継・忠雄はまだ10歳にもならない子供。
二人の母親が督姫であり、彼らが家康の外孫であるということを考えても、かなりの贔屓です。
輝政・長吉・忠継・忠雄の四人に与えられた領地を合計すると、92万石もの石高。
「輝政は西国における将軍同然」
「姫路宰相百万石」
なんて言われたそうですが、それも納得ですね。
家康としては、他の大名に池田家への反感を持たせ、結びつかないようにする……という狙いもあったのかもしれません。

徳川家康/wikipediaより引用
他には松平の名乗りも許されています。
”宰相”は、官職の”参議”の異称です。
輝政は慶長十七年(1612年)に正四位下・参議になっていたため、姫路宰相と呼ばれました。
江戸時代には他にも参議になった大名が多々おり、領地と合わせて「◯◯宰相」と称されています。
家康からの信頼や期待を寄せられつつも、大名同士の付き合いとしては難しい状況になった輝政ですが、意外なほどトラブルは伝わっていません。
それは夫婦間や親子間でも同じで、江戸時代初期の難しい時代によくここまで波風を立てなかったものです。
慶長十六年(1611年)に家康と秀頼が二条城で会見した際、加藤清正や藤堂高虎などとともに同席しており、ここからも家康の信頼がうかがえます。

豊臣秀頼/wikipediaより引用
家康自ら考案した薬を送ったほど
会見翌年の慶長十七年、中風を発症。
一度は回復しながら、慶長十八年(1613年)1月に再発して池田輝政は亡くなりました。
享年50。
中風は現代でいうところの脳卒中とその後遺症のことですから、再発もやむなしというところでしょう。
輝政が中風を患ったと聞いた家康は、自ら考案した烏犀円(うさいえん)という薬を送ったといいます。効果の程は不明ですが、家康は中風に効くと信じていたそうです。
それを送るということは、輝政にまだまだ働いてもらいたかったのでしょうね。
なんせその死は大坂城にいた豊臣家の人々にとっても衝撃的で「輝政がいる限りは、秀頼様の安泰も確保できたのに」と言われたとか。
輝政は豊臣家に対する恩を感じつつも、徳川家に睨まれないための振る舞いが非常にうまかったため、アテにされていたのでしょう。
あまり輝政のプライベートに関する逸話はないのですが、どうも日頃から寡黙な人だったようです。
そんな彼が唯一好きだったといわれているのがセリ。
現代では春の七草や郷土料理に用いられていますが、それ以外だとあまりお目にかからない野草ですね。
輝政は領地内のとあるところに生えるセリを上物とし、勝手に取ることを禁じていたのだそうです。
しかし、ある時とある者がこれを盗み、輝政に通報が届きました。
すると輝政は
「私の分に採らせたセリを強引に奪ったのならけしからん話だ。しかし、こっそり盗んだのならきっと私と同じセリ好きがやったのだろう。放っておけ」
とあっさり許したそうです。
つまり、独り占めしたくてセリ取りを禁じたのではなく、本当にそこのセリの味が気に入ったから取るのを禁じたのでしょう。
もしくはセリによく似たドクゼリとの混同を避けるために「ここなら確実に安全なセリが生えているから、取って食べても大丈夫」と保証したかったのでしょうか。
いずれにせよ、なぜそこまでセリが好きだったのかを知りたいところですね。
あわせて読みたい関連記事
-

池田恒興の生涯|信長の乳兄弟で織田家の重臣に大出世も最期は家康に討たれ
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
-

秀吉vs家康の総力戦となった「小牧・長久手の戦い」複雑な戦況をスッキリ解説
続きを見る
【参考】
国史大辞典
太田 牛一・中川 太古『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)
日本史史料研究会編『信長研究の最前線 (歴史新書y 49)』(→amazon)
谷口克広『織田信長合戦全録―桶狭間から本能寺まで (中公新書)』(→amazon)
谷口克広『信長と消えた家臣たち』(→amazon)
谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(→amazon)
峰岸 純夫・片桐 昭彦『戦国武将合戦事典』(→amazon)
姫路城公式サイト(→link)