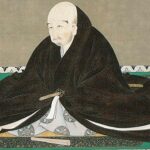こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第36回鸚鵡のけりは鴨】
をクリックお願いします。
鸚鵡のケリを、鴨でつけ
なんで本を書いただけでこんなことになるのか!
蔦重から顛末を聞いた歌麿が嘆いています。
我もまた 身はなきものと おもひしが 今はの際は さみしかり鳧(けり)
彼の残した辞世です。
鳧(けり)とは鴨のことも指し、「鸚鵡のケリは鴨でつける」という意味だと読み解かれています。
唐来三和がここで何かして北尾重演に留められています。南畝がここで読みます。
我もまだ 実は出ぬものと おもひしが 今はおかはが 恋しかり鳧
「腹壊した歌にしちまって……」
そう重演があきれると、三和はこうきました。
「だって……こんなのやってられねえじゃねえかよ! ふざけねえとよ!」
ここで蔦重が思いついたように言います。
なんでも春町の頭には豆腐がくっついていたとかで、彼なりの推理を語ります。
腹を切った春町は、最期の力を振り絞り、豆腐に頭を突っ込んだのではないか?
豆腐の角に頭をぶつけて死んだことにしたのではないか?
それに対し、喜三二が読み解きます。
「戯作者だから……真面目な、クソ真面目な男だったじゃない……ふざけるのにも真面目でさ。恋川春町は最後まで戯けねえとって考えたんじゃねえかなぁ!」
涙ぐみつつ泣き笑いだす一同。
「べらぼうでさぁ! 春町先生……おふざけが過ぎまさぁ!」
蔦重が泣きながら思いを絞り出します。
悲しい無念の死を、笑って見送る仲間たち。
そのうち幾人が、春町と同じく、理不尽な処罰に苦しめられることになるのやら……。
武家として、戯作者として、生きて死ぬ
松平定信は、松平信義から倉橋格の死を聞かされました。
信義は「腹を切り、かつ……」と言いながら、笑い出します。
「豆腐の角に頭をぶつけて……」
信義が説明を続けます。
ご公儀を謀ったことについて、武士である倉橋格としては腹を切って詫びるべきだとそうした。
戯作者の恋川春町としては、死してなお、世を笑わすべきだと考えたのだろう。そしてこのことは版元の蔦屋重三郎から聞いたことだと付け加えます。
「一人の至極真面目な男が、武家として、戯作者としての“分”をそれぞれわきまえ、まっとうしたのではないかと、越中守様にお伝えいただきたい。そして戯ければ腹を切らねばならぬ世とは、一体誰を幸せにするのか。学もない本屋風情には……分かりかねると。そう申しておりました」
蔦重が願った定信との対話は叶わずとも、こうして間接的には届いたことになります。
信義との対話を終え、一人になった定信は悄然として歩いています。そして床に落ちた黄表紙を見ると、倒れ込み、泣き伏す。
己を励まし、新たな世界を見せてくれていた黄表紙。その作家を己が殺めてしまった――これほどの悲しみと絶望はないでしょう。
文人を迫害するとは、為政者としても暴虐そのもの。始皇帝の焚書坑儒のような悪行を為したことを、後世の人々はどう思うのか!
あまりに深い絶望が、彼を飲み込んでいました。
MVP:恋川春町
史実の恋川春町は、死にいたる状況はおおよそ把握できるものの、死因や詳しい状況は不明です。
それをうまく脚色し、最高の退場が用意されていました。
死せる春町、生ける越中を哭かす――なんとも見事な最期ではないですか。
ドラマとして創作しつつも、人々の感情を組み合わせ、見事に織りなしている。
春町が中心にいるものの、その周囲まで輝いて見せてきます。
同じ目に遭いつつ、どうして朋誠堂喜三二は生き延びたのか。藩主の対応により、そのことを対照的に見せてきました。
松平信義は、なまじ春町を信じて理解していたからこそ、悲劇の結末になったといえる。
理解ある上司ゆえにかえって縛られてしまうというのは、なんとも日本的な悲劇ではないですか。
そして春町を死に追いやってしまう松平定信も、複雑で興味深く、研究を反映させた描き方となっております。
松平定信の政治姿勢は、田沼時代から踏襲した部分も多い。
そう描くことで、田沼意次と松平定信を正しく評価しています。
そのうえで、風雅を愛する定信の美質がかえって彼自身を傷つける因果も理解できます。
最新研究を取り入れ、文化を描き、人の心理を織り込んで、おもしろくドラマとして仕上げる。
毎回超絶技巧で仕上げてくる。
今回も実に見事な出来でした。
総評
とんでもねえほどに世間の風と一致してしまう本作。天意を汲み取ったらこうなっちまうということでしょうか。
今回は権力による言論弾圧を問題提起してきました。
海の向こうアメリカでは、政権の意向に沿わぬ言論弾圧の嵐が吹き荒れております。
こういうとき、西洋は「言論弾圧は恥である」という方向に向かわないのかと首を捻ってしまったんでして。
言論の自由ってぇなぁ、近代以降、西洋由来のもんじゃなかったんですかい?
ちょっと嫌味をかましてしまいましたが、これはなかなか重要なことだと思いまして。
日本ではどうにも、近代の要素とは西洋から海を越えて到来するものだという刷り込みがなされているように感じます。
それこそ松平定信の弾圧にせよ、蛮社の獄にせよ、安政の大獄にせよ、幕府の言論思想弾圧は東洋の古びた悪しき価値観ゆえのものだと説明されがちです。
果たして実態はどうなのか?
東洋にも言論弾圧を恥と考える思想はあったのではないか?
都市の発展と時代の進歩により、言論が活性化されていったのではないか?
この考え方はなかなか重要だと思えるのです。
江戸時代の言論は弾圧されっぱなしだったかというと、そう単純なことでもありません。
定信が初めてそれをしたわけでもない。
徳川綱吉時代には朋誠堂喜三二の先輩のような人物がおりました。
絵師の英一蝶(はなぶさいっちょう)です。
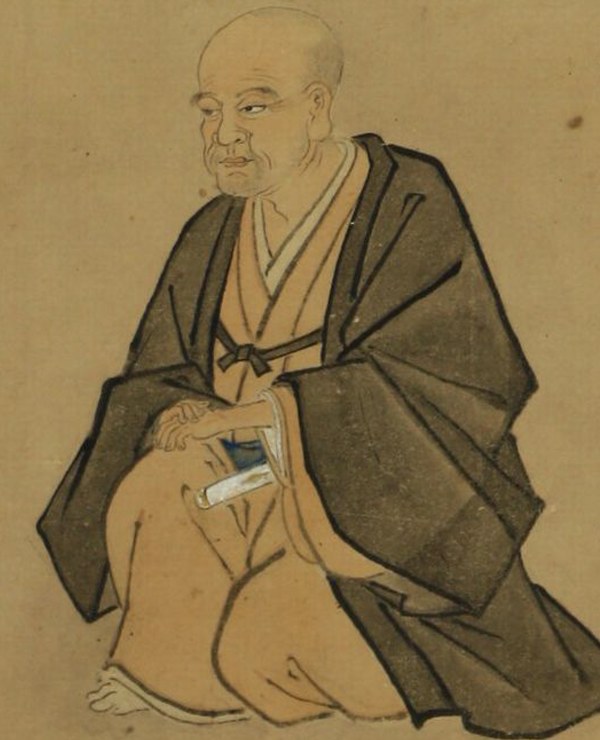
英一蝶/wikipediaより引用
彼は吉原で大名らと派手に遊び過ぎて、三宅島に12年間も流罪になっております。
身分の差といった要素もあるのでしょうが、それと比べて喜三二の処分は穏当に思えなくもありません。
春町は結果的に命が失われたものの、はなから死なせる気であったかはわかりません。
前述したように、天保年間には歌川国芳がド派手な風刺画を発表し、大ヒットを飛ばしております。
狂歌のように、男女双方が政治批判を含めた言論を交わし合う場も、実に特異的といえる。
近世日本の言論の自由とは、実に複雑怪奇なんですね。
さらに付け加えますと、始皇帝の言論弾圧である焚書坑儒は絶対悪と看做されています。
『キングダム』は始皇帝陣営が主役という時点で見る気が起きないという中国人も少なくないものです。
また、奸雄とされる曹操も、自身を痛烈に批判した文人の陳琳(ちんりん)を放免しています。
これを踏まえて「言論弾圧は曹操以下の悪行」とみなす考え方もあります。
こうした東洋の例をふまえるに、言論の自由は西洋の専売特許扱いするというのも、妙な話ではないか?と私には思えてきます。
同時に、歴史を学ぶ面白さとは、そんなところにもあるのでは……と思えてくるわけでして。
アメリカから流れてくるニュースがあまりに憂鬱で、大河ドラマで気分転換を図ることになるとは予測だにできぬことではありましたが、そうなりつつありますぜ。
あわせて読みたい関連記事
-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由
続きを見る
-

『べらぼう』尾美としのり演じる朋誠堂喜三二~蔦重と手を組む武士作家の実力は?
続きを見る
-

平秩東作の生涯|平賀源内の遺体を引き取った長老は蝦夷地にも渡る
続きを見る
-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗
続きを見る
-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由
続きを見る
【参考】
べらぼう公式サイト