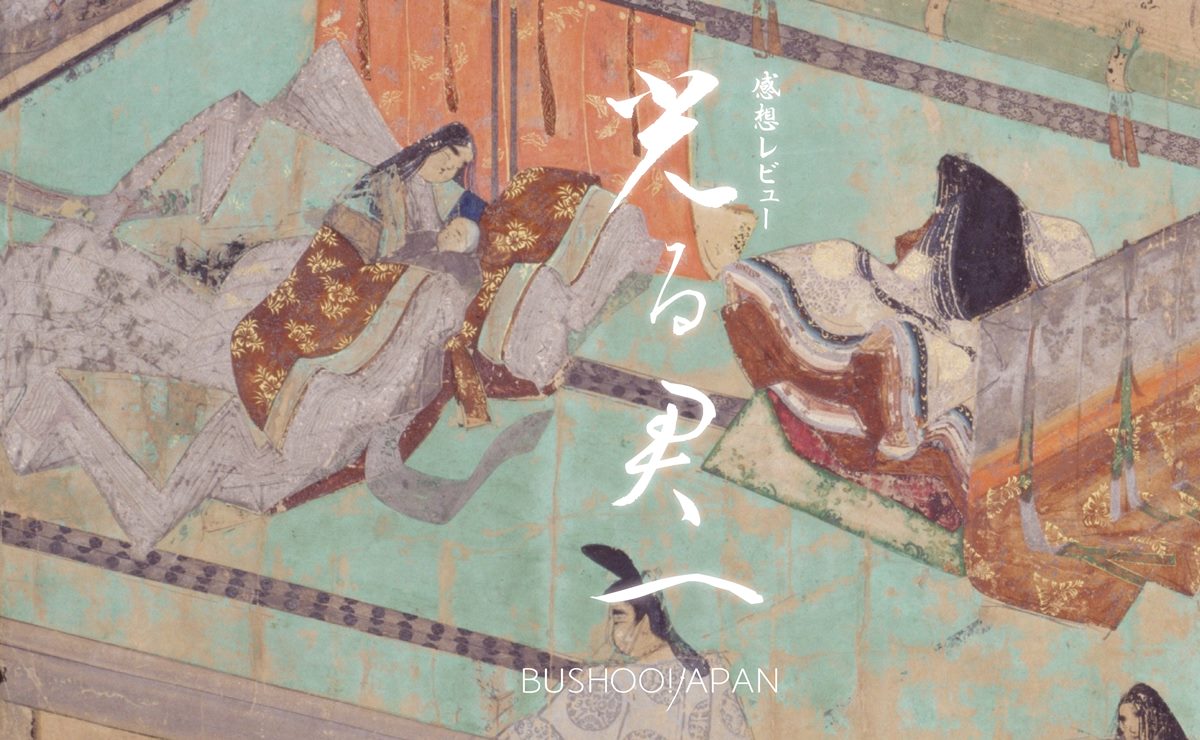こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『光る君へ』感想あらすじレビュー第25回「決意」】
をクリックお願いします。
公任が下の句を詠み 清少納言が上の句を
藤原公任が職御曹司で、帝と中宮を前にして笛を奏でています。
帝はうっとりとした顔で聞き入り、定子は嬉しそうで、どこかが痛むような切ない笑顔をしている。
公任は美しい。笛の音色も吹く所作も良い。
しかしなまじ秀才なだけに、道長に何か助言ができないのかと苛立ってしまうことも確かです。
帝は良い音色だと褒め、清少納言と公任の歌のやり取りについて尋ねます。
公任が下の句を詠み、清少納言が上の句をつける。
公任:すこし春ある 心地こそすれ
清少納言:空寒み 花にまがへて 散る雪に
空寒み 花にまがへて 散る雪に すこし春ある 心地こそすれ
寒空の下、花びらと見間違えそうに降る雪に、少し春の気配を感じる。
白居易『南秦雪』(なんしんのゆき)にある、この句を踏まえたものでした。
二月 山寒うして 少しく春あり
二月は山が寒く、少しだけ春を感じさせる
白居易『南秦雪』
定子がうっとりとこの歌を口ずさんでいると、漢詩を踏まえていることに帝が気づきました。
伊周が、公任に歌の指南を頼むと、伊周に教えるほどのことはないと謙遜する公任。
純粋に謙遜しているのか、それともまだ情勢を見定めているのか。
伊周は公任による歌の会を開きたいと言い始めました。
男も女も学ぶ場を設けたい、皆も喜ぶとの提案です。
帝も中宮もこれには賛同し、公任は承諾したのかしていないのか、曖昧な言葉を返します。
かつて為時がまひろに語ったように、確かに都では皆本音を言わないのかもしれない。そう思わされます。
-

史実の藤原公任はモテモテの貴公子だった?道長のライバル その生涯を振り返る
続きを見る
道長、辞表を提出し、諫言する
そこへズカズカと現れたのが道長でした。
途端に周囲には緊張感が走り、帝はあからさまにうんざりした顔をしています。
公任は横目で道長を見て、急に引き締まった顔になったようだ。
公任は才能を発揮できる機会があれば拒まない。そうする。しかし自負しているのは、政治の才能であり、それを自分でも活かしたいのだと思います。
かつては【貞観の治】を目標に掲げていたくらいです。
帝の元にいてもそれはできない。だが道長ならば……そう見定めるような目つきで、どこか弛緩していた顔がキリッとしました。
「ここでは政の話はしない」
帝はそう言いながら、その場から立ち去ろうとする定子の手を掴んで引き止めます。
道長は、鴨川の堤が決壊したことを告げにきていました。
被害は甚大。
事前に堤の修繕を依頼しても、まったく話が通じなかったとされます。
そもそも帝は内裏にいません。
道長は許しのないまま修繕しようとしたものの間に合わず、一昨日、ついに大事になったと語ります。
この場面の公任の目つきがどんどん鋭くなっていって、町田啓太さんが役に入り込んでいることがわかります。
帝も動揺して、彼は愚かではないとわかる。塩野瑛久さんの演技が実に細かい。
道長は、帝を直接責めず、煮え切らずに判断が遅れたせいだと結論づけ、民の命を失ってしまった罪は重いと訴えました。
そこが道長だと思います。
『真田丸』の真田昌幸、あるいは『鎌倉殿の13人』の三浦義村など。
ああいう連中は自分が正しいんだから、もうやるしかないと動いて、動いたあとでどうするか考えて、割とどうにかしてしまいます。
道長はそうではありません。
「左大臣は務められない」と言い始めました。どうあっても関白に固執したい父や兄・道隆とは違います。
「ならぬ!」
思わず帝が声を荒げます。
帝の叔父であり、朝廷の中心であり、導き支えるのは道長である。
帝はそう反省したのでしょう。
道長はわざとなのか、そうでないのか判別しにくいのですが、帝の許しを得ぬまま政治を進められないことが失態に繋がったと結論づけます。
安倍晴明が誘導してきた“根本”に到達したのです。
道長はむしろ哀れで、板挟みになった姿に見えます。
仮に兼家や道隆のように居丈高であればまた別なのでしょうが、道長は自らを弱く見せることもできます。
帝もこれ以上強くは言えず折れてしまい、「朕が悪い」と反省しきりです。
それでも道長はなおも、行成経由で辞表を提出したと言います。
ゲームではない。
本気だ。
そう訴えるようにして去ってゆきます。ただし、その後三度に渡って出された道長の辞表はついに帝は受け取らなかったとか。
重たい空気の中、公任だけは何か見出したような目つきで道長を見送っています。
伊周にあんなに媚びておいて、道長に期待をかけるなんておかしい?
いや、公任ならばこう言いそうですよ。
良禽(りょうきん)は木を択(えら)んで棲む
自分ほどの鳥ならば、道長という木を見つけたらそちらに飛び移るまでだと
無言ながら、中宮定子の表情も深い。さすが高畑充希さんです。
伊周は気づいていないかもしれないけれども、帝はさすがに気づいた。そして定子は絶望した……己の寵愛は後ろ盾あってのこと。
帝の寵愛を受け止める後ろ盾となる兄の器は、道長には到底及ばない。
権力を保持するための工作しかできない兄では早晩、また同じことを繰り返しかねない。
-

家康も泰時も一条天皇も愛読していた『貞観政要』には一体何が書かれているのか
続きを見る
ウニが結んだ縁
泥だらけになった自宅をまひろが片付けています。
乙丸が鴨川の堤を確認してきたようで、まひろは家を失った人を心配しています。
途方に暮れていた……と乙丸が端的に説明すると、大水はよくあることだからいずれ持ち直すと福丸はフォローしています。
慣れ切っているのでしょう。
平安京の左京はあまりに洪水が多すぎて、荒れ放題だったとか。
そういう水利の悪い土地に対し、どうしてこうも無策なのかとは思わず言いたくもなりますが、当時ならば限界はありますよね。
まひろはここで福丸の献身に感銘を受けています。
いとが「この人は私の言うことならばなんでも聞く」となんだか誇らしげ。そこがよいのだとか。
のろけではなく、私なりの考えを披露するいと。
歌がうまい男がよいとか、見目麗しい男がよいとか、富がある男がよいとか、話の面白い男がよいとか、皆言うけれども、いとは何もいらない。
自分の言うことを聞くこの人が尊いのだと。
まひろは目を動かしつつこの言葉を聞き、納得しています。
すると今度は、乙丸ときぬの馴れ初めをいとが聞いてきました。
乙丸はまひろのためにウニを求めた。きぬはそのウニを取る海女だったそうで、特技は息を長く止めていられること。
乙丸がまひろを思う心が、きぬと結びつけてくれました。
この作品には、愛が愛をもたらすような描き方があって好きです。今は亡きさわにせよ、為時がさわの母にあたる妾を看取ったことが出会いの契機です。
ただウニがおいしそうなだけではなく、もっとよいものがあの背後にはあったのですね。
道長のもとに、ウニが好きな宣孝が挨拶に来ました。
川岸の検分に来ていた道長を褒め、そつなく山城守になった礼を言い、さらには藤原為時が越前守になったことまでお礼を言います。
そして本題だ。
為時の娘も夫を持てるようになったと言い出しましたよ。
動揺する道長。それでも隠し、祝う道長に、宣孝はこうきます。
「実は私なのでございます」
「何が私なのだ?」
「為時の娘の、夫にございます!」
一瞬苦い顔をしつつ「それはなにより」と返す道長。
まひろの夫がこいつか!
そう言いたげな顔でした。
※続きは【次のページへ】をclick!