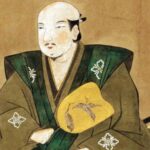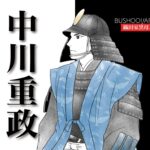こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【蜂屋頼隆の生涯】
をクリックお願いします。
ついに和泉国を任されて
天正八年(1580年)8月。
織田家の家臣団に激震が走ります。
家老の佐久間信盛と息子・佐久間信栄が、石山本願寺攻めなどの不手際を訴追され、織田家から追放されたのです。
-

佐久間信盛の生涯|なぜ織田家の重臣は信長に追放されたのか?退き佐久間の末路
続きを見る
このとき信盛が持っていた権限は様々な武将に分配され、頼隆は和泉国の支配権を得ました。
が、すぐには国入りしませんでした。
しばらくは大坂で活動し、さらに同年11月には同地の邸で茶人・津田宗及の見舞いを受けています。
体調が優れなかったために、様子を見ながらできる仕事をしていた……という感じでしょうか。
それでも天正九年(1581年)2月28日の京都御馬揃えでは、一番手・丹羽長秀のすぐ後、二番手として参加していますので、このあたりまでには回復していたようです。
-

京都御馬揃え|信長の家臣たちが勢揃いした軍事パレードは衣装もド派手だった
続きを見る
このとき河内衆・和泉衆・根来衆の一部・佐野衆を率いていることから、このエリアが頼隆の手の及ぶ範囲だったと考えられます。
やはり信長から、相変わらずの好評価を得ていたのですね。
岸和田城(岸和田市)を拠点にし始めたと考えられるのもこの頃。
他に和泉半国を領していたとされる織田信張も同じ城を使っていた時期があり、詳細は不明です。
四国方面軍に名を連ねたが
その後、天正十年(1582年)には甲州征伐へと続き、結果として頼隆が腰を落ち着けている時期が少なくなったのでしょうか。
甲州征伐では、先発した織田信忠ではなく、後から現地へ向かった織田信長に従っています。
しかし、信忠の電光石火の采配で武田勝頼・信勝親子が自害したため、頼隆を含むほとんどの武将はあまり武功を上げていません。
これは致し方ないところですね。
堅城だろう――とされていた仁科盛信の守る高遠城が、割とアッサリ落城させられた影響もあったかもしれません。
-

武田勝頼の生涯|信玄を父に持つ悲運の後継者 侮れないその事績とは?
続きを見る
それから二ヶ月後には、四国攻略の総大将として織田信孝が指名され、頼隆は丹羽長秀・津田信澄とともに彼を補佐して渡海する予定でした。
が!
そんなタイミングで起きたのが……。
【本能寺の変】です。
-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは
続きを見る
信長は、明智光秀の大軍に襲われ、頼隆も、四国へ行くに行けません。
光秀の娘婿であることから事件への関与を疑われた津田信澄(織田信勝の息子で信長にとっては甥っ子)は、信孝と長秀によって殺害されてしまいました。
-

津田信澄の生涯|信長の甥で光秀の婿・本能寺の変後に迎えた悲劇的な最期とは?
続きを見る
当日、頼隆は岸和田にいたため、信澄殺害には関与していないと考えられています。
三層の天守を持った敦賀城
毛利と和睦し、【中国大返し】を果たした豊臣秀吉。
程なくして明智光秀と対峙した【山崎の戦い】では、主筋の織田信孝が豊臣秀吉方につき、頼隆もこちら側に転居したという話もあります。
-

明智光秀の生涯|ドラマのような生涯を駆け抜けたのか?謎多き一生を振り返る
続きを見る
しかしその後、信孝が勝家と同調して秀吉と対立し始めると、頼隆も秀吉サイドに加わりました。
迎えた一戦が天正十一年(1583年)【賤ヶ岳の戦い】です。
織田家内における、この天下分け目の戦いで勝利したのは、ご存知、秀吉。
-

賤ヶ岳の戦い|秀吉と勝家が正面から激突!勝敗を左右したのは利家の裏切り?
続きを見る
勝ち馬に乗れた蜂屋頼隆は、和泉から敦賀へ移封されました。
石高の上ではおよそ1/3という大減封ですが、敦賀は陸路・海路ともに【日本海―京都】を結ぶ重要な交易ルートとなるばかりでなく、軍事拠点としても大きな価値を持つため、単純な降格とはいい難い。
むしろ栄転と捉えることもできます。
特に貨幣経済という面から見ると、物流の基本である港を押さえておくことは非常に大きな意味を持ちました。
そう考えると頼隆は、信長に続き、秀吉からも信用されていたことが見て取れます。
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
そんな富を利用してなのか。
頼隆が建てた敦賀城は、三層の天守を持っておりました。

敦賀城中門(現・来迎寺表門)/photo by Satoshin wikipediaより引用
残念ながら、元和二年(1616年)【一国一城令】の際、同城は破却されてしまったため、当時の天守は残っていません。
また、頼隆の死後に入った大谷吉継によって、敦賀城はかなり改造され、頼隆が建てた頃の遺構を見ることは難しいと思われます。
-

一国一城令が江戸時代に出された当然の理由~実際は一国に一城ではなかった?
続きを見る
秀吉のもとでも堅実に働くが
その後は小勢ながらも秀吉に従って各地で連戦する蜂屋頼隆――。
◆天正十二年(1584年)小牧・長久手の戦い
-

秀吉vs家康の総力戦となった「小牧・長久手の戦い」複雑な戦況をスッキリ解説
続きを見る
◆天正十三年(1585年)富山の役
-

佐々成政の生涯|信長の側近から大名へ 最期は秀吉に敗れた反骨の戦国武将
続きを見る
◆天正十五年(1587年)九州の役
-

戦国大名・島津義久の生涯~薩摩から九州制覇を目前にして秀吉に敗れた無念
続きを見る
といった、天下統一までの戦に参加していました。
秀吉も、その結果に上機嫌となったのでしょう。新・天下人の”羽柴”や”豊臣”の名乗りを許すなどで、評価を示しています。
亡くなったのは天正十七年(1589年)9月25日のことです。
生年不詳のため、享年も不明。
そして、これをもって蜂屋家は断絶となりました。
頼隆には幼い男子と女子が一人ずついたそうですが、二人とも何らかの障害があって歩くことができず、そのため家督を継ぐことが許されなかったのでは……といわれています。
また、頼隆の死後、敦賀に入った大谷吉継に、蜂屋姓の人物が数名仕えています。
彼らがもし頼隆の親族であれば、傍流や遠縁として血筋が残ったかもしれません。
信長の家臣の中では、不思議なくらい逸話が残っていない人なので、今後、何かのきっかけで人物像が浮き彫りになるかもしれませんね。
あわせて読みたい関連記事
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

京都上洛の信長に向け義龍が放った刺客|信長公記31話
続きを見る
-

金森長近の生涯|信長親衛隊“赤母衣衆”から大名へ 波乱万丈の85年を駆け抜け
続きを見る
-

佐々成政の生涯|信長の側近から大名へ 最期は秀吉に敗れた反骨の戦国武将
続きを見る
-

中川重政の生涯|秀吉や光秀に並ぶ織田一門の武将はなぜ歴史から姿を消したのか
続きを見る
【参考】
谷口克広『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』(→amazon)
太田牛一・中川 太古『現代語訳 信長公記 (新人物文庫)』(→amazon)
蜂屋頼隆/wikipedia