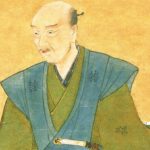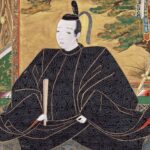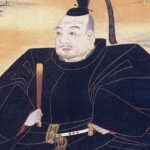こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【関ヶ原の戦い】
をクリックお願いします。
関ヶ原の決着は第二の裏切りから
家康としても余裕などなかったことでしょう。
何より戦況が膠着するのを恐れていたはず。
確かにこの時点では「秀頼や朝廷の後任を受けて会津征伐に向かった家康」を「公的な許可もなく私情で討とうとしている三成」という構図ではあります。
建前的には、家康のほうが圧倒的に有利かもしれません。
しかし、戦に負けてしまえば、そんなことは関係なくなる。
東軍が敗れれば、人柱同然になった鳥居元忠らの奮闘も、本能寺の変から18年も忍耐を重ねてきた家康の艱難辛苦もすべて水の泡。
手段など選んではいられません。
と、そこで小早川隊がついに動きます。
家康が鉄砲を撃って小早川秀秋の裏切りを促したというエピソードについては、現在、疑問視されています。

小早川秀秋/wikipediaより引用
裏切ったタイミングも定かではありませんが、ともかく小早川隊が松尾山を一気に下って西軍の大谷吉継へ攻めかかったのは事実。
小早川隊の動きを不審に感じていた吉継も、その動きに備えていたため、当初は持ちこたえるかに見えました。
しかし、思わぬことが起きます。
周辺に布陣していた脇坂安治・朽木元綱・小川祐忠・赤座直保までもが東軍に寝返り、壊滅へ追い込まれます。
吉継は病気で崩れてしまっていた顔を晒すまいと後退し、戦線から少し離れた場所で自害した後、家臣に首を埋めさせた……とされています。
-

大谷吉継の生涯|家康にも信頼された三成の盟友は関ヶ原に散る
続きを見る
続いて小西隊や宇喜多隊も崩れ、石田隊も防ぎきれず壊滅。
三成は伊吹山へ逃れ、関ヶ原の戦いは東軍の勝利となりました。
島津の退き口
敗戦が確定した西軍で、思いもよらぬ活躍を全国に披露したのが島津義弘隊でしょう。
島津隊は、あろうことか敵陣である東軍の真っ只中を突っ切って、戦線離脱を図ったのです。
【島津の退き口】として今なお戦国ファンにはお馴染みですね。
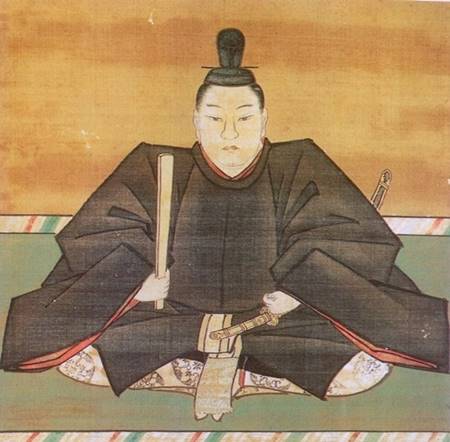
島津義弘/wikipediaより引用
実は島津隊、関ヶ原の本戦では、ほとんど戦闘をしていませんでした。
その理由は諸説あり、講談などによって脚色されたものも多いので判然としませんが……三成ら西軍の中心人物が、”鬼島津”とまで呼ばれた義弘を活かしきれなかったのは悲しい事実でしょう。
皮肉にも、この一件で島津の名はさらに高まります。
「捨て奸(がまり)」という壮絶な戦術を用いて、関ヶ原からの撤退を成功させてしまうのです。
捨て奸とは
・少数の部隊に鉄砲を持たせて、追撃してくる敵を足止めし
・その部隊は全滅するまで踏みとどまって戦い
・繰り返す
という凄まじいものでした。
要は、死を覚悟した味方に時間を稼いでもらい、その間に脱出するという戦法ですね。
数千人いた島津隊のうち、生きて戦線を離脱したのは、義弘を含むたった数十名。
犠牲になった者の中には、義弘の甥・島津豊久などもいました。
討手となった東軍もタダでは済みません。
兵卒はもちろんのこと、井伊直政は、この追撃戦で負った傷がもととなって翌々年に亡くなったとされています。
-

戦国時代の火縄銃で撃たれたらどんな死を迎える?ガス壊疽も鉛中毒も怖すぎて
続きを見る
三成の本拠地・佐和山城攻めがエグい
西軍の敗戦により、小西行長や安国寺恵瓊なども戦線から逃亡。
家康は、三成はじめ、西軍諸将の生き残りを探し出すよう厳命します。
と、その一環で東軍は9月17日、三成の本拠である佐和山城を攻め落としました。
このとき小早川秀秋などの寝返り組を先鋒に立たせて、三成の親族を攻撃させたのですから、仕方ないこととはいえ家康もやることがエグい。
三成の父・石田正継、兄・石田正澄は逃げ延びた後、自刃したといわれています。
-

佐和山城の戦い|関ヶ原直後の三成居城で起きた「女郎墜の悲劇」とは?
続きを見る
その後、家康は大坂城にいた毛利輝元を退去させ、秀頼に事の次第を報告。
戦闘でも政治的にも、家康が勝利を収めたのでした。
戦後処理
慶長5年(1600年)9月21日、逃亡していた石田三成が捕縛されました。
前後して小西行長・安国寺恵瓊も捕らえられ、同年10月1日、京都・六条河原で三人とも処刑されています。

左から小西行長・安国寺恵瓊・石田三成/wikipediaより引用
他に、宇喜多家や毛利家、そして遠方で西軍の立場だった上杉家・佐竹家などに対しても大減封を行いました。
西軍サイドから召し上げた領地は、そのまま徳川家臣や東軍大名たちへ恩賞として分配しています。
ただし、恩賞を得られた人々もただ単に加増されたわけではなく、転封を強いられた者も多くいました。
わかりやすいところでいうと、細川忠興(細川藤孝の嫡男)が丹後12万石から豊前中津・約33万石になっています。
栄転とも取れますが、これは家康が外様大名を警戒していたからのこと。
武家の人々は、同じ土地に長くいればいるほど団結力は増すものです。謀反を起こされるリスクも高まります。
むろん単に引っ越しさせるわけにもいきませんので、加増と同時に行い、バランスを取ったのでしょう。
家が大きくなれば新たな家臣を召し抱える必要が出てきますし、それによる雑務やトラブル処理に時間がかかれば、家中統制に足を取られます。
その間は江戸や徳川家は安泰になる可能性が高いわけです。
豊臣家に近い者たちも、一枚岩になるどころではない。
このあたりは家康が鎌倉~室町あたりの歴史から学び、想定しうるトラブルをできるだけ回避しようとした故の処置かと思われます。
家康もこの時点で還暦が見えてきた年齢ですから、自分が死んだ直後に徳川政権が最も揺らぐであろうことを見越していたはずですしね。
政治的にも戦略的にも、関が原の戦いは家康のこれまでの経験と学習が遺憾なく発揮された戦でした。
家康の能力や性格が最も出ていると言っても過言ではないでしょう。
戦後の各武将 石高はどう推移した?
関ヶ原の戦いで石高はどう推移したか?
東軍と西軍における主な武将たちの推移をまとめました。
小数点以下の数値は省略して表記しております。
【東軍】
福島正則:清須24万石→安芸49万石
加藤清正:肥後熊本25万石→肥後熊本52万石
小早川秀秋:筑前名島35万石→備前岡山51万石
黒田長政:豊前中津18万石→筑前名島52万石
細川忠興:丹後宮津18万石→豊前小倉40万石
京極高次:近江大津6万石→若狭小浜9万2千石
前田利長:加賀金沢84万石→加賀金沢120万石
田中吉政:三河岡崎10万石→筑後柳河32万石
堀尾忠氏:遠江浜松12万石→出雲松江24万石
真田信之:上野沼田3万石→信濃上田10万石
浅野幸長:甲斐甲府23万石→紀伊和歌山38万石
池田輝政:三河吉田15万石→播磨姫路52万石
稲葉道通:伊勢岩手3万石→伊勢田丸5万石
伊達政宗:陸奥岩出山58万石→陸奥岩出山60万石
最上義光:出羽山形24万石→出羽山形57万石
藤堂高虎:伊予板島8万石→伊予今治20万石
中村忠一(中村一氏息子):駿河府中15万石→伯耆米子18万石
富田信高:伊勢安濃津5万石→伊勢安濃津7万石
【注目枠※小早川秀秋に続いて西軍を裏切った者たち】
脇坂安治:淡路洲本3万石→安堵(開戦前から家康に通知)
赤座直保:越前今庄1万石→改易
小川祐忠:伊予今治7万石→改易
朽木元綱:近江朽木谷2万石→1万石
【西軍】
石田三成:近江佐和山19万石→改易
大谷吉継:越前敦賀5万石→改易
宇喜多秀家:備前岡山57万石→改易
小西行長:肥後宇土20万石→改易
長束正家:近江水口5万石→改易
安国寺恵瓊:伊予6万石→改易
長宗我部盛親:土佐浦戸22万石→改易
毛利輝元:安芸広島120万石→長門萩30万石
上杉景勝:陸奥会津120万石→出羽米沢30万石
佐竹義宣:常陸水戸55万石→21万石
立花宗茂:筑後柳河13万石→改易後に陸奥棚倉で大名復帰→さらに柳川11万石へ加増
丹羽長重(丹羽長秀の息子):加賀小松13万石→改易後に常陸古渡で大名復帰→さらに陸奥白河11万石へ加増
小早川秀包:筑後久留米13万石→改易
糟屋武則:播磨加古川1万石→改易
青木一矩:越前北之庄21万石→改易
蘆名義広:常陸江戸崎5万石→改易
島津忠恒(家久):薩摩鹿児島61万石→薩摩鹿児島61万石
平塚為広:美濃垂井1万石→改易
追記(2025年9月14日)
慶長5年9月15日(1600年10月21日)は関ヶ原の戦いが勃発した日――ということで関連画像を本文中に6枚追加しました。
また、戦後の石高推移についても各武将毎にまとめました。
・2025年9月14日:合戦が勃発した日に合わせて関連画像の追加ならびに、戦後の各武将における石高推移もまとめました。
あわせて読みたい関連記事
-

石田三成の生涯|秀吉と豊臣政権を支えた五奉行の頭脳 その再評価とは?
続きを見る
-

平塚為広の奮戦|関ヶ原で「第二の裏切り者」に対峙した武将の最期に涙
続きを見る
-

小早川秀秋の生涯|関ヶ原の裏切り者と呼ばれた男は秀吉正室ねねの甥だった
続きを見る
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
-

井伊直政の生涯|武田の赤備えを継いだ井伊家の跡取り 四天王までの過酷な道のり
続きを見る
-

島左近の生涯|関ヶ原に散った勇将は「三成にすぎたるもの」だったか?
続きを見る
参考文献
- 笠谷和比古『関ヶ原合戦と大坂の陣』(戦争の日本史17, 吉川弘文館, 2016年, ISBN: 978-4642066365)
出版社: 吉川弘文館 |
Amazon: 商品ページ - 戦国合戦史研究会(編)『戦国合戦大事典 岐阜県・滋賀県・福井県』(新人物往来社, 1989年, ISBN: 978-4404016429)
出版社: 国立国会図書館 書誌データ |
Amazon: 商品ページ - 本郷和人『壬申の乱と関ヶ原の戦い――なぜ同じ場所で戦われたのか』(文春新書1073, 文藝春秋, 2016年, ISBN: 978-4166610731)
版元ドットコム: 文藝春秋 |
Amazon: 商品ページ