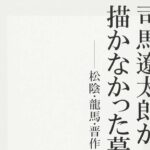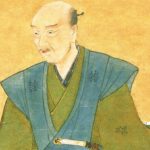こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【阿部正弘】
をクリックお願いします。
凄まじいストレスから急死?
幕府の重鎮には、様々な人が居ます。
徳川斉昭のような筋金入りの攘夷派もいれば、堀田正睦や井伊直弼のような開国派もいる。
反対派の意見もよく聞く、八方美人とも評された正弘は、まさしく板挟みに苦しんだことでしょう。
そして、そんな阿部が抜けるということは、緩衝材がいなくなるということ。
未曾有の国難を前にして、幕府は、こじれた派閥争いで揉めるという最悪の状況につながっていくのです。
ストレスが命を縮めたのか。
安政4年(1857年)、阿部は急死しました。
そしてその存在感は、死後に、より一層ハッキリします。
井伊・堀田と、斉昭の対立が激化し、次期将軍を誰にするかという将軍継嗣問題が爆発します。
これは徳川斉昭が、こう言い出したことが発端でして。
「こんな国難の時代には、強い将軍が必要である!賢い我が子である一橋慶喜を将軍に擁立すべきだ!」
条約締結書をアメリカで締結する準備で手一杯の時に、いったい何を考えているのでしょうか。おまけにこの事件の取り調べの際、長州藩の吉田松陰が老中・間部詮勝暗殺計画を唐突に自白しだしました。
井伊直弼は大鉈を振います。これが悪名高い【安政の大獄】です。
徳川斉昭の処分に怒った水戸藩士たちは、井伊直弼を【桜田門外の変】によって討ち果たします。日本は、テロルの時代へ突入してゆくのでした。

『桜田門外の変』を描いた月岡芳年の作品/wikipediaより引用
もし、バランスを取ることに長けた阿部が存命であったら?
歴史にIFは禁物ながら、日本がまるで別の国になっていた可能性も否めないでしょう。
幕閣は「攘夷は不可能」だと悟っていた
幕末の立場が語られるとき、
◆幕府……頑迷で開国に反対していた
◆倒幕派(尊皇攘夷)……開明的で新たな国作りをめざしていた
こんな単純図式で語られがちです。
これはおそらく、阿部の後任である井伊直弼が【安政の大獄】を引き起こしたことも影響しているでしょう。

井伊直弼/wikipediaより引用
しかし実際はまるで当てはまりません。
むしろ阿部、井伊、堀田らの上層部は、
「攘夷なんて絶対に無理!」
と悟り、開国しながら落としどころをつける道を探っていたのです。
「不意打ちして白刃一閃! 穢らわしい夷狄を斬る」
そんな過激な攘夷思想を抱え、むしろ遅れていたのは、倒幕派なわけです。
まぁ、これは孝明天皇が外国人を毛嫌いしていたため、天皇の意見を尊重する「尊皇」と攘夷がセットになるのも仕方なかったのですが。

孝明天皇(1902年 小山正太郎筆)/wikipediaより引用
攘夷派たちはテロ行為のような攘夷を繰り返し、諸外国から反撃されてようやく、「攘夷は無理」という結論に至ったわけです。
過激攘夷派がトライ&エラーを繰り返して悟った境地に、阿部は知識だけで達していたわけで、むしろ先進的であったと言えるでしょう。
島津斉彬とは懇意で意見が一致
もちろん倒幕派の藩でも早くから気づいていた人物もいます。
薩摩藩主・島津斉彬です。

島津斉彬/wikipediaより引用
開国派で、武力による攘夷の限界を知り、内戦の危険を察知していた斉彬。
彼は阿部と意見が一致していました。そのせいか二人は懇意にしていました。
老中とも仲がよく、母は島津家の正室――という斉彬ですから、もはや藩主相続は確定的でしたのに、「なぜ揉めたのか?」と嘆かずにはいられないのが【お由羅騒動】です。
この御家騒動にも、阿部は登場。
斉彬を引き立て、藩主就任に力を貸していました。阿部は斉彬の父である島津斉興へ引退勧告のとして“茶器”を贈ったのです。
「引退して茶でも啜っていなさい」
そんな風雅な引退勧告ですね。
安政の大獄を引き起こすことになる将軍継嗣問題でも、阿部は斉彬と立場を同じとする「一橋派」でした。
この問題がこじれたのは、一橋派が擁立をはかった慶喜の父・徳川斉昭に問題がありました。
イケイケの過激な攘夷論、日頃の言動に問題があり、大奥はじめ敵を作りすぎていたのです。
このあたり、阿部がうまくまとめて、揉めずに一致団結。攘夷派をなだめつつ幕政を舵取りしていたら……。
と、何度も想像してしまうほど、魅力のある人物。
それが阿部正弘なのです。
ただし、これも一橋派を肯定できればの話。それこそ冒頭でも指摘した通り、小栗忠順からすれば眉間に皺が寄りそうな話です。
一橋派が将軍にしようとした人物は、慶喜です。
慶喜はスタンドプレー傾向が強い人物です。
一橋派が復権し、合議政治を目指した【参預会議】は慶喜の暴走により早々に崩壊。
江戸の幕臣に計ることすらなく、突如【大政奉還】をしてしまいます。
それでも小栗忠順は、北上する西軍を迎撃する策がありました。それも怯えた慶喜は却下してしまいます。
小栗は維新の混乱の中、冤罪で斬首されてしまいます。
しかし生き延びた幕臣は、苦い回想をしています。幕府崩壊の契機となったのは、徳川斉昭と慶喜父子であったのだと。
そもそも斉昭を幕政に引き込んだのは、阿部正弘ではなかったか?
その功罪は問われるべきかもしれません。
幕臣であった福地桜痴は『幕府衰亡論』にて、阿部正弘の「言路洞開」が幕府衰亡の一因であるとしています。外交姿勢は幕閣でのみ決める慣例であったにもかかわらず、これにより破られてしまい、朝廷や大名が口出しできるようにしてしまったのだと。
前述した歌川国芳が皮肉ったように、目の前のことは見えていても遠くは見通せない――そんな悲しい近眼も、阿部正弘の特性なのかもしれません。
あわせて読みたい関連記事
-

『司馬遼太郎が描かなかった幕末』が面白いからこそ湧いてくる複雑な思い
続きを見る
-

石田三成の生涯|秀吉と豊臣政権を支えた五奉行の頭脳 その再評価とは?
続きを見る
-

なぜ水野忠邦は「天保の改革」で失敗したのか?質素倹約のゴリ押しで社会は混乱
続きを見る
-

阿部正次の生涯|家康の天下を陰で支え徳川の名門・阿部家の礎を築く
続きを見る
【参考文献】
国史大辞典
半藤一利『幕末史』(→amazon)
泉秀樹『幕末維新なるほど人物事典』(→amazon)
岩下哲典『予告されていたペリー来航と幕末情報戦争』(→amazon)