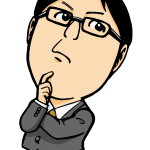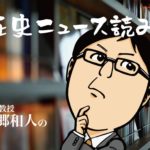日本中世史の本郷和人・東大史料編纂所教授が歴史ニュースをぶった切る「歴史ニュースキュレーション」。
今週は意外や意外、海の中に歴史の夢とロマンがある!?
海の中に夢とロマンと現実を 元寇の竜骨巨大船も発見!
◆『水中考古学』井上たかひこさん(本よみうり堂、著者来店)(読売新聞)
ワインボトルのネック、そして古い真ちゅう製の船クギを宝物のように取り出した。「触っても大丈夫ですよ」。クギを手にすると、ずしりと重い。戊辰戦争時、千葉・勝浦沖に沈んだ米国製蒸気外輪船ハーマン号から引き揚げた遺物だ。他の人にはがらくたでも、著者には夢のかけらなのだ。
子供の頃、小説『宝島』に憧れた。大学卒業後、海とは縁がない仕事に就くが、夢を捨てられず、1987年、一念発起して水中考古学の父ジョージ・バス博士が教える名門テキサスA&M大学に飛び込んだ。
本郷「水中考古学かあ。夢とロマンだなあ」
姫「夢とロマン、はある種の逃げね。そんな口当たりのいい言葉じゃなくて、それを現状の歴史学にどう役立てるかを考えないと」
本郷「厳しいお言葉、ありがとうございます! でも、まあ、その通りだね。せっかく新しい分野に挑戦して下さる方がいらっしゃるんだから、ぼくらもガンバらないとね」
姫「元寇の時のモンゴルの船ですってよ。2011年に発見されたものでしょ?」
本郷「興味あるなあ。竜骨(船の先端から船尾までを貫く材木)のある巨大な船らしいよね。日本の船はたとえば遣唐使船などもそうだけれど、竜骨を持たない構造なんだ。それから、有名な「てつはう」(鉄砲ではなく火薬を詰めて投げる武器・元軍が使用)も見つかっているんだよね」
姫「鎌倉時代の船というと、何といっても新安の沈没船が有名よね」
本郷「うん。韓国の全羅南道、新安の沖合で沈没船が見つかり、1976年から調査が行われて、中国南宋・元時代の青磁,白磁など1万8,000点以上、金属製品5,000点以上、20t以上の銅銭など、膨大な交易品が引き揚げられたんだ。この船は中国大陸の寧波を出発し、日本の博多を目指していたらしい」
姫「水中考古学で海の様子が分かってくると、ますます【東アジアの中で日本を考えよう】という広い視点が開けてくるわね」
スーパー敏腕プロデューサー重源が東大寺の再建を
◆想定外の「拡大路線」- 東大寺東塔基壇(奈良新聞)
奈良市雑司町の東大寺などの調査で、創建時よりも基壇が一回り大きかったことが分かった鎌倉再建期の同寺東塔。
興福寺中金堂(同市登大路町)をはじめ、奈良の古代寺院は規模や構造を踏襲して再建されることが多く、専門家からも「想定外」の成果に驚きの声があがる。
その背景には、大勧進を務めた高僧・重源の同寺復興に向けた熱い思いが、うかがえる。
本郷「おお、重源(ちょうげん)かあ」
姫「ん? その人は? どこかで聞いたことがあるような、ないような」
本郷「高校教科書にチラッと出てくるかな。源平の戦いの時、平家軍が東大寺を焼いちゃったじゃない。それで、聖武天皇が造らせた大仏様も焼け落ちたわけだね。後白河上皇はそれまで無名の存在だった俊乗房重源を【大勧進職】に任命し、東大寺再建の任に当たらせたんだ」
姫「へー。聖武天皇の時の東大寺造営は国家事業でしょ。莫大なお金が必要だったんじゃないの」
本郷「その通り。重源はさしずめスーパー敏腕プロデューサーというところかな。日本列島のすみずみから資金を調達し、資材を集め、技術者を招き、朝廷や源頼朝の援助を得ながら東大寺の再建を成し遂げたんだ」
姫「いまある東大寺の大仏様は3代目なのよね」
本郷「そう。重源が宋の人、陳和卿(ちんなけい)に造らせた2代目の大仏様は、戦国時代に松永久秀の焼き討ちにあって首が落ちた。ただ、胴体部分は鎌倉時代のものがのこってるんだ」
姫「ああ、それじゃあ、運慶と快慶が彫った仁王像や、その像が安置されている南大門は重源さんの頃のものなのね」
本郷「そのとおり。仁王像も南大門も、鎌倉時代を代表する彫刻であり、建築物なんだね。仏師も大工も、みんなが懸命に働いたんだろう。そうした熱い動きの中で、前より大きな東塔が再建されたんだと思うよ」
姫「東塔というからには、西塔もあったの? それから5重塔なの?」
本郷「おっ、いい質問。聖武天皇の東大寺には、東と西、二つの7重塔があった。西塔は平安時代に焼けて、それ以後再建されていない。東塔は平家の焼き討ちで失われたけれど、いったん再建され、室町時代に雷によって焼けた。そういう事情を踏まえて、現在、東大寺さんは東塔の再建を目指しているんだよ」
姫「じゃあ、巨大な塔がよみがえるかもしれないわね」
本郷「日本で一番高い5重塔は、どこのお寺のでしょう?」
姫「京都の東寺でしょう? 高さまでは知らないけれど」
本郷「その通り。高さは55メートル。これに対して東大寺の7重塔は、研究者によって説が異なるんだけど、90~100メートルとも言われる。大きなことは間違いないわけだね」
姫「ふーん。でもあなた、鎌倉時代のことになると、いきいきしてくるわね」
本郷「えへへ」
伊達氏や上杉氏が関わる舘山城の発掘調査が更に進む
◆堀跡、上杉氏時代埋設か 米沢・舘山城跡調査(河北新報)
戦国時代から近世にかけ伊達氏や上杉氏が関わった米沢市の舘山城跡の発掘調査を続ける米沢市教委は、現地説明会を開いた。
本丸跡で見つかっていた堀跡は山の斜面までつながり、上杉氏時代に埋められたとの見方を示した。斜面の土塁から中世の土鍋片1点、堀跡から16世紀代の磁器製皿片1点も見つかった。
姫「この前のお話↓
-

政宗と景勝の間で揺れる舘山城と米沢城 東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
の続きね。やっぱり、舘山城は上杉時代まで使われていたのね」
本郷「そういうことになるね。名島城と福岡城みたいなものかな」
姫「商都・博多を防衛する城として、まず立花山城があった。そこの城主が立花道雪であり、道雪の娘の女城主・立花誾千代であり、立花宗茂。でも豊臣政権下で立花宗茂は筑後の柳川に移り、小早川隆景・秀秋が筑前を領する。小早川父子は立花山城に代わり、名島城を築いたのよね。それから関ヶ原のあと、黒田長政が博多に入り、名島城を廃して、福岡城を造った。そんな感じよね、たしか」
本郷「うん、その通りだね。関ヶ原のあとは、もう戦いがないわけで、城は政庁の役割を強く求められるようになる。そうすると、新しい城作りが必要になるのかなあ」
姫「そういえば、米沢城も、福岡城も、天守閣がないのよね」
本郷「ああ、そういえばそうだね。幕府に遠慮して、作らなかったのかもしれないね」
姫「但し、福岡城の方は、天守閣はあった、という説もあるようね。天守閣再建運動もあるみたい」
本郷「そうかあ。地元の判断になるんだろうねえ。ともかく、舘山城は史跡認定を求めてるそうだから、認められるといいねえ」
あわせて読みたい関連記事
-

「難波津(なにわづ)の歌」と「かたみの歌」東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
-

ビジネスにも歴史が必要な時代が来た? 東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
-

伝説は真実だった 高尾山古墳は保存される?東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
-

本当は怖い「裸男祭り」神様への生け贄?東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
-

楽しさと受験の間でジレンマ生じる歴史の教科書 東大教授・本郷和人の歴史ニュース読み
続きを見る
-

鎌倉幕府は何年に成立したのか? 本郷和人東大教授の「歴史キュレーション」
続きを見る