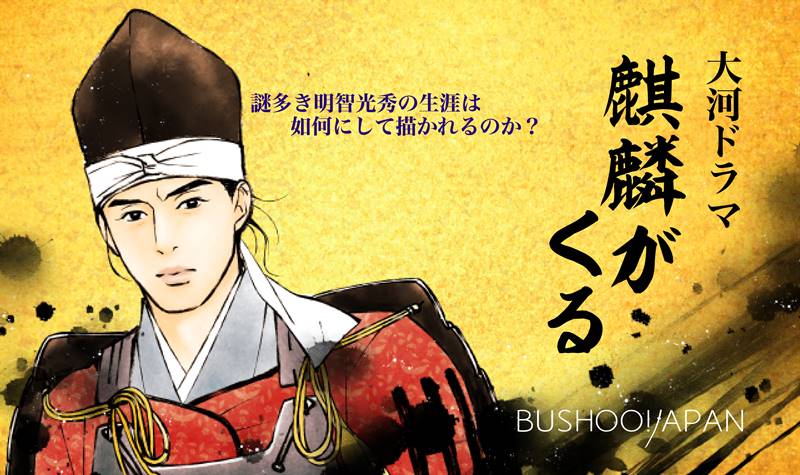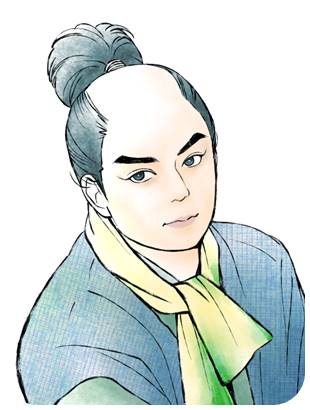こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【麒麟がくる第31回感想あらすじ】
をクリックお願いします。
奇声を発しながら進退を決める信長
光秀と信長の一件を知らない諸将は、軍議を続けています。
川を使うと雨季が迫っているといったことを話している。
やはり久秀と家康は慎重派。若い英雄を描くことは本当に大切で、家康は幼少期から慎重なところが完成しているとわかります。歳をとり力をつけたから、タヌキだのなんだの言われたとわかります。
と、ここで妙な何かが聞こえてきます。
「うう〜っ、ううっ……!!!!」
信長が奇声を発し、すごい顔をして、床を叩いている。
信長はこう言う発散をしないといけないのですね。
ただ、それをやられる周囲の気持ちは……信長が理想の上司どころか“周囲にいたら困る人”になっている――これが新解釈の信長でしょう。
勝家が誰かに見に行かせようとし、光秀が応じようとすると、信長がキリッとした顔で戻ってきました。
がんばって抑え込んだな……動揺を見せないように工夫しました。防音まで踏まえていればなおよかったのでしょうが。
信長は冷静な顔でこう宣言します。
「近江より、急ぎの知らせが参った。浅井長政が兵をあげた。狙いはこの信長。朝倉と示しあわせ、我らを挟み撃ちにするつもりであろう」
そしてこう決めます。退き口は明智に任せると。
支度を整える中、光秀と家康は目顔でうなずきあうのでした。
やはり本作の光秀と家康には、何か繋がりがあります。光秀の願いは叶えられないけれども、家康が継承して徳川の平和を築くのであれば話としてはおさまりがよい。
その流れですと、海を越えた先からも麒麟を駆逐した秀吉が“宿敵”とされるのも必然と言えます。
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
藤吉郎と妹と芋
このあと、光秀の前にその男がやってきます。
藤吉郎は土下座し深々と頭を下げ、自分の秘めた心のうちを明かすのです。
殿を務めたい。
貧乏百姓、百姓とは名ばかり、自前の田畑も持たぬ身。
年の離れた妹がいた。その末妹が病で寝込んでしまった。日々の食い扶持にこと欠く我が家に、薬を求める銭はない。弱っていく妹をただ眺めているだけ。
ある日、隣村に嫁いだ姉が芋をひとつ……粥にでもして食わせてやれと置いて帰った。
そのとき、家にいたのは兄と妹だけ。その芋を、兄は、食べてしまった!
翌日、妹は死んだ。
藤吉郎は自分を責めた。なんという浅ましさかと……このわしに生きる値打ちはあるかと。
さて、この話の真偽は?
私は“真”とします。
・年が離れた妹。家康正室となる朝日姫とは一回り以下であり、“年が離れた”とは思えない。
・身分が低いもの、成人しない妹が死んだとなれば、存在そのものが抹消される。状況的にみて、彼がこの妹の話を語り残したいとも思えない。
・光秀の性質。作劇上、光秀は人の本音を引き出す特性が割り振られている。こういう状況でも、光秀相手にも嘘をつける人物が出てくるとまずい。
・今回は三英傑の本質に迫る回。そういう本質を物語る逸話を“偽”とすると、これまたわかりにくい。
・目が透き通っている。佐々木蔵之介さんは嘘のない演技をしている。
この藤吉郎の話は、なかなか奥深いものもある。
貧しくて薬を買えない苦い経験がある秀吉が、駒の芳仁丸ビジネスをどう思うことか?
そしてこの芋一個を奪うあさましさからは、本作に漂う戦争のにおいがする。
『おとなになれなかった弟たちに…』のような、困窮する身近な誰かからでも食べ物を奪う、そういう悲しさがある。
ひどい時には、もっと恐ろしいこともあった……今期の朝ドラ主人公モデルは、地獄のインパールで牟田口廉也と牛肉を食べていたそうですが、今年の大河はそういうノリから決別しているようです。
◆<朝ドラ「エール」と史実>本当は母の病気で辞退を申し出ていた? それでも古関裕而は3度も戦地へ行った(辻田真佐憲) (→link)
自己嫌悪に苦しむ藤吉郎は、羽虫をつかみます。
この虫には羽がある。しかしこやつは使い方を知らぬ。飛ぶことを知らん。この狭い地べたを這い回って、一生を終える。
虫と己を重ね、信長様に引き立てられたいと語る藤吉郎。今は1,000人を預かっているけれど、家臣の誰もが内心この藤吉郎をひとかどの武将と思っていないのだと。
「わしにも羽はある! わしは飛ばぬ虫で終わりたくない!」
そんな相手を光秀は否定しない。ただ、殿(しんがり)の危険性、役目について釘を刺します。
僅かな手勢で敵を食い止める。本軍を守る。危うくとも味方の助けはない。
「命と引き換えになりますぞ」
「死んで名が残るなら、藤吉郎、本望でござる!」
彼はそう言い切る。
この言葉に嘘はないのでしょう。真っ直ぐな出世欲と野心がきらめくそんな像です。
ただ……彼の危うさも見えてくる。本作は残酷なまでに、破滅の種を見出せるようにしている……。
今は戦を重ねるしかない……!
かくして信長は浅井領を避けつつ退却戦を始めます。
光秀と藤吉郎は本隊の最後に陣取り、朝倉、浅井軍を必死に打ち払う。
金ヶ崎の退き口ながら、本作はそこまで戦闘シーンが多くはありませんでした。
予算なのか? ロケの都合上なのか? そういった側面もありましょうが、心理描写重視なのだとも思います。
三英傑だけではなく、光秀の心の内が左馬助相手に語られます。
わしはいままで、なるべく戦はせぬ。無用な戦はせぬ。そう思ってきた。
しかし、此度の戦ではっきりとわかった。
そんな思いが通るほど、この世は甘くはない。
高い志があったとしても、この現の世を動かす力がなければ、世は変えられぬ。
戦のない世を作るために、今は戦をせねばならぬ時なのだと。今は戦を重ねるしかないのだ。わかるか、左馬助。左馬助、なんとしても、生きて帰るぞ――。
そう誓う光秀です。
麒麟がくる世のために、血を流し、涙を落とし、生きるしかないその苦しみ。漢籍に詳しい光秀らしさも感じるし、東洋の伝統も感じました。
思い出したのは諸葛亮『出師表』です。
あれはむしろものすごくテンションが落ちる。これからやるというのに、しっかりときっちりと、不利な状況を数えて、暗いことばかりを延々と長文で突きつけてくる。
これから戦う時に、なんでそんなことするの? 嫌がらせか!……とも思いたくなりますが、実際名文です。
-

孔明が上奏した名文『出師表』と『後出師表』には何が書かれているのか 全訳掲載
続きを見る
人間には、普遍的なところがあるようで、文化圏での違いもあるのでしょう。
英語圏での出陣を盛り上げる定番は、シェイクスピア『ヘンリー五世』の「聖クリスピンの祭日(Saint Crispin's Day)」です。
これはこの日の武勲が永遠に語り継がれるであろうというテンションが高いもので、藤吉郎の名を残して死ぬ気持ちにはフィットします。
ただ、光秀や諸葛亮の悲壮感とは異なります。
本作の光秀からは、東洋伝統の美しい心の香りがする。
よいものを見せていただいております。
義昭の覚悟とは
悲痛な決意のあと、晴れた空が映り、場面は二条城へ。
摂津晴門が、越前での戦について足利義昭に報告しております。
織田が大敗を喫し、二日二晩、駆け通し、僅か10騎ばかりで妙覚寺に入ったと報告するのです。
義昭もこれには衝撃を受けています。
ただ、喜んでいるわけでもない。と言いたいけれど、実際どうなのか?
負け戦でパワーバランスが変わったと晴門も指摘しています。公方様だの幕府政所だの、聞く耳を持つようになるのではないかと言うわけです。
正月には、五箇条の覚書を突きつけてきた信長。
勝手に御内書を出すな、朝廷を敬え。それが不愉快で分を弁えぬものと晴門は不愉快だったわけです。
この先は信長一人に重きを置くわけにはいかない、越前朝倉にも内々に感状を出すよ促すのです。義昭はそれに対して「よきにはからえ」と言ってしまう。晴門は「承知仕りました」と返す。
一体今回だけで、何人が信長の逆鱗に触れてしまったのか。禍根が残りますな。
義昭はそんな晴門よりも、駒に会いたかったのか。別室で待っていた彼女の前にいそいそと座ります。
越前の戦が終わったと聞かされる駒。信長殿の負けだと。
ここでの駒とのやりとりで、義昭のこともわかります。
義昭は彼なりに抵抗をしています。信長は将軍の決裁がなくとも世の中を回る仕組みを整えようとしている。義昭もそれに判を押したけれども、従うつもりはないのだと。そしてこう言います。
御所の堀や屋根を修繕することも大事。しかし、貧しき者、病の者を救うてやるのが先ではないか。
わしがまことの将軍となったあかつきには、戦をなくす。いつか、必ず!
そのために、諸国の大名がこぞって将軍を支える世でなければならぬ。
「わしは兄上の轍は踏まぬ」
そう誓う義昭は、現実逃避をしておりますし、覚悟も足りない。【情】ばかりで【理】も足りない。
光秀が理想のための流血、戦陣に立つことを苦しみながら選んだのに対し、義昭は甘っちょろいと思えませんか?
※続きは【次のページへ】をclick!