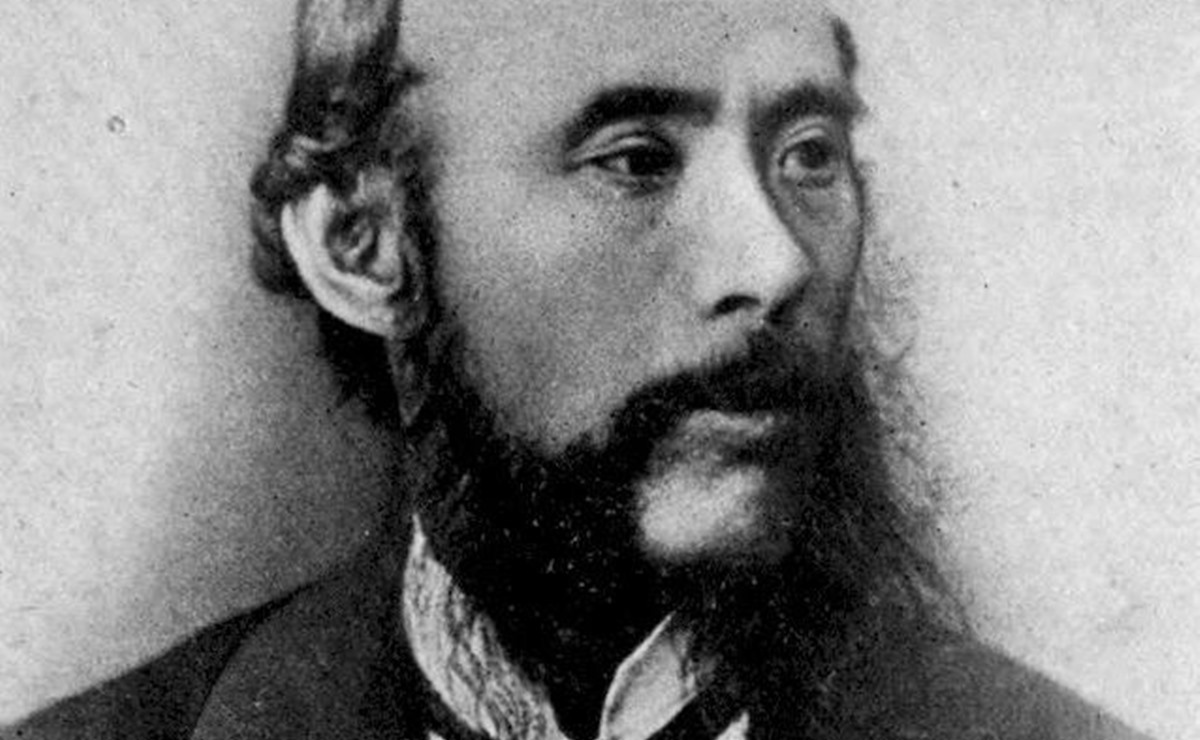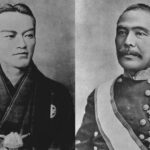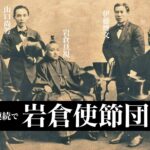こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【大久保利通】
をクリックお願いします。
お好きな項目に飛べる目次
お好きな項目に飛べる目次
見切り発車だった明治政府
明治維新を強行する大久保たち。
彼らはどんな国作りを考えていたのか?
ともあれ明治時代がいったん幕を開ければ次から次へと事を運ばねばならず、まずは「江戸」が「東京」となり首都とされるわけですが、この決定に関しても一悶着ありました。
これも大久保利通の挫折です。
彼は重ねて大阪遷都を建白するも、却下されました。
そうなれば天皇を東に迎えねばならないと焦る大久保。しかし、これもぐずぐずしていて年をまたいでしまいます。
幕臣最後の悪あがきのように軽視されがちな【函館戦争】も、実は問題でした。
蝦夷地に独立国ができるのではないか?
そう期待し、鼻息を荒くするプロイセンはじめとする諸外国もいたのです。
しかも海軍力では幕府が勝っており、新政府は明治2年(1869年)になってから、イギリスの援助を得てようやく内戦を終わらせました。
明治政府は、イギリスという教師に一から国作りを教わっているかのような、いわば幼い生徒でした。
小栗忠順はじめとする幕臣たちはイギリスの介入を警戒していたことは前述した通りです。
幕府が想定していた“悪い状態”で明治政府はスタートを切ったのです。
明治時代は実に冷たい空気の中で始まりました。
江戸っ子たちは徳川時代を恋しがり、「おはぎ(長州)とおいも(薩摩)のせいで無茶苦茶だ」と嘆くばかり。
幕臣たちは政府に仕えることだけはごめんだと、顔を背けてしまう。
大久保利通にとっての悲劇は、地元・薩摩ですら、嫌われてしまっていたことです。
帰郷した際、刺さるような目線の冷たさに、彼は困惑したといいます。
無理もないことでしょう。【戊辰戦争】では薩摩藩からも被害は出ていました。
彼らにしてみれば身内に犠牲者が出て、経済的にも被害を受けたにも関わらず、大久保利通たちは東京で贅沢三昧をしているように映っていたのです。
そしてこの薩摩の抱く敵意は、その後も和らぐどころか、ますます強まってゆきます。
明治2年(1869年)に【版籍奉還】が実施され、明治4年(1871年)の【廃藩置県】では、島津久光が猛然と反発しました。
久光が明治になってから語った言葉として、こんな荒唐無稽なものが伝えられています。
「俺はいつ将軍になるのだ」
聡明な久光がこんな愚かなことを言うわけありませんが、それでも一部の真実はあったように思えるのです。
久光は【参預会議】の構成員です。
あの体制は近代国家の合議制を先駆ける先進的なものであり、幕末の賢侯や明君と称される大名は、合議制政治を進めたいと考えていた人物がいます。
政治的な知識と経験のある幕藩体制での君主たちが意見を出し合い、新たな国を運営する。
そんなビジョンがおぼろげながらあったと思える言動が残されていて、島津久光もそうだとしても、何ら不思議はありません。
大久保利通や西郷隆盛は、久光を一切政治に関わらせず、一方的に決めたことを履行しろと押し付けてきます。自分たちの言うことを聞かない駄々っ子扱いをします。
これに久光が怒らないわけがありません。
忠誠心の面でも問題があります。
不満はあれど、駿河までついていった幕臣たち。
会津松平家を必死で守り抜こうとし、斗南藩で苦労した会津藩士。
殿様への態度はさておき、吉田松陰の神格化はぶれない長州藩士。
こうした人々と比べて薩摩藩士はいったい何なのか?
そう問われた時の言い訳として「久光を貶め、斉彬をことさら持ち上げる」ように見えるのです。
中央集権化で西洋列強と向き合う
明治政府は合議制をしようとは考えていませんでした。
中央集権化をはかることで、不平等条約を撤廃し、西洋列強と並ぶことを目指す。
明治時代といえば「四民平等」と日本史の授業では習います。
大河ドラマでも平等な社会が訪れたかのように扱われる。その結果、『西郷どん』では明治維新とフランス革命を似たようなものとして扱うという、決定的な誤誘導までなされていました。
そうではありません。明治政府は薩長土肥、後に土肥を抜いた薩長に権力を集中させることで、国家を強靭にしようとはかったのです。
政財官三者一体となった汚職は続きます。
権力を傘にきた悪事の隠蔽。
犯罪の増加。
そうした現実に国民は嫌気がさしていました。
◆幕臣および佐幕派地域の困窮
→幕臣は無職となり、困窮に苦しみました。
公共事業の整備、教育や医療施設の拡充も、首都圏および薩長の地元が優先されます。
-

倒幕で放り出された幕臣たちの悲劇~明治維新後はどうやってメシを食っていた?
続きを見る
◆薩摩藩出身者の暴力沙汰
長州は金に汚い。薩摩は暴力的。そんな汚名があります。
現に明治天皇の前で流血沙汰をやらかすような人物もいたのですから、無理もないこと。
中でも最悪の事例が、黒田清隆のドメスティックバイオレンス殺人事件を薩摩閥ぐるみで隠蔽したことがあげられます。
その主導者は大久保利通でした。
-

五代は死の商人で黒田は妻殺し!幕末作品では見られない薩摩コンビ暗黒の一面
続きを見る
◆攘夷とは何だったのか?
西洋列強に追いつけ――維新が済んで突然そんなことを言われても、理解できない人は当然のことながら大勢います。
あれほど外国人の殺傷を重ね、軟弱な幕府にはできない攘夷を断行する!と言っておいて、今度は西洋を真似しろとはどういうことか。
そんな手のひら返しについていけない人がいるのは当然のことと言えました。
-

幕末の外国人は侍にガクブル~銃でも勝てない日本刀がヤバけりゃ切腹も恐ろしや
続きを見る
西洋に国作りを学ぶ
見切り発車だった明治維新。
そんな中、明治4年11月12日(1871年12月23日)から明治6年(1873年)9月13日までという長期間にわたり、岩倉使節団がアメリカとヨーロッパに向けて出発します。
不平等条約改正が目下の政府の課題でした。
その責任は旧幕府のせいとされ、日本史の授業ですらそう習いますが、認識を改めましょう。
岩瀬忠震ら幕臣が締結した際はそこまで不平等でもありません。
攘夷を叫ぶ志士たちが外国人殺傷テロを繰り返した結果、どんどん条件が悪化していったのです。
西洋事情の見聞にせよ、幕府は【万延遣米使節団】はじめ幾度も派遣しています。
このとき一本のネジを手に入れた小栗忠順は混乱の中、冤罪で処刑され、大隈重信はこのように語っています。
「明治の近代化は、ほとんど小栗上野介(忠順)の構想を模倣したに過ぎない」
期間がやけに長く、無駄も多い岩倉使節団は当時から批判されましたが、それでも大久保利通には大きな影響を与えました。
イギリスで経済の重要性を知り、ドイツで国家の統治をビスマルクに学ぶ。
大久保利通は、殖産興業の重要性を痛感したのです。
まずは国を豊かにせねばならない――そう国家のビジョンを携え、帰国しました。
-

実はトラブル続きで非難された岩倉使節団 1年10ヶ月の視察で成果はどんだけ?
続きを見る
こう書くと希望に満ちた話のように思えます。
しかし、海外に渡航し、国内の殖産興業の重要性を痛感した日本人ならば、小栗忠順がとうに達成できています。
アメリカから小栗はネジを持ち帰ります。当時の日本にはない技術です。
このネジをわが国でも作るのだ――そう考えた小栗が先頭に立って作り上げた横須賀造船所から、日露戦争における【日本海海戦】に向けて、戦艦が出立しました。
大久保利通が西洋から学んだことは重要でしょう。
しかし、小栗忠順を殺さずに活躍させていた方が、近代化の早道だったのではないでしょうか。
※続きは【次のページへ】をclick!