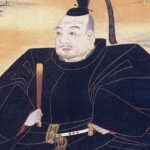こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【貞観政要】
をクリックお願いします。
女性と漢籍教養
日本史においては『貞観政要』愛読者の中に北条政子の名前があることも重要です。
『鎌倉殿の13人』では、政子の御台所修行の一環として、義母であるりく(牧の方)から漢籍を渡される場面がありました。
あの場面に出てきたのは、印刷技術が用いられた宋版の書籍。
筆写せずとも漢籍が手に入れられる時代が到来していました。
とはいえ、政子も忙しいのか、実はそこまで熱心に読み込んでいなかったとされる場面がその後に出てきます。
頼朝の不倫相手である亀と対面する場面で、「書籍を読んでいない!」と喝破されたのです。そのうえで、女にとって憧れの対象となるよう、教養を磨けと叱咤激励されていました。
女性同士が教養を高めることを奨めあっている。
こうした一連の場面から、聡明な女性が称賛の対象であったことが示されています。

絵・小久ヒロ
これが時代が下り、江戸時代ともなると、男女の学問が厳密に分かれてゆきます。
江戸時代には、女子教育に特化した書物が成立。
『女誡(じょかい)』、『女論語』、『内訓』、『女孝経』という「女四書」。
貝原益軒の『女大学』。
女子が学びたいといえば渡されるのはこうした書籍でした。
そもそも女性は積極的に政治に関われなくなっていて、本来の四書五経、ましてや『貞観政要』など読んでも意味がないとされたのです。
そんな江戸時代が終わる前夜――幕末に生きた女性たちは「女に教育は無用」という偏見のために苦闘していました。
大河ドラマにおいても2013年大河『八重の桜』の八重、2021年大河『青天を衝け』の千代はそうした偏見を否定すべく、立ち向かう姿が描かれています。
このように漢籍教養と女性を見ていけば、変化していったジェンダー観も浮かんできます。
2024年『光る君』も注目です。
紫式部は漢籍教養が豊富だったことで知られ、『源氏物語』にもそうした知識なしでは読めない表現が頻出します。
彼女と並び称される清少納言も同様。
主君である定子に「香炉峰の雪はどう見ればよいでしょう」と謎かけをされ、簾を掲げた『枕草子』の話は有名です。
二人の女性が白居易の詩を知っていたからこそ実現した話です。
忘却と曲解の漢籍教養
『鎌倉殿の13人』では坂東武者が十分に身につけていたとはいえない漢籍教養。
それも時代がくだって幕末ともなると、武士のみならず豪農層までもが身につけていました。
2021年大河『青天を衝け』では、主人公である渋沢栄一ら豪農が漢籍を読む場面が登場します。
ただし、彼が熱心に学んだ水戸学はかなり独自の漢籍解釈をしていますので、注意が必要です。
-

水戸学とは一体何なのか?斉昭のパフォーマンスが幕末に投じた思想的影響のヤバさ
続きを見る
しかし、それも明治時代からは変わってゆきます。
日清戦争における勝利で中国蔑視に繋がった影響も大きく、漢籍教養は古く、悪しきものとされるようになりました。
さらには日露戦争の勝利後、日本独自の道徳観念こそが成功の証であるとしてその模索がなされます。
新渡戸稲造の『武士道』はそうしたニーズへの答えでもありました。

新渡戸稲造/国立国会図書館蔵
このような漢籍知識の軽視論は現在でも否定できないでしょう。
「漢文の授業は役に立たないから廃止すべきだ」という意見は定期的に持ち上がります。
しかし、その結果どうなるか?
漢文で書かれた日本史の史料が読解できない。
漢籍に記されている理念がわからないから、混乱してしまう。
たしかに漢籍は中国由来ですが、日本にも深く関わっていて、無視しては日本史そのものを理解できなくなってしまうのです。
こうした状況を踏まえ、もう一度『貞観政要』について考えてみることも大事ではないでしょうか。
『麒麟がくる』の明智光秀が、主君である織田信長に絶望していたのはなぜか?
初めは、唐太宗のように諫言を聞き、才知溢れる主君だと思ったからこそ仕えていたのに、信長は変わってしまっった。
家臣の諫言を聞かなくなった。これでは「貞観の治」にはならない。
光秀はそう悟ったのでしょう。
『鎌倉幕府の13人』では、己の言葉を聞こうとすらしない後白河院に九条兼実が呆れていました。
人の意見をよく聞く北条泰時は『貞観政要』を愛読しています。
だからこそ君主の器が見えてくる。
『貞観政要』は読みやすく、翻訳や解説書も多く出ています。電子書籍もあります。
そして、なんといってもこの一冊で大河ドラマを毎年フォローでき、日本史に幅広く対応しています。
大河ドラマ書籍の定番として『貞観政要』は欠かせない――その認識が広まることを願うばかりです。
あわせて読みたい関連記事
-

人格者として称えられた三代執権・北条泰時の生涯~父の義時とは何が違ったのか
続きを見る
-

徳川家康の生涯|信長と秀吉の下で歩んだ艱難辛苦の75年を史実で振り返る
続きを見る
-

史実の一条天皇はどんな人物だった?彰子や道長とはどんな関係を築いていたのか
続きを見る
-

「時代劇らしいセリフ」とは?大河ドラマで見える文化 教養 言語能力の進化
続きを見る
-

『麒麟がくる』で「来ない」と話題になった――そもそも「麒麟」とは何か問題
続きを見る
【参考文献】
呉兢/石見清裕『貞観政要 全訳注 (講談社学術文庫)』(→amazon)
守屋洋『「貞観政要」のリーダー学 守成は創業より難し』(→amazon)
氣賀澤保規『中国の歴史6 絢爛たる世界帝国 隋唐時代』(→amazon)
他