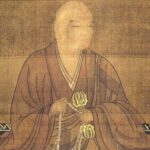こちらは4ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【藤原為光】
をクリックお願いします。
情熱的な貴公子 三男・藤原道信
藤原道信は、斉信の異母弟です。
しかし、その才覚はよく似ていました。
藤原実方・和泉式部・赤染衛門・藤原公任といった当時の有名歌人と多く交流を持ち、拾遺和歌集などに多くの歌が入選しています。
百人一首52番の情熱的な以下の歌が特に有名です。
明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき あさぼらけかな
【意訳】夜が明けても、また暮れればあなたに会えるとはわかっているのだが……わかっていても、別れを告げる夜明けが恨めしいよ
また、花山天皇に入内していた婉子女王(えんしじょおう/つやこじょおう)との恋もよく知られています。
彼女は花山天皇が退位・出家した後、そのもとを離れたため、道信をはじめとした貴族たちに求められていました。
しかし婉子女王は最終的に道信ではなく藤原実資を選んだため、道信は未練を伝える歌を送っています。
嬉しきは いかばかりかは 思ふらん 憂きは身に染む ものにぞありける
【意訳】あなたは恋が実ってさぞ喜んでいることでしょう。しかし恋に破れた私には、憂いが身にしみています
実資は婉子女王より15歳も年上であり、年齢でいえば同世代の道信のほうがふさわしいといえなくもないので、余計に悔しかったのでしょうか。
道信は兼家の養子となって出世していきましたが、正暦五年(994年)に23歳の若さで亡くなりました。
翌年に流行り病で多くの貴族が命を落としているため、道信は一足先にその病気をもらってしまったのかもしれません。
辞世の歌は『千載和歌集』にも入選している、通っていた女性に送った歌です。
口なしの 園にや我が身 入りにけむ 思ふ事をも 言はでやみぬる
【意訳】私はもう、くちなしの花園に入ってしまったようです。あなたを思っていたことを口に出せません
「くちなし=口無し=死者」に通じることから、死を悟ってから力を振り絞って詠んだのでしょう。
形見分けとして相手の女性に山吹色=くちなし色の衣を贈り、この歌を添えたといわれています。
最後の最後まで情熱的な人だったんですね。
何かと巻き込まれる娘たち
平安時代の女性にはよくある話で、為光の娘たちは様々な要人に巻き込まれ、歴史に存在感を残しています。
三女の三の君こと「寝殿の上」と呼ばれていた女性は、藤原伊周(道隆の嫡男)と関係していた人でした。
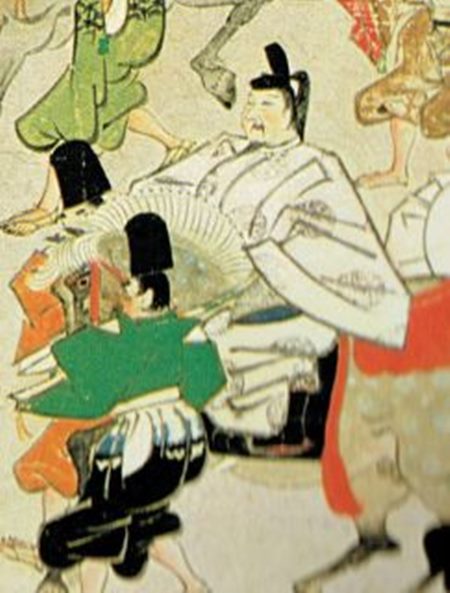
藤原伊周/wikipediaより引用
四女の藤原儼子(たけこ)は花山法皇に寵愛されています。
そのため伊周が
「俺の通っている女のところに別の男が来ている!」
と勘違いして、お忍び姿だった花山法皇に矢を射かけて……という騒動が【長徳の変】という政変に発展、伊周を含めた中関白家が失脚する原因となります。
矢を射かけただけでなく、従者同士でも闘乱して、花山法皇の下男の首を持ち去ったという話もあります。怖すぎるやろ平安京。
しかも儼子は、後に道長と関係を持ち、子を授かるのですが……長和5年(1016年)1月21日に死産し、儼子本人も亡くなったといいます。
出産が命がけの時代であったことを痛感する話ですね。
また、為光の五女・藤原穠子も道長の妾になったとされています。
長和五年(1016年)4月の賀茂祭の折、道長は「穠子が懐妊中」という理由で賀茂詣を取りやめたと日記に書いているのです。
しかし、彼女はこの時点でなんと16ヶ月も懐妊していたとか。
その後も出産した記録がなく、想像妊娠あるいは他の病気だったか、もしくは道長のサボりたい言い訳に利用されたのかもしれません。
流産・早産してしまって記録されなかったという可能性もありますが。
他の可能性としては、賀茂祭の時点で穠子が流産していて、道長がその場に居合わせてしまったため、産穢(さんえ・出産で出血した際の穢れ)に触れたとして遠慮した……というのもありうる話ですね。
穠子は寛仁二年(1018年)10月の時点で道長の娘・妍子(当時皇太后)に仕えていたとされ、その後は禎子内親王に仕えたようなので、道長との関係は長く続いたかもしれません。
超優良物件に住んでいた為光
最後に、為光一家に関する「お屋敷の話」をご紹介しましょう。
藤原行成の日記『権記』の長徳四年(998年)にこんな記事があります。
「為光の娘が経済的に苦しい立場になり、一町ほどもあった大邸宅を米8000石で売った」
買い手は佐伯公行という人で、受領の間にかなり蓄財していたのだとか。
1石=一人が一年間に食べる米の量なので、単純計算で8000人を一年養えるような金額で家を売ったことになります。
2022年の総務省による調査では、現代人の食費は毎月約3万円(外食を除く)。
これまた単純計算して年に36万円とすると、8000人分で28億8000万円です。
現代では某・超有名YouTuberさんの家が20億といわれているので、為光が残した屋敷の価値の高さがうかがえますね。
もっとも、現代では地価や景気の影響を受けたり、有名な建築家やデザイナーが絡んだりすると一気に値段が上がることもあるので、単純な比較はできません。まぁイメージということで。
「元・為光邸」は佐伯公行から藤原詮子(道長の姉で支持者)へ献上され、詮子とその子である一条天皇の里内裏として使われるようになりました。
そのため一条天皇時代にこの屋敷が多く登場します。
例えば長保元年(999年)6月14日に内裏で火事があり、一条天皇と藤原定子が一条院に遷御したことがありました。
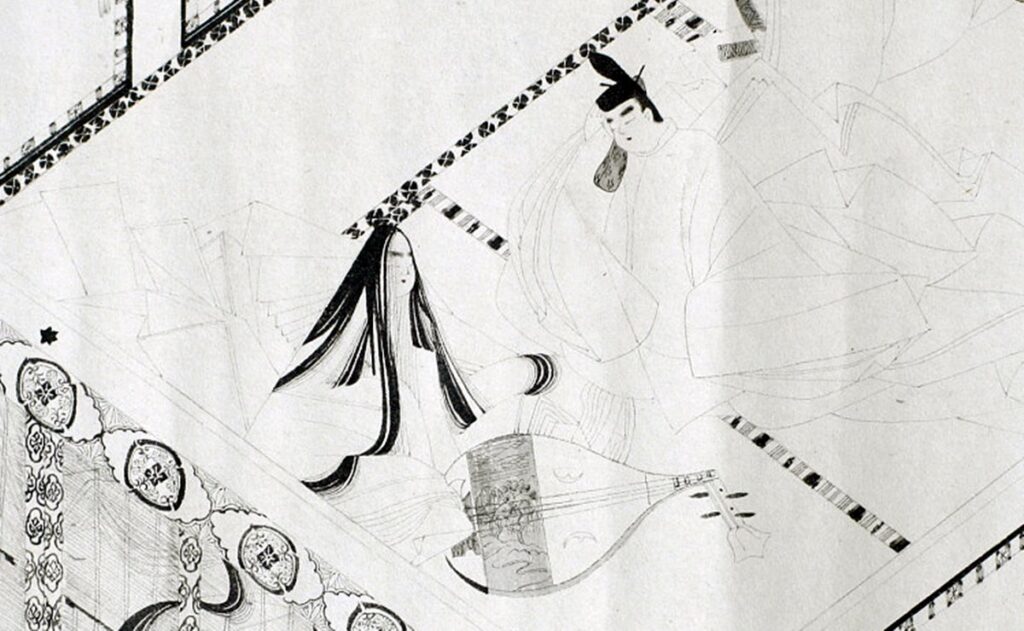
枕草子絵詞/wikipediaより引用
枕草子では、この一条院滞在中に一条天皇が定子のもとにやってきて笛を吹いたときのことが記されています。
定子は翌長保二年(1000年)12月に第三子・媄子内親王を産んだ後崩御してしまうので、晩年の安らぎのひとときといえるでしょう。
また以下のように『紫式部日記』に書かれている、寛弘五年(1008年)12月31日の強盗事件も、この屋敷でのことでした。
「彰子の御在所に強盗が押し入り、女房二人が衣装を剥ぎ取られた」
その翌年・寛弘六年(1009年)10月5日には一条院が火事で焼失してしまい、寛弘七年から再建されています。
一条院はその後も一条天皇と彰子に使われ、寛弘八年(1011年)6月22日に一条天皇がここで崩御し、彰子との間に生まれた後一条天皇も用いました。
為光は外戚になることはできませんでした。
しかし、彼の邸がその後の天皇たちに使われたというのはなかなか数奇なめぐり合わせですね。
大河ドラマ『光る君へ』でも、生前はもちろん、亡くなった後も色々な場面で藤原為光の名が登場するかもしれません。
あわせて読みたい関連記事
-

道隆から道長へ鞍替え~藤原斉信が貴族社会を生き残り「寛弘の四納言」となる
続きを見る
-

花山天皇の生涯|隆家との因縁バチバチな関係で喧嘩も辞さない破天荒
続きを見る
-

骨肉の権力争いを続けた藤原兼家62年の生涯~執拗なまでにこだわった関白の座
続きを見る
-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか
続きを見る
-

藤原詮子は道長の姉で一条天皇の母~政治力抜群だった「国母」の生涯を振り返る
続きを見る
-

史実の藤原行成は如何にして道長を助けたか? 書と政務の達人は道長と同日に逝去
続きを見る
長月 七紀・記
【参考】
木村朗子『女たちの平安宮廷『栄花物語』によむ権力と性』(→amazon)
繁田信一『庶民たちの平安京』(→amazon)
倉本一宏『平安京の下級官』(→amazon)
繁田信一『平安貴族 嫉妬と寵愛の作法』(→amazon)
京樂真帆子『牛車で行こう!-平安貴族と乗り物文化-』(→amazon)
倉本一宏『藤原道長の日常生活』(→amazon)
朧谷寿『藤原道長 男は妻がらなり』(→amazon)
ほか