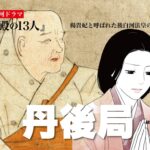こちらは3ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【鎌倉殿の13人感想あらすじレビュー第24回「変わらぬ人」】
をクリックお願いします。
丹後局に震える母娘
丹後局がしずしずと登場してきました。
彼女のような尼は墨染めの衣も着ません。尼削ぎといって肩のあたりで髪を切り、頭も剃らない。
まずはそつなく大姫を褒めます。なんでも入内に骨折りしているとか。それも高価な「土産」あってのことでしょうけどね、と。
「田舎の人は良いものですねえ。どんな言葉も素直に受け取る」
そう聞かされ、政子の顔がひきつります。
「この着物を選んだのは?」
「私にございますが」
「かような色合いのもの、都で着ているものは一人もおらぬ」
そうダメ出しをされて、前向きな政子は帝の好みを聞いてきます。
丹後局はもう決まったようなものだとふてぶてしく言う。それにそんなこと教えるわけがない。察せよ、学べ。季節ごとに異なるのだ。そういうことでしょう。
「頼朝卿はともかく、あなたはただの東夷(あずまえびす)! その娘がたやすく御台になるなどできるとお思いか?」
立ち上がり、容赦なく見下す丹後局。
厚かましいにもほどがある! そう言い切る相手に、それでも政子は頭を下げ、知恵を授けて欲しいと言える。
しかしその横で大姫は顔色が悪い。
丹後局から数多いる女の一人に過ぎぬと聞かされ、絶望しています。『源氏物語』でその辛さも学んではいるのでしょう。
-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは
続きを見る
-

光源氏ってゲスくない?ドラマ『いいね! 光源氏くん』が人気だけど
続きを見る
耐えようとする母。心が折れる大姫。
すでに兼実の子・任子と通親の子・在子が身籠っているのはご存じかと念押しする丹後局。
政子は動揺しつつ、知らなかったと答えるほかありません。
帝の寵愛を受け、子を産み、それが男子でなければならない――都ではその一点に賭け入内させる。
その覚悟を問われる政子と大姫。
「頼朝卿に伝えよ。武力を傘に着て、何もかも押し通せると思われぬようにと」
はい、世間話はこれまでといい、どこに行き誰に会うべきか指南すると急に微笑む丹後局。
大姫は不安で潰されそうになり、政子ですら怯えが見えます。
丹後局って、実はこの入内ルートに入らない特殊な出世街道を歩んでいます。
乱世ゆえに成り上がったからこそ、後進は許さない。そんな気概を感じます。
堂々たる京都の化身として、この女性が立ち塞がる。
-

丹後局こと高階栄子は後白河法皇の寵姫~現代にまで伝わる悪女説は本当か?
続きを見る
なお、このあとこの枠には、シルビア・グラブさん扮する藤原兼子が待ち受けております。
大姫の子が天皇になれば外曽祖父だが
「言わせておけ」
寝室の頼朝は、政子の言葉を聞いても背中を向けて不貞腐れたように寝転がっています。
なんでも頼朝も嫌な目にあったとか。
唐(から)の国の匠に会うはずだったが、叶わなかったと。
日本ではどの王朝になろうが中国大陸を「唐(から)」と呼びました。
陳和卿の「天から見放されている」という言葉が気になっているようです。
政子は「言わせておきましょう」というものの、お互い何か不穏なものを察知しているようです。
「都は好かん」
そう吐き捨てる頼朝。かつては都風であることを己のアイデンティティにしてきただろうに。坂東武者と自分は違うと思っていたのだろうに。
夜、大姫は外へ飛び出します。
そのころ、お供の坂東武者たちは上機嫌で酒と双六を楽しんでいます。
三浦義澄と義村の父、それに土肥実平。
-

初戦で敗北の頼朝を支えた土肥実平~西国守護を任される程にまで信頼された
続きを見る
義澄と実平は大姫が入内し、次の天皇を産むことまで考えていてお気楽です。
となれば時政はなんだっけ……と息子に聞く義澄。
義村が「外曽祖父」と返答し、はしゃぐ父を呆れるように諭します。
「情けないとは思わぬのですか」
かつて、三浦は北条より上だった。それがこれほど差がついてしまった。どうなってんだ、と。
それでも義澄は気楽で、どんなに出世しようが時政は幼なじみ、頭をこづいてやると能天気に言っております。
義村は話が合わないと諦めたのか、先に戻ろうとします。
孤独だなぁ。友が少ない……彼を理解するものはあまりに少ない。義時がここにいればいいのに。
呪詛を仄めかす大江広元
大姫のことを察知したのか、畠山重忠が探して結果を政子に報告しています。
政子は大姫に無理をさせているという、そもそもが入内は無理だったと悔やんでいます。頼朝が何かに怯えていることも察知していました。
すると大姫は、偶然、義村と会いました。
義村は大姫の話を聞き、悪くないと慰めています。人は生きたいように生きるべきだと。
「帝に嫁いだところで、それが何になりましょう。きっと今日のようなことが繰り返される。それでは姫の身が持ちません。鎌倉殿のことはお忘れなさい。北条の家のことも。人は、己の幸せのために生きる。当たり前のことです」
「私の、幸せ?」
そう言いながら、ぐったりと義村によりかかる大姫。そのまま彼女は病に倒れ、入内は延期となりました。
鎌倉へ戻っても容体は悪化する一方。
政子が何か食べさせようとすると、大姫は好きに生きてはならないのかと聞いてきます。
入内の話はなかったことにするという政子に、大姫はこうつぶやきます。
「好きに生きるということは、好きに死ぬということ」
「母を悲しませるようなことを言わないで」
そう娘の手をとる政子。
「死ぬのはちっとも怖くない。だって死ねば義高殿に会えるんですもの。楽しみで仕方ない」
生きることを拒んだ体は、そのまま衰弱の一途をたどり、建久8年(1197年)、二十歳の生涯を終えたと語られます。
呆然とする政子。泣く時政。政子を強くあれと励ますりく。
そこへ頼朝が入ってきます。娘の遺体を前にし、涙を流すこともできない。政子と手を重ねあうも、こう言います。
「わしは諦めぬぞ。わしにはまだ為すべきことがあるのだ」
そして義時に、次女・三幡寿代の話を進めるよう命じるのでした。
愕然とする政子。
頼朝は、さらに大江広元にこう言います。
大姫の死はおかしい。広元は呪詛か?といい、頼朝は思い当たる者が一人いる、生かしておくべきではなかったと言います。
「梶原平三を呼べ」
頼朝が凄まじい形相を浮かべます……。
と、ここで大江広元のことでも。
広元は現実的です。
熊谷直実の子・直家が「父が宣告して亡くなる時期なので上洛したい」と申し出たところ、「人間ごときに死ぬ時期なんてわかるわけないでしょ」と却下しております。
子は怪力乱神を語らず。『論語』「述而」
立派な人物はオカルトホラー話をしません。
未だ生を知らず、焉(いず)くんぞ死を知らん。『論語』「先進」
生きるということがわからないのに、死のことなんてわかるわけがない。
こういう漢籍をバッチリこなした大江広元が、こんな呪詛を信じるとは思えません。
話を合わせたのは彼なりの処世か、それとも……?
-

頼朝の参謀で鎌倉幕府の中枢だった大江広元の生涯~朝廷から下向した貴族の才覚に注目
続きを見る
善児の刃が貫いた
伊豆修善寺では、範頼が大きな茄子を収穫して喜んでいます。
茄子は鎌倉時代の定番メニューで、便所跡から種が大量に出てくるほど。蒲殿が丁寧に育てたと民も喜んでいる。
するとそこへ何者かが接近してきます。
「次は何を植えようか」
そう振り返ると、話していたばかりの農民が倒れている。
咄嗟に身構える範頼。
「真桑瓜なんかがいいなぁ」
「真桑瓜……」
そう振り向く範頼の腹を、善児の刃が貫きました。
偶然、一部始終を見ていた少女は、怯えながらも手にした鎌を構える。善児は気が変わったのでしょうか。少女を殺すことはやめたようです。
範頼の最期は梶原景時の軍勢に攻められて自害とされますが、本作では善児が始末しました。
いい加減、警戒されてもおかしくないでしょうし、善児は修善寺のある伊豆の出身でしょう。そこは深く考えても仕方ない。ある意味、善児こそ一騎当千の気がします。
頼朝はもう、熟睡できなくなっていました。
天から生かされてきた頼朝は気づいているのです。自分の死が、間近に迫っていることを。
己の死のみならず、源氏の範頼を殺すことで、彼が源氏将軍の宿命そのものを縮めた。
叔父の血が染み込んだ修善寺に、頼朝の子である源頼家も幽閉されることとなります。
MVP:源範頼と大姫 ついでに三浦義村
比企尼は、人は立場によって変わるといった。
巴も変わったと自分を認めている。
口にはしないけど、義時だってすっかり変わってしまった。
それでも変わらない人はいます。
源範頼は、ずっと兄を支えて変わらないでいようと思っていた。御家人というより弟という気持ちがあったからか。それが裏目に出てしまった。
大姫も変わらない。
『鎌倉殿の13人』では、鎌倉入りを果たした時、政子が幼い大姫を抱いて頼朝と再会していました。
このときが幸せの絶頂で象徴だと思いました。
何も知らず、真っ直ぐに生きているときが、頼朝と政子にとっての幸せの頂点だったのだろうと。
しかし、二人とも変わってしまい、そのためどんどん恐ろしい結末へ向かってゆきます。
それにしても、迫田孝也さんの範頼は素晴らしかった。
範頼はかわいそうなんですよ。
人生そのものもそうなのだけれども、義経顕彰系のフィクションの中で、対比のため必要以上にダメなお兄さん扱いをされてきた。
そのせいで地味で役に立たない人とすら思われている。
そういうところを否定すべくマッチョにするのではなく、ただただ真面目で温厚で、こういうリーダーがいたらきっと最高だと思わせてくれた。
素晴らしい範頼でした。
南沙良さんの大姫。暗くなくて明るい笑顔も見せるのに、常に底に穴が開いているようで。悲しいけれど、それだけではない素敵な大姫でした。
そして実は変わらないと言えば、三浦義村。
彼は陰謀のせいでくるくる変わるようで、実は自分を中心に置いて生きていると思えます。
俺が楽しいか、楽しくねえか。それが常に中心にどかっとある。
楽しくねえなら隠居してやる……って、どこまで本気なのやら。
彼は動かないのに、周囲は嵐のように動いている。
でも、そう思っているのは本人くらいで、周囲からすれば彼はぐるぐると姿を変えて回りつつ、何かおかしなことをしているように思えるのかもしれない。
孤独なんですね、彼は。理解者が圧倒的に少なくて、だから理解してくれる義時はありがたいはず。
彼は『真田丸』の真田昌幸も思い出します。
昌幸は真田を守る一点集中で生きている。
でも天下は武田、豊臣、徳川と回る。
回る中で自分だけ回らないでいたら理解されず「表裏比興」と言われてしまったのです。
※続きは【次のページへ】をclick!