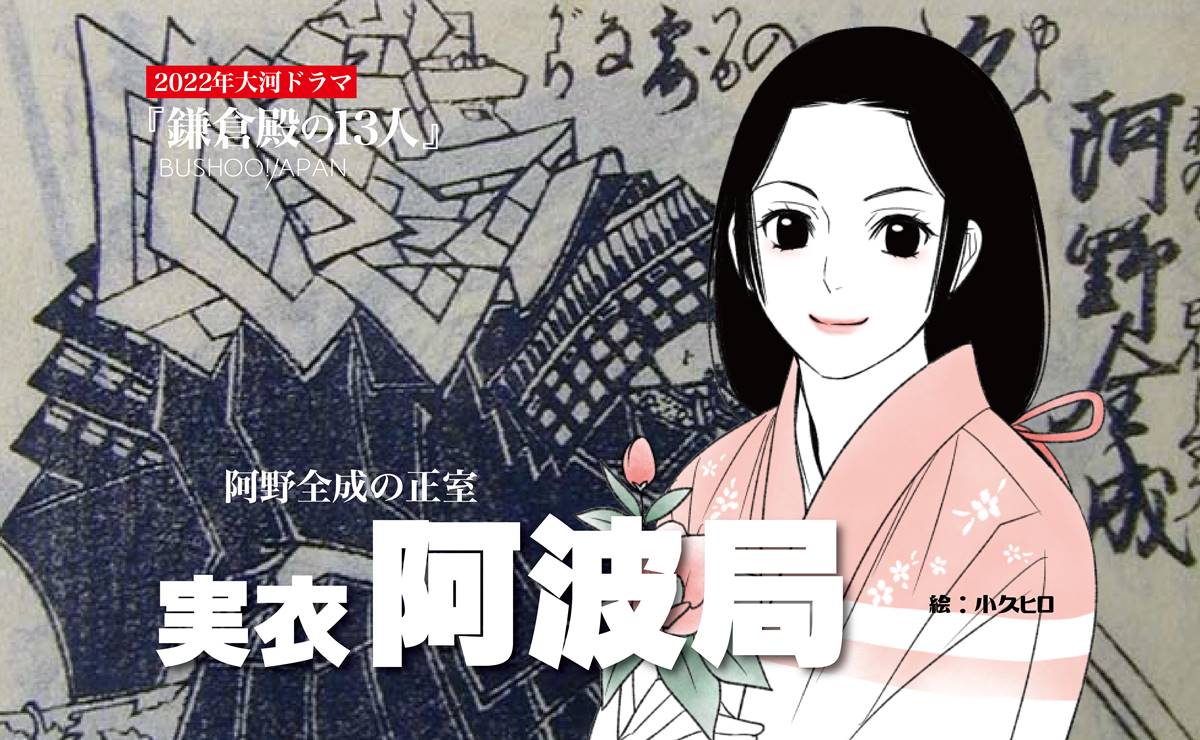嘉禄3年(1227年)11月4日は阿波局が亡くなった日です。
2021年までだったら、即座に「誰ですか?」と聞き返された方かもしれませんが、今は違うでしょう。
大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に序盤から登場し、途中、夫の阿野全成が誅殺されるという不幸に遭いながら、3代将軍・源実朝の乳母を務めるなど。
鎌倉幕府でもなかなかの重要ポジションに就く実衣を宮澤エマさん演じ、姉で小池栄子さんが演じる北条政子との姉妹トークは、ドラマの見どころでもありました。
そんな阿波局は史実では一体どんな人物だったのか?
彼女の生涯を振り返ってみましょう。
阿波局が阿野全成の妾とは?
阿波局(実衣)の父は北条時政です。

北条時政/wikipediaより引用
史実における生年は不明で、母も不明。
兄の北条宗時や北条義時と同じ母とされることが多く、『鎌倉殿の13人』でも
・宗時
・政子
・義時
・実衣
というきょうだいの並び順で、4人の母が同じような設定になっていました。
つまり伊東祐親の娘になりますね。
時政の子は、ドラマに出ている以上に大勢いるのですが、省略されています(詳細は以下の記事へ)。
-

悲劇の最期を迎えた北条時政の娘達~畠山重忠や稲毛重成の妻たちは一体何処へ
続きを見る
娘たちは多くの有力御家人に嫁いでゆき、阿波局(実衣)もまた、源頼朝の弟・阿野全成という相手に恵まれたのでした。
表記上は全成の「妻」ではなく「妾」とされることもありますが、いわゆる愛妾ではなく正妻ですね。
当時は身分の釣り合いが取れない場合「妾」と呼ぶことがしばしばあり、河内源氏・源義朝の息子(阿野全成)と北条時政の娘(阿波局)では、立場的には月とスッポンで仕方ありません。
そして、頼朝の信頼する弟と結ばれた阿波局(実衣)が、鎌倉殿の跡取りをめぐる血生臭いパワーゲームに巻き込まれてしまうのは不可避でした。
頼朝は乳母子を大事にするからこそ
寿永元年(1182年)8月12日――源頼朝と北条政子の間に、長男・万寿(後の源頼家)が生まれたのが始まりです。
待望の長男誕生に鎌倉は祝賀ムード!
と思いきや、不穏な空気が漂っていたと『鎌倉殿の13人』では語られます。
頼朝と浮気相手が絡んだトラブル。
【亀の前事件】が起きたのです。
頼朝が亀という女性と密通し、それが時政の妻りく(牧の方)から政子に伝わり激怒&襲撃!
亀は邸を壊され、直前に命からがら逃げ出していましたが、こうしたドタバタからついには北条時政までキレてしまい、伊豆へ引っ込んでしまいます。
史実でもユーモラスな事件で、ドラマでも笑える場面として描かれました。しかし……。
政子としても、単なる嫉妬だけで、ああも激しい行動に出たとは言い切れません。
頼朝の妻であり、その子を産む母であればこそ、北条氏の地位も保たれる。つまり北条氏の者としては、それを脅かす女性を排除せねばなりません。
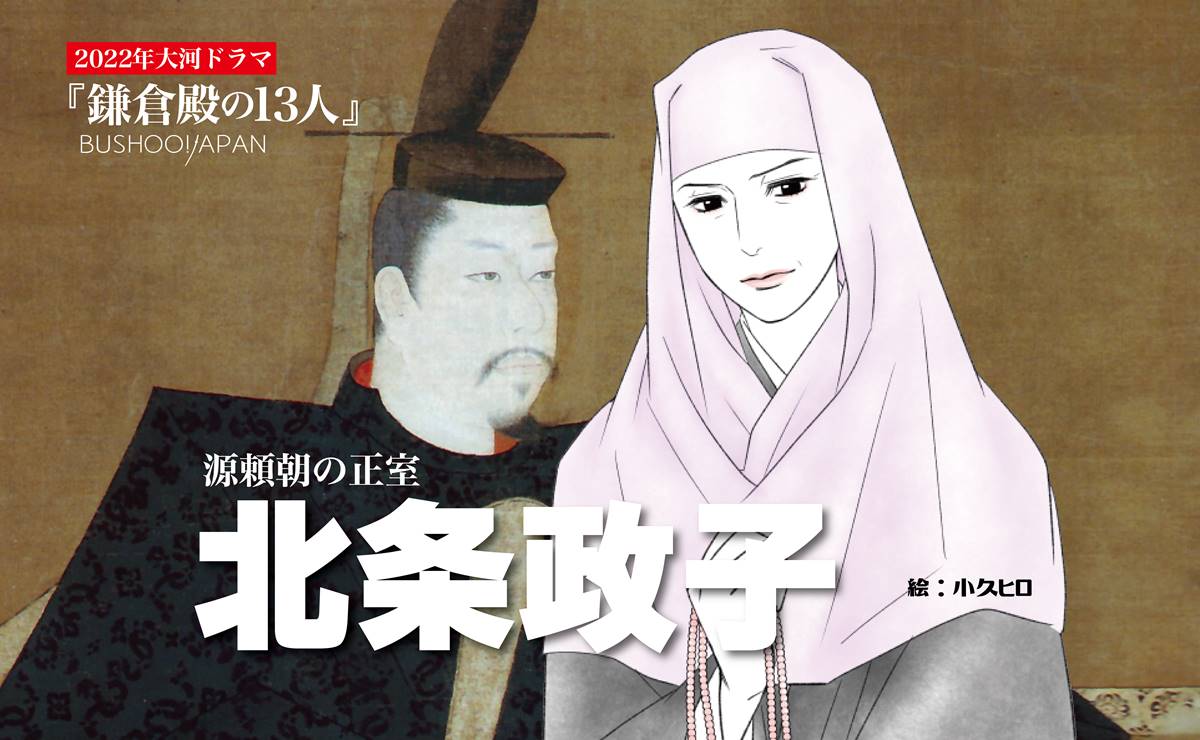
また、ドラマにおける万寿の誕生では、何人かの御家人たちも浮足立っていました。なぜか?
乳母夫(めのと)のポジションです。
劇中での上総広常は、万寿が生まれると乳母夫(めのと)になりたいと志願し、断られていました。さすが関東随一の実力者だけあって、彼は鎌倉での変化を嗅ぎ取っていたのでしょう。
石橋山の戦いで頼朝に矢を放った山内首藤経俊が助命されたり、比企尼には頭が上がらなかったり。
広常は「頼朝が乳母子を大事にする」と語っていました。
そうした状況を踏まえ、何かあったとき救いのカードとなる――として乳母夫を志願したのでしょう。
頼家の誕生前にそんな風潮が生まれつつあり、かつそれが御家人たちに段々と伝わってゆき、不満や謀反の火種にもなっていく……という細やかな描写です。
結局、万寿の乳母には、頼朝の乳母でもあった比企一族が指名されました。
千幡の乳付役となる
時は流れます。
源義経の活躍もあり、寿永4年(1185年)に【壇ノ浦の戦い】が勃発。
この戦いで平家を滅亡させた頼朝は、文治2年(1186年)2月26日、大進局という女性に男児を産ませました。
ドラマでは完全スルーされたのでご存知ない方もおられるかもしれません。
頼朝が女房の一人・大進局に手を付けたのですが、これに激怒した政子は出産の儀を全て省略させ、生まれた子も出家させられ「貞暁」という僧になります。
文治5年(1189年)には源義経が自害。
比企氏の血を引く正室・郷御前も運命を共にしました。

源義経/wikipediaより引用
そして運命の建久3年(1192年)がやってきます。
3月に後白河法皇が崩御すると、7月に頼朝は征夷大将軍の号を授かり、8月9日には頼朝と政子の二男・千幡(後の源実朝)が生まれました。
二男の誕生は、阿波局(実衣)にとって激しくインパクトのある出来事でした。
彼女は乳付役(ちつけやく・初めて乳をふくませる役)に任命されたのです。
他の女房を従え、御所へ。
大勢の御家人が見守る中、大役を果たし、ホッと一息……つく暇はありません。
鎌倉幕府は日本史上初の「幕府」です。
それゆえ、後世なら常識なことがそうではなく、例えば征夷大将軍の号も、九条兼実が数種類の候補を挙げ、頼朝が選んだものでした。

九条兼実/wikipediaより引用
阿波局(実衣)に関わってくるのは相続の話です。
当時は長子の相続が確定しておらず、兄の万寿、弟の千幡、どちらにも資格はありました。
万寿を擁する比企か?
千幡を擁する北条か?
そんな対立の構図がありました。
鎌倉では、文治5年(1189年)7月から9月にかけての奥州合戦が終わると、戦の時代に終止符が打たれ、代わりに権力闘争が激化していたのです。
※続きは【次のページへ】をclick!