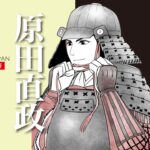加賀百万石の礎を築いた前田利家。
豊臣秀吉に敗れ、最終的に切腹へ追い込まれた佐々成政。
両者に共通する最大の特徴は?
それぞれ信長の親衛隊である「赤母衣衆」「黒母衣衆」に所属していたことであろう。
◆前田利家「赤母衣衆(あかほろしゅう)」
◆佐々成政「黒母衣衆(くろほろしゅう)」
二人共、この精鋭部隊から後に国持大名へと大出世を遂げるが、なぜそこまで評価されたのか?というと、やはり若い頃から常に信長の背中を追いかけ、数多の戦場で活躍してきたから。
単に信頼されていただけでなく、誰よりも信長の近くで戦い続けていたからであろう。
いったい彼らは織田軍の中でどんな存在だったのか?
黒母衣衆と赤母衣衆に注目してみたい。

そもそも母衣とは?
まず「母衣」とは何か?
というと、以下の絵をご覧いただくと理解が早いと思われる。
馬に乗った若い男性にご注目を。

母衣のイメージ(室町時代以降は布を広げるための骨組みも作られた)
背中に背負ってるのが「母衣(ほろ)」。
歴史的には次の一枚が有名であろう。

熊谷直実/wikipediaより引用
平敦盛を追いかける熊谷直実。
大きく赤い布が背中でたなびいているのが一目瞭然であろう。
背中に大きな母衣(布)を背負うということは、味方だけでなく敵からも一目瞭然の存在となり、目立つがゆえに背後から弓で狙われても、その母衣が矢を防いでくれる効果があるともされる。
いずれにせよ戦場では目立つ存在――。
ゆえに武勇がなければ務まらず、味方を鼓舞する名誉のある役目でもあった。
織田軍では、信長直属の部下として「馬廻衆(うままわりしゅう)」や「小姓衆(こしょうしゅう)」などがいて、そのうち選りすぐられた10名(計20名)のメンバーが黒母衣衆と赤母衣衆に選出された。
桶狭間の戦いをはじめ、稲生の戦い、天王寺砦の戦い、朝倉軍の追撃など。
信長は、緊急事態に自ら戦場へ駆け出していくことで知られるが、そうしたときに最初から付き従うのが小姓や馬廻であり、その筆頭が黒母衣衆と赤母衣衆だったのである。
では、実際に誰が名を連ねていたのか?
本記事で確認してみよう。
※母衣衆のメンバーは入れ替わりなどがあり、本記事では10名以上の記載となっています
黒母衣衆
まずは黒母衣衆から見ておこう。
河尻秀隆
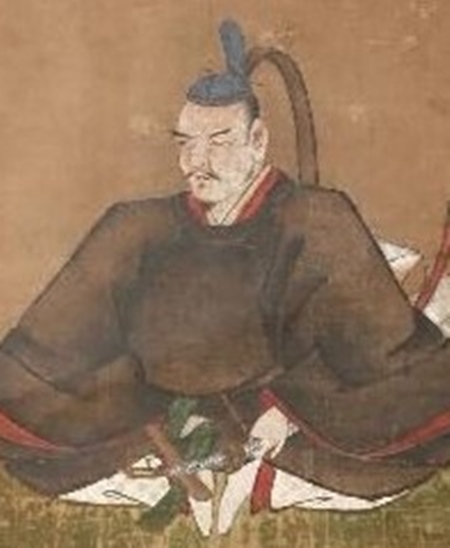
河尻秀隆/wikipediaより引用
信長の父・織田信秀の代から仕え、桶狭間の戦いにも参加。
後に織田信忠を補佐する役目を担い、甲州征伐後は甲斐一国を任せられるまでになる。
本能寺の変後、武田の旧臣に討たれた。
中川重政
織田一門の武将。
信長の上洛後は京都の内政を任されるなど、秀吉や光秀らと並んで重用されていた。
しかし、実弟の津田隼人正が、柴田勝家の代官を斬殺してしまい、兄弟揃って改易。
後に呼び戻されるも、その後の活躍は伝わっておらず。
津田盛月
中川重政の弟で、初名は織田左馬允。
兄の中川重政が安土に置かれると、その補佐として同居。
上記のとおり改易に処されると、本能寺の変後は秀吉に仕え、外交などで活躍を。
佐々成政

佐々成政/wikipediaより引用
生年や出自などは不詳。
黒母衣衆として活躍した後、前田利家・不破光治と3人で越前2郡を任せられる。
秀吉とは折り合い悪く、肥後を任されるも一揆を起こして切腹へ。
毛利良勝(新助・新介)
なんといっても【桶狭間の戦い】で今川義元を討ち取ったとして知られる武将。

毛利新助と服部小平太が襲いかかる(作:歌川豊宣)/wikipediaより引用
しかしその後は武人としてではなく、通常の役人としての活動しか記録に残されていない。
本能寺の変では織田信忠のいる二条御所で討死。
生駒勝介
生駒親正の従兄弟とされる。
当初は犬山城の織田信清(信長の父・織田信秀の従兄弟)に従っていたが、後に信長のもとへ。

こちらは生駒親正/wikipediaより引用
水野帯刀左衛門
刈谷の水野氏一族の者と推定される。桶狭間の戦いでは丹下砦の守備につき、その後、名前が消えてしまう。
松岡九郎次郎
茶に通じていて、本能寺の変後は豊臣秀吉に仕える。
平井久右衛門
弓が得意な武将で、有岡城攻めでは弓衆を率いて、町に火矢を射ち込んだ。
京都馬揃えで弓隊を率いるほど。
-

京都御馬揃え|信長の家臣たちが勢揃いした軍事パレードは衣装もド派手だった
続きを見る
蜂屋頼隆
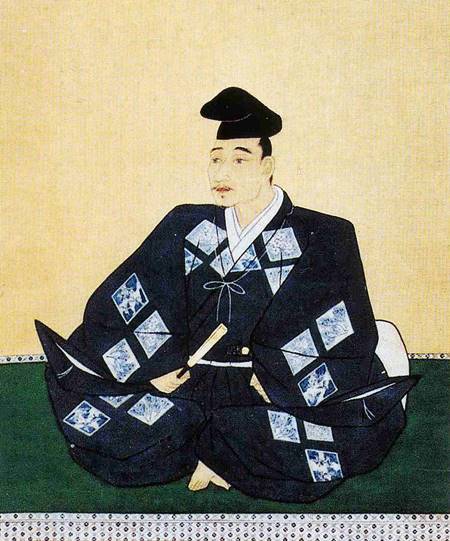
蜂屋頼隆/wikipediaより引用
美濃出身の武将。
早くから馬廻衆として活躍し、上洛後は畿内での政務に携わり、その後も信長の主な合戦で活躍。
一時は和泉国も任されるも、豊臣政権の下では不遇であり、越前敦賀5万石へ。
-

蜂屋頼隆の生涯|信長の親衛隊・黒母衣衆から大名へ 地味なれど秀吉にも重用され
続きを見る
野々村正成
当初は美濃斎藤家に仕え、後に黒母衣衆へ。
長篠の戦いでは鉄砲衆を指揮したことでも知られる。
本能寺の変では二条御所に駆け込み、討死となる。
伊藤武兵衛
早い段階で信長に仕えていたが、後に、同僚を斬って出奔、今川家に仕えた。
中島主水正
織田信清の家臣で、犬山城では家老の一族だったと推測される。その後、信長の下で黒母衣衆へ。
赤母衣衆
次は赤母衣衆を確認しよう。
前田利家

前田利家/wikipediaより引用
言わずとしれた加賀百万石の藩祖。
若い頃は織田家を追い出されたこともあるが、その後は北陸方面で柴田勝家らと共に武功を挙げる。
勝家と秀吉により賤ケ岳の戦いでは、秀吉勝利のキッカケを呼び込み、豊臣政権で五大老へと大出世。
山口飛騨守
信長の小姓で赤母衣衆に選抜。
信長の近臣・坂井道盛を殺害して出奔すると、徳川家康を頼り、三方ヶ原の戦いで討死となる。
毛利長秀(秀頼)
信長の馬廻で赤母衣衆に選抜。
一説によると尾張守護・斯波義統の子とのこと。
甲州征伐で武田家が滅亡すると、信濃伊那郡を与えられて飯田城主となる。
木下雅楽助(織田薩摩守)
読み方は「きのした うたのすけ」で、中川重政や津田盛月の弟。
兄二人と同様に赤母衣衆へ。
兄の改易に連座して、その後は消息不明も、豊臣秀次に仕え、長久手の戦いで討死したとも伝わる。
織田越前守
信長の馬廻から赤母衣衆へ名を連ねるも、その他の事績は全くの不明。
岩室長門守
信長の小姓から赤母衣衆へ。
桶狭間の戦いで活躍するも、翌年、小口の戦いで討死。
当時、信長最愛の家臣だったとも目されている。
伊東長久
武力を誇る赤母衣衆。
尾張三本木村での戦いで編笠をかぶって戦い「編笠清蔵」と呼ばれる。
天正元年(1573年)、浅井長政の本拠地へ攻め込んだ小谷城の戦いでは、刀と脇差しを紛失しながら敵3人を討ち取ったと伝わる。
豊臣政権では、腰母衣衆・旗奉行を務めたとのこと。
飯尾尚清
桶狭間の戦いでは今川軍に鷲津砦を落とされるも生還。
その後、馬廻りとなり赤母衣衆となるも、役人としての活躍のほうが目立つ。
福富秀勝
信長の馬廻で赤母衣衆に選抜。
黒母衣衆の野々村正成と同様、長篠の戦いでは鉄砲衆を指揮した。

長篠合戦図屏風より/wikipediaより引用
本能寺の変では二条御所で討死するが、それまで平時は小姓や馬廻の指揮官を務めていたと思われる。
塙直政(原田直政)
信長の馬廻で赤母衣衆に選抜。
上洛後は畿内の行政に携わり、信長と義昭の間では使者役も務める。
荒木村重や明智光秀らと共に石山本願寺と戦い、討死。
渥美刑部丞
『高木文書』の中にだけ見られる名前。他の史料では確認できない。
金森長近

金森長近/wikipediaより引用
元は美濃出身だが、織田信秀の時代から仕官して信長の家臣へ。
美濃攻略の功を認められて赤母衣衆となり、その後も活躍。長篠の戦いでは酒井忠次の別働隊と共に織田軍5000を率いて、勝頼背後の砦を陥落させている。
その後も信長、秀吉、家康の下で活躍し、関ヶ原後は飛騨を中心に約6万石の領主となる。
猪子一時
織田信清(犬山城)から信長に仕えて赤母衣衆へ。
本能寺の変後は秀吉に仕えている。
黒田次右衛門
三河出身ながら、信長に見出されて馬廻から赤母衣衆へ。
加藤弥三郎
尾張熱田の豪族・加藤順盛の次男。
桶狭間の戦いで活躍するも、山口飛騨守と共に信長の近臣・坂井道盛を殺害して出奔。
徳川家康を頼った後、三方ヶ原の戦いで討死する。
浅井政澄
信長の馬廻から赤母衣衆へ。
嫡男の織田信忠に従うも、程なくして活躍の記録は見られなくなる。
黒と赤ではどちらが上だったのか?
織田信長の行動を支えた黒母衣衆と赤母衣衆。
いずれも小姓や馬廻から選ばれたエリート部隊であることは前述の通りだが、黒と赤では差があったのか?
ぶっちゃけ、どちらが強いとかあったのか?
というと、前田利家の言葉として「黒のほうが赤より少し上」というのが伝わっている。
しかし、当初の黒母衣衆は馬廻から、赤母衣衆では小姓から選ばれていて、「黒のほうが年長者が多かったため一段上だとされたのではないか?」と『信長の親衛隊』(中公新書)では指摘している。
あわせて読みたい関連記事
-

佐々成政の生涯|信長の側近から大名へ 最期は秀吉に敗れた反骨の戦国武将
続きを見る
-

金森長近の生涯|信長親衛隊“赤母衣衆”から大名へ 波乱万丈の85年を駆け抜け
続きを見る
-

原田直政の生涯|赤母衣衆出身の武将が死して信長に罵倒されたのはなぜなのか
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
参考文献
- 谷口克広『信長の親衛隊――戦国覇者の多彩な人材(中公新書 1453)』(中央公論社, 1998年12月20日, ISBN-13: 978-4121014535)
書誌(公的): 国立国会図書館サーチ |
Amazon: 商品ページ - 日本史史料研究会(編)『信長研究の最前線――ここまでわかった「革新者」の実像(朝日文庫)』
(朝日新聞出版, 2020年10月7日, ISBN-13: 978-4022620309)
出版社: 朝日新聞出版(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ