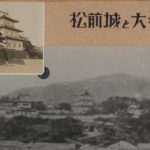こちらは5ページ目になります。
1ページ目から読む場合は
【『べらぼう』感想あらすじレビュー第21回蝦夷桜上野屁音】
をクリックお願いします。
「俺たちは、屁だぁ〜!」という地獄絵図
「朝から晩までふざけやがって、てめえらなぁ! てめえら、てめえらなんかなぁ!」
恋川春町の怒りも頂点に達し、いよいよどうなってしまうんだ?
と緊張感が最大になったとき、部屋の中に「ブゥ~」というマヌケな音が鳴り響きます。
次郎兵衛の放屁でした。
呆れ果てる蔦重。
困惑する歌麿。
「す……すいません、すいません、へへッ!」
笑いが起き、タイミングよく南畝が絶叫。
「俺たちは、屁だぁ〜!」
かくして「屁! 屁! 屁!」コールと共に、皆踊り出し、狂歌を詠みます。
七へ八へ へをこき井手の 山吹の
みのひとつだに 出ぬぞきよけれ
四方赤良
芋を食ひ 屁をひるならぬ 夜の旅
雲間の月を すかしてぞ見る
元木網
芋の腹 こき出てみれば 大筒の
響きにまがふ 屁(兵)の勢ひ
知恵内子
嗚呼、水樹奈々さんの美声をなんてことに使うんだ……。
山里に 尻込みしつつ 入りしより
浮世のことは 屁とも思わず!
そう四方赤良が詠む中、春町は脱力し切った顔になっています。
そして懐から筆を取り出すとこう言いながら、筆をへし折り去ってゆくのでした。
「恋川春町、これにて御免」
なんてこったい!
でもま、そりゃそうなるよな。春町先生は一体どうなってしまうのやら。
MVP:松前道廣
まず松前のお殿様が大河に出るということが、画期的で素晴らしいことだと思います。
そんなものすごく珍しいお殿様が、いきなり縛りつけた女を銃で狙う乱行をぶちかます。無茶苦茶ですよ。異常です!
お殿様というのは地元の民衆からすれば、思い入れがあります。
こんなド派手なパリピバカ殿にしたら、抗議は必至かもしれない。
大河ドラマでいえば『独眼竜政宗』における最上義光という先例があります。あまりに悪どく描かれたため、山形の皆さんが怒ったという話ですね。
しかし、松前のお殿様はこのリスクが非常に低い。
全国随一ではないでしょうか。
というのも、松前藩の評判は、悪い!
なんなら当時から悪い!のです。

松前城と桜
アイヌに対する暴虐酷使ぶりは、それを目にした松前武四郎のような人物が心を痛め、人を人と思わぬ扱いだと憤りをこめて書き記してきました。
そういった人道的な視点を抜きにしても、松前藩の政治はどこか後ろ暗いところがあり、問題視されてきています。
今回は、抜荷が問題視されていましたが、情報隠匿のようなことは常習的。
そんな歴史の積み重ねがあるので、松前藩についていえば、だいたい「ともかく悪い」で終わるようなところはある。
そしてそれをフィクションで描いても、さして抗議はありません。
例えば人気作品『ゴールデンカムイ』でも、土方歳三が「松前藩の産んだよいものは永倉新八と松前漬けだけだな」と身も蓋もないことを言っておりました。
そもそも北海道のご当地ヒーローというと、松前藩がらみではなく、明治維新の前に一瞬滞在して戦死した土方歳三があげられるあたりにも、北海道の歴史とイメージの奇妙な点が見えてきます。
個人的にはもっと永倉新八を推して欲しいものです。
土方と共に戦った榎本武揚も、あまりに影が薄い。
このあたりからも、何か複雑なものを感じさせるんですね。

砲撃を受ける松前城/麦叢録附図/函館市中央図書館蔵
なぜ、松前藩を無茶苦茶に描いても許されるのか?
松前藩や歴代藩主の器量や事績もあるのですが、それ以上に道民のアイデンティティが重要かと思います。
要するに、江戸時代のお殿様と、現代の道民の間に断絶があるわけです。
道民のルーツ語りといえば「おれの先祖は◯◯藩の屯田兵だべさ」となる方が圧倒的に多い。
今はさすがにないでしょうが、かつては「あの藩の連中とはつきあってなんね!」なんて出身藩ごとの対立関係もあったとされます。
それより以前の松前藩には、ほとんど誰も思い入れがないのです。
ましてや箱館戦争で松前藩と敵対した側からすれば、なおのことなんですね。
ここまでは、あくまで和人ルーツ側の都合でして、もっと重要なアイヌのことも考えらなければなりません。
さんざんアイヌを苦しめた松前藩なんて、愛着が湧くわけもないでしょう。
アイヌの被った被害からすれば、松前道廣の火縄銃パフォーマンスなんて、子どもの遊び程度に思えます。
劇中で田沼意知が語った通り、蝦夷の民への扱いは本当に酷い。
そのことが大河ドラマで語られただけでも本当に重要であり、北海道史を考える契機も与えてくれました。
屯田兵から始まる北海道の歴史というのは、アイヌをどう定義するのか、ここに問題があります。
移住した先にいて、寒さを凌ぐ知恵を教えてくれたりしてくれる。
そういう脇役扱いをされてしまいがちですが、それでいいのか?
いい加減、北海道ご当地大河をやってほしい!
私は何度でもそう主張したいのですが、それは今ひとまず横におきまして。
日本史におけるアイヌとは何か?
それを考えるとなると、まさにこの田沼時代が重要なターニングポイントと言えるでしょう。
蝦夷地だけでなく、ロシアが出てきた、これが重要なのです。
ドラマにも出てきたように、江戸時代の蝦夷地統治については徳川家康が決めています。
この時点でアイヌは「化外の民」とされました。この言葉は中華思想に基づくものとされますが、日本史においても日本における中華思想として登場します。
要するに、アイヌとは和人とは別、統治の外にいる民だと定義したということです。
それが変わってくるのが、ロシアとの接触以来です。
江戸幕府としては、蝦夷地をロシアの領土とされてはまずい。
自分たちが実効支配していると示さねばなりません。
日本は島国なので、線引きはしない。代わりに島には自分たちの民が住んでいて、宗教施設があると示していく必要が生じます。
アイヌを日本人とするという発想は、ここから生じてくるわけです。
しかしくどいようですが、それは和人とロシア人が勝手に決めた話であり、アイヌ当事者が意見を出して決めていることではない。
そういう当事者からすればたまったものではない理不尽な状況を知る上では、この時代の政治について考えねばならない。
大河ドラマは大きな一歩を踏み出したのです。
このチームでなら、北海道ご当地大河もいけるんでないかい? そう確信した記念すべき回。
もうひとつ、権力者のあまりの暴虐ぶりにも痺れました。
大河ドラマはこうでなくてはならない。こういうものが見たかった。そう震えてしまいました。
権力者はそもそもが残酷になり得るリスクをはらんでいる。
松前道廣だけの話でもありません。
あの場で平然と食事をしている一橋治済も島津重豪もどういうことなんだ!と思いませんか?
暗い顔をしていた田沼意次は随分まともに思えます。
江戸時代の殿様というのは、どうしたってこういう一面はある。それが権力者の姿でもある。住む世界が違っていて、虫ケラのように民を扱うことだってある。
全てがそうではないけれども、権力というものは使い方ひとつなのです。
権力者に必要以上に忖度したり、感情移入することは危険です。
そのことを思い知らせれくれる作用が、かつての時代劇にありました。
たとえば『柳生一族の陰謀』のような作品は、徹頭徹尾ワクワクして面白いのだけれども、権力の持つ酷薄さはブレずにあります。
だからこそ見ている側は、こんな権力者がいない今の時代は、封建制の時代とは違うのだと知ることができるのです。
大河の歴史が変わる素晴らしい瞬間を、えなりかずきさんが狂った微笑みと共に見せてくれるなんて、これは夢か、夢でござぁるるぅ〜〜と脳内で叫びました。いやはや、感服です。
総評
今回はあまりに巧妙でした。
吉原の持つ搾取と差別の構造は、初回から終始一貫して描かれてきました。
江戸中期の理不尽さも出てきています。
それをよりハッキリとわかりやすくするため、馬鹿殿のお遊びや田沼意次たちの反応を通して、スケールを一気に大きくしてきました。
理不尽なのは吉原だけのことでもない。
松前道廣の暴虐で盛り上がる権力者たちは酷い。
そんな中で暗い顔をしていた田沼意次ですら、松前藩の悪事として認識するうえでは、蝦夷の民への虐待よりも「抜荷」というルール違反が重要だと感じているのです。
人の命をあまりに軽んじる、そんな社会の構図そのものが理不尽ではないか?そうドドーンと突きつけてきました。
さらに、江戸の情報流通という、出版業を考える上で必須の要素も描いてきています。
この大河ドラマは、かなりの珍品に入ります。
テーマや主役、時代の選び方だけでなく、扱う視点も相当妙なことになっている。
スパイもののような要素が実に難解かつ珍妙です。
一見、蔦重と幕政を強引に結びつけているようで、実はそうでもない。
田沼意知と誰袖の関係のように飛躍している部分もあるのですが、狂歌と蝦夷地政策は実際に繋がっていたのです。
平秩東作が幕府の秘密エージェント業務を担っていたこと。
狂歌連に出入りしていた土山宗次郎が蝦夷地政策の中枢に関与していたこと。
これは史実です。
つまり、狂歌でアホのように浮かれ騒ぐ場所が、インテリジェンスの舞台になっていたという、おそるべき史実ありきの設定です。
あんな「屁! 屁!」と踊り狂う連中がはしゃぐ場所で密談なんて、そんなバカな! そう驚愕してしまいますが、実は根拠はあるわけですね。
この江戸時代のインテリジェンスというのは、なかなか注目されにくい分野かもしれませんぜ。
しかし、それがめっぽう面白いし、江戸時代の出版業を追う上では欠かせない。
幕末の錦絵なんて、どうしてこうも情報を入手していたのか?と、驚いてしまうような作品が多数あります。
日本人の好奇心はてえしたものなんですよ。
人間が集まると情報が錬成されてゆく。その様をインテリジェンスとして捉える。
そんな歴史を見せてくれる本作は、近年随一の大河ドラマといえます。
こんなすごいドラマはそうそうありやせんぜ。こりゃとんでもねえ、紛れもねえ傑作だ!
いいドラマになるとは信じていましたが、その斜め上を毎回毎回突き抜けてきやがる!
とはいえ、そういう知識がないと、無理に主役と政治を結びつけてしまうように思えてしまうかもしれません。
おそろしい作品ですよ。
大河のコンフリクトというのは、視聴者と製作者の知識が往々にして発生させます。
近年はネットの普及やSNSもあり、視聴者の知識が製作者に近づき、場合によっては追い越して揉めることも増えてきています。
2023年『どうする家康』における「清洲城が紫禁城に見える」というツッコミが、その一例でしょう。
今年はその点、製作者の知識量に視聴者が追いつきにくく、マイナーな時代や文化面での話のために、読み解きが追いついていない現象が見られます。
しかも偽装が抜群にうまいので、まんまと騙されちまう。
下ネタやエロネタもその偽装テクニックになっていて、狙っているのかそうでないのかわからないものの、結果的に騙されてしまいます。
時にシリアスな話題や問題提起があるのに、パワーとアホなセンスがありすぎて理解されにくい。
そんな作風は前にも指摘しましたけれども、山田風太郎、あるいは今週言及した『衛府の七忍』はじめとする山口貴由若先生の作品を彷彿とさせますぜ。
そんなノリの大河がまさか見られるなんて思いもよらなかった。
今回もありがた山でやんす!
🎬 大河ドラマ特集|最新作や人気作品(『真田丸』以降)を総まとめ
あわせて読みたい関連記事
-

平秩東作の生涯|平賀源内の遺体を引き取った長老は蝦夷地にも渡る
続きを見る
-

なぜ松前藩は石高ゼロでも運営できたのか?戦国期から幕末までのドタバタな歴史
続きを見る
-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由
続きを見る
-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察
続きを見る
-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット
続きを見る
【参考】
べらぼう/公式サイト